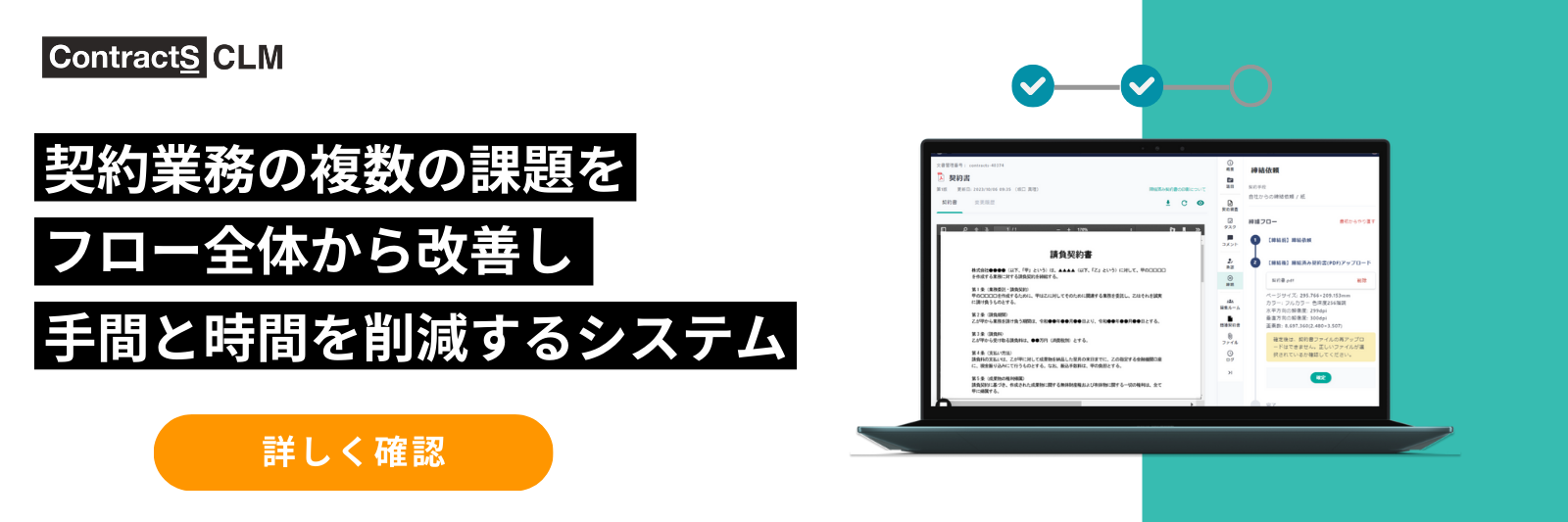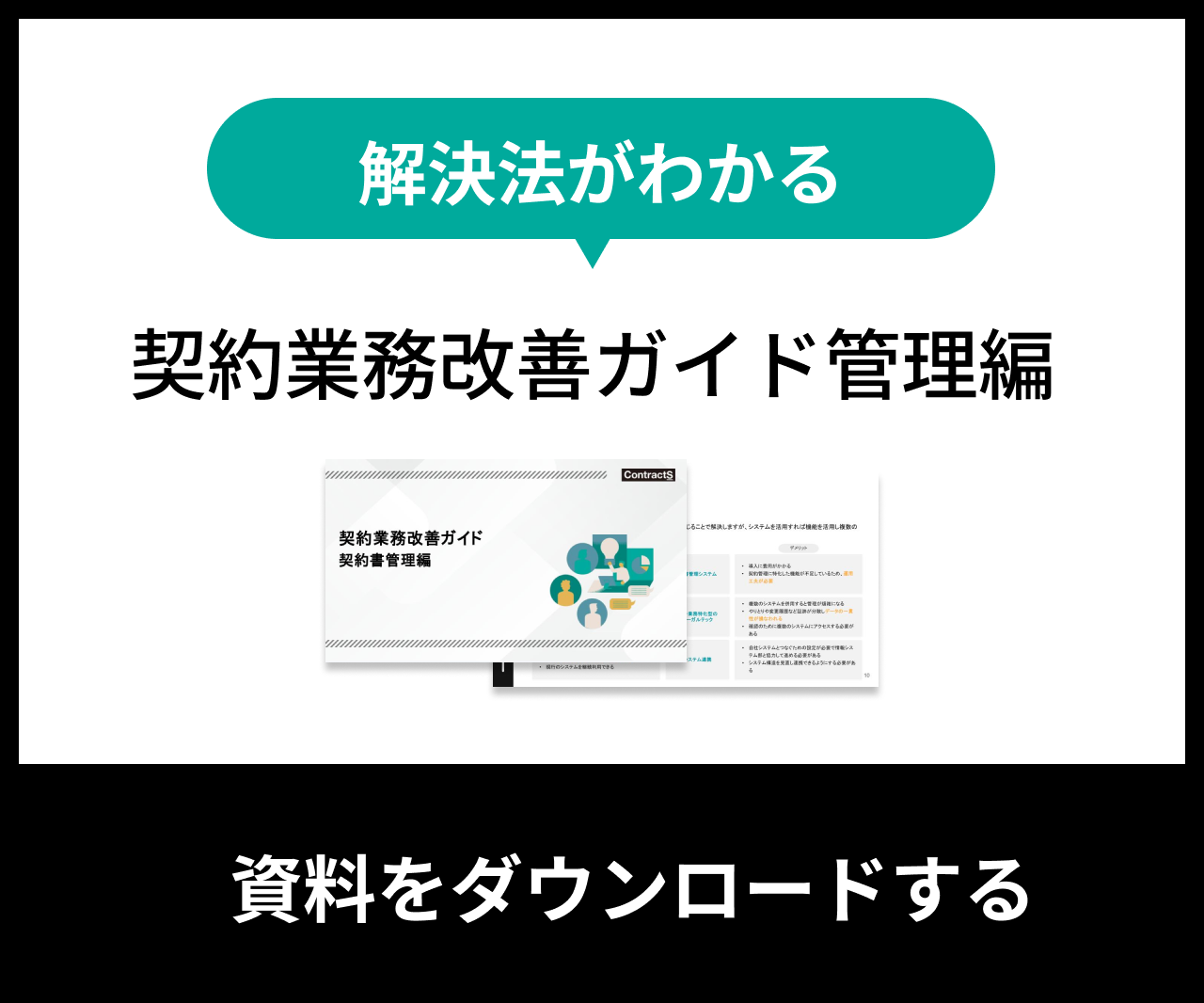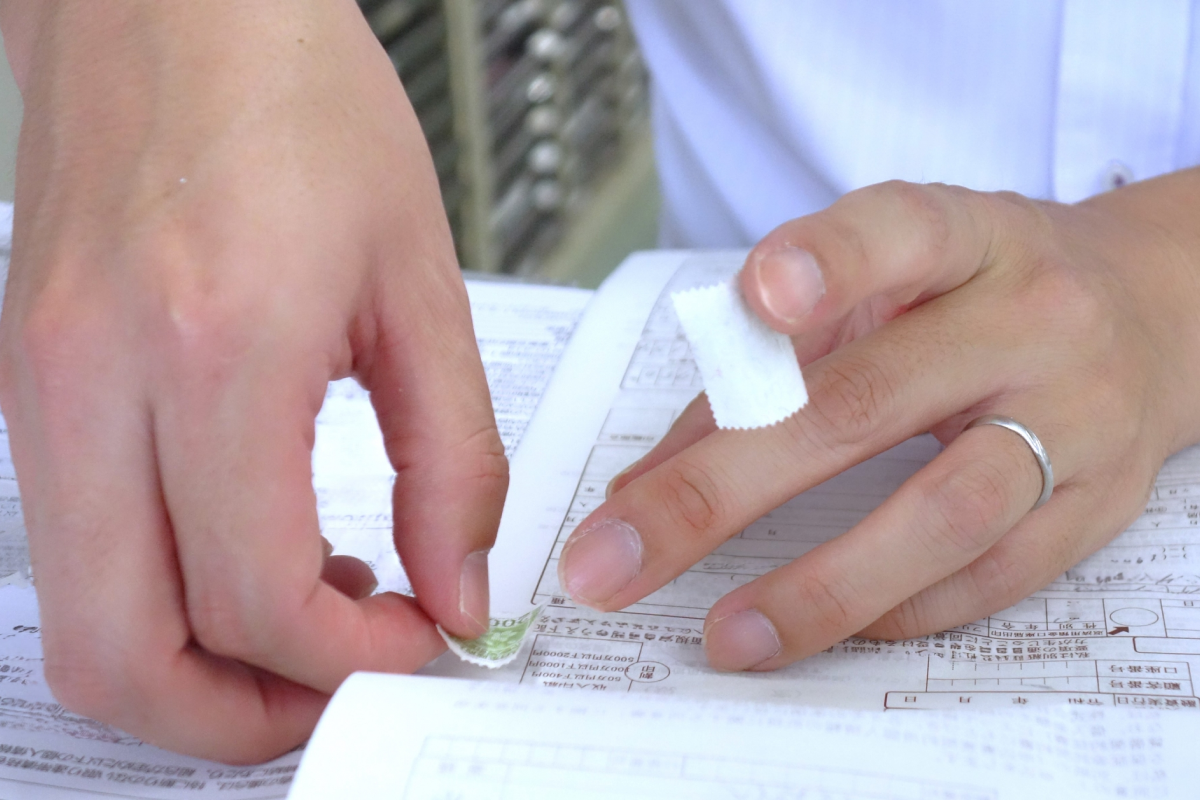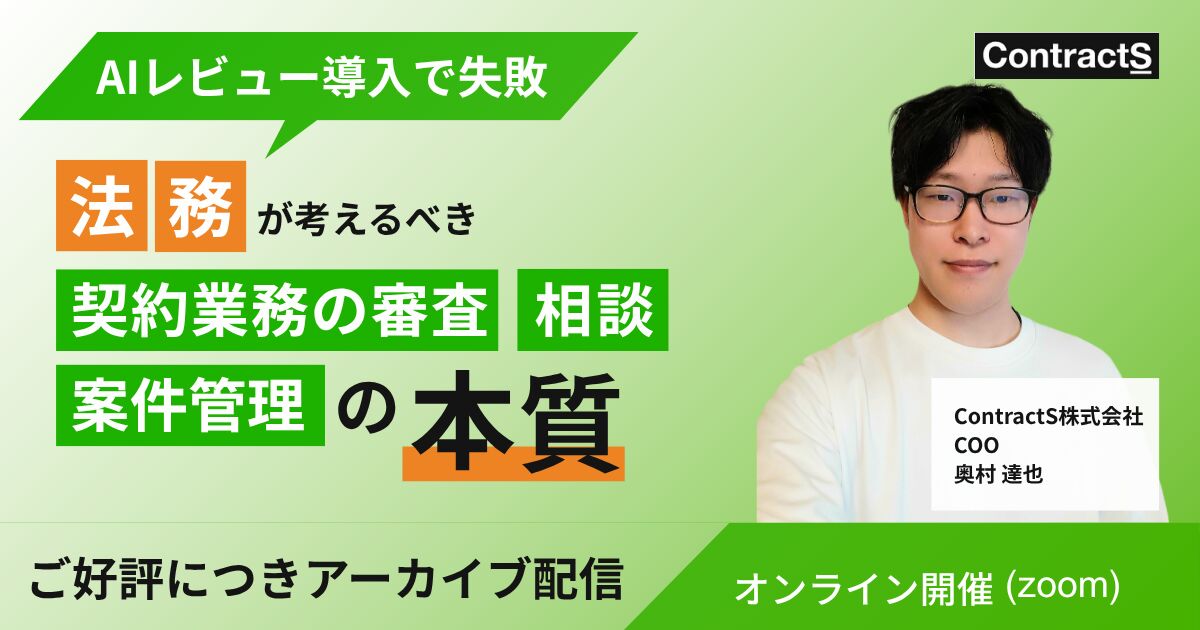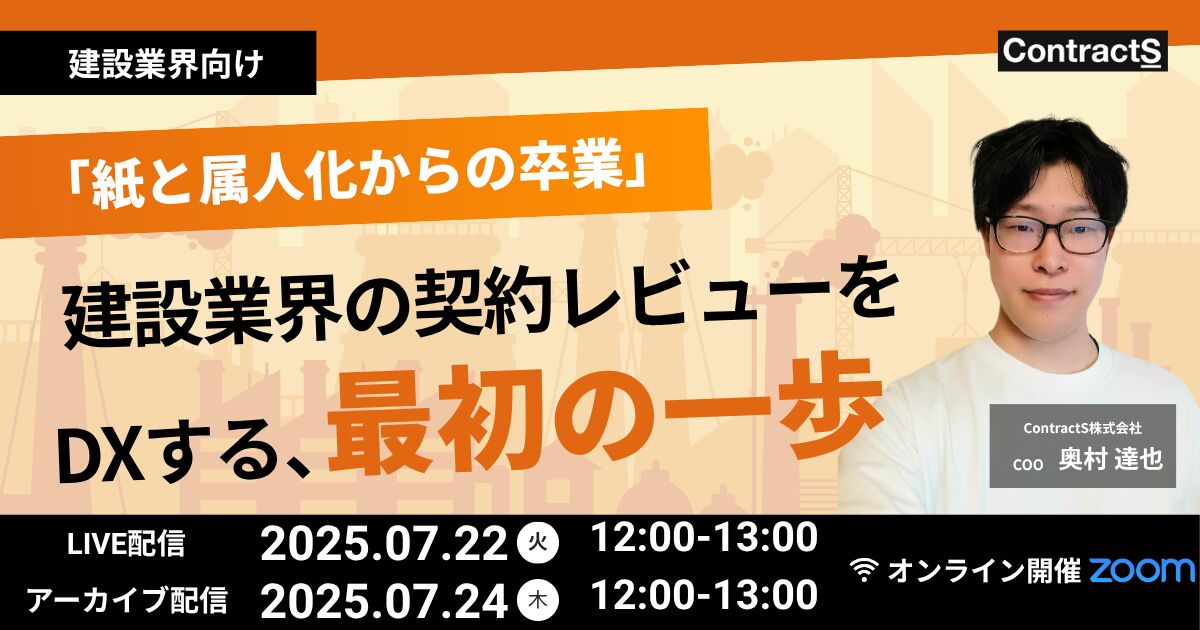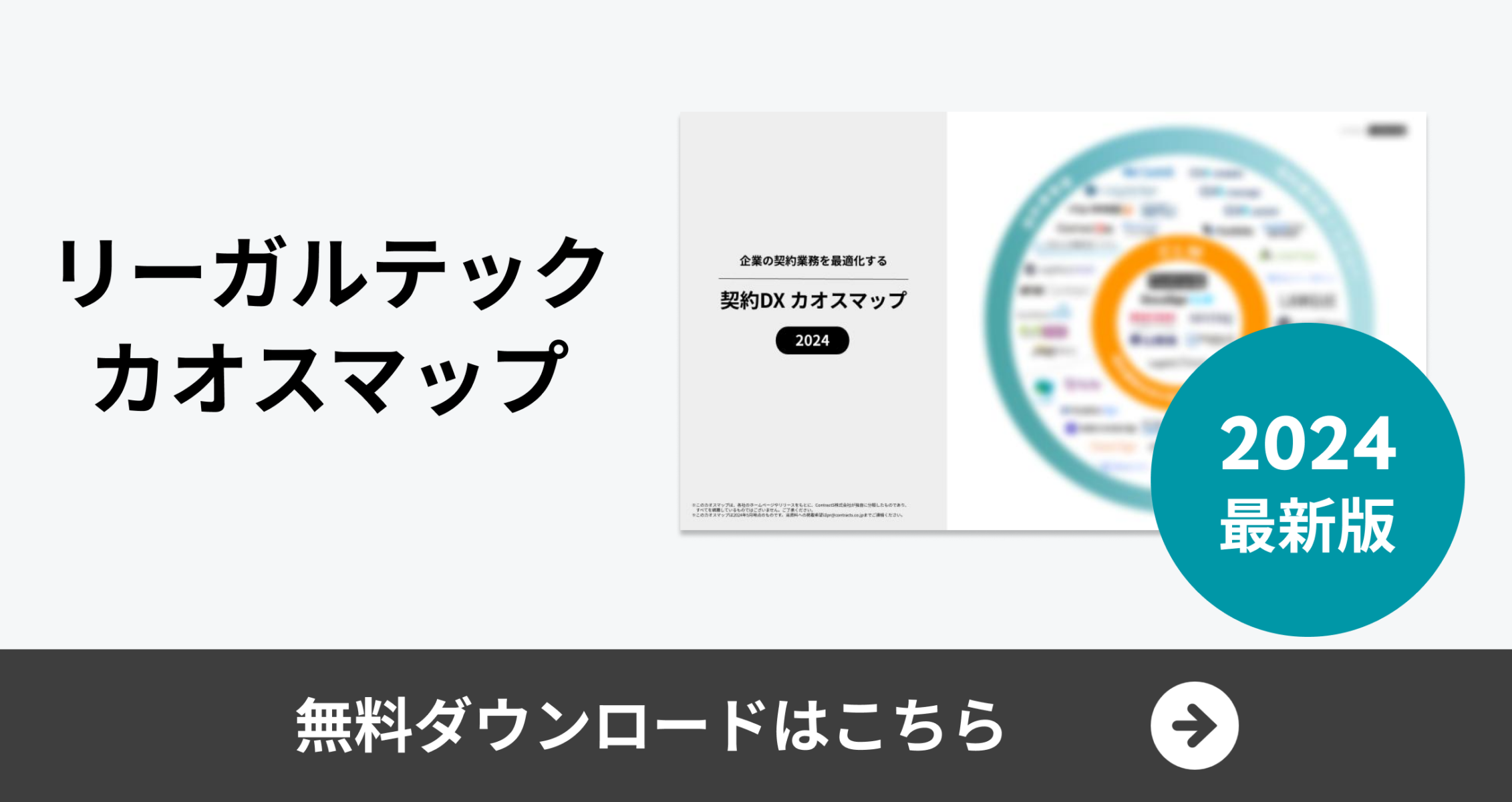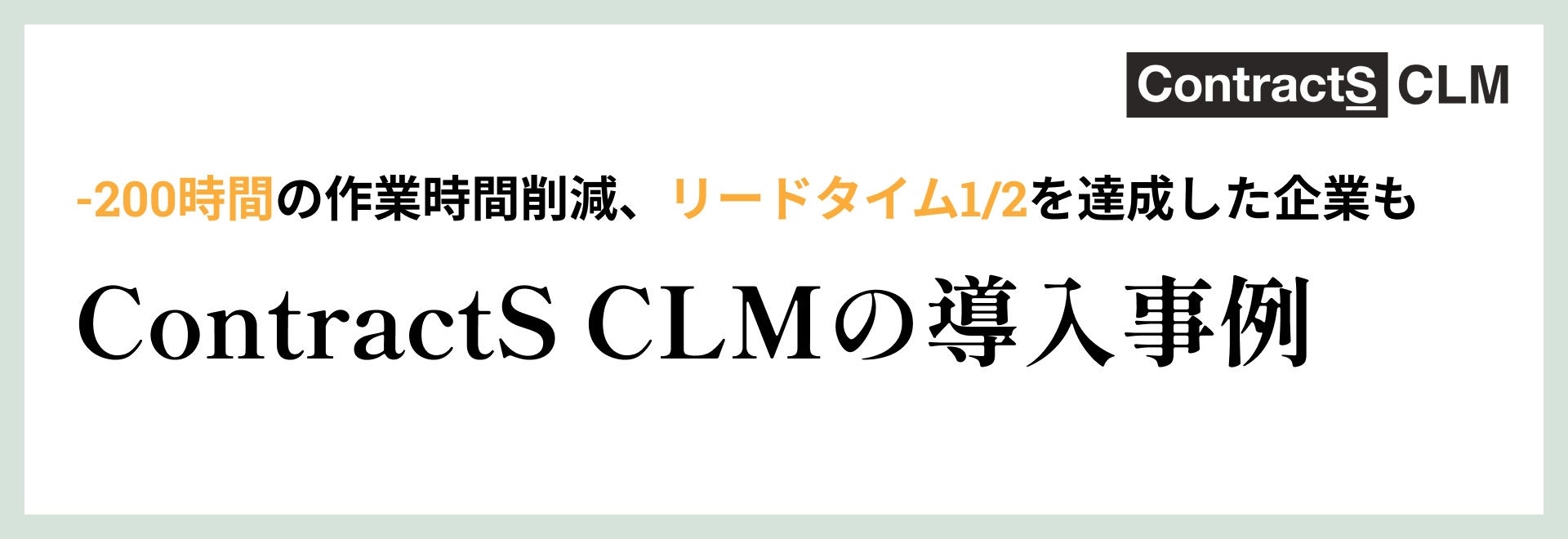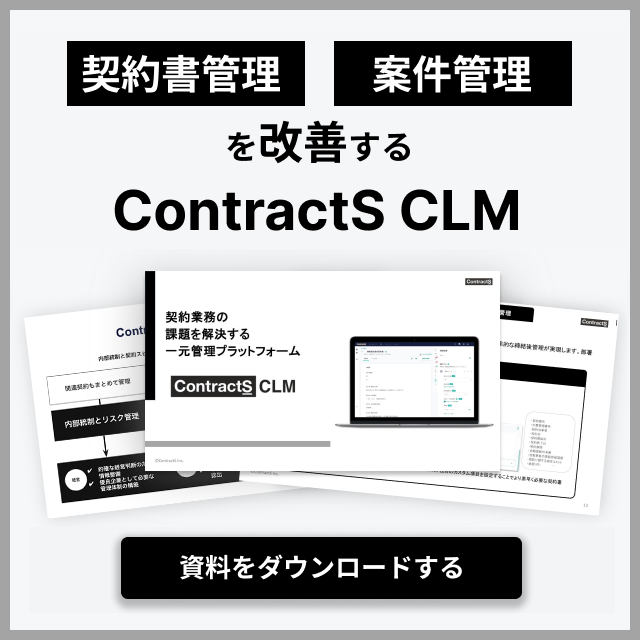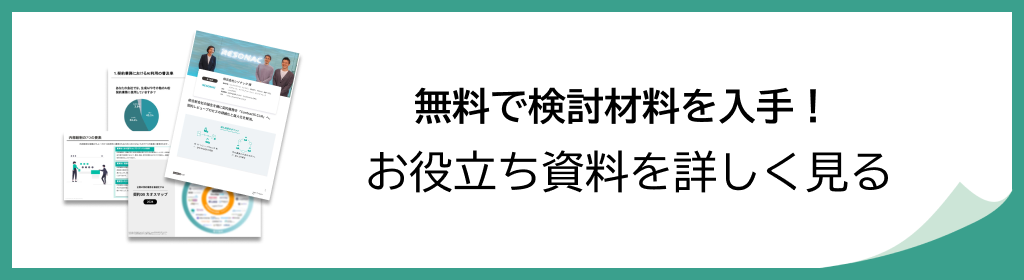ノウハウ 契約書の甲と乙とは?今さら聞けない契約書の基本!
更新日:2024年11月28日
投稿日:2021年08月16日
契約書の甲と乙とは?今さら聞けない契約書の基本!

日本で契約書を読んでいると、「○○○○(以下「甲」)」と「○○○○(以下「乙」)」は、次のとおり○○○○契約(以下「本契約」)を締結した。」というように、当事者のことを「甲」「乙」と略称していることが多いですよね。
日常生活では使わない「甲」や「乙」の表記に戸惑ってしまう法務の方も多いのではないでしょうか。契約書の「甲」や「乙」に関する基本事項をまとめました。
▶︎▶︎【無料ダウンロード】『5分でわかる契約書作成方法』はこちらこの資料で契約書作成方法の基礎を確認!
契約書の「甲」と「乙」とは?
結論からいうと、「甲」や「乙」には法的な意味はまったくありません。
最初に個人名や団体名などの正式名称を書いたら、その後は「甲」「乙」といった略称で記載して、毎回正式名称を書く手間を省いているだけなのです。
実は、「甲乙」である必要すらなく、「AB」や「アイ」でも構いません。
略称を使うと、会社が協力しあって共同制作する場合など、当事者が大勢登場するときも、「株式会社A社、株式会社B社、株式会社C社及び株式会社D社(以下総称して「出資者」という)」と書けば、その後にいちいち固有名詞を出さなくて済むので、大幅に労力を節約することができます。
「甲」と「乙」を使う場合、当事者が三者以上になる場合には、「丙」「丁」「戊」「己(き)」「庚(こう)」「辛(しん)」「壬(じん)」「癸(き)」という順番を使っていきます。これは干支の十干に由来するものです。
|
当事者 |
使う略称 |
|
2者 |
甲・乙 |
|
3者 |
甲・乙・丙 |
|
4者 |
甲・乙・丙・丁 |
|
5者 |
甲・乙・丙・丁・戊 |
契約書に甲乙を使うメリット
上で述べたように、略称を使うことで、契約書作成の煩雑さが軽減されます。
また、契約書全体の文字数を減らし、全体をシンプルな構造にできるというメリットもあります。契約書を読み慣れた法務の方にとっては、略称を使った方が読みやすいかもしれません。
さらに、一度作成した契約書をひな形化し、別の案件で再利用することができます。主語を書き換えなくて良いのは楽ですよね。
契約書に甲乙を使うデメリット
甲乙を使う場合、特に登場人物が増えると、関係性が複雑になり、しばしば混乱することがあります。誰が誰だかよくわからなくなって、いちいち最初のページに戻って確認しなくてはならない、というようなことも頻繁にあります。
最悪の場合、甲と乙を逆にしてしまう可能性も考えられます。契約条項の主語が逆になっては、致命的な損害を負いかねません。
慣習ですので、甲乙丙を使うことは構いませんが、書き間違いにはくれぐれも注意しましょう。
基本的には、お客様を甲、事業者を乙とすべき
甲と乙には、本来は上下関係の意味合いは含まれていません。したがって、契約書でも、甲乙の順番や上下について特に決まりはありません。
しかし、昔の成績表、等級・階級や「甲乙つけがたい」という言い回しから、なんとなく「甲の方が乙より偉い」という風潮があります。そのため、契約の相手によっては、甲を上位、乙を下位として捉える場合があります。
その点をったく気にせずに契約書を作成すると、契約書の表記一つで相手方を不快にさせてしまうかもしれません。
特に、ビジネスの場合は、お客様を甲として、事業者を乙とすることが多くあります。
また、不動産賃貸借契約書では貸主を甲、借主を乙としたり、業務委託契約では委託者を甲、受託者を乙とすることが多いようです。
大企業と規模が大きくない企業間の取引においては、大企業側が「甲」とされることが多いです。これは、大企業側が契約書を作成することが多いからです。
(契約書を作成する側の企業の方が、より自分の企業の利益になるように契約書を作成するため、契約の主導を取りやすいといえます。)
このように正確な決まりはないですが、迷ったときには、契約の相手を甲とするのが無難かもしれませんね。
甲乙以外にも契約書の類型によって異なる略称が使われる場合がある
甲乙のような記号的なものよりも、「売主」「買主」などある程度具体性のある略称の方が相手方にとってわかりやすくなります。
契約書の類型によって慣習的に使われている略称は異なります。
絶対的なものではありませんが、以下の表を参考にしてみてください。
| 契約書の類型 | 作成者(であることが多い) | |
| 秘密保持契約 | 開示当事者 | 受領当事者 |
| 取引基本契約書 | 売主・委託者・発注者 | 買主・受託者・サービス提供者 |
| 業務委託契約書 | 委託者 | 受託者 |
| 金銭消費貸借(融資)契約書 | 貸主 | 借主 |
| リース契約書 | 賃貸人 | 賃借人 |
| 売買(譲渡)契約書 | 売主・譲渡人 | 買主・譲渡人 |
| 供給(購買)契約書 | 売主・発注者 | 買主・サプライヤー |
| 賃貸借契約 | 賃貸人・オーナー | 賃借人・テナント |
| 工事請負契約書 | 発注者 | 受注者・請負人・工事業者 |
| ライセンス契約書 | ライセンサー・特許権者etc | ライセンシー |
| 代理店契約書 | 売主・サプライヤー・メーカー | 買主・販売店・代理店 |
| システム開発委託契約書 | 委託者・ベンダー | 受託者・ユーザー |
※原則として、契約書はどちらの当事者が作成しても構いません。
例外的に、法令により作成が義務付けられている契約書では、作成が義務付けられた当事者が作成しなければならない場合があります。
英文契約書では?
英文で作成される契約書では、当事者を甲乙のような単なる記号で記すことはまずありません。中国や台湾では使うこともあるようですが、英米ではあまり使われません。
売主ならSeller、買主ならBuyerといった表記がされることが多いです。他にも、開発者が登場したら、Developer、銀行ならBankとなります。
また、英文契約書に登場する用語に、Party,Partiesがあります。ここでは、(契約)当事者(ら)を指します。
主に、当事者両方を指すときにはthe Partiesと使ったり、他方当事者を指すときにはthe other partyと使ったりします。
なお、「第三者」を表現するときは、それが人(person)であろうと企業・法人(entity)であろうと、third partyと表記します。日本語の契約書における「丙」のことではないので、注意しましょう。
日本で作られた英文契約書には、「甲」「乙」の名残りで、Party A,Party BやFirst Party, Second Partyとしていることもあります。
まとめ
契約書の「甲」「乙」に関しての基本事項について説明してきました。
略称をうまく使いこなして、契約書を作成していけば、契約相手との関係性もより良好なものになるはずです。