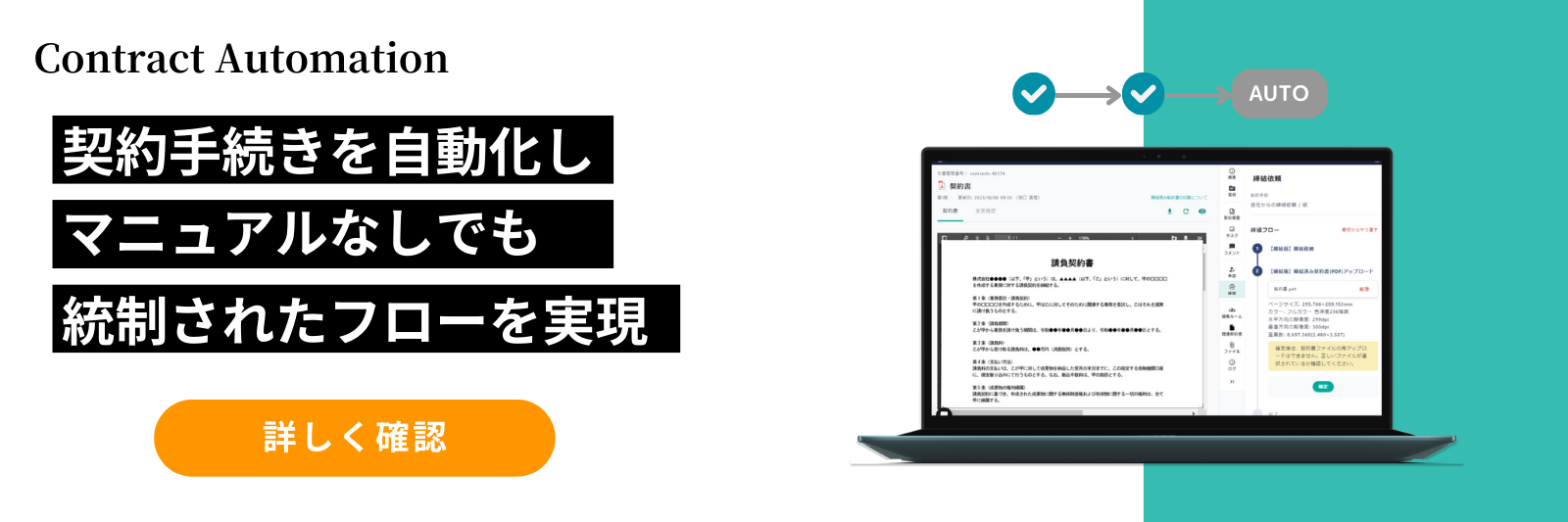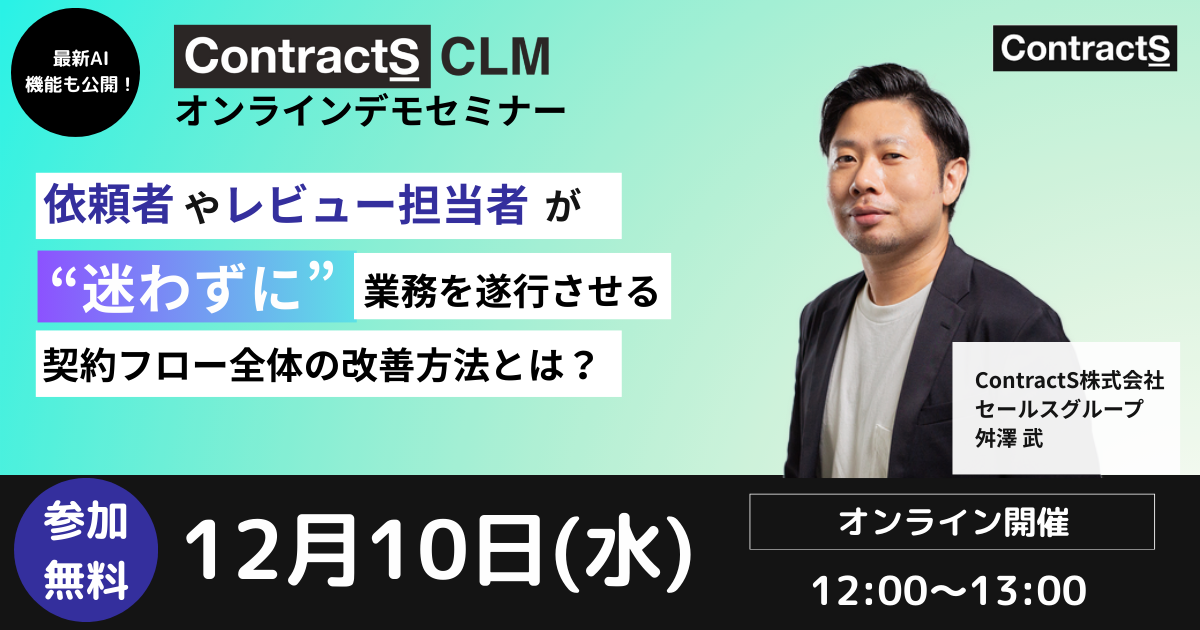ノウハウ 基礎からわかる反社チェック。一般的な方法からシステムを使った方法まで解説
更新日:2025年04月25日
投稿日:2021年07月30日
基礎からわかる反社チェック。一般的な方法からシステムを使った方法まで解説

企業にとってコーポレートガバナンス強化のために、企業にとって欠かせない反社チェック。仕組みを整備し、確実に進めるルールが企業内で明確に定められていることが多いものの、必要となっている背景や、実際に取引してしまった際どのように対処をしたらよいかあまり理解していない、というご担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、反社勢力の排除に取り組む企業の法務・コンプライアンス担当者向けに、反社チェックを行う背景や概要・調査方法について解説します。
反社チェックとは?
反社チェックとは、取引先や社員・株主など自社と関わる人物、団体、会社が「反社(反社会的勢力)」に該当しないか、または繋がっていないかどうかを調査することです。
詳細は後述しますが、企業にとって反社チェックは自社の信用確保や善管注意義務の遵守などの点で重要な取り組みです。
反社会的勢力の定義
反社会的勢力の定義については、政府・警視庁それぞれが提示しています。
政府(法務省)が示す反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法で経済的利益を追求する集団あるいは個人」としています。
暴力だけでなく、法を逸脱するような不当な要求(それに値する行為)を行う集団・個人も該当します。
参考:資料8 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について|法務省 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ
警視庁では、東京都暴力団排除条例にて「暴力団・暴力団員・暴力団関係者」などを反社会的勢力として定義づけています。
暴力団に属していなくても、暴力団・暴力団員と密接に関係する者も反社に該当します。
参考:東京都暴力団排除条例
したがって、企業が反社とみなされないためには暴力や法に反する行為はもちろんのこと、暴力団との接触や交際も避ける必要があります。
反社チェックの必要性
では、反社チェックはなぜ必要とされているのでしょうか。
実際に反社チェックを怠ると、どのような悪影響があるかを説明します。
会社の信用の失墜
反社との関わりによって生じる悪影響として、まず思い浮かぶのは、会社の信用問題ではないでしょうか。いわゆる「レピュテーションリスク」というものです。
今日においては、反社会的勢力と関わりがある、というだけで悪い印象を持たれてしまいます。
また、取引があることによって、反社会的勢力の資金源となっている可能性があります。「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(法務省)」でも、取引が適正か否かなど、内容問わず、反社会的勢力との取引遮断が求められています。
このように、国家機関を含めた国全体において、“反社会的勢力の排除”の風潮ができているため、気づかずに取引をしてしまったなどの些細な関わり合いでも、非常に悪い印象を世間に与えてしまうこととなります。
善管注意義務違反による責任追及
会社の取締役は、会社や第三者に対して任務懈怠責任(会社法423,429条)を負っています。その内容として、善管注意義務(会社法330条、民法644条)に違反すると上記責任が追及されることとなります。
善管注意義務とは、要は“取締役としてやるべきことをやっているか”という問題です。したがって、反社と関わりを持つことが法律に違反していなかったとしても、善管注意義務違反となることはあります。その結果、反社との関わりがあることをもって、この善管注意義務違反が認められ、損害賠償責任等を求められる可能性があるのです。
詳しく説明いたします。
現在、反社会的勢力と関わってはならないと規制していたり、反社との関わりによって罰則があったりする法律は存在しません(金融機関については銀行法26,27条によって業務停止命令や免許の取り消しがされる可能性があります)。例えば東京都の暴力団排除条例についても、①反社チェックの実施と②解除権を備えた反社条項の設定が努力義務とされるにとどまっています。
したがって、“反社との関わり”それ自体は法律違反ではないのです。
しかし、前述の通り、法律違反でなくとも、善管注意義務違反となることはあります。そして、善管注意義務違反か否かの判断において、各都道府県の暴力団排除条例や「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(法務省)」が参照されます。
例えば、上記指針には、「反社会的勢力による被害を防止するための基本原則」として下記のような事項があげられています。
- 組織としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
また、上述のように、暴力団排除条例には反社との関わりを断つことが努力義務として規定されています。
このような指針や条例を参照すれば、“反社との関わりを持つべきでないこと”は一目瞭然であるため、反社との関わりをもった場合には“取締役としてやるべきことをやっていない”として善管注意義務違反となるわけです。
営業停止リスク
上記のように、信用を失ったり役員が損害賠償請求を受けたりするだけならまだしも、“反社との関わり”によって会社存続の危機に陥る可能性もあります。
また、金融機関の場合、法律により厳しく規制されており、法的に処分される可能性もあります。以下、詳しくみていきます。
金融機関の場合
まず、金融機関の場合には、銀行法等により業務改善命令、業務停止命令、免許の取り消しといった処分が下る可能性があります。
実際に、平成25年9月27日に金融庁は、株式会社みずほ銀行に対して、以下の理由より業務改善命令を出しています。
①提携ローンにおいて、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜本的な対応を行っていなかったこと
②反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等
以下の参考条文を見ていただければわかるように、最大で免許の取り消しの処分まで用意されており、会社の存続に関わってくる問題といえます。
【参考:銀行法26〜28条】
(業務の停止等)
第二十六条 内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。(免許の取消し等)
第二十七条 内閣総理大臣は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第四条第一項の許を取り消すことができる。
第二十八条 内閣総理大臣は、前二条の規定により、銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第四条第一項の免許を取り消すことができる。
その他企業の場合
金融機関以外の場合にも反社との関わりがある会社であるとのレッテルを貼られてしまうと、その会社の取引先もまた、取引をすることで間接的に“反社との関わり”があると認識されてしまうリスクを負うことになります。当然その取引先としてもそのリスクを負いたくないので、会社は取引を停止されてしまったり新規取引を取り付けられなかったり、といったことが起こります。これが主要な取引先であった場合には、会社にとって死活問題になります。
また、金融機関は、前述のように反社会的勢力との関わりを厳しく規制されているので、反社との関わりがある会社に対して融資を停止するといったことも考えられます。これもまた、事業会社にとっては死活問題となります。
証券取引所の新規上場審査基準に抵触
会社の上場において、コンプライアンスリスクの低減は大切な観点であり、その一環として反社チェックは上場を目指す企業の基本ルールの一つになります。反社との関わりがあることにより、証券取引所が市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと認める場合、上場審査基準に抵触する可能性があります。
事実、上場申請時には反社会的勢力との取引排除のために、体制整備の上、その体制を証明する書類の提出が求められます。市場ごとに上場審査のガイドラインは異なるため、必要書類や実施項目などは都度専門会社と連携して、確実にパスできる方法を検討することをおすすめします。
反社会的勢力への資金源遮断に協力するため
先述した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、暴力団の資金源に打撃を与えることが重要な課題であると記されています。
反社が違法行為に利用する資金は、企業との取引で得ているケースも多いです。
取引により反社の違法行為を助長させないためにも、企業は反社と取引を含む一切の関係を持たないこと、資金提供は絶対に行わないことが求められています。
反社チェックが必要となった背景
そもそも反社チェックが徹底して企業で行われるようになった背景には前述の通り2007年に施行された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の制定にあります。
この指針は暴力団の排除は警察のみならず社会全体で取り組むべき課題としてとらえることで、根絶を狙う目的で制定され、その後都道府県の排除条例の制定につながっています。
法律ではなく条例であるものの、令和2年における 組織犯罪の情勢によると、暴力団構成員は2007年以降資金獲得活動は制定当時の2007年と比較すると大幅に減少傾向にあります。
参考:令和2年における 組織犯罪の情勢 警察庁組織犯罪対策部
反社チェックの対象範囲
企業が反社チェックを実施する対象は、大きく分けて以下の3通りです。
- 取引先
- 内部の人物
- 株主
取引先に関しては、主に企業そのものや役員だけでなく、その企業の大株主・顧問弁護士・顧問税理士といった重要な外部関係者も調査すべきです。
内部の人物は、自社の従業員や役員を指します。
従業員なら正社員・アルバイトを問わず調査する他、入社前の学生に対する調査も実施しましょう。
学生でも、SNSなどを通じて故意かどうかにかかわらず反社と繋がってしまうケースがあるからです。
自社の株主も、個人・企業・組織にかかわらず調査します。
株主が法人や組織の場合は、取引先と同様に重要な外部関係者も併せて確認しておきましょう。
反社チェックを実施すべきタイミング
取引先・内部の人物・株主それぞれに反社チェックを実施するタイミングは、以下の通りです。
|
対象 |
チェックのタイミング |
|
取引先 |
・新規の取引先:取引前 ・既存の取引先:一定期間(3年に1回以上) |
|
内部の人物 |
・従業員:入社前 ・役員:就任決定時 |
|
株主 |
株主を増やすとき、または変更するとき |
反社の動向は流動的であり、当初は問題がなかった人物も、後から反社とのつながりを持ってしまう可能性があります。
そのため、取引前・契約前・雇用前などのタイミングだけでなく、その後も定期的にチェックを実施しましょう。
反社チェックの方法
近年、準暴力団(半グレ集団)や周辺者の勢力の拡大、組織実態・活動様態の潜在化(組事務所で代紋を掲げないなど)、偽装解散・脱退、活動態様の偽装などにより、反社会的勢力の把握が難しくなっています。
そのため、調査は複数の項目を並行して行う必要があります。
一般的な調査方法
①反社条項を設定して反応を見る
まず、第一に対社内、対外部と締結する契約書面には、反社会的勢力との関係がないことを表明してもらう項目を必ず明記することをお勧めします。
例えば、前述の通り東京都暴力団排除条例では「暴力団排除に係る特約条項」を契約書に定めることが、努力義務として定められています。これは、反社であることが発覚した場合に契約を解除し関係を遮断するためのものです。したがって、このような条項に対して、排除や修正を求めてきた場合は反社である、ないし反社との関係があるとの疑いが生じるといえます。
また、類似の方法として、取引前に「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」を提出してもらうのも有効です。
②検索
検索エンジンでの検索と合わせて新聞記事や専用のデータベースを使い、複数の方法で横断的に検索をかけることで、調査が補完され実効性が高まります。
(例)
- インターネット検索:Google・Yahoo検索、RISK EYESなど
- 新聞記事データ検索:日経テレコン、G-Searchなど
- 反社会的勢力情報データベース検索:エス・ピー・ネットワーク社提供
(具体的な方法)
法人名や取締役などの役員、株主の氏名などを検索
インターネット検索では、法人名や取締役などの氏名に加え、「暴力団」「総会屋」「検挙」「摘発」などのネガティブワードをand検索することで、過去にあったトラブルが判明する場合があります。
インターネットでのキーワード検索時に使用すると良いネガティブワードの例を以下に列挙します。
*インターネットでのキーワード検索時に使用するネガティブワードの例
暴力団 総会屋 検挙 摘発
逮捕 違反 脱税 行政処分 行政指導
詐欺 不法 違法 被害 脅迫 恐喝
横領 漏洩 着服 粉飾 迷惑 不正 など
③企業情報の確認
商業登記情報をチェックすることで、不審な点を見つけられる場合もあります。登記は国税庁の「法人番号公表サイト」で取引先の登記情報を検索できます。
(具体的な方法)
- 頻繁に商号や本社所在地、役員などを変更していないか
- 業績や提供するサービスや商品に不審点はないか
商号等の変更が頻繁にされている企業は、反社勢力のフロント企業ではないか注意する必要があります。 - 本店所在地をインターネットで検索、実際に事務所へ足を運ぶ
立地や事務所の雰囲気が異様でないかをチェックする
④取引経緯や条件の再確認
取引を始めようとした流れを改めて確認し、不審な点がないか確認しましょう。直接契約しようとしている会社の反社チェックでは何も見つからなくても、取引に関わる人物や会社が反社であるといった場合もあります。
取引条件も重要です。世間の相場から大きく外れた破格の好条件である場合や、相手が契約を急いでいる場合などは入念なチェックが必要です。
反社チェックシステムを使う
反社チェックシステムとは、取引先などの法人や個人が反社との関係・繋がりがないかを検出できるシステムです。
搭載されている機能としては、以下のようなものがあります。
- データベースの検索機能
- 情報源や重要度などの条件で絞込検索する機能
- 証跡保存機能
- 外部システムとの連携
主に、対象の法律違反や犯罪の履歴、所属団体の役職といった情報を、官報・裁判例・新聞・ニュース・SNSなどから収集できます。
様々なデータベースから必要な情報を効率的に収集でき、手作業よりも抜け漏れやミスが起こりにくい点がメリットです。
怪しいと思ったら
怪しいと判断した場合には、より高度な調査が必要です。
①調査会社・興信所へ依頼
調査会社の調査方法は、官公庁情報や各種メディアの情報などの調査のほか、内偵調査まはでを含む詳細なものから、独自に構築した反社データベースを元に検索する簡単なものまでさまざまです。
専門調査機関に依頼する際は、実際にどのような内容の調査を行うか事前に確認し、費用などとともに検討する必要があります。
②行政機関に照会する
行政機関に問い合わせや相談を行うこともできます。
例えば、警視庁の組織犯罪対策第三課や、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターで相談が可能です。
行政機関では、情報開示に際して所定の書類を揃えることを要求される場合があります。例えば、確認したい相手の氏名、生年月日、可能であれば住所が分かる資料や、対象企業の登記事項証明書、「暴力団排除に係る特約条項」を定めた契約関係資料、反社の疑いがあると判断した資料などが考えられます。相談前に問い合わせ、必要書類を揃えておきましょう。
反社とわかったら
①社内で相談し、取引停止となる経緯を相手に伝えない
まずは直ちに情報を共有し、社内で相談の場を設ける必要があります。
2006年に改正が行われた会社法に基づき、大企業では内部監査室の設置が必須となっている関係上、このような問題が起きたときは「内部監査室」への連絡が適切になるでしょう。
前述した通り、反社会的勢力との取引は企業にとって多大なリスクを伴います。
発生してしまった原因調査、評価、報告の上、再発しないよう改善アクションについても具体的に取り決めする必要があります。
また、反社と判断して取引を止めるにしても、その詳細は相手方には伝えないことが重要です。反社チェックが理由であると伝えてしまえば、相手から反社出ない旨の根拠を提示するなど対抗策を講じられます。すると、判断が難しくなり、取引の停止などがしにくくなってしまう恐れがあります。
②弁護士・警察に相談
うまく対応ができないと判断した場合には、早めに専門家・行政機関に相談しましょう。
反社のフロント企業などであれば、弁護士からの内容証明郵便・受任通知だけで、取引から手を引いてもらえるなどの効果を発揮することもあります。
実際に、取引が開始されてしまった場合にも、受任通知のみで不当要求が止むなどの効果が見られたケースや不当要求禁止等の仮処分の申立ての成功事例も多数報告されています。
反社チェックの方法を選ぶ基準
反社チェックの方法は複数あり、どの方法を実施するかによってコストや精度が変わります。
そのため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが効率的かつ適切なリスク管理につながります。
反社チェック方法を選ぶ際、基準となるポイントが「取引に伴うリスク」や「上場か未上場か」です。
取引先が反社だった場合に被る損失・損害(リスク)を想定し、リスクが高い取引ならコストをかけても精度の高い方法でチェックすることが望ましいです。
一方で、取引が中~低程度なら効率性を重視してチェックツールを活用するといった手段をとっても良いでしょう。
また、日本取引所グループは反社による証券以上の濫用防止・証券市場の秩序維持と信頼向上を図るため、反社の排除に向けた企業行動規範などを定める「反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備について 」を公開しています。
上記の資料では、上場企業は反社による被害を防止するための社内体制の整備や、コーポレートガバナンスに関する報告書において「反社会的勢力排除に向けた体制整備」を開示することなどを行動規範として定めています。
上場企業はもちろん、上場準備中企業も日本取引所グループが提示する反社排除に向けた対応の内容を理解のうえ、より正確な反社チェックの実施が重要です。
契約書では反社との取引を防ぐ「反社条項」も重要
取引先との契約締結に用いる契約書では、反社チェック・排除の観点から「反社条項」を設けましょう。
反社条項とは、当事者が反社ではないこと、将来にわたって反社に該当しないことを示し確約するための条項です。
契約書の反社条項としては、以下のような項目を定めます。
- 反社に該当しないことの表明と確約
- 反社との関係性をもたないことの表明と確約
- 暴力的な要求行為等をしないことの確約
- 違反時は契約解除をできる旨
- 違反時の損害賠償について
内容にかかわらずすべての契約に反社条項を定め、反社とは一切の関わりを持たない・関わらせないことを表明しましょう。
まとめ
ここまで、反社チェックの重要性とその方法について言及してきました。
まずは、反社チェックを通して法的リスクの排除を試みるとともに、事務作業自体を効率的に進めるために様々な方法やツールを駆使することが重要です。