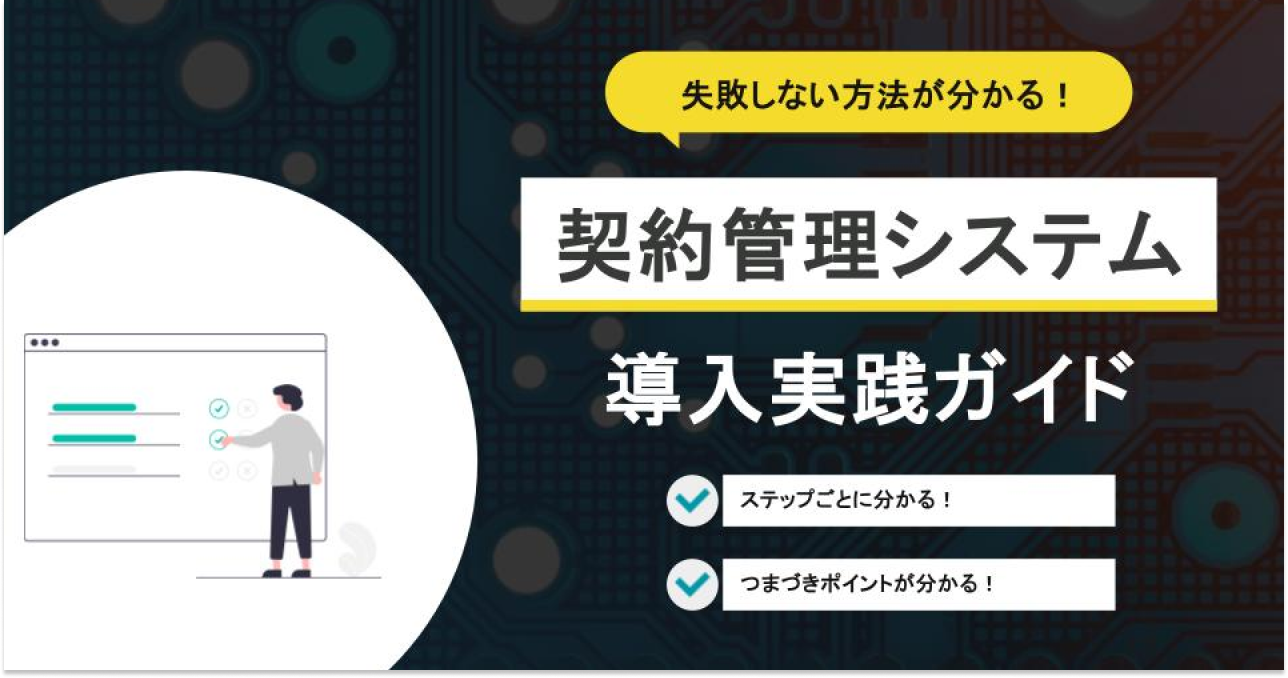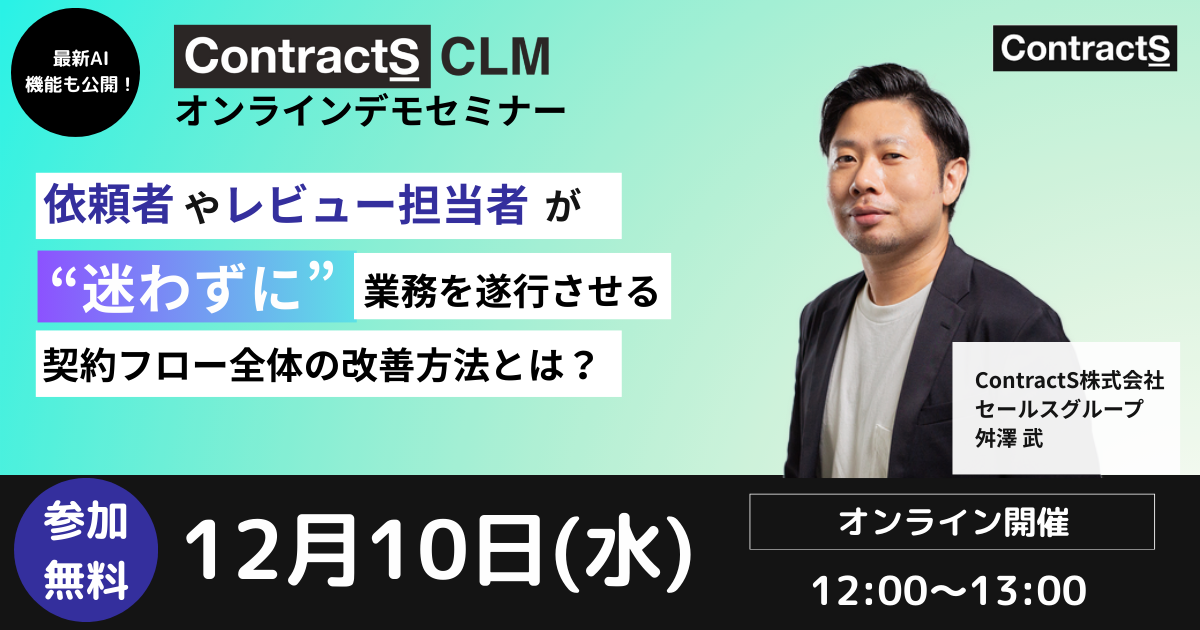ノウハウ 生産性向上とは?メリット・方法・施策・注意点をまとめました
更新日:2025年05月7日
投稿日:2020年10月30日
生産性向上とは?メリット・方法・施策・注意点をまとめました

「生産性向上」とは、業務の実施方法を改善し働く人の手間や時間を削減し、利益向上を目指す取り組みのことです。
近年、労働者不足や国際競争の激化などを背景に、今まで以上に企業に対して生産性向上が求められています。自社の競争力を高めるために、DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用も視野に入れながら生産性アップに取り組む企業も多いでしょう。
本記事では、生産性向上の施策で得られる4つの主なメリット、具体的な方法、進め方のコツや注意点、NG施策まで分かりやすく解説します。さらに、導入に役立つツールや企業の成功事例もご紹介。業種や規模を問わず、すぐに活用できるヒントが詰まった内容となっています。
▶︎【こちらの記事もおすすめ】デジタルトランスフォーメーションとは?DX推進に向けた法律改正も
生産性向上とは
生産性向上とは、労働・設備・原材料などの資源をより効率的に活用し、生産物や付加価値の増加を目指す取り組みを指します。企業や経済全体の競争力を高めるためには、生産性を高めることが不可欠です。
生産性を向上させるためには、まず現状の生産性を定量的に把握し、どの要素に改善の余地があるかを分析することが必要です。具体的な改善策として、業務プロセスの効率化、最新技術の導入、従業員のスキル向上などが挙げられます。
日本は、労働生産性の国際比較で遅れをとっていることが指摘されています。
労働生産性とは、労働者一人あたりがどれだけ生産したかを示す指標であり、日本生産性本部が2019年に発表した結果によると、日本の労働生産性は先進7カ国(アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス、カナダ、イタリア、日本)の中で最下位でした。これは、日本が他国と比べてリソースを有効活用しきれていないことを示しており、生産性向上の余地が大きいことを意味します。
生産性には主に「物的生産性」と「付加価値生産性」の2種類があります。それぞれの概念を理解し、適切に計測することで、自社の生産性向上のための具体的な施策を検討できます。
物的生産性
物的生産性とは、生産物の個数や量を基準として測定する生産性の指標です。製造業では特に重視され、工場の生産効率を評価する際に用いられます。
物的生産性の計算式
物的生産性は、以下の計算式で求められます。
物的生産性=生産量÷労働量
例えば、1時間あたり100個の製品を10人の労働者で生産した場合、物的生産性は「100(個) ÷ 10(人)=10個/時」となります。生産ラインの効率改善や設備投資などでこの値が高まれば、労働生産性が向上したと言えます。
付加価値生産性
付加価値生産性とは、企業が生み出した価値(付加価値)を基準として測定する生産性の指標です。経済全体の視点ではGDP(国内総生産)を用いた生産性の評価も行われます。
付加価値とは、売上高から原材料費や修繕費、人件費などのコストを差し引いた金額のことを指し、企業の収益性や経営効率を示す重要な指標となります。
付加価値生産性の計算式
付加価値生産性は、以下の計算式で求められます。
付加価値生産性=付加価値額÷労働量
例えば、企業が年間10億円の付加価値を100人の労働者で生み出した場合、付加価値生産性は「10(億円)÷100(人)= 1,000万円/人」となります。
付加価値生産性は、業務プロセスの改善やコスト削減による利益率の向上、他社との差別化を図れる付加価値額の高い商品開発などによって高めることができます。この値が高まったとき、生産性向上が実現されていると言えます。
生産性向上と業務効率化の違い
「生産性向上」と似た意味で使われる言葉に「業務効率化」があります。両者は関連性が深いものの、その意味合いは少し異なります。
生産性向上とは、投資に対して現在よりも多くの成果や生産量を得ることを指します。一方で業務効率化は、生産にかかる時間やコストの負担を最小限に抑えることを目的とした取り組みです。
業務効率化を進めることで、少ない投資でも生産量が増えるため、結果的に生産性の向上につながります。つまり、業務効率化は生産性向上を実現するための手段のひとつと考えることができます。
生産性向上が必要な理由
企業に生産性向上が必要とされる主な理由として、労働人口の減少と国際競争の激化が挙げられます。
それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。
労働人口の減少
まず、労働人口の減少による人手不足が挙げられます。国立社会保障・人口問題研究所の「出生中位(死亡中位)推計(平成29年推計)」によると、2017年に7,578万人だった生産年齢人口(15~64歳)が、2030年には6,875万人、2060年には4,793万人にまで減少すると予測されており、労働力不足をどう補うかが社会的な課題となっています。
参照:出生中位(死亡中位)推計(平成29年推計
日本全体における働き手の減少は、農業、製造業、サービス業などあらゆる業界で労働力の確保が難しくなることを意味しています。労働力を確保できずに倒産する人手不足倒産も急増しています。。外国人労働者の受け入れなどの対策が進められてはいるものの、こうした外部対策と並行して「一人あたりの生産性を高める」取り組みが不可欠です。
国際競争の激化
インターネットの普及により、ビジネスのグローバル化が急速に進んだことも、生産性向上が必要とされる理由のひとつです。
日本企業は海外市場へ進出しやすくなった一方で、海外企業にとっても日本市場への参入が容易になりました。その結果、国内外の企業が同じ市場で競い合う状況が生まれています。
しかしながら、日本は他の先進国と比べてITの活用が遅れており、業務の効率化も十分に進んでいないのが現状です。さらに、人件費や税制面では海外企業のほうが優位であることも多く、日本企業はこの競争に勝ち抜くために、より高い生産性を実現する必要があります。
生産性向上のメリット
生産性向上には、企業の経営基盤を強化し、持続的な成長を実現するためのさまざまなメリットがあります。特に、人手不足の解消やコスト削減、従業員満足度の向上など、企業が直面する課題を解決する4つの主要なメリットについて紹介します。
人手不足の解消
少子高齢化によって労働人口の減少が進む中、生産性向上は企業にとって不可欠な施策です。
業務プロセスの見直しやシステムの導入により、限られた労働者でも利益率の高いより多くの製品やサービスを生産できるようになります。特に、AIやロボティクスを活用した業務効率化は、労働力不足を緩和し、企業の競争力を高める手段となると考えられています。
また、業務を自動化することで、人にしかできない業務に人材を注力できるようになり、組織全体の生産性を向上させることが可能となります。
コスト削減
生産性向上は、企業のコスト削減にも直結します。業務効率化によって作業のムダを削減することで、人件費などのコストを抑えられます。その結果、設備やツールの予算を増やし、必要なタイミングで導入しやすくなるでしょう。
また、労働時間の短縮にもつながります。残業が減ることで残業代を抑えられるだけでなく、作業時間の短縮によって生まれた時間を、製品・サービスの付加価値向上のための業務に活用できるといったメリットもあります。
さらに、従業員の育成に時間を割きやすくなります。従業員のスキルアップが進むことで、さらなる生産性向上が期待できるでしょう。
従業員満足度の向上
生産性向上の取り組みは、従業員の働きやすさを高める要素でもあります。例えば、業務の効率化によって負担が軽減されると、長時間労働の削減やワークライフバランスの改善が期待できます。また、スキルアップ研修や教育制度を充実させることで、キャリア成長の機会が増え、モチベーション向上につながります。
さらに、業務改善によるコスト削減を福利厚生の充実に充てることで、働きやすい環境を整え、従業員の満足度向上と定着率の向上が期待できるでしょう。結果として、企業全体の生産性も向上し、良い循環が生まれます。
顧客満足度の向上
生産性が向上すると、より高品質な製品やサービスを効率的に提供できるようになります。これにより、納期の短縮や価格の最適化が可能となり、顧客満足度が向上します。
また、業務効率化によって生まれた余力を新たな商品開発やサービス向上に充てることで、他社との差別化を図ることもできます。
さらに、カスタマーサポートの質を向上させることで、迅速で的確な対応が可能になり、顧客の信頼が深まります。その結果、顧客一人ひとりのニーズに合ったサービスの提供につながり、満足度が向上します。
満足度の高い顧客は継続的にサービスを利用しやすく、口コミによる新規顧客の獲得にも貢献するため、企業の成長が期待できます。
生産性向上のための施策
労働者不足や国際競争の激化といった課題に対応するため、多くの企業が生産性向上の方法を検討しています。ここでは、生産性を向上させるために行う9つの対策についてご紹介します。
1.業務の「見える化」
生産性向上のために、まず取り組みたいのが業務の「見える化」です。アンケートやヒアリング、マニュアルの整備などを行い業務の流れや成果・コスト等の情報を可視化することで、次の効果が期待できます。
社員の意識向上
1つ目は、情報の共有による意識向上です。例えば製造現場で、原材料や人件費、営業利益などプロセスごとのコストを可視化したり、計画数と生産数をリアルタイムで表示したりすることで、コスト意識が向上し目標を達成しやすくなります。
業務の効率化
2つ目は、情報の伝達ミスを減らすことによる業務の効率化です。トヨタ自動車が開発した生産管理手法に「かんばん方式」があります。これは自動車部品が入った箱に作業指示書(かんばん)を付けておき、後工程の担当者が外したかんばんを見て必要な部品だけを生産するものです。これは必要な部品を必要なタイミングで、必要な量だけ作るための手法ですが、工程を可視化することにもつながります。担当者がひと目で必要な情報を把握できるため、伝達ミスが減り、効率的な生産が可能になります。
課題の発見と改善
3つ目は、課題の洗い出しです。可視化した業務フローを分析することで、どの部分がボトルネックになっているのか、または無駄・重複はどこかを明確にできます。
中には「前任者がこの方法で行っていたから現在も同じ方法で作業している」といったように見直しがされていない業務があり、それが業務進行のネックになっていることがあります。こうした課題を洗い出し、効率化に向けた対策や適切なツールの導入を進めることができます。
2.業務のムダをなくす
業務のムダとは、例えば複数の担当者が個別に同じような作業をしているケースや、不要な承認プロセス、手戻りの多い工程、時間がかかる非効率な手続きなどを指します。こうしたムダを放置していると、経営資源の浪費につながるだけでなく、業務に余計な負担がかかることになり、モチベーションの低下を招く恐れもあります。
業務のムダを見直すことで、業務効率の向上や時間の削減といった効果が期待できます。
まずは、前述のように業務を「可視化」し、どこにムダがあるかを洗い出します。その上で、以下のような改善策を講じていきます。
- バラバラに行われている作業の標準化とマニュアル化
- 定型業務の自動化
- 同じ内容の作業の集約
- 不要な作業の削除
例えば、備品の注文をExcelで管理している場合を考えてみましょう。業務の可視化を進める中で、入力ミスが頻発し、そのたびに修正が発生していることが判明したとします(=課題の発見)。
担当者にヒアリングしたところ、商品コードの入力ミスが原因で、発注担当者が依頼主に毎回確認しなければならない状況になっていることがわかりました(=原因の特定)。
そこで、Excelの入力セルに入力規則を設定し、桁数のミスを防ぐようにしたうえで、提出前に商品コードの再確認を促すメッセージを表示する仕組みに変更しました(=改善)。その結果、入力ミスが減り、発注担当者の確認や修正作業といったムダが削減されました。こうした小さな改善でも、長期的には大きな効果をもたらします。
なお、業務のムダを見つけるにはある程度の経験が必要です。一人で取り組むと見落としがちな部分も多いため、可能であればプロジェクトチームを組んで改善に取り組むのが望ましいでしょう。
「課題に対して何かツールが活用できないか」「顧客満足に影響しない業務は削減できないか」など、複数人でアイデアを出し合うことで、より効果的な改善策を導き出すことができます。特に、発生頻度が高い業務や、関係する担当者が多いプロセスから優先的に改善していくと、より大きな効果が得られやすくなります。
3.労働環境の改善
企業の生産性向上には、社員のエンゲージメントの向上が不可欠です。エンゲージメントとは、社員が企業や仕事に対して感じる愛着や意欲のことで、高いエンゲージメントを持つ社員は、自発的に業務へ取り組み、より良い成果を生み出します。
リモートワークやフレックスタイム制といった働き方の種類を増やす制度の導入や、評価基準を公開し公正さを示す評価制度、給与や各種手当といった待遇改善、コミュニケーション活性化など、働きやすい環境を整えることで労働意欲が向上し、生産性向上につながります。仕事にやりがいを感じ、働き方に満足してもらえるような体制づくりがエンゲージメントを高め、生産性向上につながります。
一方で、有給が取得しにくい環境や長時間労働などはモチベーション低下につながり、生産性が減少する要因になるので注意が必要です。
4.人材配置
適材適所という言葉があるように、強みを最大限に生かし、企業にとって最大の効果を得られるような人材配置の最適化を行うことが生産性向上につながります。
そのためには一人ひとりの特性を把握することが求められます。リーダーがヒアリングを行った上で、特性に合わせた役割分担を行うのもよいでしょう。一人ひとりの生産性が向上すると、ひいては組織全体の生産性も向上します。
一人ひとりの生産性が高まれば、結果として組織全体のパフォーマンスも向上します。逆に、人材配置が適切でないと、職務とのミスマッチが生じ、モチベーション低下やストレス増加を引き起こす可能性があります。優秀な人材の離職を防ぐためにも、適切な人材配置が不可欠です。
5.システム・ツールの導入
生産性の向上には、適切なシステム・ツールの導入も不可欠です。今まで手作業で行っていた業務を効率化・自動化することで、時間短縮と負担軽減が期待できます。
例えば、2017年ごろから導入が進みはじめたRPA(Robotic Process Automation)は、定型的な業務をプログラムが代行する仕組みで、交通費精算や基幹システムへのデータ転記作業など繰り返し発生する業務を自動化することで、人手不足の解消や人的リソースの確保にもつながります。
また、紙管理の注文情報をOCRでデジタルデータ化する、遠方のクライアントとの定例会議を訪問形式からビデオ会議に変更し、出張を削減するといったことも生産性向上に貢献します。
そのほか、AIやクラウドサービス、チャットボットなど、生産性向上に貢献するシステム・ツールが多く存在します。特に効率化しやすい定型的な業務、マニュアル化できる業務は、ツールによる自動化を検討するとよいでしょう。
6.アウトソーシング
生産性向上の推進にあたっては、直接売り上げに影響しない間接部門の業務などをアウトソースするのも有効な手段です。一見、コスト増加と思われがちですが、実際にはアウトソーシングによってコスト削減につながる場合も多くあります。担当者の業務引き継ぎや指導が不要になるほか、社員の負担軽減につながります。
最近ではBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)と呼ばれる、業務プロセスを一括して専門業者にアウトソーシングする企業も増加しています。例えば、コールセンター、経理、広報、ヘルプデスクなどのノンコア業務を外注することで、社内の限られた人的資源をコア業務に注力することが可能になります。専門企業に委託することで、自社で行うよりも専門的で質が高いサービスを受けることができる点もメリットです。
少人数のスタートアップでは、請求書作成や広報業務などをBPOに任せる企業が多く見られます。少数精鋭でコア業務に取り組むためにはアウトソーシング、BPOは有効な選択肢でしょう。
7.助成金・補助金の活用
生産性向上を目指す際には、助成金や補助金の活用も積極的に検討しましょう。ITツールや新たな設備の導入には一定の投資が必要となりますが、条件を満たせば国や地方自治体の支援を受けることができます。申請には手間がかかるものの、費用面の大きな支援となる場合があります。
例えばIT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)は、中小企業、小規模事業者等がソフトウェア、クラウド利用費等に使える補助金で、費用の半分、最大で450万円の補助があります。導入できるツールの種類も多く、請求業務効率化システム、販売管理システムなど生産性向上に役立つツールも多数あります。
そのほか、以下のような補助金があります。自社で申請可能かどうか確認してみてください。
【人材開発支援助成金】
厚生労働省による助成金で、専門スキル習得を支援するものです。認定を受けたコースを受講すると経費の最大45%、生産性の向上が認められる場合は最大60%が助成されます。
【業務改善助成金】
こちらも、厚生労働省による助成金で、中小企業、小規模事業者が生産性向上のために機械やPOSシステム等の設備を導入して事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合には、費用の最大4/5、生産性の要件を満たした場合には9/10が助成されます。
8.個人のスキルアップ
組織の生産性を向上させるためには、一人ひとりのスキル向上も効果的です。個人のスキル習熟度が上がれば、同じ時間でも出来る作業量は増加します。例えばExcelで関数やVBAを取得すれば今まで毎月同じ様式の集計とレポート作成を1時間かけて行っていたのを、プログラム作成によって毎月20分に削減することも可能です。
スキルアップを支援する制度として社内勉強会などの学習機会を定期的に提供するほか、専門資格取得に対して手当を出すなどインセンティブを与えるのも良い方法です。スキルアップできる環境づくりを整えることで、社員のモチベーションアップにも繋がります。
9.属人化の解消
属人化が進むと、業務の引き継ぎが難しくなり、担当者の不在時に業務が停滞するリスクが高まります。また、特定の方に業務が集中することで負担が偏り、結果として生産性の低下や離職リスクの増加につながる可能性があります。
属人化を解消するためには、業務の標準化やマニュアル整備が不可欠です。業務プロセスを見える化し、具体的な手順や判断基準をまとめることで、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになります。
さらに、組織全体で業務を分担できる環境を整えることも重要です。そのためには、教育・研修制度を充実させ、業務に必要な知識やスキルを複数のメンバーが習得できる仕組みを作ることが有効です。
例えば、業務に関する情報共有を定期的に実施することで、複数人が一つの業務を担当できるようになります。
また、タスク管理ツールやナレッジ共有システムなどデジタル技術を活用し、誰でも業務の進捗や手順を確認できるようにすることで、担当者が不在でも業務が滞りなく進む環境を整えることも可能です。
こうした取り組みにより、業務のブラックボックス化を防ぎ、属人化のリスクを軽減することができます。結果として、企業の生産性向上と業務の安定化につながります。
生産性向上の進め方
生産性向上を実現するためには、計画的かつ継続的な取り組みが必要です。以下の手順に沿って進めることで、業務の最適化と効率向上を図ることができます。
- 自社の現状の見える化
- 目標設定
- 改善施策の導入
- 効果測定と改善
- 継続的な改善
現状の見える化
まず自社の業務を可視化し、現状を正確に把握します。具体的には、担当者や担当部署、業務にかかる時間、方法を明確にし、どこに課題があるのかを分析します。
具体的には、業務の流れをフローチャートや業務マニュアルに落とし込むことで、非効率な工程や無駄な作業を発見しやすくなります。また、従業員1人あたりの生産量や付加価値、業務にかかる時間やコスト、成果物の質などを数値で可視化することで、生産性向上の妨げとなっている要因を客観的に分析できます。
さらに、聞き取り調査を行うことも、現場レベルでの課題を明らかにする有効な手段です。担当者の視点から改善すべき点や業務の重複、非効率なルールなどを把握することで、より具体的な課題を特定できます。
このように、多角的な視点から現状を分析することで、効果的な改善策を立案するための基盤を築くことができます。
目標の設定
生産性向上のためには、具体的な数値目標や指標を設定することが重要です。例えば、「電子契約サービスを導入し、承認までの期間を○日短縮する」といった明確な目標を立てることで、施策の方向性を定めやすくなります。
また、全ての業務をそのまま維持するのではなく、業務の優先順位を明確にし、取捨選択を行うことも必要です。利益や付加価値を生まない業務(ノンコア業務)に過度なリソースを割いていないかを見直し、不要な業務は削減・統合・アウトソーシングを検討することで、重要な業務に集中しやすくなります。
このように業務を整理することで、目標達成に向けた道筋が明確になり、より効率的な業務管理が可能になります。
改善施策の導入
設定した目標に基づき、具体的な改善施策を導入します。まず、業務の取捨選択を行い、不要な業務を削減・統合・自動化することで、業務プロセスの最適化を図ります。例えば、手作業が多く時間のかかる業務や、複数の部署で重複している業務は、優先的に効率化を検討すると良いでしょう。
基本的には、組織の生産性向上の目標や優先度に応じて進めますが、どの施策から着手すべきか迷った場合は、基本手順が参考になります。
- 個人のスキルアップ
- 属人化の解消
- 人材配置
- 労働環境の改善
- システム・ツールの導入
- 助成金・補助金の活用
効果測定と改善
施策を実施した後は、定期的にその効果を測定し、必要に応じて修正を加えることが重要です。そのために、KPI(重要業績指標)を設定し、数値データを基に評価を行います。
KPIとは、施策の成果を測るために設定する具体的な指標のことです。例えば、売り上げ・利益の増加率、作業時間の削減数、コスト削減率などがあります。
具体的な指標を設定することで、施策の効果を客観的に判断でき、どの施策が成果を上げているのか、どこを改善すべきかが明確になります。
また、数値データだけでなく、周りの方の意見を取り入れながら柔軟に施策を調整することも大切です。このように、数値データと現場の意見の両方を活用しながら、継続的に改善を進めることで、生産性向上の取り組みを効果的に推進することができます。
継続的な改善
生産性向上は、業務環境や市場の変化に対応しながら、常に最適な方法を模索することでより高い効果を得られます。
そのためには、PDCAサイクルを繰り返し回しながら、長期的に生産性向上を図ることが成功の鍵となります。具体的には、以下のような流れで改善を進めると効果的です。
- 計画(Plan): 現状を分析し、改善目標や具体的な施策を設定する
- 実行(Do):計画に基づいて施策を実施する
- 評価(Check):KPIや従業員のフィードバックをもとに成果を確認する
- 改善(Act):課題があれば施策を見直し、次のアクションにつなげる
このプロセスを定期的に繰り返すことで、一時的な成果にとどまらず、持続的に業務の効率化や生産性の向上を実現できます。また、企業全体で改善の意識を共有し、現場の声を積極的に取り入れることも、継続的な成長のために欠かせません。
生産性向上の注意点と避けたい3つの取り組み
生産性向上を目指す際、取り組み方を誤ると逆効果になってしまうことがあります。
特に、短期的な成果を求めるあまり、負担が増大し、かえって業務の効率が低下するケースも少なくありません。ここでは、生産性向上の取り組みの中で注意すべき3つの行動をご紹介します。
1.長時間労働・残業
長時間労働や残業は生産性を低下させる要因の1つです。労働時間が増加しても生産量が比例して増えるとは限らずむしろ時間とコストだけが増加して生産量は変わらないケースも見られます。1時間当たりの労働生産性は「生産量÷労働者数×労働時間」で表すことができるため、労働時間の増加は生産性の低下に直結します。
また、労働環境改善という点でも、長時間労働・残業は心身に負担をかけ、離職につながるため、健康を守るためにも、長時間労働をできるだけ避ける取り組みが必要です。
2.マルチタスク
マルチタスクとは、複数のシステムを同時並行して実行するコンピューターのことを指します。そこから転じて、複数の作業を同時に並行して行う働き方を指すようになりました。
一見、効率的に思えるマルチタスクですが、実は生産性を下げる原因となることが多いです。なぜなら、1つの作業に集中しにくいため、逆に効率が落ちてしまうためです。また、同時にさまざまな業務をするため「仕事が進んでいる」という感覚に陥りやすいのも難点です。生産性向上を意識するのであれば、ひとりに複数の業務を任せすぎないよう、業務の振り分けを工夫することが大切です。
3.個人の生産性を意識しすぎる
個人のスキルアップや生産性向上は、組織全体の生産性を高める上で重要です。しかし、個人の生産性にばかり意識を向けると組織よりも自分を優先してしまい、逆に全体の生産性が低下する恐れがあることに注意が必要です。
それらを避けるためには、業務の見える化によって組織内の目標やチーム内のタスク配分などを情報共有することが効果的です。管理者が上手にマネジメントしてメンバー間で連携させることで、より良い成果が得られやすくなります。
生産性向上のポイント
生産性向上を目指すうえで重要なのは、単なる業務効率化にとどまらず、企業の方針や業務の実態に合わせた取り組みを継続的に行うことです。ここでは、生産性向上を成功させるために押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。
目的と目標を明確にして進める
生産性向上に取り組む際は、まず「なぜそれを行うのか」という目的と、「どこまで達成したいか」という目標を明確にすることが重要です。目的や目標が曖昧なままだと、施策の方向性がぶれてしまい、現場の混乱や非効率を招く可能性があります。
また、「生産性」と一口に言っても、企業の課題や置かれている状況によって、その定義や目指す方向は異なります。例えば、労働者の負担軽減を目的とする企業であれば、「時間外労働を月○時間削減」「業務量を○%削減」といった数値目標が考えられます。
一方で、小売業などにおいてコスト削減を重視する場合は、「在庫管理の見直しによって保管コストを○%削減する」といった目標が適しているでしょう。
このように、自社の課題や業種特性に即した目的と目標を設定することで、施策の方向性が明確になり、組織全体で一体感を持って取り組むことができるようになります。
自社の理念と事業コンセプトを意識する
生産性向上を図る上で、自社がどのような理念を持ち、何を目指しているのかという根本的な方向性を確認することが重要です。
まず、自社がどんな目的で存在しているのかを明らかにしましょう。提供している商品やサービスが社会や顧客にとって持っている価値をいま一度見つめ直すことで、生産性向上の取り組みにも、ブレのない判断軸ができ、自社の目的に沿った進め方が可能になります。
そのうえで、事業コンセプトの整理も欠かせません。たとえば「誰に(ターゲット)」・「何を(商品やサービスの価値)」・「どのように(提供手段)」を明確にすることで、業務プロセス全体の一貫性が生まれ、無駄のない改善が可能になります。
こうした視点を取り入れることで、単なる効率化に終始せず、企業の理念と合致した、持続可能な取り組みができます。
適切な情報共有
生産性向上は、特定の部門だけで完結するものではなく、組織全体が連携して取り組むことが重要です。そのためには、施策の目的や進捗状況、得られた成果などを関係者同士で共有することが欠かせません。
情報共有が不十分なままだと、業務が属人化しやすくなります。属人化が進むと、担当者が不明確になり、同じ業務に複数人が重複して取り組んでしまうなど、ムダな工数や混乱が発生する可能性もあります。
こうした状況を防ぎ、効率化を図ることで、組織全体で成果を出せる体制を整えることができます。それが、継続的な改善にもつながっていきます。
トライアンドエラーを恐れない
生産性向上は、すぐに結果が出るものではありません。また、他社で成功した施策をそのまま自社に導入しても、同じような効果が得られるとは限らないのが現実です。実際に取り組んでみなければ、どの施策が自社に合っているかは分からないことも多いでしょう。
だからこそ、初めから完璧を目指すのではなく、PDCAサイクルのように小さな改善を積み重ねながら、柔軟に調整していくことが重要です。そうした環境や仕組みを整えることで、最終的な成果へとつながっていきます。
長期的な視点で実施する
生産性向上に取り組む際には、新しい設備やシステムの導入、研修の実施、マニュアルの整備など、コストや時間をかけた取り組みが思うような成果に結びつかないこともあります。
しかし、生産性向上は一過性の施策ではなく、継続的に取り組むべき長期的なテーマです。PDCAサイクルを意識して、定期的な見直しと改善を重ねていくことで、時間はかかっても着実に効果が現れてきます。
長年続けてきたワークフローに慣れていると、新しいやり方に抵抗を感じることもあるかもしれません。それでも時代に合わせた手法を取り入れることは、生産性を高める上で欠かせない一歩となります。
生産性向上に役立つツール
企業の生産性を向上するためには、各種ツールを上手に活用するとより効果的です。ツールの提供形態は自社でサーバーを構築するオンプレミス型と、インターネット上で利用するクラウド型に分かれます。最近では、導入時のハードルの低さや他システムとの連携の容易さなどから最近はクラウド型が主流となっています。ここでは生産性向上に役立つ7つのツールをご紹介します。
グループウェア
グループウェアとは、ビジネスを円滑に進めることを目的として提供される情報共有やコミュニケーション、スケジュール管理といった機能を搭載したソフトウェアのことです。サイボウズ Office(サイボウズ)、Google Workspace(旧称G Suite)(Google)、Microsoft365(Microsoft)などがよく知られています。
主な機能は、掲示板、スケジュール共有、ファイル共有、設備・備品管理、Webメールなどです。グループウェアを導入することで、リアルタイムでの情報共有やデータの一元管理ができるようになり、業務がより円滑に進められます。
時間管理ツール
時間管理ツールとは、プロセスにかかる時間を計測してタスクごとの作業時間を可視化するツールです。タイムトラッキングツールとも呼びます。
管理者側では、プロジェクトごと、社員ごとに集計してグラフ化できるため、どれくらいの作業時間がかかったのかが把握しやすくなります。社員側では、毎日タスクにかかる時間を管理することで、時間を意識しながら作業できるようになるほか、比較ができるためムダな時間の見直しにもなります。
さらに集中力アップ効果のほか、タスク単位で時間を計測する習慣をつけることでマルチタスク抑制効果も期待できます。TimeCrowd(タイムクラウド)、Toggl(TogglOÜ)などがあります。
タスク管理ツール
タスク管理ツールとは、プロジェクトを円滑に実施する目的で導入されるツールです。誰がどの作業(タスク)を担当しているか、内容、進捗状況、納期などを管理・可視化します。前述の時間管理ツールがタスクごとの時間を管理するのに対して、タスク管理ツールはプロジェクト内のタスクを管理します。社員の作業進捗状況が一元管理できるほか、チーム間での作業内容共有にもなります。Asana(Asana)、Trello(Atlassian)などが良く知られています。
タスク管理だけでなく、プロジェクト管理機能や分析機能を備えたツールもあるので自社のニーズに合わせて適したツールを選定するとよいでしょう。
コミュニケーションツール
ビジネスチャットが代表例で、テレワークをきっかけに導入したという企業も少なくありません。Slack(Slack Technologies)、Chatwork(Chatwork)などが良く知られています。
リアルタイムでやりとりができ、チーム間でメッセージを共有できるのが特徴です。多くのサービスがビジネス向けに暗号化、ログ管理、権限管理などの機能を備えているので、自宅やサテライトオフィスなどでも安全に利用できます。社内コミュニケーションが活性化すれば、業務上の伝達ミスを防ぐとともに、社内全体の生産性の向上につながります。
ビデオ会議ツール
ビデオ会議ツールとは、PCやスマホ経由でインターネットに接続することで遠隔地にいる相手と動画や音声で通話できるツールです。Web会議ツールとも呼ばれます。2020年に入り、新型コロナウイルスの影響による外出制限や企業のテレワーク推進により導入が激増。2019年末には40%あまりだった利用者が、2020年4月末には60%以上に急上昇しました。
(参照:https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=420)
インターネット環境があればどこでも利用できるのがメリットです。Zoom(Zoom)、Microsoft Teams(Microsoft)、Meet(Google)などが良く知られています。
ビデオ会議ツールを活用することで会議の移動時間や日程調整の手間を省くことができ、業務効率化に役立ちます。また見込み顧客獲得のためのウェビナーツールとして活用する企業も増えており、営業ツールとしての役割も果たしています。
営業支援システム
営業支援システムとは、営業の効率化を目的としたデータ管理・分析ツールです。顧客管理、見積・請求書の作成支援、営業活動の分析や報告書の自動作成などが可能で、Salesforce や eセールスマネージャー などが代表的です。
営業支援システムの導入により営業活動が可視化されるのが最大のメリットで、顧客データや営業の進捗など営業状況が共有できます。ままた、外出先からでもデータ入力ができるため、訪問先から直帰できるようになり、営業担当者の労働時間削減にもつながります。さらに分析機能によって効率的に売上拡大、新規顧客獲得などの効果が期待できます。
電子契約システム
電子契約システムとは、従来、紙で交わしていた契約書をインターネット経由でデジタル化し締結できるシステムです。電子契約システムは、クラウドサイン(弁護士ドットコム))などが有名です。
テレワーク推進に伴い、紙での契約書のやりとりや押印などを電子契約システムに置き換えようという動きが浸透しました。電子契約システムを導入することで、クラウド上での契約書データ一元管理ができるメリットのほか、契約期間締結の短縮化、ペーパーレス実現による契約書の郵送やファイリングが不要になるといった業務効率化が期待できます。
ツール導入時に確認すべき3つのポイント
前項で紹介したような各種ツールを自社で導入する際に、失敗を防ぐにはどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。ここでは、ツールを選定する上で確認しておきたい3つのポイントを説明します。
自社のニーズに合っているか
1つ目は、自社の課題に合わせてツールを選定することです。知名度やイメージだけで選んでしまうと、期待した効果が得られない場合があります。
まず自社の業務フローを可視化して現状や課題を把握した後で、その課題解決につながる機能を備えたツールを選定します。例えば、自社の課題が「社内で業務連絡ミスが頻発する」、「部門間の情報共有がうまくいかない」ことであれば、リアルタイムで情報共有ができるコミュニケーションツールの導入が効果的です。さらに自社のニーズに合わせて役職ごとに閲覧権限を設定できるなど、自社に合った細かな機能も確認しましょう。
特に、業務上でボトルネックとなっている部分を解消できるツールを導入できると、大きな生産性向上が期待できます。
使いやすいツールか
2つ目は、使いやすいツールを選ぶことです。どんなに高機能なツールでも、使いこなせなければ効果を発揮できません。また、マニュアルや研修などの回数がかさみ、コストが増えてしまう可能性もあります。トライアルなどで実際に試してもらうなど、慎重にツール選定を行うことが重要です。
さらに、ツール導入後も操作知識を持った部門やスタッフが、不慣れな社員をサポートできるような体制づくりを整えておくと安心です。
スモールテストができるか
3つ目は、テスト運用ができるツールを選ぶことです。多くのツールでは、無料使用期間を設定しており、実際に勝手や満足度を確認することができます。試してみないと分からない部分もあるため、まずトライアル期間で様子を見てから、導入を決めましょう。
今回ご紹介した3点のほかに、他ツールとの連携や拡張性についても確認しておくと安心です。また全てのツールに共通することですが、データを一元管理できるようになることで、データ分析ができるようになるというメリットも生まれます。それをふまえてツールを導入する際には、独自データでなくCSVなど汎用性が高いデータで出力できるかなどについても確認しておくと良いでしょう。
生産性向上を実現した企業の事例
システム導入によって生産性の向上を実現した2つの企業の事例をご紹介します。
それぞれの企業が抱えていた課題や導入の背景、そして得られた効果を通して、自社に活かせるヒントを探ってみましょう。
紙ベースの契約管理から脱却し、業務の見える化と標準化を実現した事例

株式会社第四北越ITソリューションズでは、月間約100件の紙ベースの契約書に対してのマンパワーや業務体制を不足を解消するために「ContractS CLM」を導入、契約前後のプロセスを一気通貫で管理することで業務効率を改善しました。
導入後は、100万円を超える契約から順次ContractS CLMに移行。
契約業務のDXが進んだことで、申請から問い合わせまでの紙でのやり取りによる修正や差し戻しのタイムロスが解消し、システム上にやり取りやコメントがナレッジとして蓄積されることで、状況に応じた対処法のナレッジマネジメントも可能になっています。
続きを読む>> 契約フローの見える化で契約スピードの改善&ナレッジ蓄積に成功
分散した契約情報を一元管理し、リードタイムと工数を大幅削減した事例
全研本社株式会社では、上場や事業拡大に伴って法務業務が急増しました。契約書や関連情報は、チャットツール、社内サーバー、稟議システム、電子契約システム、台帳など、複数の場所に分散して管理されており、情報の二重管理や進捗状況の把握が困難であることが大きな課題となっていました。
また、契約書のバージョン管理や押印稟議との突合せ、電子契約システム上での二重稟議など、非効率な業務も慢性化していました。
これらの課題を解消し、法務業務の属人化や契約フローの非効率を改善するために、契約業務を一元管理できるシステムの導入が急務となりました。比較検討を経て、契約の全工程と関連情報を一元管理できる「ContractS CLM」の導入を決定しました。
このシステムは、事業部の担当者が契約業務の主体となり、法務部門と最新の契約書を共有しながら、やりとりやタスクをひとつの流れとして管理できる点が高く評価されました。
導入後は、すべての契約業務がContractS CLMに集約され、誰でも最新の情報にアクセス可能となりました。契約の進捗がひと目で分かるようになったことで、契約締結までのリードタイムが大幅に短縮され、業務の停滞も解消されています。
さらに、契約書の最新版管理や台帳管理なども効率化され、契約1通あたり約30分の業務時間を削減。結果として、契約業務にかかる時間は年間でおよそ420時間の削減につながるなど、大きな業務効率化を実現しています。