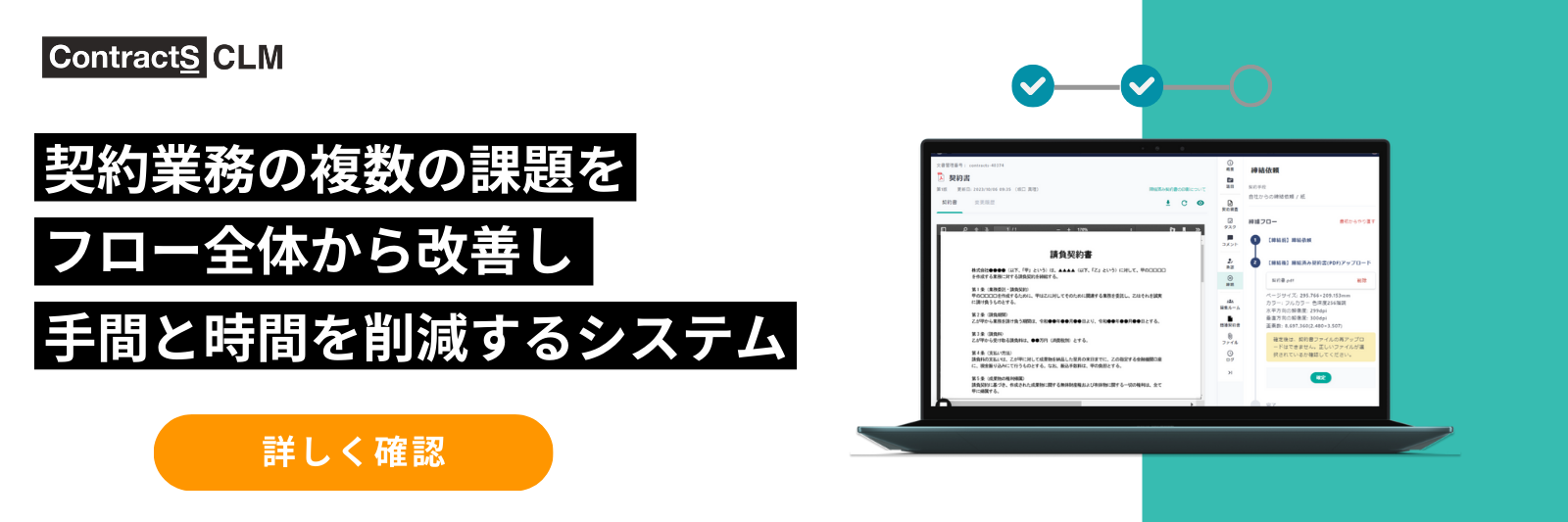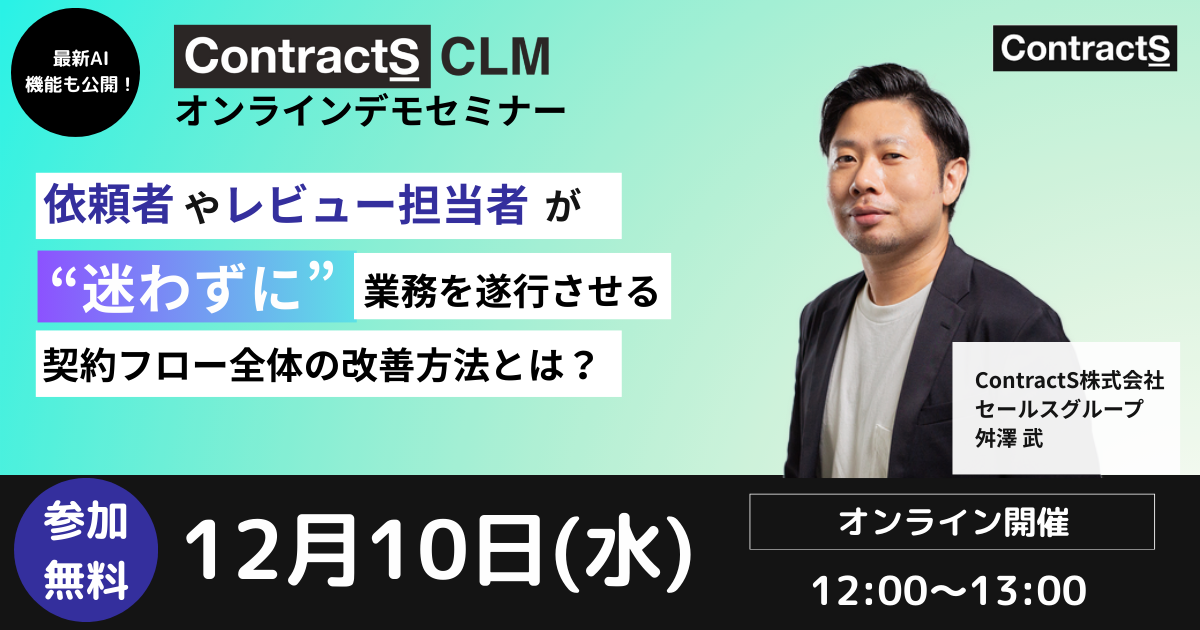ノウハウ 業務プロセスの課題を解決するには?運用改善のステップとポイント
更新日:2025年02月4日
投稿日:2024年10月17日
業務プロセスの課題を解決するには?運用改善のステップとポイント
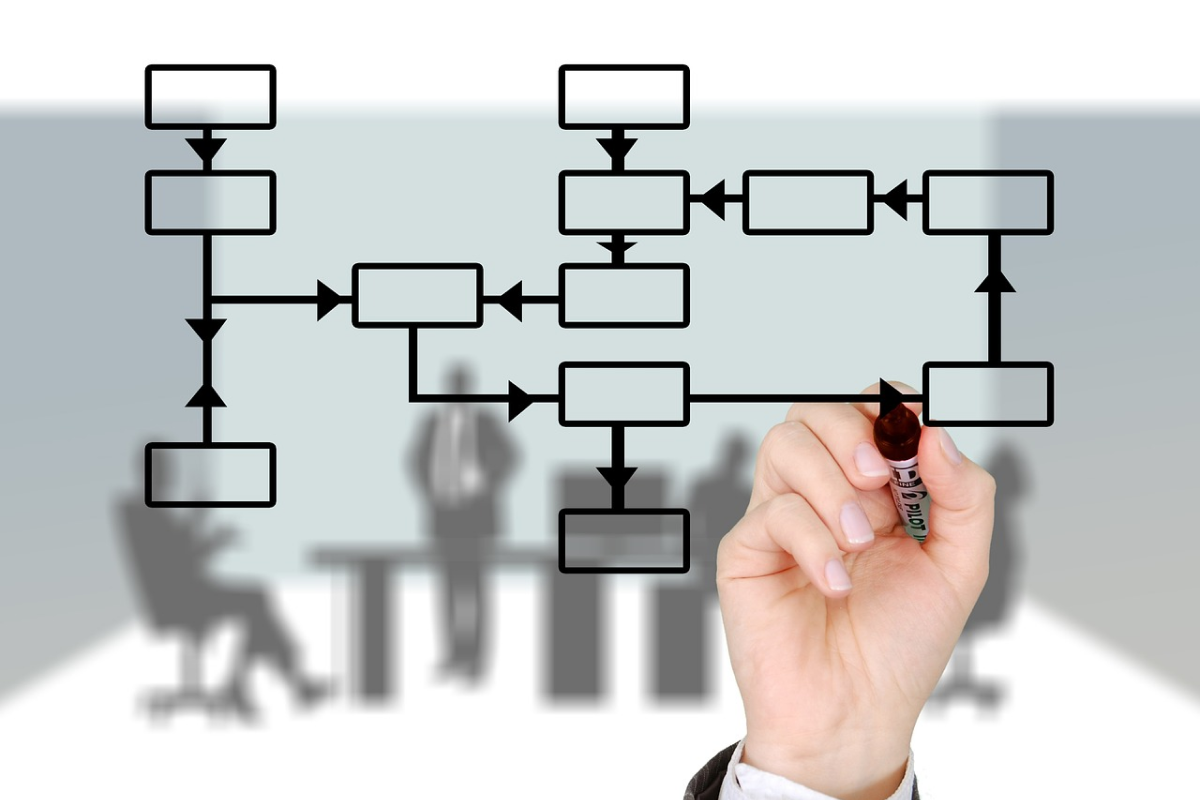
属人化や複雑な運用に課題を抱えている企業は多く、これが生産性の低下や業務の非効率化につながるケースもあります。しかし、業務プロセスの改善に取り組むことで、これらの問題を解決し、生産性向上やコスト削減などのメリットを得ることができます。
運用改善を成功させるためには、計画的なステップを踏んで実施することが重要です。本記事では、運用改善に取り組むためのステップや、効果的なポイント、さらに注意すべき点について解説しています。
業務プロセスにおける課題
業務プロセスに課題を感じている場合、その具体には属人化、形骸化した管理、非効率・複雑な運用といった問題が挙げられます。ここでは、それぞれについてどのような課題があるのか見ていきます。
属人化によるリスク
特定の業務やプロセスが特定の人物に依存している場合、その担当者が不在、病気、退職などで突然対応できなくなると、業務の進行が大幅に遅れたり、場合によっては業務全体が停止する可能性があります。
管理の形骸化
システムなどの運用管理は、目的を持って適切に行わなければ、ルールが形ばかりで機能しなくなることがあります。管理の形骸化とは、組織や企業が導入した管理プロセスやルールが、表面的には存在しているものの、実質的に機能していない状態を指します。
つまり、「管理のための管理」となり、本来の目的を果たせず、形だけが残ってしまっている状況です。このような状態では、業務の効率化やリスク管理が十分に行えず、企業活動にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。
非効率、複雑な運用
業務が複雑で非効率だと、その業務に関連する他の業務にも影響を及ぼします。
例えば、不必要な申請・承認プロセスが存在する場合や、担当者単位で判断できないルールがあり、その都度確認が必要な場合などは、業務効率を大きく低下させます。
業務の進行がスムーズでないと、結果として顧客対応の遅れにつながる可能性もあります。
また、ビジネスの成長に伴い、運用が複雑化するケースも少なくありません。新しい環境に適応できないプロセスは、次第に非効率となり、関係者にとって時間の無駄と感じられるようになります。
業務プロセスを改善するメリット
生産性向上は業務プロセスの改善で得られる大きなメリットです。さらに、コスト削減、製品・サービスの品質向上ももたらします。
生産性の向上
業務プロセスの改善は、無駄の削減につながります。また、業務効率がアップすることで、生産性向上につながります。
生産性は大きく下記の3つに分類されます。
- 労働生産性
- 資本生産性
- 全要素生産性
労働生産性とは、従業員1人あたり、または1時間あたりの成果を数値で表したものです。プロセスの見直しで、各従業員の高い生産性を期待できます。
資本生産性とは、設備や機械などが生み出す成果を数値にしたものです。活用されてないシステムの利用を止めるといった不要な投資をしない、成果を出すスピードアップなどで生産性向上を見込めます。
全要素生産性とは、労働・資本以外の要素も含めて生み出された成果の指標です。例えば人材育成、業務プロセスやリソースの最適化などで増える成果物が該当します。
全ての要素の数値化は容易ではないため、全体の生産の変化率から労働と資本の投入量の変化率を引いて計算することが一般的です。
コスト削減
業務プロセスの無駄をなくすことで、従業員の長時間労働が是正される可能性があります。長時間労働が減れば残業代を減らせます。
労働時間を短くしてもこれまでと同等かそれ以上の成果を出せれば、重要な業務にかける時間を増やせます。人件費の有効活用と言えるでしょう。
さらに、アナログ作業のうちデジタル化できるプロセスを電子化すれば、ペーパーレスにもつながります。印刷代や郵送代といったコストの削減も見込めます。
製品・サービスの品質向上
業務プロセスの見直しでミスやヒューマンエラーの減少を期待できます。複雑な業務プロセスが見直され、最適なエネルギーで各業務を処理できるようになればヒューマンエラーを起こしにくくできます。
また、見落としやミスをシステムが知らせたり、自動化すれば防ぎづらいミスへも対策ができます。
また、システムによる自動化などの結果、業務効率化と製品・サービスの質向上を両立できます。品質の良い製品・サービスで顧客満足度も向上するでしょう。
手間で属人的な契約書管理にお困りですか? ContractS CLMなら作成~管理までの契約プロセスを改善できます
⇒ContractS CLMの資料を見てみる
運用改善の具体的なステップ
- 業務可視化
- 課題を整理して解決策を見出す
- 運用コストの見直し
- 改善施策の実行と振り返り
業務を可視化する
業務内容やプロセスを客観視できる状態にします。
業務の担当者と作業内容、頻度や実施するタイミング、進め方などが具体的に分かるようにしましょう。業務フローも含めて細かく把握できることで、改善の必要な箇所が見えてきます。
イレギュラー対応もあわせて可視化を進めます。
担当者が複数いる業務については、属人化していないかも確認します。
課題を整理し解決策を見出す
業務内容とプロセスに無駄がないか洗い出します。例えば重複している業務の有無の把握などです。
業務を進めるにあたり不要と判断した作業については、プロセスから省きます。必要な業務でも、フローを見直す必要はないか検討の余地はあります。
従業員間で必要な業務か否かの判断が割れることもあるかと思います。判断が分かれたとしても、業務を整理する目的が運用改善であることを念頭に置くと、結論を導くための話し合いと整理がスムーズに進むはずです。
業務内容やプロセスを整理したら、どのように課題解決するかを考えます。
運用コストの見直し
システムの導入・入れ替え、アウトソーシング、どの場合においても、コストがかかります。費用対効果を見る前に、コストの見直しも大切です。
既存のシステムと改善したいことがマッチしているか、機能が重なるシステムや使われていないシステムはないかなどを分析します。よりコストパフォーマンスの良いシステムへの入れ替え、使用しないシステムの停止などは、コスト削減に有効です。
改善施策の実行と振り返り
策を講じても改善が見られない場合があるため改善策を実施した後にも振り返りが必要です。取り組んだ結果、新たな問題に気づくこともあるためです。
定期的に振り返りを行い、改善策の効果は現れているか、他に課題が出てきていないかなどをチェックします。運用改善は、他の策が必要と思われたら施策を変え、再度振り返る、というサイクルの繰り返しです。
運用改善のポイント
運用改善のポイントは、属人的で非効率的なプロセスをなくし、最適なプロセスを構築することです。
属人化の排除
業務や知識が特定の担当者に依存しないようにします。
このためには、特定の人がいないと進められない業務を洗い出し、業務を行うために必要なナレッジを共有します。そのうえで、標準化できる部分はないか検討し、複数人で業務を担当できるように整えます。
ナレッジのリアルタイムでの共有に手間がかかる、ぬけ漏れが起きる場合には日々のナレッジが自動的に記録されるような仕組みを考えましょう。
非効率の解消
運用改善を行うなら、非効率が改善されていることが成功のポイントです。課題に対しどのようにしたら解決できるか、目的と手段を整理し業務改善に努めましょう。
注意が必要なのは既存のシステムです。機能の拡張などでシステムが複雑化していると使い勝手が悪く、社内全般の業務効率低下の原因になり得ます。
使用する方に広く意見を求め、誰もが使いやすいシステムの導入や入れ替えを検討しましょう。
【関連記事】業務改善に有効なシステム導入の流れとは?注意点や準備のポイントも
効率的なプロセスの構築
無駄がなく、標準化されたプロセスを目指します。シンプルなプロセスは、運用管理業務も簡単にします。
継続的な見直しや改善のためのフィードバックを取り入れる仕組みを整えることも大切です。新たなニーズや市場の変化に柔軟に対応できるように、業務プロセスの柔軟性を確保しましょう。
【関連記事】業務プロセス改善の目的とメリット。業務プロセスを見直すには?
運用改善の注意点
改善策の実行と振り返りを繰り返すことに加え、周りの意見を取り入れながら改善策を考えることも大切です。自身の意見が反映されていると分かれば納得感を得られ、積極的に改善に取り組めるためです。
改善策が現実味のある内容であることは必ず確認しましょう。
理想の策はあると思います。ところが、現場で取り組める内容でないと、計画だけで終わってしまうことが懸念されます。
業務プロセスの変更で現場が混乱しないよう、少しずつ取り組める内容とすることもポイントです。
まとめ
業務プロセス改善によって、生産性向上やコスト削減、商品・サービスの品質向上の実現を期待できます。業務プロセスで属人化や管理が機能していない、非効率的で複雑な運用といった課題を抱えているのであれば、改善に取り組みましょう。
【関連記事】総務など管理部門の業務改善方法とメリット。業務効率化成功例も