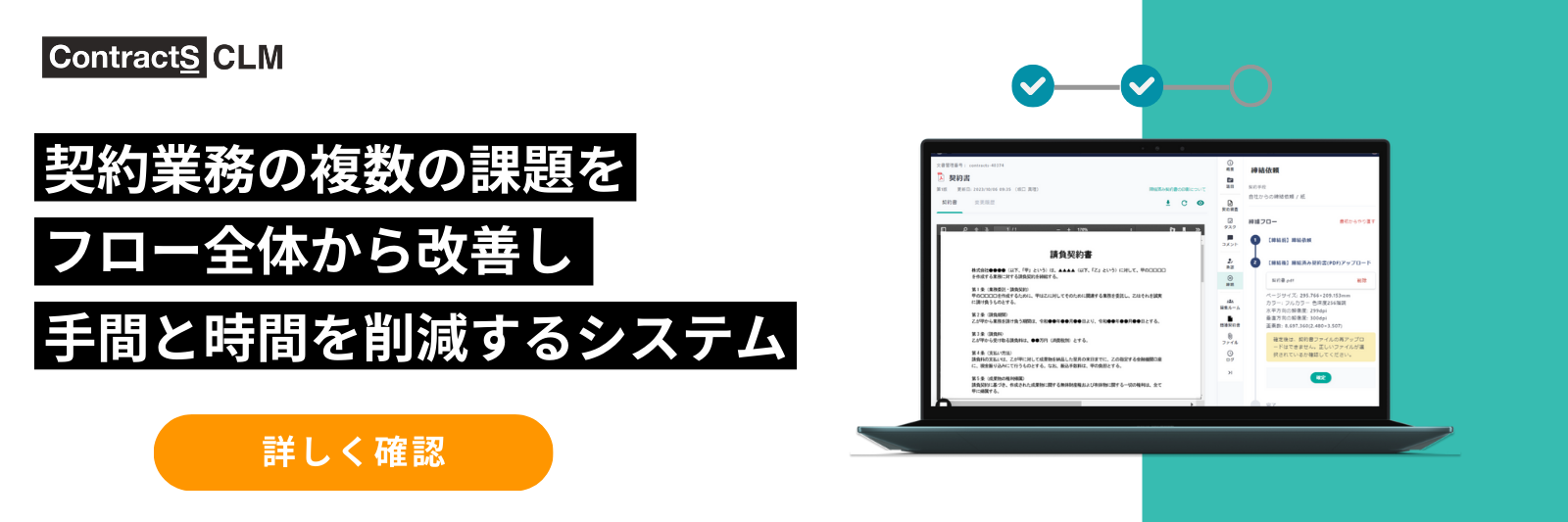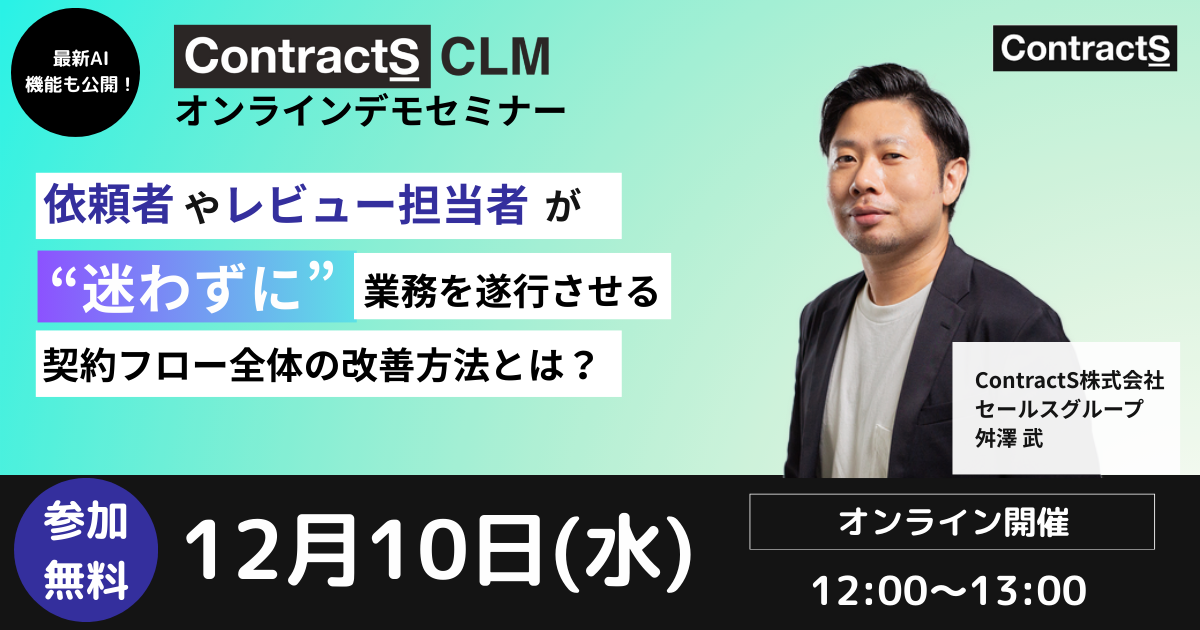ノウハウ 経済産業省が示すDX推進3つのフェーズとは?各フェーズの進め方と施策
更新日:2025年04月18日
投稿日:2024年09月24日
経済産業省が示すDX推進3つのフェーズとは?各フェーズの進め方と施策
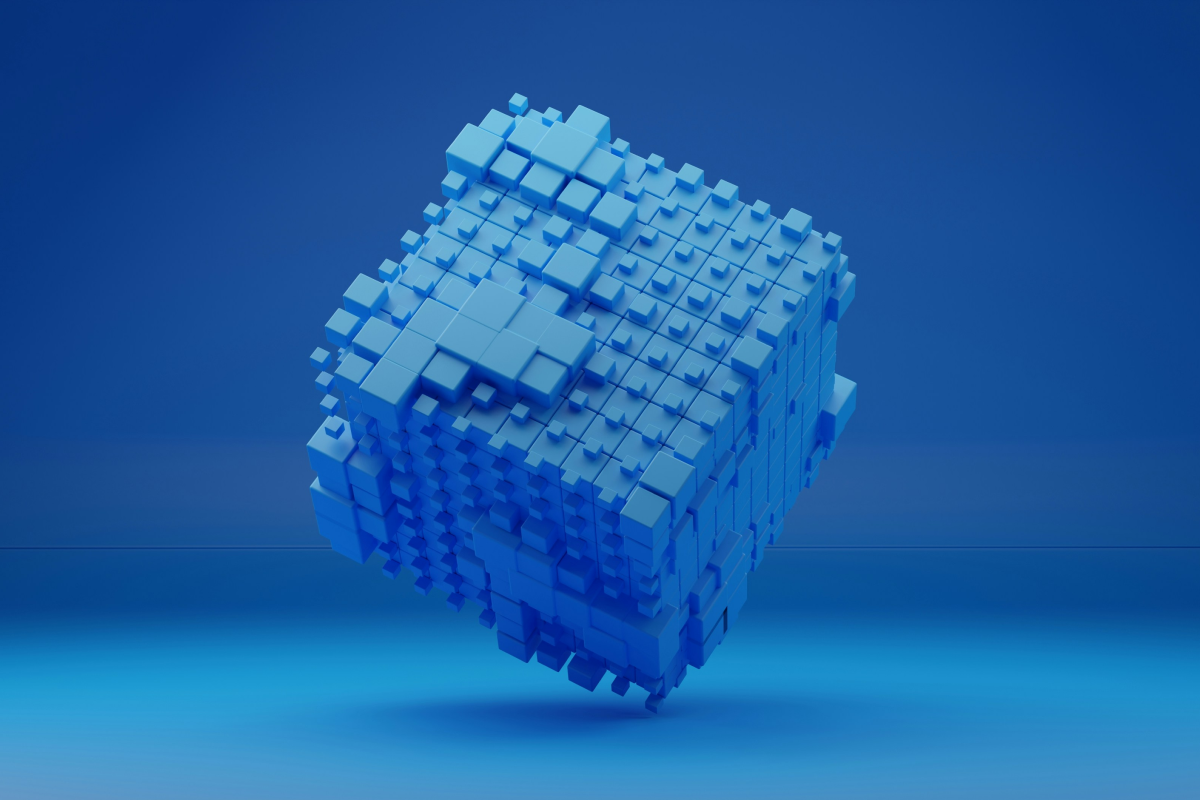
DX推進はどのように進めればよいか情報がまだ少なく、迷う方も多くいらっしゃるでしょう。DX推進の3つのフェーズが経済産業省より示されています。各フェーズで取り組みの目的と施策が異なり、自社の状況に応じて施策立案の参考にすることができます。
本記事では、各フェーズでどのように進めれば良いのか、DX推進のメリットとポイントを成功事例とあわせて紹介します。
経済産業省が示すDXの3つのフェーズ
経済産業省はDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現には3段階あるとしています。
- デジタイゼーション
- デジタライゼーション
- デジタルトランスフォーメーション
上記の順でDXに移行することが基本ですが、実際には組織の状況や課題、DXで叶えたいことに合わせて調整していきます。
1.デジタイゼーション
アナログな手段で作成して物理的に保管しているデータのデジタル化を進める段階です。
取り組みにより業務標準化・効率化による従業員の負担軽減やコスト削減といった効果があらわれ始めます。
2.デジタライゼーション
個別の業務フローや製造プロセスにデジタルを取り入れる段階です。デジタル化したデータを有効活用できるよう、プロセスを見直します。
デジタルツールの活用による業務効率化やコスト削減に加え、データの利活用による業務改善も期待できます。
3.デジタルトランスフォーメーション
経済産業省のデジタルガバナンス・コード2.0でDX(デジタルトランスフォーメーション)は次のように定義されています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
組織全体で業務フローや製造プロセスのデジタル化に取り組み、顧客に新しい付加価値を提供できるよう、事業やビジネスモデルに変革を起こす段階です。
新しい事業・ビジネスモデルに伴う競争力の強化が期待でき、データ分析による新製品・サービスの開発や販路拡大などを目的とします。
【関連記事】DXとは?業務に導入するメリット・課題・方法・ポイント
各フェーズの進め方と具体的なプロセス
D X レポート 2 中間取りまとめ (概要)では、DX成功に向けたフレームワークがまとめられています。
デジタイゼーションの進め方と具体例
デジタイゼーションは下記のように進めます。
- 業務フロー・製造プロセスの見える化
- デジタル化できる作業とできない作業に分類
- 紙媒体の電子化などデジタル化に必要なツールの選定
- 電子化の着手
具体的には下記のような対策を講じます。
- 紙ベースの契約や連絡に代わり電子契約やメール・チャットツールを用いる
- 電子媒体をクラウドサービスに保存 など
業務フローや製造プロセスにデジタルを導入するためには、デジタル化可能な工程を見つける必要があります。進め方やリソースを詳細に見える化できると、デジタル化できる(した方が良い)作業とできない作業に分類しやすいです。
デジタル化すべき作業や工程が明確になると、必要なツールも見えてきます。
ツールが決まり研修などで使える状況になったら、業務のデジタル化に向けた準備を始めます。
デジタライゼーションの進め方と具体例
デジタイライゼーションは下記のように進めます。
- デジタル化がどこまで進んでいるか確認
- 目標設定
- 計画立案
- 新しいプロセスやシステムの導入
具体的には下記のような対策を講じます。
- 1つのシステムで業務を完結できるツールの導入
- 在庫情報システムで在庫と発注の管理
- 顧客管理システムによる販売分析の自動化 など
業務フローにデジタルを取り入れるにあたり、アナログで行っていたことがどこまでデジタルに移行dできるか確認し、導入までの計画を立てることがポイントです。
同時に、業務や製造プロセスで入れ替えた方が良い工程はあるか、統一できる工程の有無も検討します。
実際の業務にデジタルを導入して実現したいことを明確にしたら、実現までの計画を立てます。
計画に従い、優先度の高い業務やすぐに着手できる業務から、新しいプロセスやシステムを取り入れましょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の進め方と具体例
デジタルトランスフォーメーションは下記のように進めます。
- DXを進める目的を明確にする
- 現状を分析して課題を洗い出す
- DX推進の担当者を選定
- 計画立案
- ITシステムの選定
- 実行
- 施策の効果分析と改善
具体的には下記のようなことも可能です。
- 蓄積されたデータを基に販路拡大や新商品・サービスの開発に活かす など
DXはデジタル化によって顧客に新しい価値を提供することが求められます。DXで社会に何をもたらしたいかを最初に明確にすることで、取り組みを考えやすいです。
まず、自社のデジタル化の進捗状況、市場を取り巻くDXの現状から、最新トレンドを取り入れながら自社の目標達成に必要なことを明らかにします。実務に関する課題は現場の方がより気づきやすいため、ヒアリングを通じての洗い出しも効果的です。
洗い出しにより複数の課題が上がることは珍しくありません。今すぐに改善が必要な業務や、効果がすぐに分かりそうなものから取りかかることがおすすめです。
チームが組成できたら、DXの目標達成に向けた計画を考えます。どれくらいの時間をかけて実施するのかはもちろん、予算確保と経営層への合意も重要なミッションです。
システムを導入することが目的になりがちですが、DXで実現したいことを振り返ることで本質的なDXまで到達できます。
取り組みを通じて新しい課題が見つかることもあるため、新たな課題解決に向けた対策と振り返りを続けることも欠かせません。
【関連記事】社内DXの進め方とは?成功事例や役立つツールも紹介
DX推進によるメリットと推進しないリスク
| メリット | 推進しないことのリスク |
| 業務効率・生産性の向上 | 効率アップやコスト削減を妨げる |
| コスト削減 | 競争力の低下 |
| 新製品・サービスの開発機会を広げられる | 新規ビジネスの機会損失 |
| データを有効活用しやすくなる | セキュリティリスクの高まり |
| 働き方改革への対応 | システムの複雑化・ブラックボックス化 |
| BCPによるリスク回避 |
DXのメリット
業務効率・生産性向上やコスト削減の他、新製品・サービスの開発機会を広げたり、データを有効活用しやすくします。働き方改革に対応しやすくなるのも、大きなメリットです。
業務効率・生産性の向上
デジタルツールの導入で、作業のスピードアップが見込めます。システム導入をきっかけによる業務の進め方の見直しで、効率アップも期待できます。
また、アナログで進めていた業務にツールを活用して自動化すれば、ヒューマンエラーの防止になります。ミスの修正作業が不要となり、重要度の高い業務に時間や人材を費やせます。
コスト削減
例えば紙ベースで書類のやりとりをしていた企業が電子媒体・ツールでのやりとりに変更すれば、印刷代や郵送代、書類の保管スペースを削減できます。
業務フローを可視化できるツールもあります。業務の無駄に気づいてなくすことができると、人材を他の業務に配置できます。
新製品・サービスの開発機会を広げられる
ツールの活用で、消費者のニーズの分析が的確かつスピーディーに行えます。また、業務プロセスの見直しで、新しい製品・サービスの開発スピードを早めることもできます。
分析結果を用いて自社の強みが把握できることで、独自性の高い商品やサービスを次々と提供することも可能になります。
データを有効活用しやすくなる
業務ごとに異なるシステムを用いている場合、多くの業務を1つのシステムで完結できるようにすれば、あらゆるデータが集約され、複数のデータを分析しやすくなります。
働き方改革への対応
業務フローの見直しで無駄がなくなれば、長時間労働の是正につながります。
残業が減って好きな場所で働けるようになると、ワークライフバランスを整えやすくなりモチベーションや企業への信頼がアップするでしょう。
BCPによるリスク回避
BCPとは事業継続計画のことで、災害やシステム障害時に事業が継続できるようにするための計画です。
例えば事業に必要な資料や書類を電子化してクラウドへ保存しておけば、事業の復旧に必要な情報をすぐに取り出せます。従業員がオフィスに出社したり、顧客と直接接触することが難しい環境でも、リモートワーク環境やオンライン上のサービスの整備で、業務を進めたりといった顧客対応が可能です。
DX推進を行わないリスク
DX推進を行わない場合、効率の悪化やコスト削減を妨げたり、新規ビジネスの機会が失われたりする以外にも、競争力の低下やセキュリティに関するリスクなどが懸念されます。
効率アップやコスト削減を妨げる
デジタルツールの導入は業務効率化やコスト削減に有効です。もちろん、デジタルを導入しなくても業務フローや人員配置の変更などできることはあります。
しかし、ベストな施策を考案するスピードは、システムには敵いません。また、ヒューマンエラーによる業務の無駄をなくすには、ツールのサポートが必要です。自動化による人件費の有効活用も、アナログの取り組みだけでは難しいです。
競争力の低下
デジタルツールを用いた顧客の分析や新製品・サービスの迅速な提供がしづらいと、市場のスピードに追いつくために時間がかかります。高度なデジタル社会において、顧客の製品選定の範囲は国内だけではなく海外市場も含まれます。
そのため、外部要因は多く従来の営業活動では収集できないデータも多く生じるようになりました。必要なデータを収集し、分析できる状態を作ることが近代のビジネス環境において重要です。
新規ビジネスの機会損失
手作業や旧システムに依存し続けると、手続きの遅延やヒューマンエラーが増加し、結果的にコストも上昇します。
さらに、データの活用が不十分なため、消費者ニーズに迅速に対応できず、市場の変化に乗り遅れるリスクがあります。これにより、新しいビジネスモデルやサービスの提供機会を逃すだけでなく、他社に先を越される可能性も高まります。この用意、成長機会の損失だけでなく、既存ビジネスの維持が危うくなる恐れがあります。
セキュリティリスクの高まり
古いシステムは、いつサポートが終了してもおかしくない状態です。サポートの終了したシステムは、情報漏えいやサイバー攻撃などのリスクを高めるため企業の情報流出リスクにもつながります。
システムの複雑化・ブラックボックス化
オンプレミスのシステムなど、システムがカスタマイズされ過ぎると事業の変化に伴う業務プロセスの変化に対応できなくなり、かえって使い勝手が悪くなります。
また、退職などで当時の担当者がいないために使いこなせないシステムは、手つかずのままにされがちです。システムを活用できないにもかかわらず、保守運用費だけがかかってしまいます。
DX推進における具体的な施策
DX推進による具体的な施策を2つご紹介します。
まず、老舗飲食店の施策です。
天気や売上のデータからAIが来客数を予測するツールを開発しました。販売情報といったデータも一覧で確認できるツールです。
ツールの活用により、売上・客単価・利益の増加を実現しました。
物流業の施策も参考になります。
運送の配車や人員配置を紙媒体で管理していたため、属人化が進みやすかったとのことです。
そこで、業務プロセスにクラウドサービスを導入しました。クラウドサービスによって、誰もが場所を問わず配車や人員配置を確認できるようになりました。受注のスムーズ化や業務最適化につながった事例です。
デジタルガバナンス・コード実践の手引きでは、他にも具体的な事例が紹介されています。
では、DX成功にはどのように計画を立てていくと良いのでしょうか。
DXプロジェクトの効果的な進め方
DXプロジェクトの効果的な進め方をご紹介します。
- 現状把握
- DXで達成したいことを明確にする
- 社内に周知
- プロジェクトの立ち上げ
- 社内環境の整備
- 新しいやり方などの定着
現状把握
まず、自社を取り巻く状況から課題を明らかにすることから始めます。DXは、自社の取り組みを通じて外部に新しい価値を提供することが求められます。そのため、外部環境や将来の予測と、自社の現状を照らし合わせた時にあるべき姿とのギャップを見つけることが重要です。
DXで達成したいことを明確にする
DXは課題を解決するだけでは終わりません。問題を解消した先に達成したいことが重要です。
着実な目標達成に向けた計画も必要です。計画に無理はないか、そもそも現実的な目標を掲げているかなども考慮します。
社内に周知
全従業員がDX推進の理由を知っていることが求められます。
個人やチームの掲げる目標と組織の目標に乖離があっては、現場からの協力は得られにくいです。事前に部門ごとのミッションを確かめ、チームの目標達成の先に組織全体で達成できる目標がある、というイメージを持って内容を決定しましょう。部門のリーダーからの合意があると安心です。
プロジェクトの立ち上げ
個人やチーム、そして組織の目標実現に向けたプロジェクトを立ち上げます。
どのような施策が必要でどの範囲まで実施するか、なぜ施策が必要なのかを決めていきます。
例えば、電子契約を原則とする施策であれば全従業員に行ってもらう必要がありますが、アプリの開発といった専門的な業務であれば特定の部署のみの実施で良いでしょう。
施策が必要な理由については、業務効率化のため、顧客満足度向上のためなどが挙げられます。
社内環境の整備
社内体制が原因でプロジェクトの進行が妨げられるケースは少なくありません。例えば既存のシステムがプロジェクトと相性が悪い、部署の垣根を越えて協力し合える仕組みができていないなどです。
この場合、個人やチームに権限を持たせて自発的にスピーディーに進められるようにする、部署に関係なくコミュニケーションをとりやすい工夫をするなどが求められます。
新しいやり方の定着
試行錯誤を繰り返しながら効果の出た施策については、正式に業務フローに取り入れ、DXの定着を図ります。
【関連記事】社内プロジェクトの進め方とポイント。おすすめのツールは?
DX推進の成功に向けたポイント
デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションそれぞれのフェーズごとのポイントと、リテラシー教育の重要性を紹介します。
デジタイゼーションに関する施策
デジタイゼーションは社内全体で取り組むDXの準備段階と言えることもあり、社内で協力して進めることが求められます。
優先順位を明確にする
書類をデジタル化してクラウドサービス上に保管するなど、アナログで行っている業務をデジタル化すると、業務進行が楽になります。
一方、アナログからデジタルへの移行を一気に進めるのは大変です。すぐにデジタル化したい業務、移行の手間が小さい業務から始めてみることをおすすめします。
社内全体で協力してデジタル化を進める
DXに取り組む段階になった時、社内で共通して使える書類やデータにもかかわらずアナログ管理とデジタル管理の部署が混在すると、一括での利用・管理が妨げられます。
そこで、将来的に企業がデジタルの活用を前提に業務を進めることを社内全体に周知し、理解を得た上で部署単位でできることからデジタルに慣れてもらうことが大切です。
現場の声を取り入れる
現場にとって使いやすいものでないと、実際に使用してもらうことは難しいでしょう。
どのような業務にデジタルを取り入れたくて、どのような機能が使えると理想的か、現場の意見も尊重しながらのツール選定が求められます。
デジタライゼーションに関する施策
デジタライゼーションには、DXを見据えた施策がポイントです。
顧客のニーズまで考えた目標設定をする
DXは社内で横断的にデジタルを取り入れ、新しい価値の提供が求められます。デジタライゼーションは、社内で試験的にデジタルを取り入れるフェーズにあります。顧客の視点も取り入れた目標を設定できると、今後に活かせます。
社内外の環境変化に応じて施策を調整する
新たに従業員が入社した、人員配置や社内の仕組みが変わった、市場環境や情勢の変化で消費者の購買行動やニーズが変容したなど、ビジネスを取り巻く環境はめまぐるしく変わります。
社内外の変化に対応するためには、新たな施策が必要です。
場合によってはデジタイゼーションと同時に進める
DXに向けた3つのフェーズは、順序が必須というわけではありません。異なるフェーズの同時進行も可能です。
デジタイゼーションはチーム・部署単位で進めることができます。そのため、マニュアルなど業務に必要な書類のデジタル化と業務フローの自動化を同時に進めることができます。
業務プロセスのデジタル化も一括で行えば、社内のデジタル化がスピーディーに進みます。
デジタルトランスフォーメーションに関する施策
データやスキルを1ヶ所にまとめることと、新しいビジネスモデルや価値の創出を意識することはもちろん、ツールの導入を目的としないことや全従業員の協力も大切です。
データの一元化
データを一元管理すると必要な時にすぐに取り出すことができ、クラウド上で保存すれば情報共有もスムーズになります。
システムを複数使って管理する必要がある場合は、システム同士が連携できると社内全体でデータの利活用が進みます。
スキルやノウハウの集約
業務に必要なデータや書類に限らず、マニュアルなど進め方やポイントの分かる資料もまとめて管理すると、業務の属人化が解消されます。
あらゆるスキルやノウハウの共有は、新しいビジネスの実現可能性を高めます。
ビジネスモデルの変化と新しい価値の創出を意識する
デジタル化にあたって業務フローを変更した方が良い場合は少なくありません。業務の進め方をその時のトレンドにマッチする形に変えると、DXのメリットをより実感できる可能性があります。
そして、業務の取り組みを試行錯誤しながら、新しい価値を生むために自社だからできることを発見しましょう。
ツールの導入を目的としない
最新のツールを導入しただけで、終わりとしてしまうとツール導入の結果もたらされるメリットを十分に享受することができません。
ツール導入のもととなった目的が達成されているか、プロセスの変更によりかえって業務効率が悪化していないか確認することで真のデジタル化が実現できます。
周囲との協力
社内でデジタルを定着させるためには、周囲の協力が不可欠です。
取り組む目的が理解されないと、前向きに取り組んでもらうことは難しいため、DXに関する啓もう活動がおすすめです。
リテラシー教育の重要性
IT人材が不足していることで、DXを進められないこともあります。
外部の手を借りることもひとつの手ですが、社内の人材をDX人材として育成することも求められます。
DXの必要性、データやデジタルツールの活用方法などを知ることで、DX推進を前向きに考えられて、DXに向けて積極的に試行錯誤できるようになるでしょう。
デジタルツールの使い方などDXに関する知識は専門性が高いです。デジタルリテラシー向上のためのプログラムを提供する外部の研修の利用も検討してみましょう。
DX推進例と成功事例の紹介
契約業務の属人化解消や可視化・見える化によるメリットを得た2つの事例を紹介します。
株式会社レゾナック様の例
2つの会社が統合するにあたり、契約業務に異なる課題が存在すると分析した同社は、作業の複雑化や属人化を解消するために契約プロセスを統一することを決めました。
複数のシステムを比較検討する中で、契約業務の課題解決や契約レビュープロセスの統一、案件の可視化が実現できる点が決め手となり、ContractS CLMの導入に至りました。
進捗状況の可視化により業務効率が向上し、メンバー間の情報共有が容易になったことで属人化の解消にもつながっています。
事例を詳しく見る>> 契約レビュープロセスの煩雑化と属人化を解消
株式会社ネオキャリア様の例
社内の情報が集約されないため、依頼の見落としや期日管理の難しさといった課題を抱えていました。
契約締結前後のプロセスの効率化、情報の一元化、進捗状況の可視化、そして契約業務のデジタル化を目指し、ContractS CLMを導入。契約ステータスを一目で把握できるようになり、業務効率が向上。契約審査のリードタイムは半分に短縮され、一元管理によりガバナンス強化を達成しています。
事例を詳しく見る>>契約業務の可視化・自動化を実現! 「迷わない」仕組みでリードタイムの短縮に成功
まとめ
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進は、業務改善を可能とすることはもちろん、新しいビジネスチャンスをつかむ可能性を広げます。
進め方のモデルとして3つのフェーズが示されていますが、絶対ではないので、自社の課題解決とDXで実現したいことを達成できる順に取り組むことがポイントです。
自社の現状を把握し、目標を明確にし、実現に向けてできることから着手しましょう。
【関連記事】契約DXを実現!CLMで契約管理を行うビジネスインパクトを解説