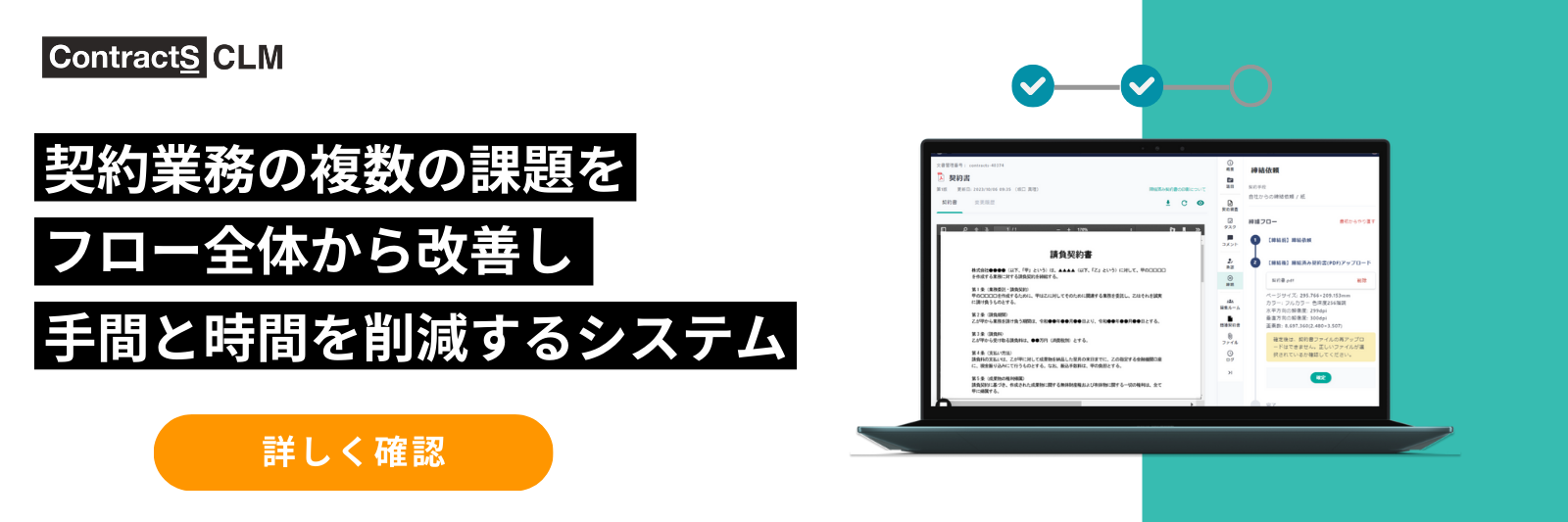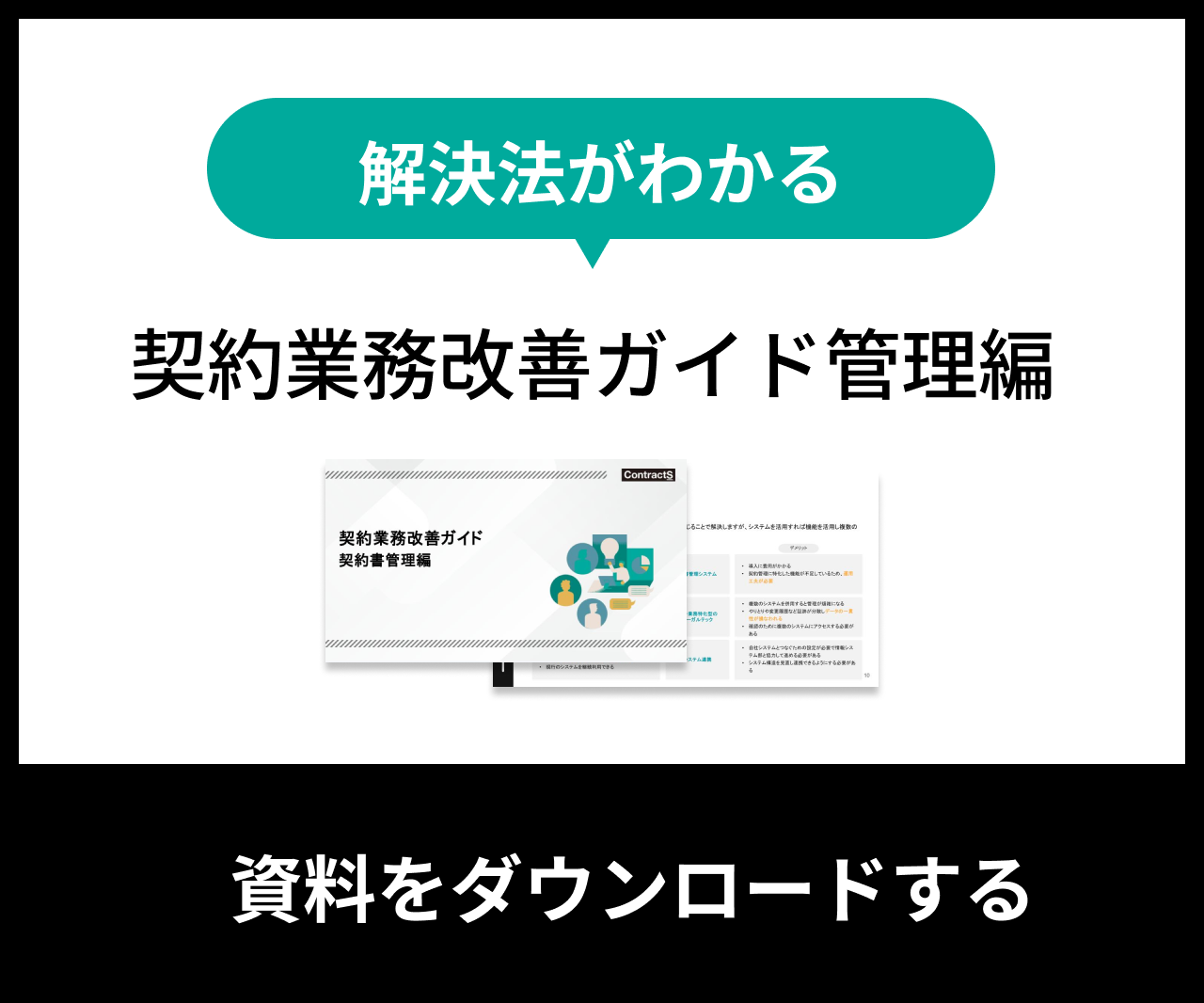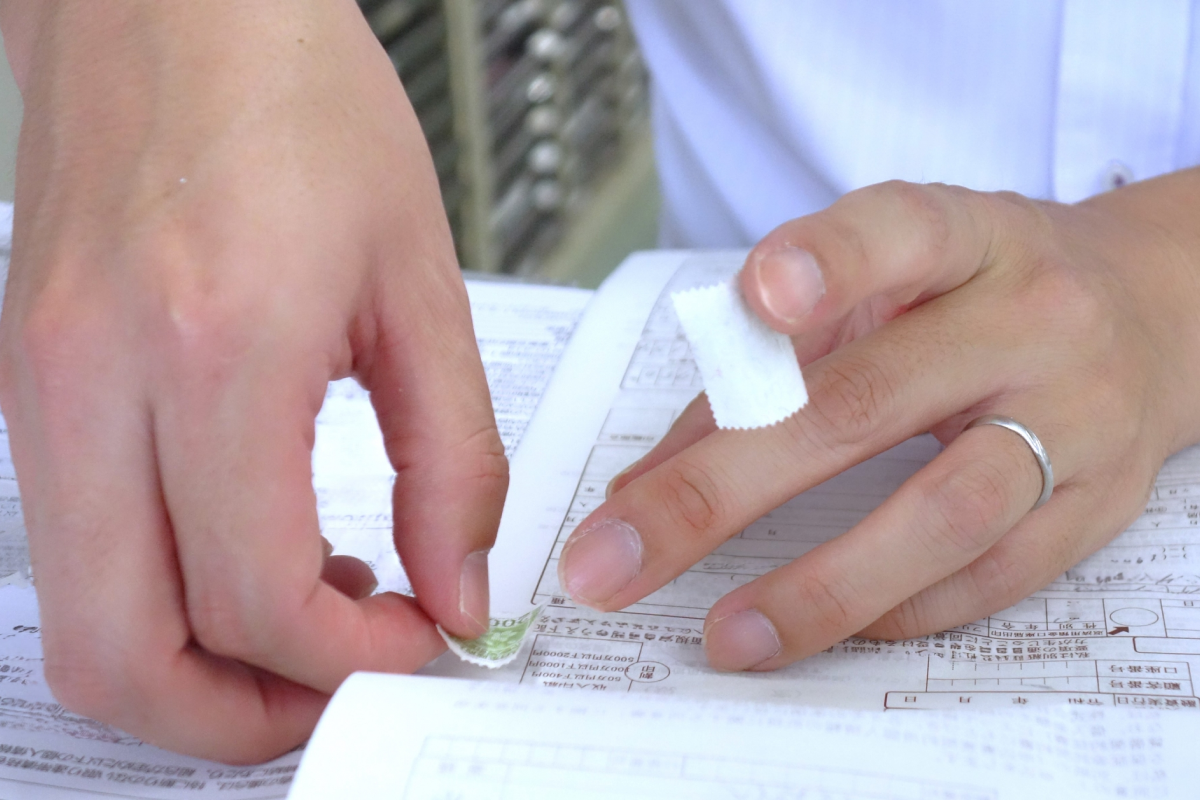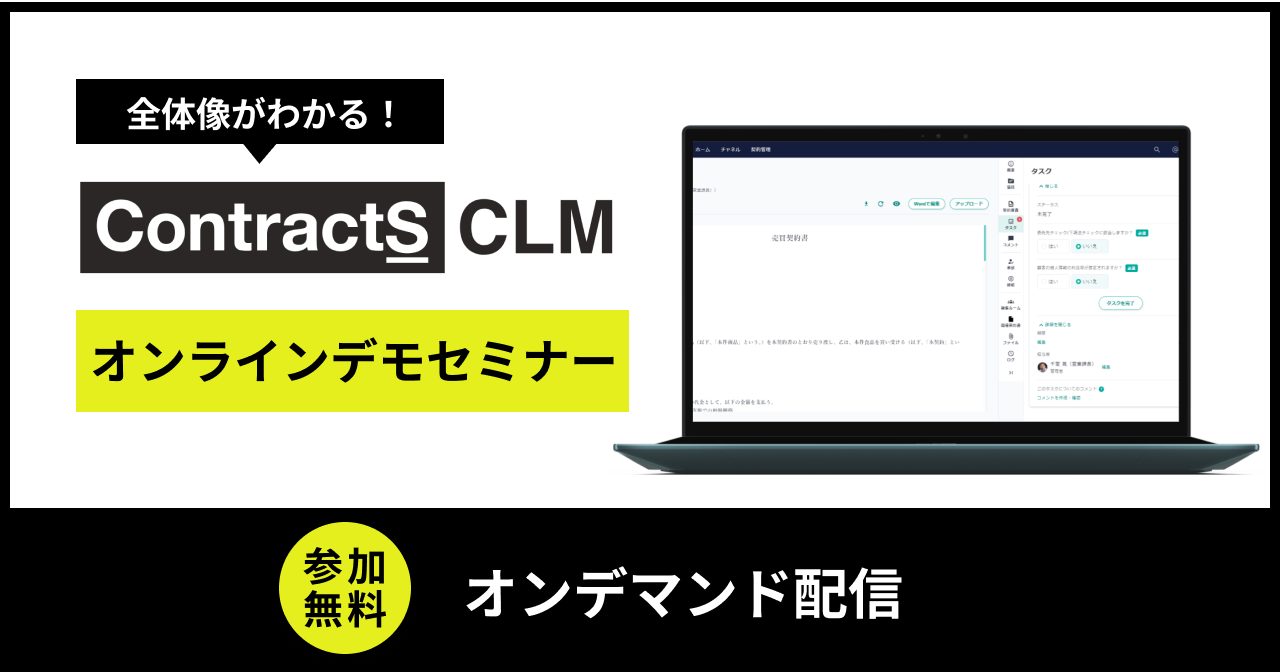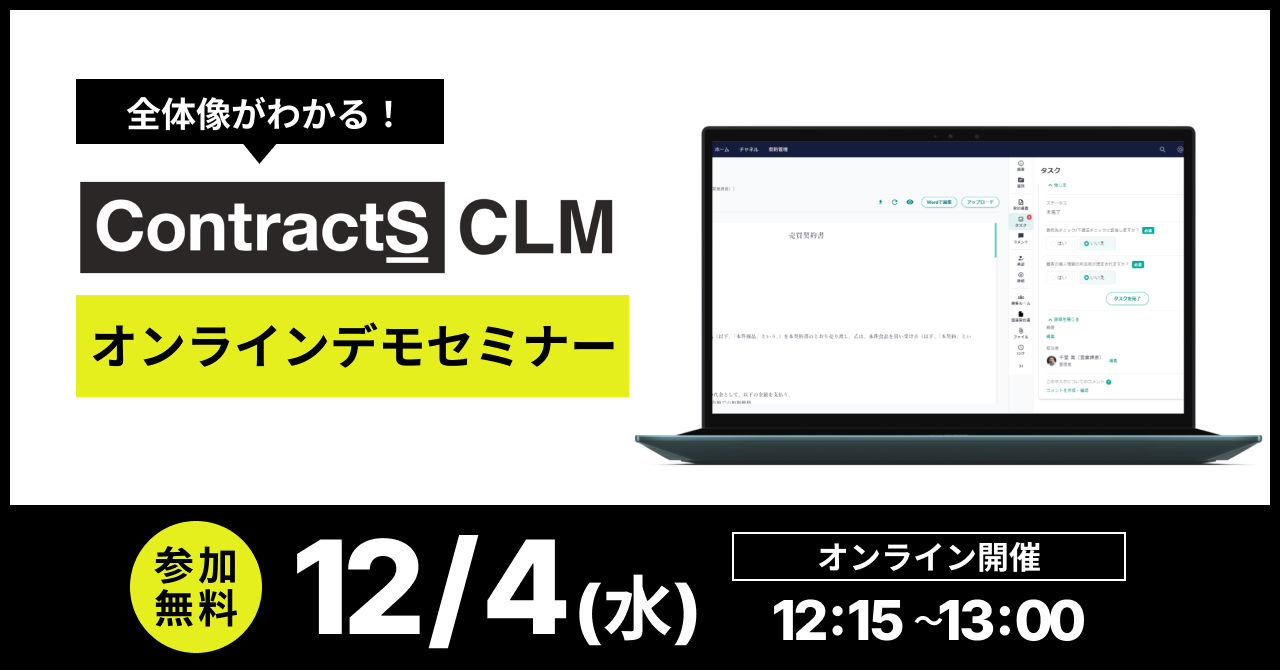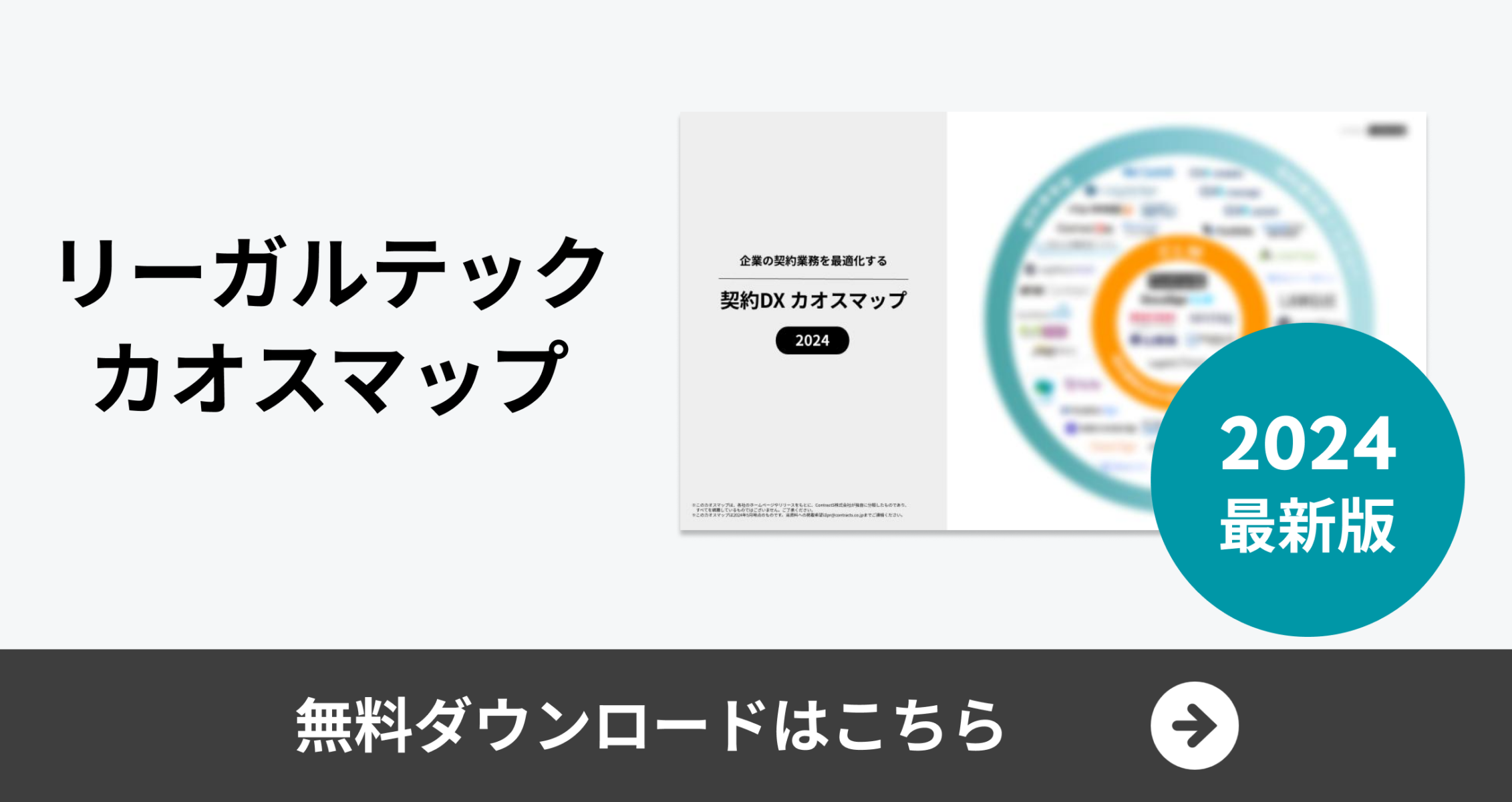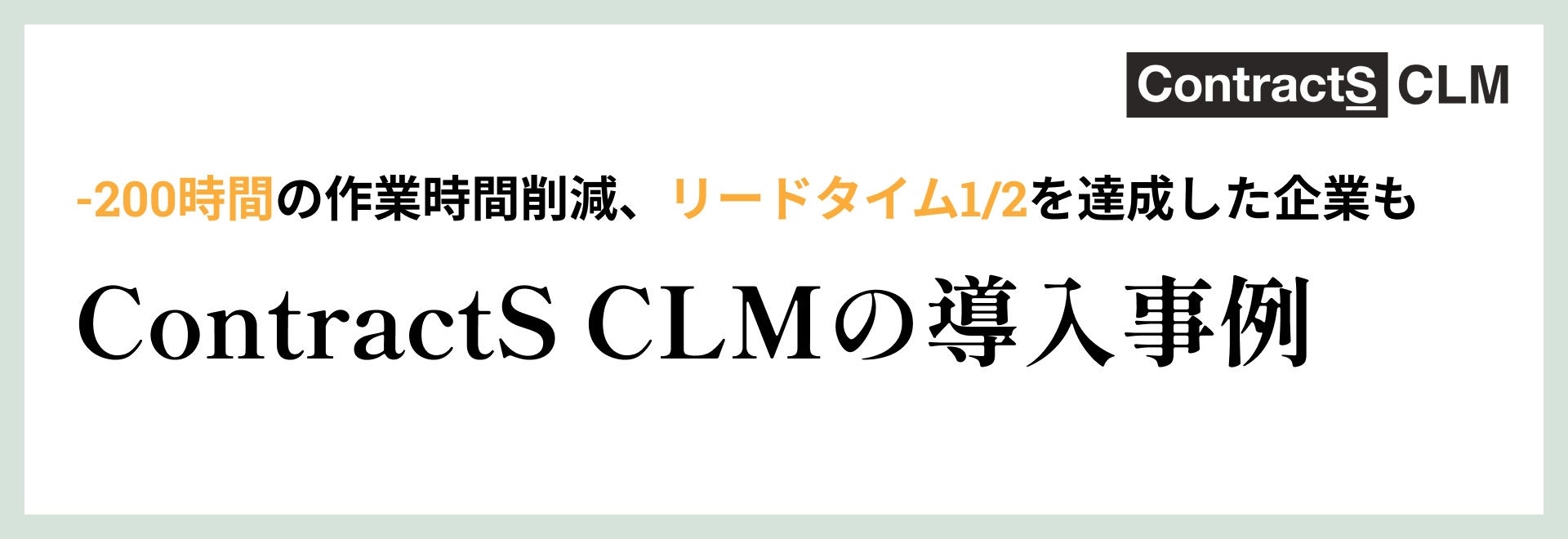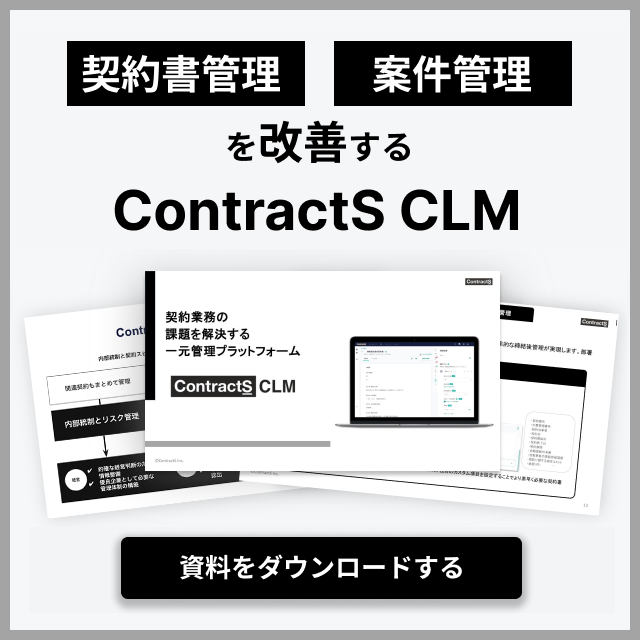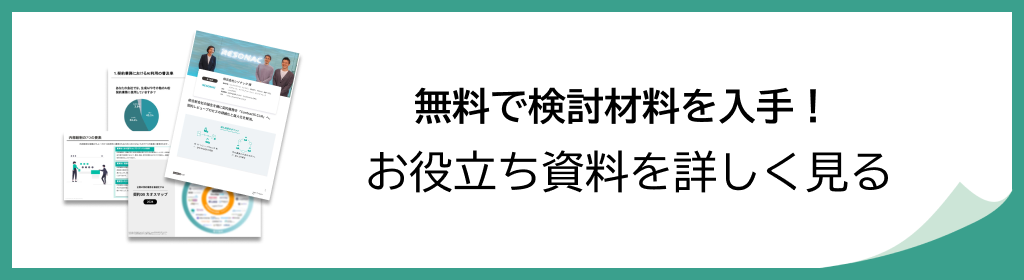ノウハウ 新リース会計基準とは?影響や対応方法などわかりやすく解説
更新日:2025年03月27日
投稿日:2024年08月27日
新リース会計基準とは?影響や対応方法などわかりやすく解説

2023年5月に公表された「新リース会計基準」では、リース契約だけでなくレンタル契約や不動産の賃貸契約を利用する企業も注目すべき、ある変更点が話題となりました。
今回は新リース会計基準の概要や主な変更点、それによって企業が受ける影響などを、分かりやすく解説します。
新リース会計基準の適用範囲についても記載していますので、自社は新リース会計基準の対応が必要かどうか分からない担当者の方も、ぜひ参考にしてください。
リース会計基準とは?
リース会計基準とは、企業が利用するリース取引の種類や会計処理について定めた基準のことです。
リース取引の定義・種類や、対象となるリース取引の会計処理を行ううえでのルールなどが明記されています。
日本では、1994年に初めてリース会計基準が適用されました。
しかし日本と海外ではリース取引において異なる点が多いことから、2007年にASBJ(企業会計基準委員会)より、「リース取引に関する会計基準」が発表されます。
これにより、後述するファイナンスリース取引の会計処理にオンバランス処理を適用させることが義務付けられました。
その後も国際的なリース会計基準(IFRS)の見直しに伴い、現在に至るまで何度か改正が行われています。
リース会計基準で定められたリース取引の種類
リース会計基準におけるリース取引の定義は、「特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は合意されたリース料を貸し手に支払う取引」とされています。
そして、そのリース取引には大きく分けて「ファイナンスリース取引」と「オペレーティングリース取引」の2種類があります。
ファイナンスリース取引は、さらに「所有権移転」と「所有権移転外」があり、リースする物件の所有権の扱いが異なります。
各種リース取引の特徴は、以下の通りです。
ファイナンスリース取引 | 【所有権移転】 ・物件の所有権がリース期間終了時に借手に移転すると認められる ・リース契約に基づくリース期間中、原則として中途解約はできない ・物件の使用に伴うコスト(保険料、維持費など)は、借手が実質的に負担し、リース料に含まれる場合が多い 【所有権移転外】 ・所有権移転ファイナンスリース取引に該当しないファイナンスリース取引。つまり、リース期間終了後も物件の所有権が貸手に残るリース取引 ・この場合、借手はリース期間中に物件を使用する権利を有するが、リース期間終了後は物件を返却することが通常 |
オペレーティングリース取引 | ファイナンスリース取引に該当しないリース取引 |
現時点(2024年8月)でのリース会計基準では、ファイナンスリース取引は通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うものと定められています。
一方で、オペレーティングリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとされています。
2023年5月の新リース会計基準の公開草案
2023年5月2日、ASBJより新たなリース会計基準の公開草案が発表されました。
ここでは新リース会計基準の概要や変更点などについて、詳しく解説します。
新リース会計基準の公開草案の概要
新リース会計基準の公開草案では、以下の項目が記載されています。
- 本公開草案公表の経緯
- 開発の基本的な方針
(借手の費用配分の方法、 IFRS第16号と整合性を図る程度) - 会計基準の開発方法
- 貸手の会計処理
- 範囲
(他の会計基準等との関係、個別財務諸表への適用) - リースの定義
- リースの識別
- リース期間
- 借手のリースの会計処理
(使用権資産及びリース負債の計上、 利息相当額の各期への配分、使用権資産の償却、短期リースに関する簡便的な取扱い など) - サブリース取引
(基本となる会計処理、中間的な貸手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、転リース取引) - 借地権
- 開示
(表示、注記、連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における表示及び注記事項) - 適用時期
- 経過措置
新リース会計基準の変更点
本公開草案において特に重要なポイントは、「会計処理においてファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の区別をなくす」という提案です。
この内容が適用されれば、ファイナンスリース取引だけでなく、オペレーティングリース・レンタル契約・不動産賃貸契約の費用もオンバランス処理(賃借対照表に費用を計上)しなくてはなりません。
ただし、一部の短期リースや少額資産のリースはオンバランス処理の例外とされており、リース料を直接費用計上できます。
リース会計基準の変更の目的・背景
リース会計基準に上記のような変更が提案された背景としては、「投資家が企業の経営実態を正しく把握できるようにする」というねらいがあります。
リース会計基準の参考元であるIFRSや米国会計基準ではすでに賃借対照表への計上が義務付けられており、公開草案ではその内容に合わせるような変更が提案されています。
海外の会計基準に足並みを合わせれば、海外投資家も日本企業の決算書をもとに分析しやすくなり、投資が容易になるからです。
ASBJとは?
ASBJ(企業会計基準委員会)は、公益財団法人財務会計基準機構内にある企業会計基準委員会のことです。
会計基準の開発や研究調査などを通じて、国際的な貢献を行うことを主な役割としています。
民間団体ですが日本の会計基準を作成しており、金融庁の承認を得てその内容が適用されています。
新リース会計基準の対象企業
リース会計基準の適用対象とされている企業は、以下の通りです。
- 株式上場会社
- 株式店頭公開会社
- 社債・CP等有価証券発行会社
- 会社法上の公開会社およびその子会社
- 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社およびその子会社
- 会計監査人を設置する会社およびその子会社
なお、リース会計基準の対象外である中小企業は「中小企業の会計に関する指針」に基づく会計処理でリース取引を計上するため、新リース会計基準の影響は受けません。
新リース会計基準で企業が受ける影響
新リース会計基準の内容が適用されると、対象企業では主に財務諸表と企業経営の面で影響が生じます。
具体的にどのような影響が出るのか、以下より解説します。
財務諸表への影響
従来のリース会計基準では、オペレーティングリース・レンタル契約・不動産賃貸契約の会計処理に関しては、リース料の支払い時に費用計上するのみとされていました。
しかし新リース会計基準が適用されれば、それらの取引もオンバランス処理が必須となるため、毎月経費処理をしなくてはなりません。
リース取引では使用権資産(リース期間中に物件を使用する権利)とリース負債(使用権に対して支払う債務)を帳簿に記録します。
リース開始までに費用が発生しなければどちらも同額ですが、リース料の前払いや運送費など事前の費用が発生した場合は、使用権資産の額に含めて計上します。
支払処理に関しては、使用権資産は固定資産と同じく減価償却の対象であり、リース期間中は月次で減価償却費を計上します。
また、支払金額から支払利息(リース債務の残高に割引率をかけたもの)を引き、その金額をリース負債の返済分として減額する処理が必要です。
各リース契約に対して上記の処理が必要になるため、オンバランス処理が適用されなかった取引をしていた企業にとっては、会計処理において大幅な負担増大を実感することでしょう。
企業経営への影響
従来の会計基準では、ファイナンスリース取引以外では固定資産と負債の計上が不要でした。
しかし先述の通り、新リース会計基準ではすべてのオペレーティングリース取引・レンタル契約・不動産賃貸契約でも使用権資産とリース負債の計上が必須になります。
つまり、使用権資産とリース負債が賃借対照表に計上されるため従来よりも負債が増え、自己資本比率が低くなるということです。
数値によっては借入金に依存した経営を行っているというイメージがつき、銀行融資ができない・貸付条件が厳しくなるといった可能性が考えられます。
ただし、企業経営の面において新リース会計基準の適用はデメリットばかりではありません。
従来は、リース料や賃借料は販売費や一般管理費として処理されていました。
新リース会計基準ではその一部を営業外費用の支払利息に振り替えられるため、営業利益は増えます。
さらにEBITDA(利息・税金・減価償却前利益)の計算においてマイナスの影響を及ぼすリース料や賃借料を、利息と減価償却に振り替えることができるため、EBITDAの上昇にもつながります。
その結果、自社の企業としての収益力に関する評価が高くなります。
新リース会計基準に対応するための準備
新リース会計基準が適用されると、主に経理で業務フローの大幅な変更を余儀なくされることが見込まれます。
そのため、適用に向けて以下の準備を着実に進めていきましょう。
現状の把握と影響分析
まずは自社が利用しているリース取引の把握が必要です。
新リース会計基準では、一部を除くリース取引・レンタル契約・不動産賃貸契約でオンバランス処理が必要になります。
自社が利用している取引のうちどれがオンバランス処理の対象となるのか、対象外の取引はあるのかについて整理しておきましょう。
併せて、経理業務の担当者への現状のヒアリングも必要です。
新リース会計基準では会計処理の工数が増加するため、現状の体制で対応しきれない可能性がある場合はこの段階で対策を検討しましょう。
【関連記事】自社が利用している取引を洗い出すのに有効な契約書管理台帳とは
内部体制の整備
現状と新リース会計基準の適用後に見込まれる影響を明らかにしたら、それに対応するための内部体制を整えます。
会計処理の工数増加により従来の担当者にかかる負担も増えることを前提に、既存の業務設計を見直しましょう。
伝票の手入力や紙契約などアナログな手法で進めていた部分があれば、システム導入でデジタル化するという手がおすすめです。
また、新たな業務フローの構築と併せて経理担当者の増員を検討しても良いでしょう。
新リース会計基準の対応方針が定まったら、運用開始に向けて社内の関係者や経営陣への報告を行います。
システムを導入する場合は、導入までのスケジュールに合わせて関係各所との調整を行いましょう。
システム導入と運用
新リース会計基準が適用されると、対象となる取引ひとつひとつをオンバランス処理しなければなりません。
取り扱う契約の件数によっては、従来の担当者だけでは手が回らなくなる可能性があります。
また、Excelで処理しようにも複数のファイルが存在し、更新・集計の手間がかかりデータ管理の煩雑化や入力ミスの増加が見込まれます。
効率的かつ正確に契約を管理しつつ、新リース会計基準に沿った会計処理を効率的に行うなら、会計システムと契約管理システムの併用がおすすめです。
会計システムは入力した取引データを自動で仕分けするなど、会計処理に伴う負担を大幅に軽減させる機能が備わっています。
加えて、契約書の一元管理が可能な契約管理システムなら、必要な契約書の情報をすぐに引き出すことができます。
システム間を連携することで、膨大な量の契約書を1枚ずつ確認しては会計システムに情報を打ち込む作業を省けるため、新リース会計基準の適用後も経理担当者への負担を抑えながら正しく処理することが可能です。
【関連記事】契約書管理システムとは?種類・主な機能・比較ポイント
新リース会計基準はいつから適用されるのか
新リース会計基準への対応準備を進めるうえで知っておきたいポイントが、具体的な適用時期です。
公開草案が公表されたのは2023年5月ですが、2024年8月現在に至るまで適用の兆しはみられません。
そのため、「新リース会計基準はまだ適用されないのか」「そもそも適用されるのか」…と不安に感じる方も多いことでしょう。
公開草案によると「公表から2年経過した日」から適用!しかし…
公開草案では、新リース会計基準の適用時期について「会計基準の公表から原則として2年(2事業年度)」と記されています。
これは公開草案の公表ではなく、最終基準化から2年後の4月に適用されるということです。
しかしASBJからは公開草案の公表以降、新たな情報や最終基準化の時期については明らかにされていません。
仮に本記事執筆時点の2024年8月以降に公表されたとして、原則の時期に準拠するとなれば2026年4月適用となってしまい、2年にも満たない期間での準備を強いられることになります。
公開草案に対するパブリックコメントでは3年以上の準備期間を求める声が多いこともあり、2026年度に適用される可能性は低いといえます。
上記を踏まえると、最も早くて2027年4月に適用される可能性が考えられます。
【関連記事】新リース会計基準の適用時期はいつから?草案の概要と改正への備え
新リース会計基準の対応はまだ間に合う!早めの準備とシステム導入の検討を
新リース会計基準では、ファイナンスリース取引だけでなくオペレーティングリース取引やレンタル契約、不動産賃貸契約でもオンバランス処理の対象となります。
それに伴い、会計処理の煩雑化・負荷増大や自己資本比率の低下といった影響が見込まれます。
具体的な適用時期は未だ不明ですが、まだ期間は残されているため、業務の現状把握と影響度の評価、その結果に合わせた対応方針の決定といった準備を進めておきましょう。
新リース会計基準は、取り扱う契約の件数が多いほど影響も大きくなります。
会計処理と契約管理の両方を効率化させるなら、システムの活用がおすすめです。
【関連記事】新リース会計基準の適用が延期に?適用時期や新基準の影響など解説