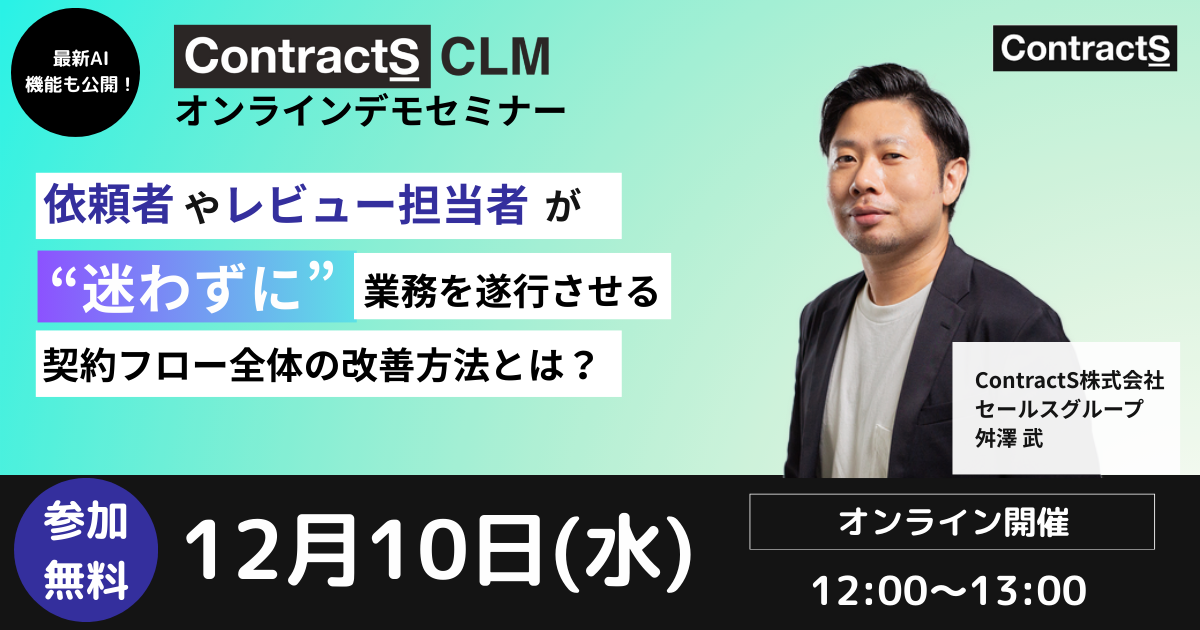ノウハウ 書類を電子化する6つのメリットと紙書類の電子化方法
更新日:2024年12月26日
投稿日:2024年05月21日
書類を電子化する6つのメリットと紙書類の電子化方法

「文書管理の効率化が図れそう」「必要な書類がすぐに見つかりそう」などの理由から、紙書類の電子化を検討する企業が増えています。
実は、書類を電子化すると業務効率アップや検索性の向上、コスト削減以外にもメリットがあります。
もちろん、電子化できない書類があるなど、書類の電子化にあたって注意点やデメリットもあります。では、なぜ電子化が推奨されるのでしょう。
本記事では、電子化のメリット・デメリットとあわせて、紙書類を電子化する方法と手順、電子化を検討すべき書類について解説します。
紙書類の電子化とは
紙書類の電子化とは、作成済みの紙の書類を、スキャンしたりPDF化したりして、パソコンやスマートフォンで閲覧できるようにすることです。権限さえあれば在社せずとも書類の内容を確認できるため、支店や子会社のデータが検索でき効率的に業務を進行できます。加えて、紙書類で必要な印刷や記入といった作業を省くことができるため事務コストの削減も可能とします。
書類の作成から受領までのやりとりを電子的な方法で行うことも、書類の電子化と言えます。
書類の電子化が推奨される背景
電子帳簿保存法やe-文書法で、紙書類の電子化は確実に進みました。多くの企業が電子化の推進を検討したきっかけは、働き方改革と言えます。働き方改革の取り組みのひとつにリモートワークがあります。
ところが、文書のやりとりや保管とリモートワークは相性が悪いです。承認のための押印や郵送、書類整理のためにリモートワークを導入していても出社が必要なためです。
そこで、書類を電子化することで、クラウドサービスやシステム上で書類管理や送信ができるようになります。電子契約であればシステム上で署名と押印も可能です。リモートワークで書類に関する業務対応を可能とします。
クラウドやシステムなら書類の検索もスピーディーです。進捗状況の把握や共有も電子的な方法で行えるため、紙媒体だと発生してしまう待機時間を減らせます。
紙の文書のまま回覧が進められると、進捗状況が分からず、誰が対応すべきタスクか不明なまま進められることがあります。結果、担当者が自分のタスクに気づくのが遅くなり、処理も遅れるケースが少なくありません。
さらに、処理の遅れや漏れを生じさせる従業員自身が遅延などに気づいておらず、トラブルを他部署のせいにすることも現場では起こり得ます。
進捗を正確に把握して遅延のリスクを減らすには、電子化による業務可視化と効率化が役立ちます。
業務効率化に向けても電子化は進められています。業務効率化が働き方改革にもつながります。
紙書類電子化の6つのメリット
コスト削減や業務効率アップなど、紙の書類を電子化すると得られる6つのメリットを紹介します。
コスト削減
書類を電子化すると、印刷や送付にかかる費用を節約できます。印刷などに費やしていた手間も省けます。
【関連記事】なぜ電子契約では印紙が不要なのか?理由と根拠を分かりやすく解説
検索性向上
紙書類を見つけるとなると、保管してあるファイルから必要なものを探し出さなければならないなど、検索に時間がかかって大変です。
電子化された書類であれば、保管しているクラウドなどから検索機能を用いてすぐに探し出せます。
業務効率向上
書類の電子化によって、印刷や郵送といった作業が不要になるだけではありません。思い立った時に書類の共有を行えるため、受け取りまでの時間が短縮されます。
作成から受領まで一括管理されるツールを用いれば、入力漏れの際には先の工程に進みません。書類不備に伴うやりとりをなくせる点でも、書類に関する業務の円滑化につながります。
保管スペース軽量化
紙の書類は、増える度に保管スペースを拡大しなければなりません。オフィス内に保管しきれないものについては、倉庫を借りなければならないこともあります。保管費用がかかることに加え、書類の取り出しに手間がかかります。
電子書類であれば、ストレージの拡張で済みます。物理的なスペースを増やさなくて済むということです。
物理的なスペースが不要なおかげで、オフィスの空間を有効活用できるようになります。
紛失防止
紙の書類だと、持ち出し時の紛失リスクがあります。一方、電子書類であれば、データのままパソコンなどから閲覧・編集できるため、紛失リスクに備えられます。複製やバックアップが容易なことから、万が一書類を削除しても、すぐに復元可能です。
アクセス制限をかけることで、重要文書のセキュリティ性も高められます。紛失に伴うリスクだけではなく、経年劣化の心配がないのも、電子文書の特徴です。
【関連記事】文書管理規程とは?重要な理由から作成の流れ・注意点まで解説
BCP対応できる
BCPとはBusiness Community Planning(事業継続計画)の頭文字をとった言葉で、自然災害やシステム障害などの非常事態が発生した時に重要な業務を中断することなく、事業を継続できるようにするための計画のことをいいます。
BCPは、企業の危機管理戦略の一環として不可欠であり、緊急時に迅速かつ効果的に対応するための手順やリソースを明確に定めることで整備することができます。
BCPを効果的に実施するためには、必要な情報や書類に即座にアクセスできる体制が不可欠です。この点で、検索性が高く、バックアップも容易に取れる電子化システムが役立ちます。電子書類を利用することで、災害やシステム障害が発生した場合でも、重要な契約書や指示書、計画書などを迅速に検索し、適切な対策を講じることが可能です。
例えば、クラウドベースの電子文書管理システムを導入しておくと、書類が失われるリスクを回避でき、遠隔地からでも必要な資料にアクセスすることができます。また、セキュリティ面にも対策を講じることで、情報漏洩やデータの消失といったリスクにも備えられ、事業の継続性がさらに向上します。
紙の書類を電子化する際の3つのデメリット
紙書類を電子化するにあたり、電子化ツールの選定や文書整理、ルールの整備といった準備すべきことがある点は、デメリットと言えるかもしれません。
電子化ツール選定に工数がかかる
あらゆる事業者が、電子化ツールを提供しています。ツールによって特徴が異なり、比較検討が必要と考えると、自社にマッチするツールの選定・導入は、即日できるものではありません。
紙書類を電子化するまでには、やるべきことが多いです。例えば、書類のスキャンなど。電子化完了までに時間がかかることも、考慮しなければなりません。
文書整理が必要
紙書類の電子化にあたってのルール、例えばファイル名や、1つのPDFに何枚の書類をまとめるかなどが統一されないと、電子化後の管理が大変です。
共通のルールに従って電子化できる書類を分類するためには、人の手が必要です。
ルールの整備が必要
紙書類を電子化するための作業に関するルールはもちろん、電子化してからのルールも設けなければ、書類が適切に利用されません。
電子化によって業務工程が変わると予想されることからも、滞りなく業務を進めるための新たなルールが必要になります。
電子書類は紛失リスクが低いものの、不正アクセスなどへの対応、要するにセキュリティ対策が求められます。アクセスに関するルールなども必要ということです。
電子化が検討される書類
e-文書法という法律で電子化が認められていない書類を除き、管理の手間が軽減されることを考えると、電子化を検討する価値はあります。
取引や決算、会社経営や財務に関する書類は、電子化が認められています。具体的には以下のような書類です。
- 契約書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 監査報告書
- 稟議書
- 定款
- 議事録
- 見積書
- 請求書
- 注文書 など
e-文書法をはじめ、法律に則った方法で行いましょう。書類の電子化が関わる法律については、後に詳しく解説します。
【関連記事】電子化できない書類とは?法律の要件や改正ポイントを解説!
書類のうち電子化できないもの
紙での作成・保管が求められるものは電子化できません。電子化できない書類として以下が該当します。
- 事業用借地権設定契約書
- 農地の賃貸借契約書
- 任意後見契約
上記は借地借家法といった関連法令で「公正証書により」「書面により」と定められています。
船舶備え付けの手引書といった緊急性の高い文書や、免許証・許可証など現物性の高い文書も、電子化が認められていません。
国税関係帳簿や決算書類については、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトで電子的に作成すれば、電子化した状態での保管は認められています。
注意が必要なのは、電子化したものを紙に出力して手書きで修正・加筆した場合です。元は電子的に作成した書類であっても、出力して手書きで訂正・加筆したものの電子化は認められていません。
【関連記事】電子化できない書類とは?法律の要件や改正ポイントを解説!
紙書類を電子化する手段・方法
自社の複合機やスキャナーを用いたスキャンは、電子化にすぐに取りかかれる方法です。自社で複合機やスキャナーを所有していない場合、スキャンサービスも活用されます。
電子化したい書類が大量にあるケースでは、外部委託も検討されます。
書類作成や管理といった付随業務も電子化したいのであれば、クラウドサービスの利用も有効な手段です。
文字情報の編集をして電子化したい時には、OCRという方法もおすすめです。
複合機やスキャナー、スキャンサービスによるスキャン
自社の複合機や専用のスキャナーを使用して、紙書類を電子化する方法です。スキャンしたデータは、PDFや画像ファイル形式で保存されます。
普段使用している機器で電子化に取り組むことができ、コストも抑えられます。
社内にスキャン機能を持つ機器がなければ、スキャンサービスを利用することも一つの手です。機密情報を含む書類など、外部の業者に依頼するのが躊躇される書類も、自社で電子化できます。
外部委託
外部の業者に委託することで、大量の書類も迅速に電子化可能です。
分厚い書類や、自社の機器では対応できないサイズの書類などの電子化に便利です。費用がかかること、自社の書類を安心して預けられるかなどに注意して、委託先を選ぶことが求められます。
クラウドサービス
電子契約システムなど、様々なクラウドサービスが存在します。
クラウドサービスの利用で、書類作成に携わる複数人が好きなタイミングでアクセスできます。バックアップや共有も、簡単です。
サービスに早く慣れることで、業務効率化につながります。研修やマニュアルがあると、より安心です。
【関連記事】紙で締結した契約書の理想の管理方法、作業フローを解説
OCR
OCRとはOptical Character Recognitionの略で、紙書類を光学的に分析して電子データにする仕組みです。
例えばOCRが搭載された文書管理システムなら、紙文書をスキャンして電子化する際、文字情報を検索できるようになります。元は紙の文書でも、契約書に含まれる文字情報から必要な書類をシステム上から見つけ出すことができます。
Googleドライブに保存した書類や書類を撮影した画像をワード検索できるのも、OCRが搭載されているためです。
カメラで単語や文章を翻訳したりコピーしたりできる機能も、OCR機能のおかげです。
OCRで読み取った箇所は文字データに変換されるため、書類の内容に変更が生じた際には変更を加えてから電子化した状態で保存できます。
紙書類電子化の手順
紙書類を電子化する場合、一般的に下記のような手順で進めます。
- 電子化する書類の選別
- 電子化方法や電子化後のルール設定
- 電子化する手段の決定
電子化する書類を把握でき、電子化を進めるためのルールや方法が決定次第、必要な書類の電子化を進めていきます。電子化の準備に必要なことを、手順ごとに見ていきましょう。
電子化する書類の選別
社内全ての紙書類を一度で電子化するのは負担が大きいです。通常業務に影響しない範囲で進めるためにも、優先度の高いものから進めることをおすすめします。
現場の声を聞きながらスムーズに完了しそうな書類から始めたり、社内で使用する書類から始めて電子化の効果を見たりなど、すぐに取りかかれそうなものから始めるのも良いでしょう。
電子化方法や電子化後のルール設定
電子化したファイルを保存する時の名称を統一します。例えば「作成日時_書類名」というルールであれば、ファイル名は「20241125_契約書」となります。ファイル名に法則があると検索しやすいです。
加えてスキャンやOCRで文字情報を抽出する場合、保存形式や解像度の共有も大切です。
ファイルの保管場所、書類ごとにどこまでアクセス権を与えるかも決めておきます。
電子化する手段の決定
自社で行うのか委託するのか、自社で進める場合にはシステムを導入するのか複合機などでスキャンするのか検討します。スムーズに電子化に移行できる方法を選択しましょう。
紙書類電子化のポイント
法律を確認することとシステムの比較、電子データの信頼性を証明するタイムスタンプの要否を知ることは欠かせません。OCRについても、検討の余地があります。
法律を確認する
法律の要件を満たした電子書類でなければ、適切に作成・保管された書類として認められません。「電子帳簿保存法」「e-文書法」は、紙書類の電子化にあたり確認すべき法律です。
電子帳簿保存法
税務関係帳簿書類をデータ化して保存することを可能とした法律です。「電帳法」とも略されます。
電帳法では、以下3つの保存方法に分類し、必要な対応を定めています。
- 電子帳簿等保存
- スキャン保存
- 電子取引データ保存
電子帳簿等保存は、会計ソフトなどで作成した帳簿や書類を、電子データのまま保存する方法です。
スキャン保存は、受領・作成した紙書類を、スキャンしてデータとして保存する方法です。
電子取引データ保存は、電子メールなどでやりとりした書類(請求書など)は、データのまま保存しなければならないと定めたものです。
電子データの保存を行う場合、下記4点の条件が定められています。
- マニュアルなどシステムに関する書類の備え付け
- データを確認できるディスプレイやアプリの備え付け
- 検索機能の確保
- データの真実性を担保する装置
e-文書法
電磁的記録による文書の保存、作成、閲覧などを可能とする法律です。
対象となる文書は、厚生労働省が所管する法令で保存を義務づけている書類です。
企業が使用している電子計算機に備えられたファイルか、磁気ディスクなどで作ったファイルでの保存・文書の作成が求められます。
システムによってできることが異なるので精査する
機能や性能はシステムによって異なり、特に検索性能は大きな違いがあります。
企業のニーズにマッチし、コストパフォーマンスの高いシステムを導入できるよう、料金・機能を比較検討することが重要です。
OCRを活用する
OCRを活用することで、書類からテキストデータを抽出できるようになります。文字情報の利活用が容易になり、価値ある書類を作成できるでしょう。
タイムスタンプの要否を確認する
タイムスタンプとは付与された時点でデータが存在していたこと、付与された以降にデータが改ざんされていないことを証明するためのシステムです。電子媒体で取引する際の信用性を担保する役割をします。
電子帳簿保存法でもタイムスタンプの定めがあります。タイムスタンプが必須となるのは、スキャンして保存する場合と、電子メールなどで送受信した書類をデータのまま保存する場合です。
電子帳簿保存法に対応した電子契約システムなどのクラウドサービスを用いる場合、タイムスタンプは不要です。
【関連記事】電子帳簿保存法でタイムスタンプは必要?不要となる要件を解説
書類電子化の成功事例
システムを活用した電子化で業務効率化に成功した2社の例を紹介します。1社は検索性の向上、もう1社は属人化解消への期待も実感いただいています。
契約業務の一元管理で業務効率化を果たした事例
株式会社つみきでは、紙ベースで契約書をやりとりしていた時は、保管体制が整備されていませんでした。過去の契約書の検索にも時間のかかる状態でした。
加えて、契約業務の進捗の把握にも課題がありました。契約の作成から締結、保管に至るまで体制を整える必要性を感じていました。
コロナ禍で在宅勤務に切り替わったこともあり、DXで課題解決できないか考えるようになりました。電子契約システムを比較検討し、保管も含めて契約業務を一元管理できるシステムが良いと考えました。自社の課題解決に最適と判断し、ContractS CLMを導入することになりました。
過去の契約書はスキャンしてシステムにアップロードし、契約書の作成から管理まで一元管理を実現しています。全ての契約業務の状況が可視化され、進捗がひと目で分かるようになりました。過去の契約書の検索性も向上しました。
印刷や郵送代のコスト削減も実感しています。契約業務の可視化と検索性の向上で、業務が円滑になりました。事実、契約業務1件あたりにかかる時間はスピードアップしています。
紙中心だった契約管理業務を「ContractS CLM」に集約。 タイムリーな進捗把握と検索性向上により、業務スピードアップを実現!
業務効率化を実現しながら属人化解消も期待される事例
株式会社第四北越ITソリューションズでは、ContractS CLM導入前から月間100件前後の契約が発生していました。全ての契約で紙の契約書が用いられていました。確認や差し戻しのやりとりは少なくありませんでした。担当者間の情報共有ができていない故のトラブルも起きていました。
契約締結はもちろん、締結前後の業務効率化の必要性も感じていました。
属人化、紙ベースで生じる無駄な作業やタイムロスといった課題も明らかになり、ペーパーレス化で解決できないかと考えました。システムのリサーチ中に、ContractS CLMなら1つのシステムで全て管理できると知り、導入を決定しました。
ContractS CLM導入後も、100万円以下の契約は紙ベースで行われているものの、約6割の契約は電子契約に移行できています。契約の可視化による業務効率化を実感しています。
ミスもすぐに確認と修正ができること、リーガルチェックによる差し戻しの減少などからも、契約業務がスピーディーに行われていると感じます。
また、1件の契約の対応にかかる時間は確実に短くなっています。
さらに、システム上で複数人でのチェックが可能となり、やりとりやコメントも履歴に残せます。ナレッジの蓄積で担当者の法的知識が深まり、属人化解消も期待しています。
100%紙ベースの契約から「ContractS CLM」導入へ。 契約フローの見える化で契約スピードの改善&ナレッジ蓄積に成功!
まとめ
紙書類の電子化は、業務の効率化やコスト削減、迅速な検索性の確保、さらに紛失防止といった多くのメリットをもたらします。加えて、BCP対応にも役立つ手段です。
一方で、電子化を進めるには、文書整理や電子化ツールの選定など、事前準備が欠かせません。また、電子帳簿保存法やe-文書法など、関連する法律の遵守も重要です。全ての書類を電子化できない点にも注意が必要です。
自社に適したツールを選ぶためには、サービスごとの特徴を比較し、目的に合ったものを選定することが求められます。書類の電子化でリモートワークといった働き方改革を進めながら、適切かつ効率的な文書管理も実現しましょう。
電子契約システム選び方や導入手順が分かる資料を
無料でダウンロード
この資料では、電子契約システム比較検討のカギ、具体的な手順、注意点、普及の様子、導入後の課題についてご紹介しています。