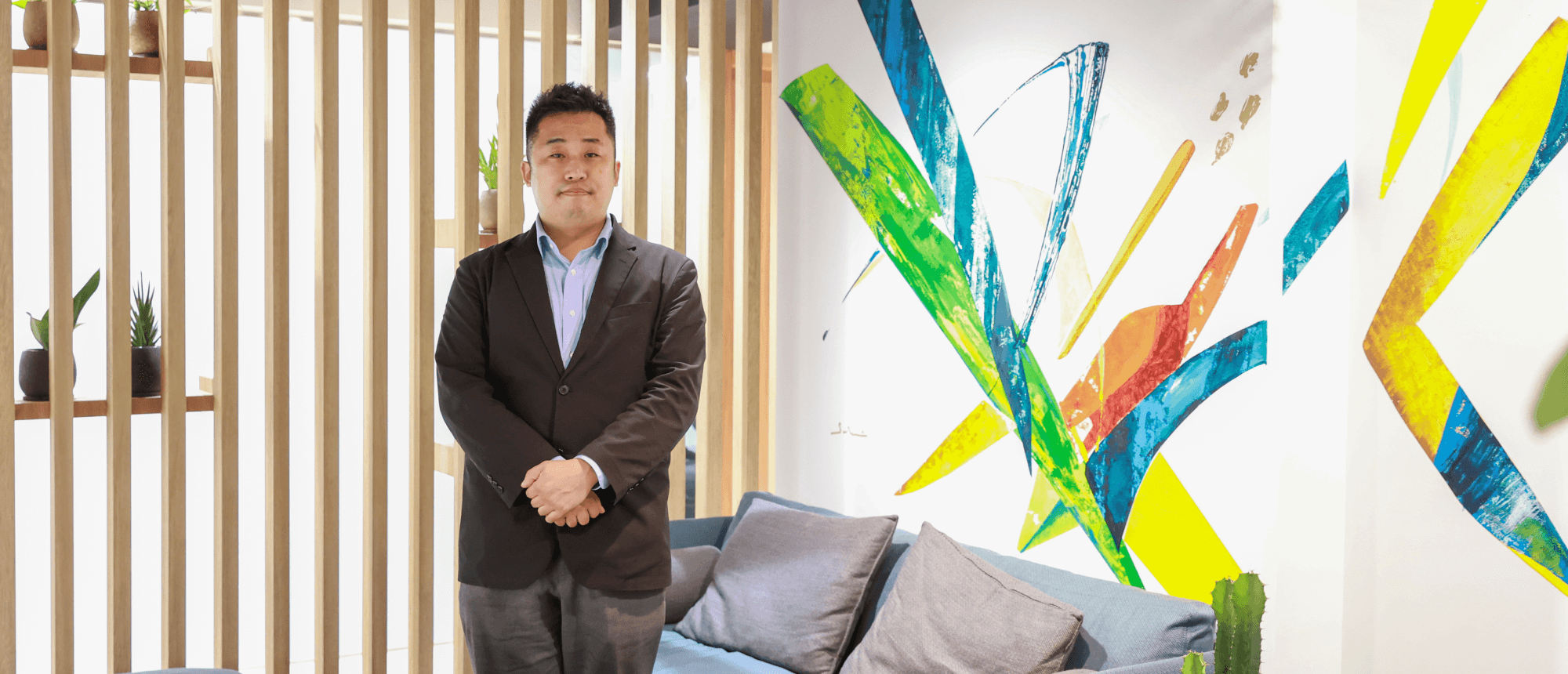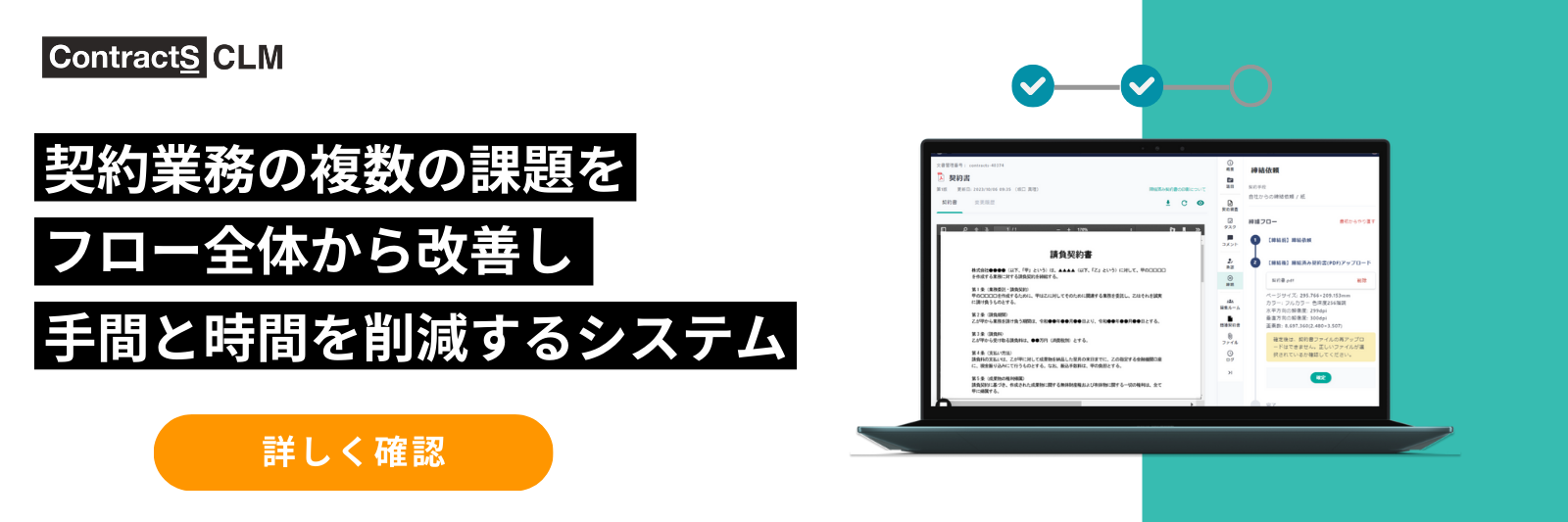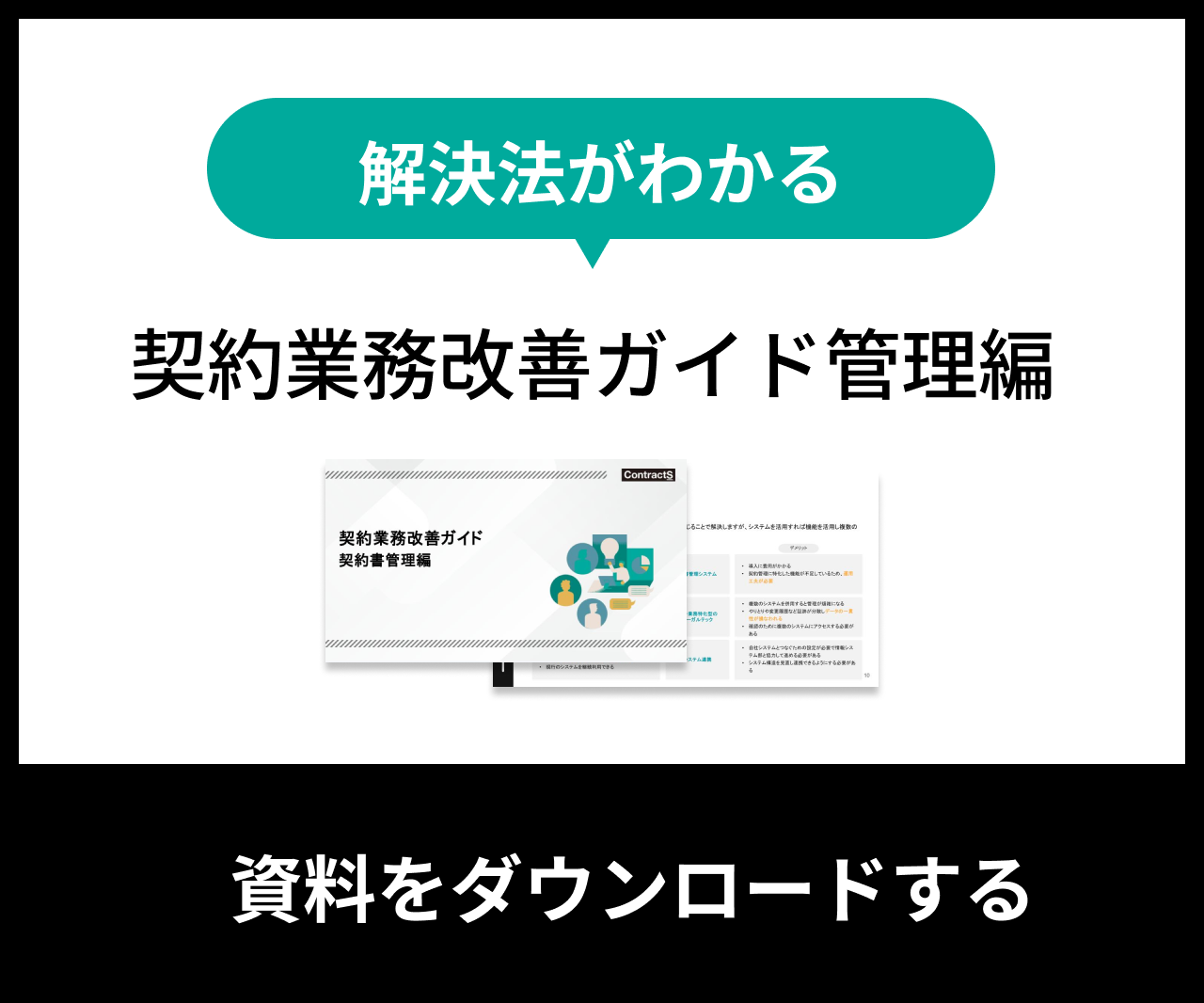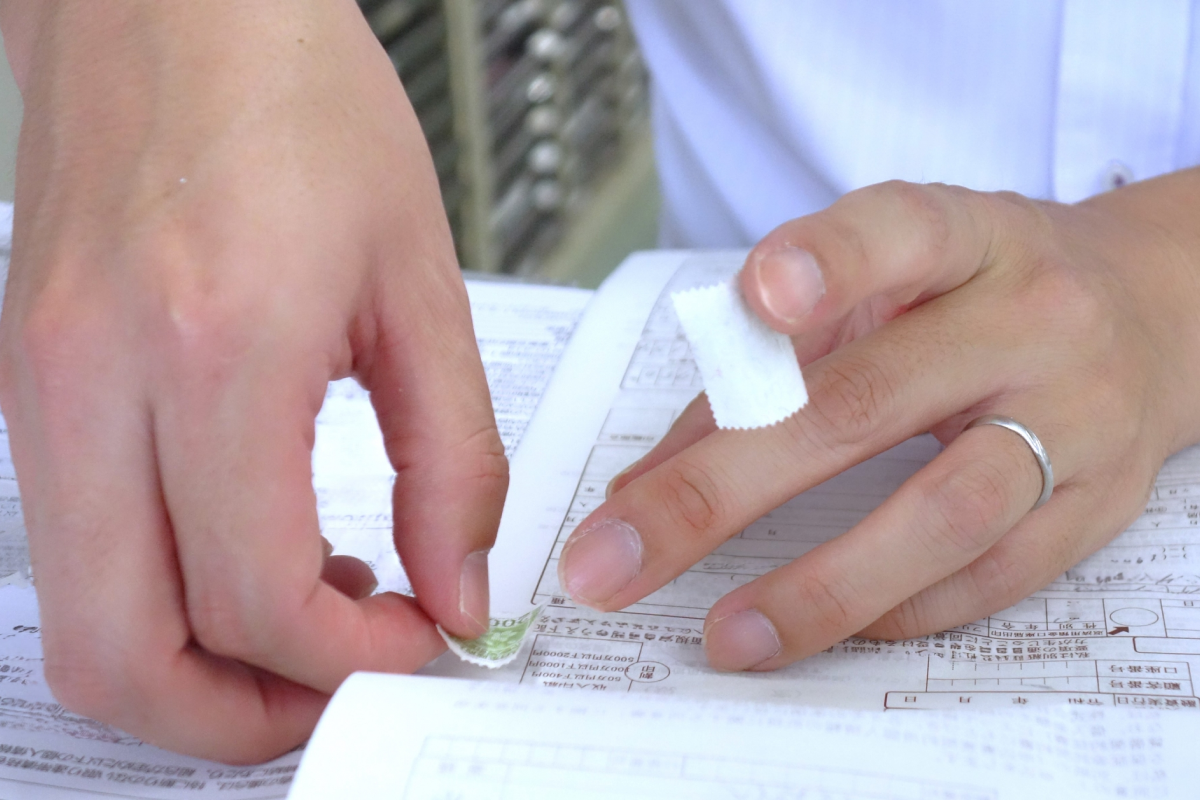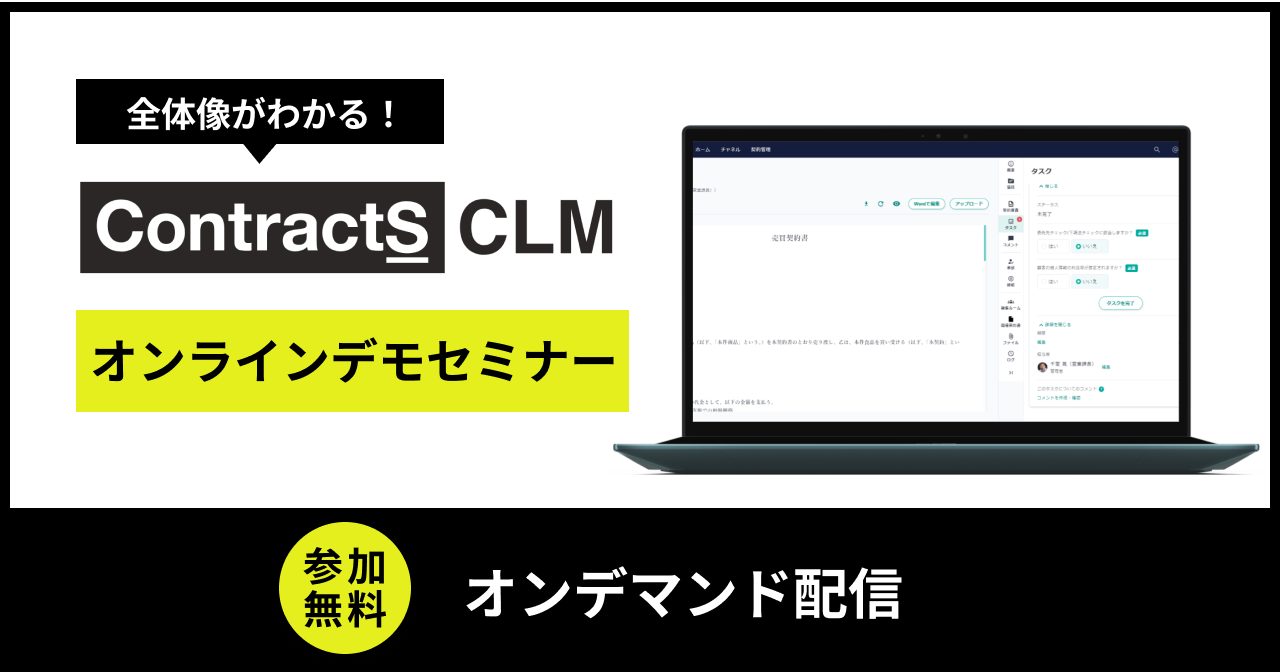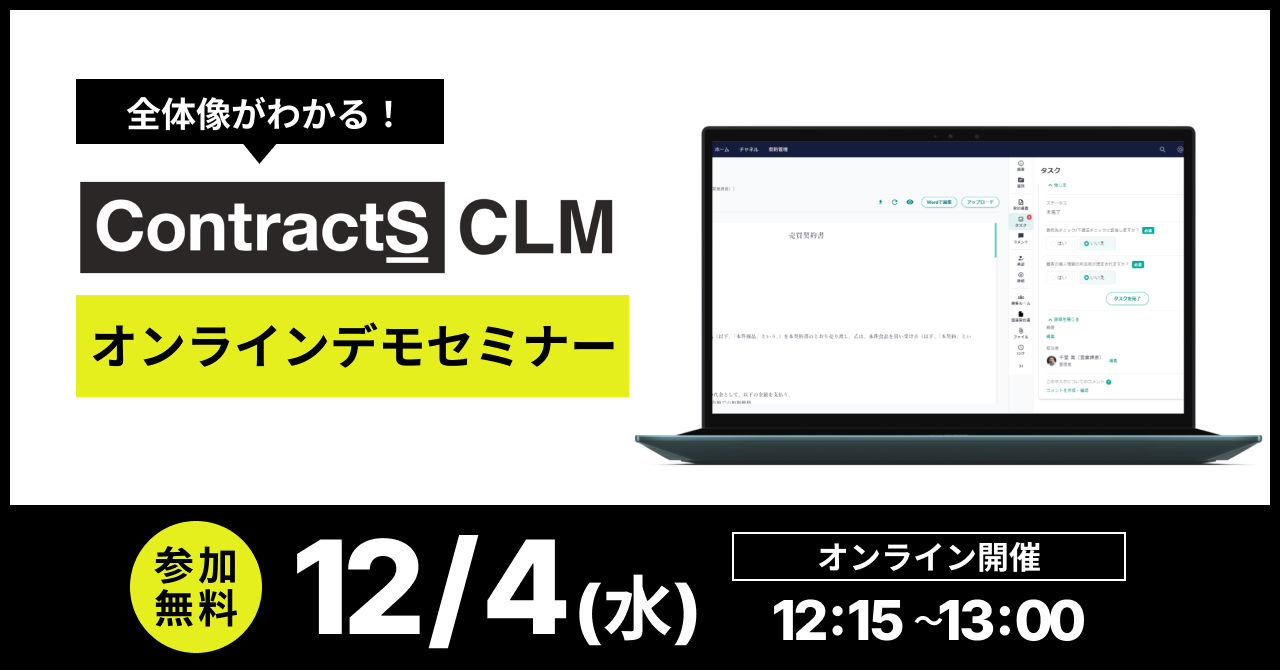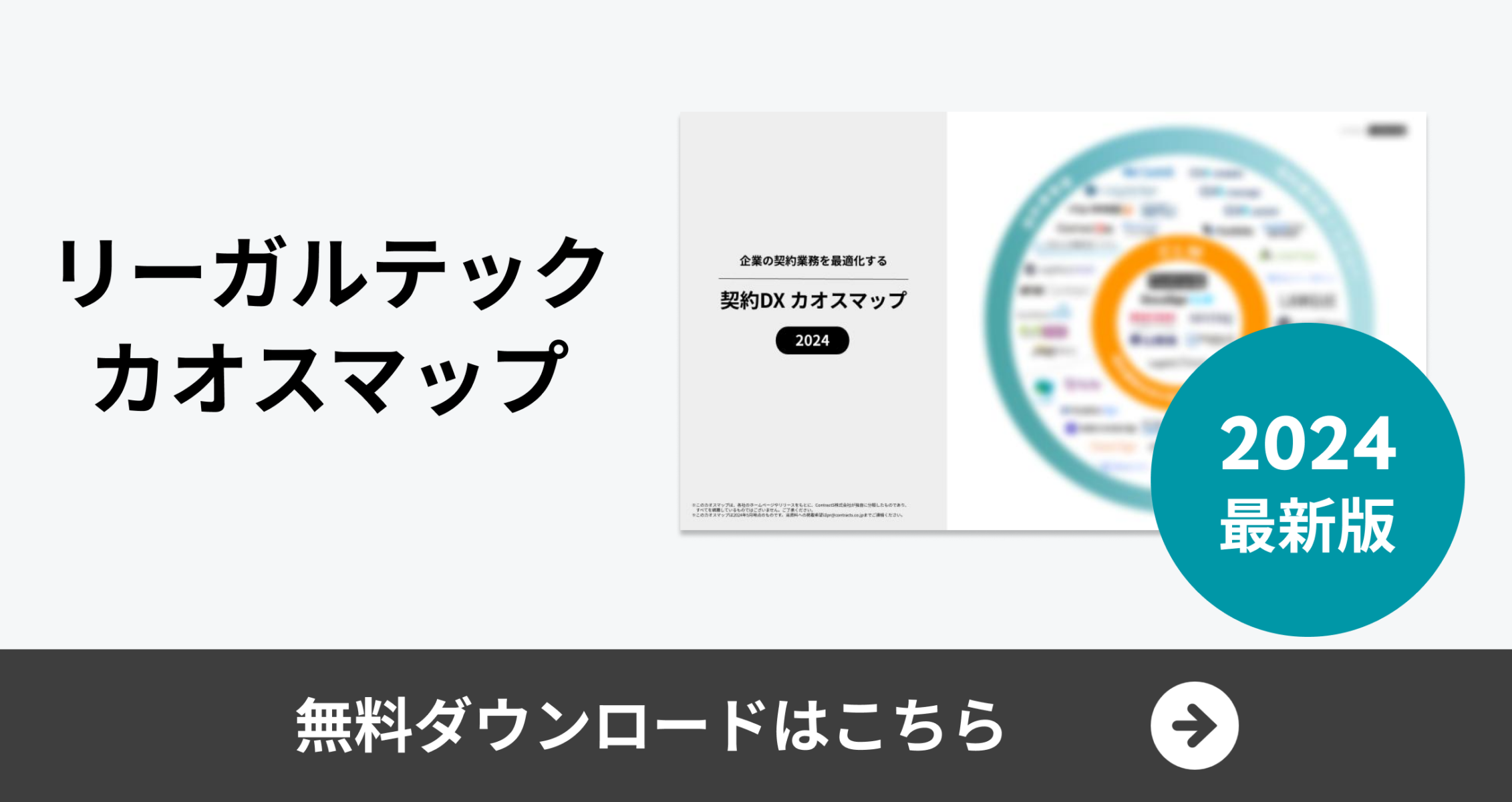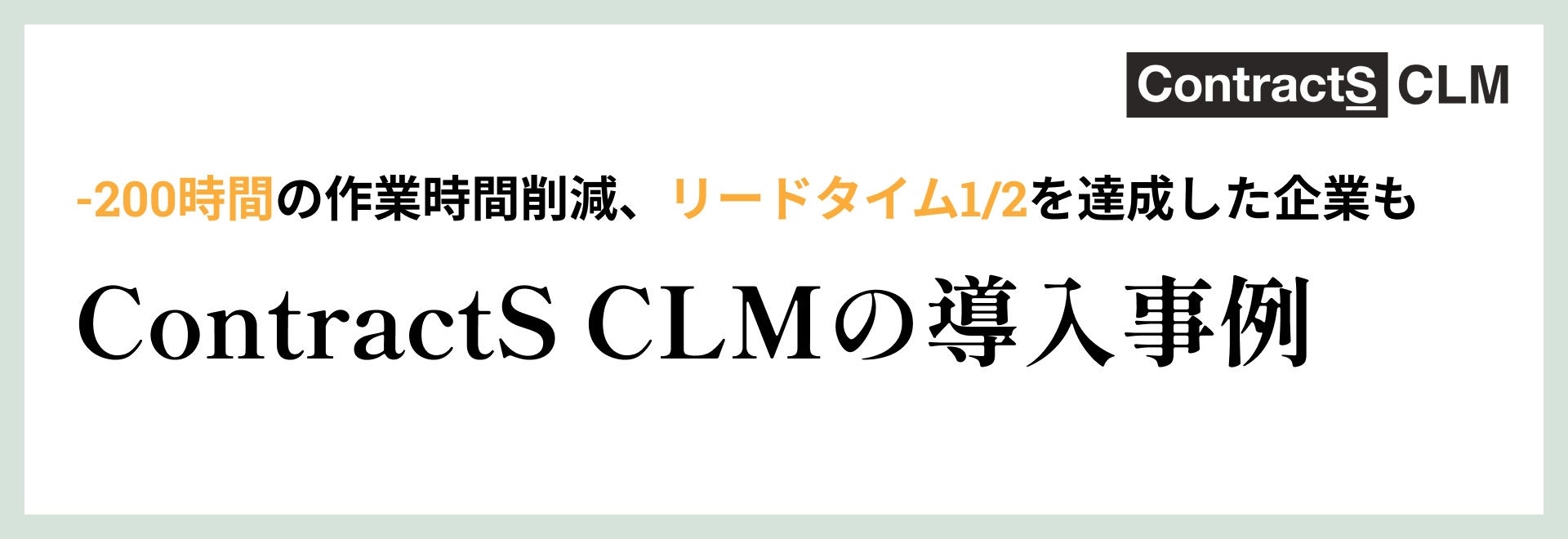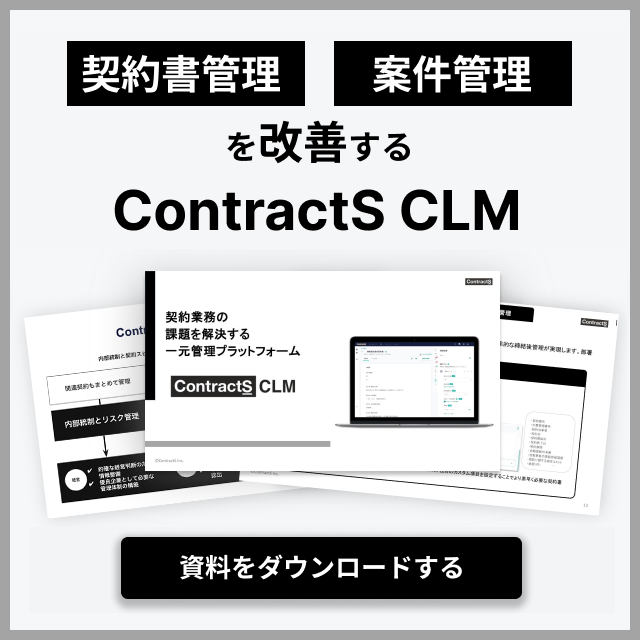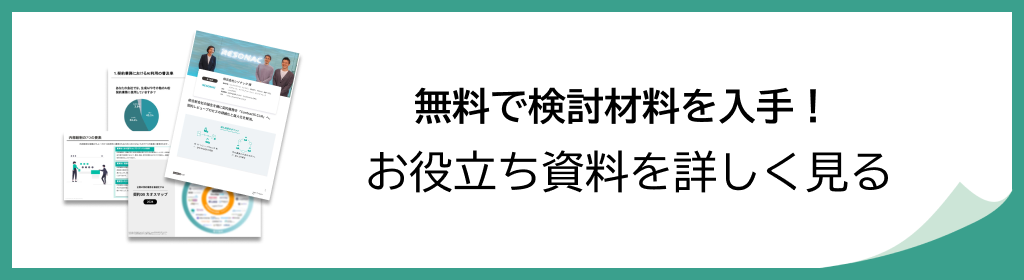ノウハウ BPRとは?メリット・デメリットと成功するシステム選びのポイント
更新日:2025年03月11日
投稿日:2024年03月18日
BPRとは?メリット・デメリットと成功するシステム選びのポイント

BPRとは業務プロセスを根本から見直し、全体的な改革を目指す考え方です。働き方改革やDX推進を受け、多くの企業の注目を集めています。
BPRが上手くいけば、生産性向上や顧客・従業員満足度の向上、コスト削減などを期待できます。ただし、工数・費用の課題や社内調整が必要な点などは注意しなければなりません。
本記事ではBPRの基本的な考え方や目的、業務改善やDXとの違いを解説しながら、進め方と手法、成功するためのポイントと成功事例についてご説明します。
BPRとは?
BPRとは「Business Process Reengineering」の略称で、業務改革のことを指します。
業務本来の目的に併せて既存の業務プロセスを全体的に見直し、業務フロー・組織体制・情報システムなどを再構築するという考え方です。
業務プロセスとは具体的に、特定の業務開始から終了までの一連の流れを指します。
PRの考え方は1990年代にマイケル・ハマーとジェームズ・チャンピーの著書『リエンジニアリング革命』で広く知られるようになりました。本書で、業務プロセスの根本的な再考と劇的な再設計によって、コスト、品質、サービス、スピードなど、業績における劇的な改善を目指すべきだと提唱されています。
両氏は従来の業務プロセスが部分的な改善にとどまっており、業務プロセス全体の改善に至っていない点を批判し、ITを活用しながら全体的な改革を行う必要性を説きました。
BPRの必要性を受けて、アメリカでは多くの企業がBPRを導入し、競争力強化や市場変化への迅速な対応に成功しました。
1990年代、日本でもBPRは注目を集めました。ところが、一過性の話題に終わり、広く浸透するには至りませんでした。しかし、ビジネスを取り巻く環境の変化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、民間企業や地方自治体など幅広い組織でBPRが再注目されています。業務効率化やコスト削減を実現するためにも、抜本的な改革というBPRの手法が再評価され、多くの組織が取り入れ始めています。
なお、「業務改善」や「DX」と混同されることもありますが、それぞれ異なる意味を持つ言葉です。
以下より、BPRが行われる目的や業務改善・DXとの違いを解説します。
BPRの目的
BPRを実施する主な目的としては、業務効率化・生産性向上・コスト削減・従業員満足度の向上などが挙げられます。
社内部署の分業化・専門化が進むにつれて、各部署における業務が個別に最適化されていくのはよくあるケースです。
結果として全体の業務プロセスが分断されて効率が低下する他、無駄な業務の発生によるコストの増幅なども起こり得ます。
そのような事態を防ぐための取り組みが、BPRです。
BPRと業務改善の違い
業務改善とは、業務に関わる人・モノ・情報といった一部の要素の無駄を削減する取り組みを指します。
BRPのように業務プロセスそのものは変更しないことが特徴で、必要な部分だけ見直し・改善してスムーズに業務を遂行できるようにします。
BPRとDXの違い
DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタル技術を活用して業務を改善する取り組みです。
クラウドやAIなどのデジタル技術で組織体制や業務プロセスを改善し、ビジネスモデルを変革して企業としての優位性の確立を目的としています。
一方で、BPRは既存の内部プロセスを見直して無駄を削減し、業務改善を図るのが目的です。
DXのように、ビジネスモデルの変革のために行うものではありません。
BPRが注目される背景
BPRは1990年初頭にアメリカで提唱された概念ですが、なぜ30年以上もの時を経て再び注目を集めているのでしょうか。
その背景には、近年の「社会的・市場的変化」と「デジタル技術の活用推進」があります。
社会的・市場的変化
『2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について(経済産業省)』で提示された生産年齢人口比率グラフでは、2020年から減少傾向が見え始めています。
また、2050年には人口約1億人まで、生産年齢人口比率はピーク時の50%程度にまで減少する見込みです。
働き手の不足により既存の業務プロセスでは対応しきれなくなり、何らかの対策を講じなければ業務の縮小を余儀なくされます。
加えてグローバル化の影響による企業競争の激化も見込まれることも踏まえ、国内企業におけるBPRの重要性が高まっているのです。
デジタル技術の活用推進
『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(経済産業省)』ではDXを推進しないことによる企業にとってのリスクや現状の課題などがまとめられており、BPRと同等にDXの重要性も説かれています。
ビジネスモデルに変革をもたらすDXを推進するにあたっても、既存の業務プロセスを維持したままでは思うように取り組めない可能性が高いです。
したがって、DXの推進が求められる現代の傾向に合わせてまずはBPRから取り組む必要もあります。
BPRのメリット
企業がBPRに取り組むことで、以下のようなメリットを得られます。
- 業務効率化と生産性向上
- 顧客と従業員満足度の向上
- リスクマネジメントの強化
- コスト削減
どのようなメリットを得られるのかそれぞれ解説します。
生産性向上と業務効率化の促進
BPRでは既存の業務フローから組織体制を見直すことになるため、業務プロセス全体の現状を俯瞰的に把握できます。
これにより、業務プロセスの中に潜む生産性・業務効率の低下の要因を的確に見つけることが可能です。
そのため、生産性向上・業務効率化において精度の高い対策を実行できるようになります。
顧客満足度・従業員満足度の向上
BPRの実施により業務プロセスに生じた無駄を省くことで、各従業員の負担の軽減につながります。
業務負担が軽減すれば労働時間の短縮につながり、各従業員がコア業務に集中しやすくなるため、満足度およびパフォーマンス向上にも期待できます。
結果として顧客へより良質なユーザー体験を提供でき、顧客満足度の向上という効果も現れます。
リスクマネジメントの強化
特定の従業員がいなければ進められない業務があるといった、「業務の属人化問題」を抱えている企業にとってもBPRのメリットは大きいです。
業務の属人化が進むことで、以下のようなリスクが生じます。
・業務のブラックボックス化により効率が低下する
・業務の品質管理が難化する
・担当社員の退職により業務の継続が困難となる
BPRに取り組めば業務プロセスを抜本的に見直すため、改めて業務を標準化させたりマニュアルを作成したりといった対応ができ、属人化の解消が可能です。
主に属人化に伴うリスクマネジメントを強化する手段としても、BPRは有効と言えます。
コスト削減
事業を続けていると、知らぬ間に業務プロセスの中に無駄な工程が生じており本来は不要な経費や人件費を出し続けていたというケースも珍しくありません。
BPRに取り組めば、業務プロセスの見直しを通じて無駄なコストが発生している要因も把握できます。
その要因に合わせた対策を講じることで従来よりも資金に余裕が生まれ、自社の成長に向けてより多くの投資ができるようになります。
BPRのデメリット
BPRは企業に様々なメリットを生み出す一方で、取り組みに工数・費用がかかることや社内調整が必要な点は考慮しておきましょう。そして何より、準備不足は失敗の要因であることは忘れてはなりません。
工数・費用に関する課題
BPRは業務プロセス全体を対象として再構築に取り組むため、相応に多くの工数と費用を要します。
詳細は後述しますが、基本的な工程だけでも従業員へのヒアリングや観察を通した現状の把握、データ分析、対応策の検討は必須です。
予想以上に手間がかかるからといってBPRを途中で断念すると社内に混乱が生じ、更なる状態の悪化につながります。
また、対応策の内容によっては新しい設備やシステムの導入に伴い多額のコストが発生する可能性もあります。
そのためBPRを実施するなら、一連のフローを完遂させるための入念な計画と実施後の費用対効果を意識した対策検討が必要です。
社内調整が必要
BPRの実施にあたって従来の業務プロセスから大きな変更が生じる場合もあり、従業員によっては混乱したり抵抗感を覚えたりする可能性も考えられます。
従業員が被る影響を考慮し、BPRの実施が決定したらその必要性や具体的な変更内容を社内に周知することが大切です。
これを怠ると、経営層と従業員の間に軋轢が生じてプロジェクトが失敗に終わる恐れもあります。
失敗リスクがある
BPRは、業務プロセスを根本から再設計するため、大きなメリットを期待できます。ただし、準備や業務プロセスの分析が不十分だと、失敗に終わる可能性が高いです。
例えば、現在の業務プロセスを詳細まで洗い出せていない、従業員の協力や理解が得られないなどで、計画通り実現することが難しく、計画立案で終わってしまうことがあり得ます。
また、目標設定が曖昧なために、成果を十分に得られないことも予想されます。
BPRは大規模な改革を伴うことが多いため、業務プロセスの大幅な変更によって従業員の負担が増加したり、既存の組織文化との摩擦が発生したりする可能性があります。
結果、従業員のモチベーションの低下や抵抗感が生じ、プロジェクト全体が停滞するケースも起こり得ます。
BPRの進め方
ではBPRは、どのような流れでどのように進めるべきなのでしょうか。
BPRの基本的な進め方は以下の通りです。
- 検討
- 分析
- 設計
- 実施
- モニタリングと評価
それぞれの工程で何をすれば良いのか、段階ごとに紹介します。
検討
まずは、BPRを行う目的と目標、実施する業務範囲を明確にします。
経営課題や業務の問題点を洗い出し、改革によって実現したいことを具体的にします。対象となる業務を担当する従業員へヒアリングすると、改善点とゴールを詳細に設定しやすくなります。
現場から経営陣まで巻き込み、共通認識を持った状態とすることがポイントです。
分析
現在の業務プロセスを見える化します。業務の流れから、効率低下の要因となるフローや無駄な作業を明らかにし、改善の必要な箇所を特定します。
分析段階でも現場の声を参照することで、実務レベルでの課題の把握に活かせます。
設計
洗い出した課題を基に、新しい業務プロセスの設計などの改善策を立案します。同時に、変更後の業務フロー、課題解決に必要なツールやシステムも明確にします。
複数の課題を一度で解決するとなると、従業員への負担が大きいです。そこで、解決の優先度を決定し、優先度の高いものから実施できるスケジュールも改善策とあわせて考えましょう。
実施
計画を実行に移します。新しい業務プロセスにすぐに慣れてもらうことが目的でもありますが、新しいツールやシステムを導入する際は特に、研修の実施やマニュアル作成・用意を行うことが好ましいです。
また、BPRの対象業務に携わる全ての従業員が確実に目標達成できるよう、実施目的とゴールを周知します。
BPRの最終ゴールに到達するための小さなゴールを設定することも有効です。例えば、契約業務の効率化のために社内全ての契約を電子化したい場合、電子化の効果を確かめながら移行する部署を徐々に拡大するといった進め方です。
モニタリングと評価
BPRは一度の実施で終わるものではありません。
新しい業務プロセス導入後は定期的にモニタリングを行い、成果を確かめることと、新たな課題がないか振り返ることが重要です。
新たに改善が必要な事項については、評価結果を参考にプロセスを見直し、再考したプロセスを評価する、というようにPDCAサイクルを意識して改善に取り組みます。
BPRの手法
BPRに用いられる代表的な手法は、以下の通りです。
手法 | 概要 |
業務の仕分け | 既存の業務を詳細に見直して優先順位をつけ、優先順位が低い業務は廃止やアウトソーシングを検討する |
ERPの活用 | 財務会計管理・予算管理・人材管理・在庫管理などの業務に活用できる「ERP(基幹系情報システム)」で日々の業務を管理する |
BPOの活用 | 「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)」で特定の部門やビジネスプロセスをそのまま外部企業に委託する |
シックスシグマ | 統計学を利用して事業経営の中で起こるミスを最小限に抑え、顧客満足度向上と品質改善を図る手法。 |
BPRを成功させるポイント
BPRは簡単な取り組みではなく、やり方を誤ると失敗に終わるリスクも十分に考えられます。
BPRを成功へ導くには、以下のポイントを意識することが大切です。
- 自社が抱える問題を明確化させる
- プロジェクトリーダーに適した人材を探す
- PDCAサイクルを継続させる
- 適切なツールやシステムを選ぶ
それぞれのポイントで意識して行うことをご説明します。
自社が抱える問題を明確化させる
BPRを実施するにあたって、現状の見直しと課題の洗い出しは必要不可欠です。
このフェーズを怠ると、BPRの方向性を定められずプロジェクトの開始すらままならない状態となります。
現場の従業員に任せきりにせず、経営層自らが自社の現状を理解したうえでBPRの方針を明らかにして組織全体に伝える必要があります。
プロジェクトのリーダーに適した人材を探す
BPRの実施前に、プロジェクトのリーダーを自社の人材から選任できるかどうかも確認しましょう。
企業によっては外部のコンサルタントに協力を依頼することもありますが、コンサルタントは必ずしも自社内に常駐したり完遂までフォローできるわけではありません。
プロジェクトの進捗状況を常時把握・管理して目標通りの方向性に導くプロジェクトリーダーは自社の人材が望ましいため、事前に探しておくことが大切です。
PDCAサイクルを継続させる
BPRの効果を高めにあたって、主要なプロセスを完遂したらそれで終了ではなく効果測定・改善・試行を繰り返す必要があります。
BPRの実施中に情報収集できる仕組みを構築し、評価結果に基づいてその都度異なる改革手法を採用する企業も多いです。
適切なツールやシステムを選ぶ
業務プロセスに適したツールやシステムを導入しながら効果的な改革とすることも、BPRの成功には欠かせません。
例えば契約業務におけるBPRでは、CLMシステムの導入が有効です。
CLMシステムとは契約書の作成から締結、管理や更新といった契約業務全体を一元管理するツールで、以下のような課題解決をサポートします。
- アナログ作業による非効率性の解消
- リスクの軽減
- 透明性の向上
契約業務の改善を目的とし、ビジネス全体の効率改善までできるように設計されたシステムであるため、豊富な機能群により電子契約、ペーパーレスといった目の前の課題改善以上にBPRへの効果も期待できます。
例えば、個別の企業に合わせた申請ルートのガイド表示や取り扱う契約書や業務負荷のレポーティング機能、CRMシステムとの連携による契約書作成の自動化やテンプレート機能の活用で、契約書管理や案件管理にかかる時間が短縮されます。
契約期限の通知機能は、更新の有無の対応漏れを防げます。契約書の内容に不備があって正しい内容が反映されずに締結されると、トラブルの要因になりかねません。しかし、バージョンごとに自動で保存されたり最新版が反映されているか否かを検知したりする機能で、法的リスクを小さくできます。
すべての案件の契約書はもちろん、関連書類もシステム上で保存・管理できるツールなら、契約に関する文書を一元管理でき、必要な書類を確実に見つけられる環境を構築できます。
加えて、スムーズな情報共有も可能にします。進捗確認もシステム上で行えるため、業務フローのどの段階に進んでいるのか誰もがひと目で把握できます。
契約業務プロセスに限らず、BPRが実現できること、自社に適していることの両方を満たすツールやシステムを選ぶためには、現状の課題を正確に把握し、解決に必要な機能を明確にすることがポイントです。
契約業務におけるBPRの成功事例
BPRを実施した企業は、具体的にどのような効果を得ることができたのでしょうか。
ここでは、「ContractS CLM」を用いたBPRの成功事例を2つご紹介します。
契約フローのすべてをContractS CLMで可視化
株式会社清和ビジネスでは従来、契約業務の多くを紙ベースで運用していました。
担当者は法務業務から契約書チェックまですべて担っており負担が大きいだけでなく、契約依頼・経緯の確認やレビュー内容などの情報も一元管理できておらず、情報の煩雑化が問題に。
そこで「ContractS CLM」を活用し、契約書作成・レビュー・承認・締結・管理まで、契約業務におけるすべての工程を一元管理する方法に切り替えます。
その結果、業務量や「収入印紙・郵送費」といったコストの削減に加え、契約業務に関する情報が一箇所に集約されたことで属人化の解消と業務効率化にもつながりました。
事例の詳細はこちら>>事業拡大に伴い、契約業務の負担が増加。 DX化で属人的な契約管理からの脱却と業務効率化を実現!
全国支店の契約業務を集約
日本システムバンク株式会社は「システムパーク」ブランドで全国7,000ヵ所にコインパーキングを展開しています。
コインパーキングを開設する際、土地所有者との契約締結は基本的に紙ベースで行っており、契約書の作成は総務部が担っていました。
しかし契約書の管理体制は全国に位置する各拠点でバラつきがあり、本社で進捗状況が把握できなかったり、拠点から届く契約書作成依頼の方法が異なったりして契約業務が煩雑化。
この現状を改善すべく、同社は契約書依頼から管理までの業務を「ContractS CLM」で対応し、全国7,000ヵ所の契約を集約させます。
本社で拠点ごとの契約進捗状況を管理できるようになった他、過去の契約書もContractS CLMにアップして検索性が向上したという効果も現れました。
事例の詳細はこちら>>全国15拠点ある事業所の契約情報を一元管理! コンプライアンスリスク低減を目指すフロー構築を実現
BPRで大きな効果を得るなら正しい理解と慎重な進行が重要
BPRは、業務プロセスの抜本的な見直しと再構築を通じて、業務効率化・生産性向上やコスト削減だけでなく、従業員や顧客の満足度向上にもつながる重要な取り組みです。ただし、実施にあたって綿密な準備と詳細な計画が求められます。
本記事で紹介した進め方や手法、適切なツールやシステムの選び方といったポイントを参考に、自社に最適な形でBPRを取り入れることで、目まぐるしく変化するビジネス環境に対応できるでしょう。
【関連記事】業務改善に有効なシステム導入の流れとは?注意点や準備のポイントも