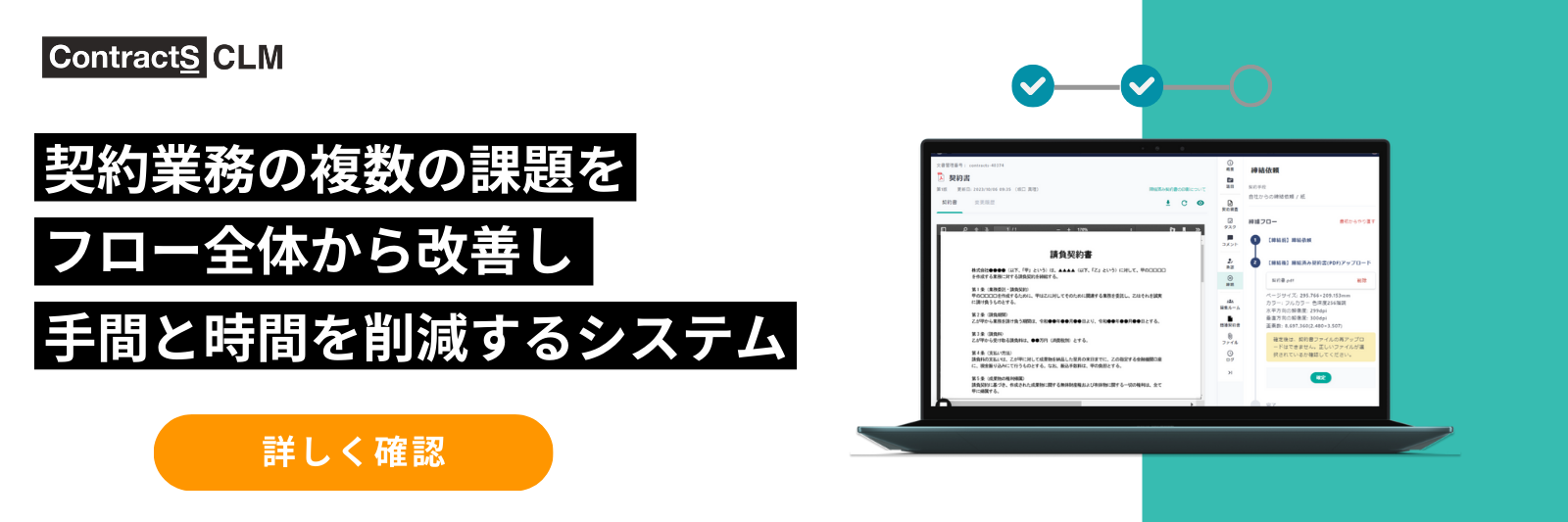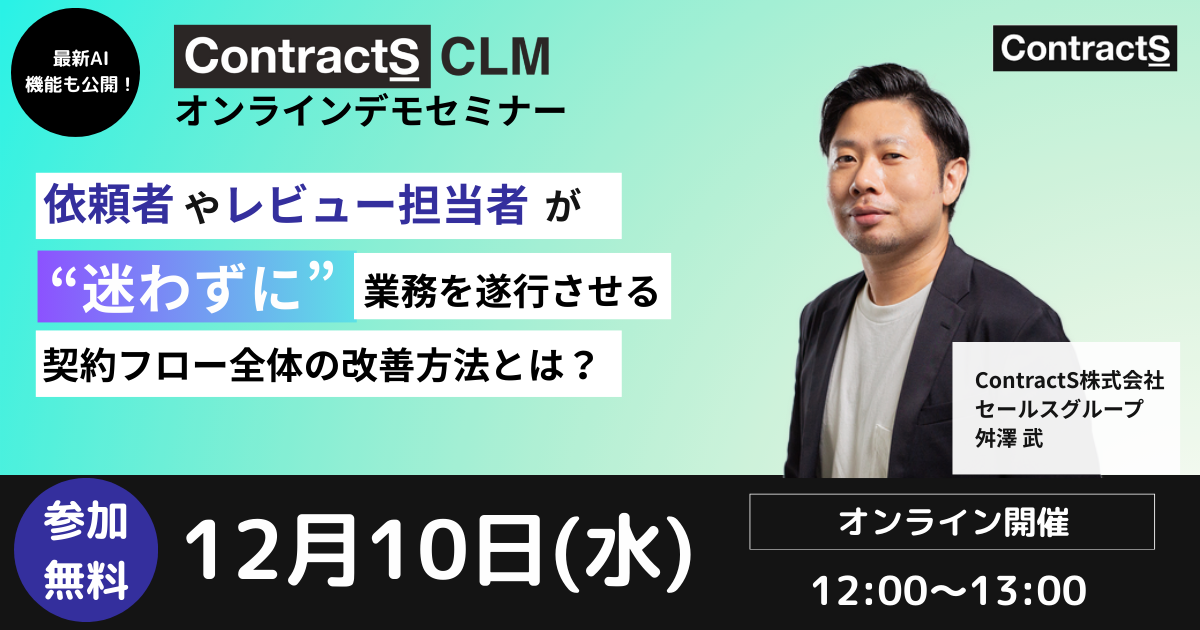ノウハウ 社内DXの目的と成功の鍵とは?必要性・成功事例・活用ツールを紹介
更新日:2025年03月11日
投稿日:2024年02月21日
社内DXの目的と成功の鍵とは?必要性・成功事例・活用ツールを紹介

企業におけるDX推進の重要性が説かれている現代、その一環として「社内DX」に取り組む企業は増えています。
社内DXを進めることで、業務効率化や競争力の強化といった大きなメリットが得られます。
そこで本記事では社内DXの定義と必要性を説明しながら、進め方、成功させるためのポイントと注意点、活用できるツールについて解説します。
社内DXとは?
社内DXとは、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ITやデジタル技術を活用して自社のビジネスモデルに変革をもたらすことです。
DXにあたる取り組みは様々なものがありますが、その中でも組織の体制や働き方など、範囲を社内に限定して変革を図る取り組みを「社内DX」といいます。
例えば従来は紙で管理していた書類を電子化したり、単純なデータ入力作業をITツールで自動化したりといったことも社内DXに含まれます。
社内DXが重要視される理由
企業にとって、社内DXは非常に重要性の高い取り組みです。その主な理由としては、以下の5つが挙げられます。
- BCP(事業継続計画)対策のため
- 業務プロセスの効率向上
- 迅速な意思決定
- 競争力の強化
- 従業員エンゲージメントの向上
それぞれの理由を補足します。
BCP(事業継続計画)対策のため
BCPとは、災害など予期せぬ事態に陥っても事業を継続・迅速に再開できるようにする対策のことです。
地震や台風などの自然災害が起こりやすい日本の企業にとって、BCP対策の強化は必須と言えます。
書類のペーパーレス化を進めたりオンライン会議システムを活用したりといった社内DXに取り組めば、自然災害・事故の発生時でも重要な書類や情報を失わず、各従業員がテレワークで安全に業務を続けられるといった効果が得られます。
業務プロセスの効率向上
社内DXでは基本的に何らかの業務プロセスをデジタル化するため、効率性に悩む企業にとっても有効な改善策になります。
例えば、ペーパーレス化により書類管理の手間を省く、手作業で行っていたデータ入力の自動化といった社内DXにより、少ない労力でより多くの業務量をこなすことも可能です。
また、ヒューマンエラーのリスクも下がるため生産性の向上にも有効です。
迅速な意思決定
従来は、経営側の経験を参考に自社の指針を定めるケースが一般的でした。
しかしそれは主観的な考えになりやすやすく、客観的な意見やデータを参考にしようにも収集に手間がかかります。
社内DXとしてITツールを導入すれば、社内外に分散するデータの収集から分析まで容易に行えるため、迅速かつ精度の高い意思決定が可能になります。
競争力の強化
情報技術が発達している現代社会において、その時流に沿った内部体制を整えなければ競争力において他社と大きな差がつきやすくなります。
今や消費者は自ら情報を収集のうえ製品やサービスを選択することが当たり前になっており、ただ製品・サービスを提供するだけでなく、いかに付加価値を提供するかが競争力を落とさないためのカギです。
社内DXを推進すれば顧客対応のスピード・満足度や品質の向上につながり、企業競争力の維持・強化がしやすくなります。
従業員エンゲージメントの向上
従業員エンゲージメントとは、各従業員が会社の理念に共感して自発的に貢献しようとする意欲のことです。
少子高齢化問題や正規雇用にこだわらない人が増加傾向にある現代、人員不足を防ぐには従業員エンゲージメントの向上が重要になります。
社内DXを進めて社内に蓄積された情報のデジタル化やテレワークツールなどを導入すれば、各従業員が自分に合ったスタイルで働きやすくなり、結果として従業員満足度の向上からエンゲージメントの向上につながります。
社内DXは必要?しないとどうなる?
社内DXは、業務効率の向上や競争力強化、コスト削減などのために不可欠です。デジタル技術を活用しないと、どのようなリスクが想定されるのでしょうか。
業務の非効率化
社内でDXを推進しない場合、業務の非効率さがさまざまな場面で顕在化します。
例えば、紙や異なるシステム間での情報管理が続くと、データの検索や共有に時間がかかり、必要な情報をすぐに見つけられないといったことが発生しやすくなります。
また、手作業が多いため、ヒューマンエラーのリスクが高まり、修正や確認作業が増加します。部署ごとに異なるツールや管理方法を採用している場合、情報の分断が発生し進行の遅れを引き起こす可能性があります。
競争力の低下
社内でDXを推進しない場合、業務の競争力は徐々に低下していきます。
DXが進んだ企業は、AIや自動化を活用して業務効率を向上させ、コストを削減することで競争力を高めています。競合他社がデジタル技術を活用して業務効率やサービス品質を向上させる中、自社だけが従来の方法に固執していると、コストが高止まりし、価格競争でも不利な立場に置かれる可能性があります。
また、DXが進んでいない企業は、新しいビジネスモデルへの対応が遅れ、業界全体のデジタル化の波に乗り遅れることで、顧客や取引先からの信頼を失うことにもつながります。結果として、企業の成長が停滞し、市場における競争力の低下が避けられなくなります。
ビジネスチャンスの取りこぼし
社内でDXを推進しない場合、ビジネスチャンスを逃す可能性が高くなります。
まず、アナログな業務フローのままでは、市場の変化や顧客のニーズをリアルタイムで把握することが難しく、機会を見極める前に競合に先を越されるリスクが生じます。
例えば、データの活用が進んでいなければ、顧客の購買傾向や市場の動向を正確に分析できず、新しい製品やサービスの開発が遅れてしまいます。
コスト増加
社内のDXを行わない場合、業務にかかるコストは年々増加していきます。まず、紙ベースの書類管理では、印刷代や郵送料などを負担し続けることになります。これらの費用は値上げとともに増加し、経費の負担はさらに大きくなります。
また、手作業でのデータ処理が続くことで、人的リソースが過剰に必要となり、人件費が膨らみます。
さらに、業務フローがデジタル化されていないと、同じ情報を何度も入力する手間が発生し、入力ミスによる修正作業や確認作業が増えてしまいます。これにより、単純な作業に多くの時間とコストを費やすことになり、本来注力すべき業務に割けるリソースが減少してしまいます。
セキュリティに関するリスクの高まり
機密情報をデジタルで保存・管理する場合、セキュリティ対策の万全なツールを導入しなければ情報漏えいなどのリスクが高まります。しかし、全ての文書を紙のまま扱っていると書類の紛失による情報漏えいのリスクが懸念されます。
暗号化して保存される、閲覧・編集の制限が可能なシステムを活用すれば、アナログ管理と比較して情報漏えいのリスクは低くできます。ただし、デジタルツールを導入していたとしても、適切なタイミングで新しいシステムへ更新しなければ、新たな脅威に対応できない点は注意が必要です。
社内DXの進め方
社内DXの基本的な進め方は、大きく以下5つのプロセスに分けられます。
- 目標、目的を設定する
- 課題を掘り起こす
- DX化を行う対象業務、部署を決める
- DX化後の業務プロセスを描く
- DX化ツールの検討
それぞれの工程で何を行うのか、プロセスごとに解説します。
1.目標、目的を設定する
社内DXに失敗する原因として特によく見られるものが、社内DXを目的として取り組んでしまったというケースです。
社内DXはあくまで企業に改革をもたらすための手段であるため、「なぜ社内DXに取り組むのか」「社内DXでどんな効果を得たいのか」という目標・目的から定める必要があります。
2.課題を掘り起こす
目標や目的を設定するにあたって、自社の現状を把握のうえ課題を掘り起こしていきましょう。
そのためには、現場の従業員から意見を収集する必要があります。
現状の業務で不満に感じていることや社内DXで改善を求めることなど、様々な意見を集めましょう。
その中で優先度を評価し、どんな課題から解決していくかを定めます。
3.DX化を行う対象業務、部署を決める
明確化した課題を元に、優先度の高い課題から社内DXによる解決方法を策定していきます。
課題を解決するために、どんな業務や部署のDX化に取り組むかを決めましょう。
4.DX化後の業務プロセスを描く
対象業務・部署を定めたら、現状の業務プロセスと既存のシステムに潜む問題点を整理します。
そのうえで、DX化に取り組んだ後の業務プロセスを見直し改めていきましょう。
例えばペーパーレス化や電子契約、データ入力の自動化などは比較的簡単に導入できます。
DX化のために通常業務を停止することはできないため、まずは手軽にできる取り組みから着実に業務プロセスへ組み込んでいくことも1つの手です。
5.DX化ツールの検討
DX化後の業務プロセスを描いたら、どんなツールやシステムでそれが実現できるのかを考えます。
ハードウェア・ソフトウェア・通信環境・操作性など、様々な観点から最適なツールを定めて選ぶことが大切です。
社内DXを成功させるためのポイント
社内DXは、ただ基本的な進め方をなぞっただけでは成功につながりません。
- DX化プロジェクト担当者を設定する
- DX人材を設ける
- DX支援を活用する
上記3つのポイントを意識しながら、自社に適したやり方で進める必要があります。
DX化プロジェクト担当者を設定する
社内DXを効率的に進めるには、設定した目的・目標へ向かって正しくプロジェクトを進行させるための担当者が必要です。
特に、DXでは以下のようなスキルを持つ人材がいるかどうかが重要になります。
・プロジェクトをマネジメントする能力がある人
・ビジネスにおけるデジタル技術やデータ活用に対する理解が深い人
・社内DX推進の重要性を理解している人
また、DXを進めるには社内全体の理解も必要不可欠です。
担当者を集めたチームには、DX研修を行うなどして社内の理解を深める役割もあります。
DX人材を設ける
DXプロジェクト担当チームを設ける場合、DXに関する知見が豊富な人材も重要になります。
最先端のIT技術に精通しており、なおかつ社内での影響力も持つ人材が理想的です。
自社に適した従業員がいなければ外部のDX人材育成セミナーに参加してもらうなどして育成したり、DXプロジェクトに携わった経験を持つ人材を採用したりしましょう。
DX支援を活用する
DX支援とは、DX人材の育成や基幹システムの整備など、企業のDX推進を専門的にサポートするサービスのことです。
DXを推進する目的を明確化する方法からIT技術の導入・運用まで、総合的なサポートを受けられます。
初めてDXに着手する場合や、すでに着手したものの期待した効果が得られなかった場合はDX支援の活用も視野に入れましょう。
また、政府もDXに取り組む企業の支援制度を設けており、条件を満たせば「IT導入補助金」や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」などを利用して必要な資金を調達することも可能です。
社内DXに活用できるツール
DX推進に役立つツールは数多くありますが、目的や対象業務などによって選ぶべきツールは異なります。
社内DXに活用できるツールとしては、大きく分けて7種類あります。
ここでは、社内DXで活用できるツールの種類と特徴を詳しくご紹介します。
RPAツール
RPAツールとは、ロボットを利用して業務を自動化できるシステムのことです。
データ入力やコピー&ペーストといった、単純な反復作業の自動化に活用できます。
Excelなどに搭載されている「マクロ」と似ていますが、RPAツールはプログラミングがなくても簡単な操作で業務の自動化を設定できることが大きな違いです。
処理量が多く、人の判断を必要としない業務に導入すると効果的なツールと言えます。
SFAツール
SFAツールは「営業支援システム」とも呼ばれており、顧客情報・案件情報・営業活動の行動と結果などを管理できるツールです。
営業活動のプロセス・進捗や顧客へのアプローチ方法・結果を簡単に報告できたり、それらの情報を可視化して営業活動の分析とフィードバックができたりという効果を得られます。
BIツール
BIツールとは、企業に蓄積された膨大なデータから必要な情報を集約・分析して経営や業務に活かせるように支援するツールです。
企業が持つデータの中には、売上データや生産管理データなど、部署や店舗など異なる場所に分散されてしまうものもあります。
BIツールを使えばそのようなデータも1つのシステムでまとめて管理でき、経営状況の傾向や新たなビジネスの可能性を見出すことができます。
タスク管理ツール
タスク管理ツールとは、チームメンバーごとのタスクを簡単に管理できるツールのことです。
メンバーごとのタスクの開始・終了日時や進捗状況がカレンダー上に表示されるため、タスクの優先順位が分かりやすくなるうえに全体のバランスを見ながら効率的にスケジュールを立てられます。
製品によってはチャット機能もあり、メンバー間のコミュニケーションを円滑化させる効果も期待できます。
人事管理ツール
人事管理ツールとは、従業員の採用・評価・勤怠管理・労務管理・給与計算など人事業務の効率化に役立つツールです。
製品によって特化している業務は異なるため、DXを進めたい業務内容に合ったものを選ぶ必要があります。
人の手で行われていた人事業務の工数削減や、精度の高い人事評価が可能になることが大きなメリットです。
ワークフローシステム
ワークフローシステムは、業務の中で発生する「申請・承認・決裁」といった手続きの流れをシステム化できます。
フォーマット化した申請書類を使って各種申請ができ、内容に合わせたルートで承認が進んでいくため工数の削減とヒューマンエラーの防止につながります。
ナレッジマネジメントツール
ナレッジマネジメントとは、従業員が持つ知識・経験・ノウハウといった「ナレッジ」を社内で共有したり活用したりする取り組みです。
会社に蓄積されたナレッジを社内で共有し社内全体のパフォーマンスが向上したり、業務の属人化を防止できたりといった効果があります。
ナレッジマネジメントツールは、ドキュメントやFAQなどの機能でスムーズなナレッジ共有の実現をサポートし、ナレッジマネジメントの効果を高めるのに有効なツールです。
社内DX推進の注意点
システムの導入がDXの目的ではないことと、社内全体で必要性を認識した状態で進めないと、DXのメリットを得ることは難しいです。また、DX人材や予算を事前に確保することなどもポイントです。
システム導入を目的にしない
DXの目的は業務効率化やビジネスチャンスの拡大、従業員エンゲージメントの向上などです。システム導入は、企業の課題を解決して目標を達成するための手段に過ぎません。
デジタル化の目的が分からないままツールの導入を目標としてしまうと、課題解決に適したシステムを選定できず、社内にDXが浸透せず、かえって無駄に終わってしまうことが懸念されます。
例えば契約業務の効率化を実現したいのか顧客情報の分析を効率化したいのかでは、もちいるシステムは異なります。
DX人材など最適なリソースを確保する
DXを成功させるためには、適切な人材の確保と育成に加え、十分な予算や適切なツールなどを準備することが不可欠です。リソースが不足すると戦略が形だけのものになり、実施されずに終わる可能性があります。
DX化を進める人材として、IT部門やITに詳しい上層部などが挙げられます。ただし、DX推進の担当者のみがITに詳しい状態だと、現場の従業員に必要性を理解されないリスクが高まります。そこで、デジタル技術の基礎知識、DXの重要性や自社へのメリットなどを理解してもらう機会を設けることも必要です。
そして、必要なツールの要件を明確にし、予算確保へ動きましょう。
全社全体で必要性を再確認する
DXをスムーズに進める上では、経営層から現場の従業員までDXの必要性を理解し、納得していることが重要です。
システムの導入で既存のプロセスに変更が生じることは珍しくありません。また、デジタルツールが苦手な方にとっては、業務のデジタル化に負担を感じることも懸念されます。
事前に十分な説明や教育を行わないと、反発が生じ、プロジェクトが頓挫する可能性もが高まります。
DXの必要性を理解してもらうことはもちろん、優先度の高い業務や部門からDXを導入してみて効果が分かると、自身の業務や部門で取り組む必要性を実感してもらいやすいでしょう。
社内全体で一度に取り組むことで現場が混乱するのを避ける意味でも、段階的な導入が推奨されます。
社内DXの成功事例
実際に社内DXに成功した企業は、どのような課題に対してどのように取り組んでいたのでしょうか。
ここでは、経済産業省が公表した「DX Selection 2023」に掲載されている成功事例を2つご紹介します。
製作指示書のペーパーレス化
室内建具・造作材製造業を手掛ける株式会社田代製作所では、独自の生産管理システムの構築・進化で「納期の短縮」と「品質向上によるクレームの削減」を目的にDX推進に取り組みました。
社内にITやDXに詳しい人材がおらず、何から手を付けるべきかも定められなかった同社は外部のDX支援事業者に相談してプロジェクトを進めます。
DX支援事業者の助言を元に、従来は紙にコピーのうえ配布していた製作指示書のペーパーレス化を目標と定めました。
独自システムを開発のうえ生産管理システムの開発及び各工場作業員へタブレット端末の支給を進めた結果、従来と比較してコピー用紙の70~80%削減に成功。
さらに指示書をコピー・配布する時間がカットされたことで、出荷までのリードタイムを変更せずに制作時間を延ばすことも実現しました。
契約業務の属人化と業務削減に成功
全研本社株式会社では事業の拡大と上場をきっかけに、事業部単位で行っていた契約業務を全て法務部で集約する必要が生じました。
すると、法務部門の業務範囲が拡大し、マンパワーでカバーしていたために担当者の負担が増えました。法務部の人員も増えたものの、業務の属人化が進んでおり、業務の分担が難しい状況でした。加えて、ノウハウの蓄積にも課題を感じていました。
チャットツール・社内サーバー・稟議システム・電子契約システム・台帳管理と、契約書を一元管理できていなかったことも課題の要因だったと思われます。情報の分散によって最新版の把握が難しく、法務部と事業部間の進捗管理が複雑になっていました。
バージョン管理の散逸や契約書と押印稟議の突合せの手間、電子契約システムでの二重稟議など、非効率性の課題も浮き彫りに。
属人化や非効率性といった複数の課題を解決するためには、早急に業務フローを一から見直すことが必要と判断。ナレッジの蓄積・検索と、契約業務の一元管理を可能とする契約システムの導入を検討しました。
上場・事業拡大に伴い、増加する法務業務にどう対応していくか。「ContractS CLM」で年間約420時間の業務効率化に成功。
社内DXは「手段」!自社の目標に適した手法とITツールで推進を
自社のBCP対策強化・業務効率化・競争力の強化を実現させるには、社内DXの推進が必要不可欠です。
しかし、ただ社内DXに取り組めば自然とメリットが発生するという訳ではありません。
現状の把握と課題点の明確化、それを解決するための手法とITツールの活用が重要になります。
効果的な社内DXを目指して取り組みましょう。