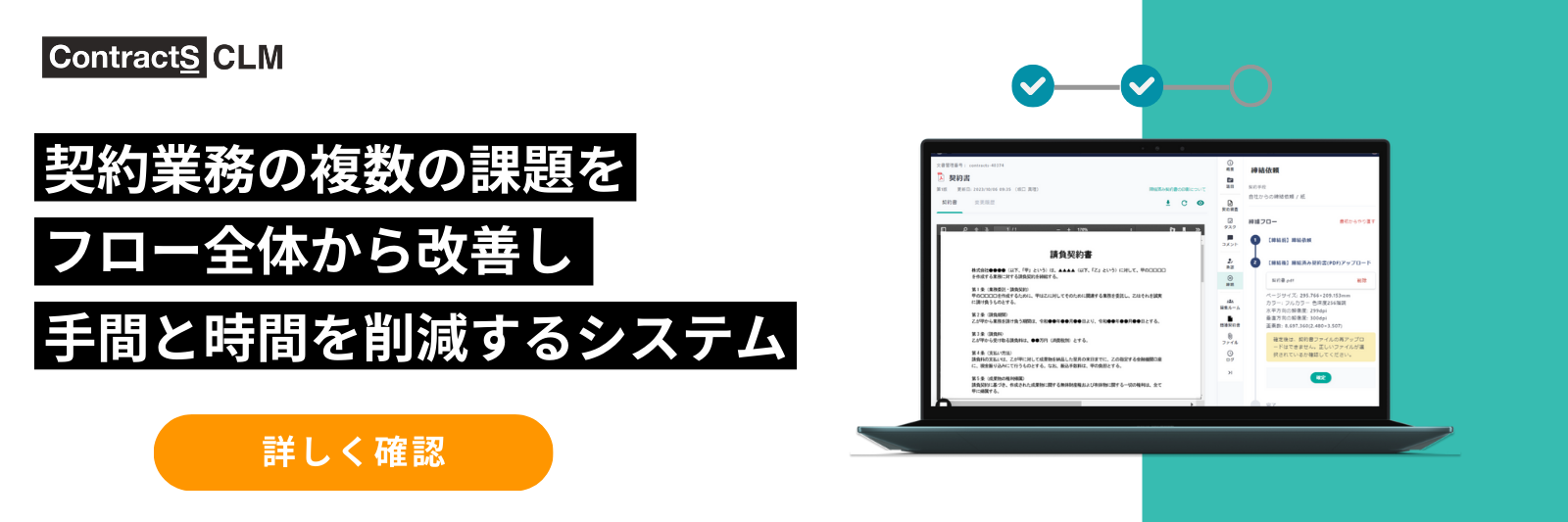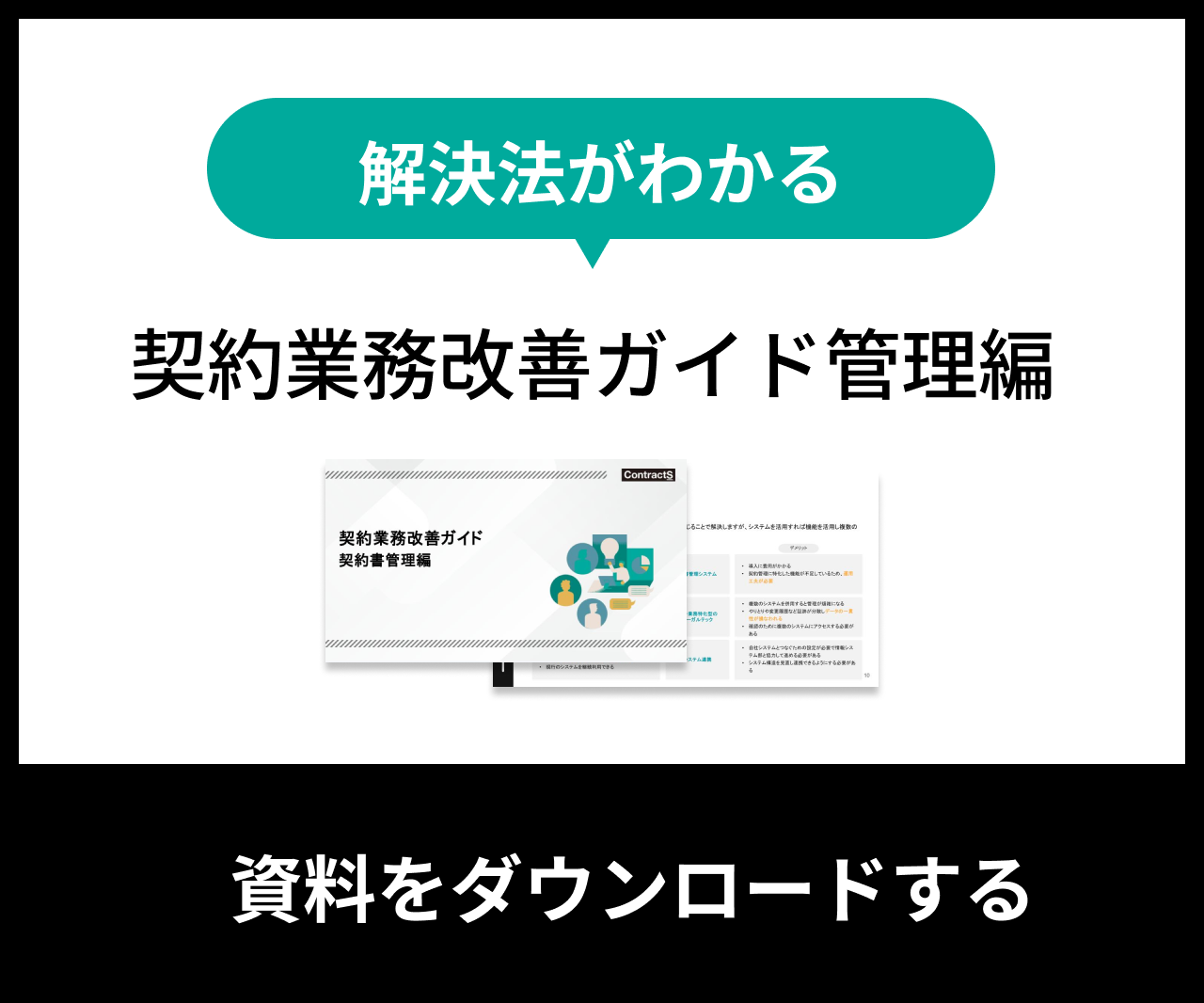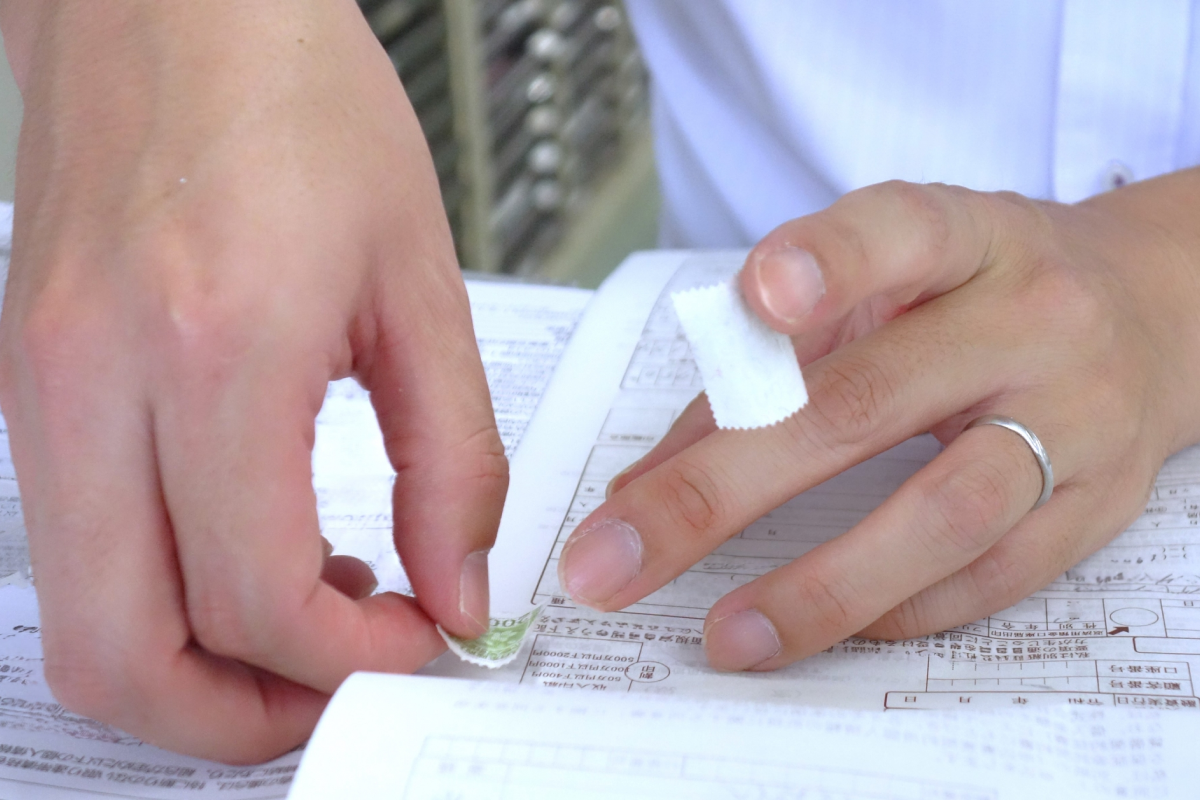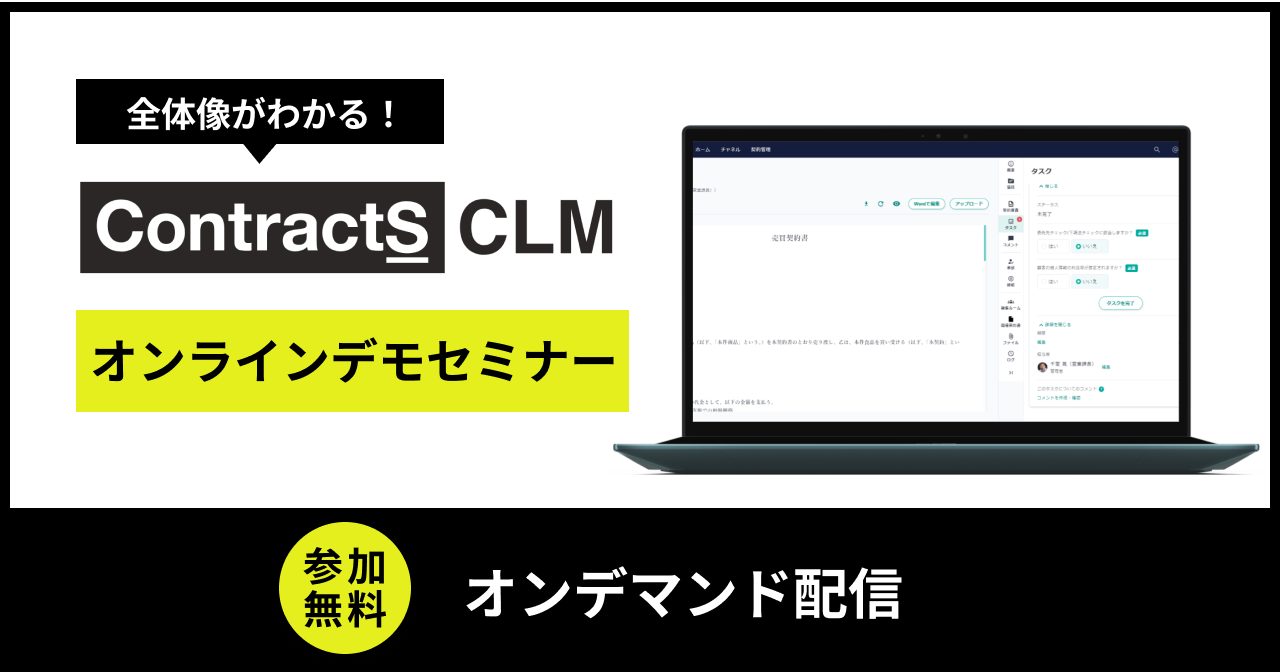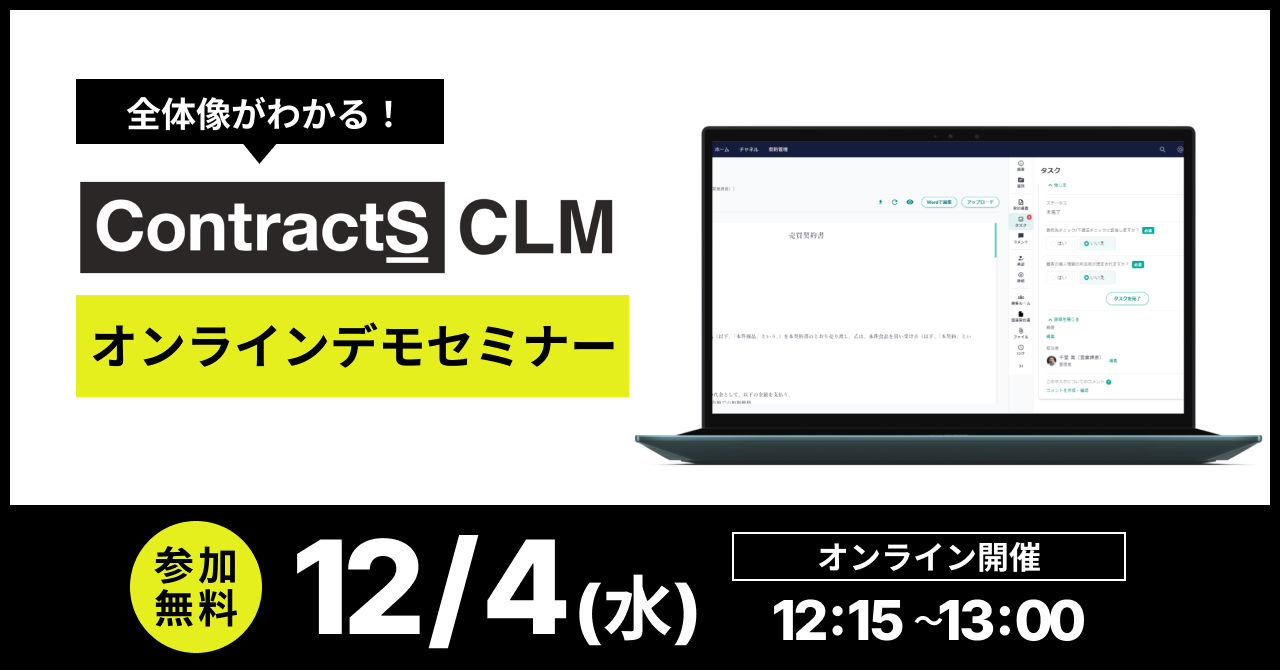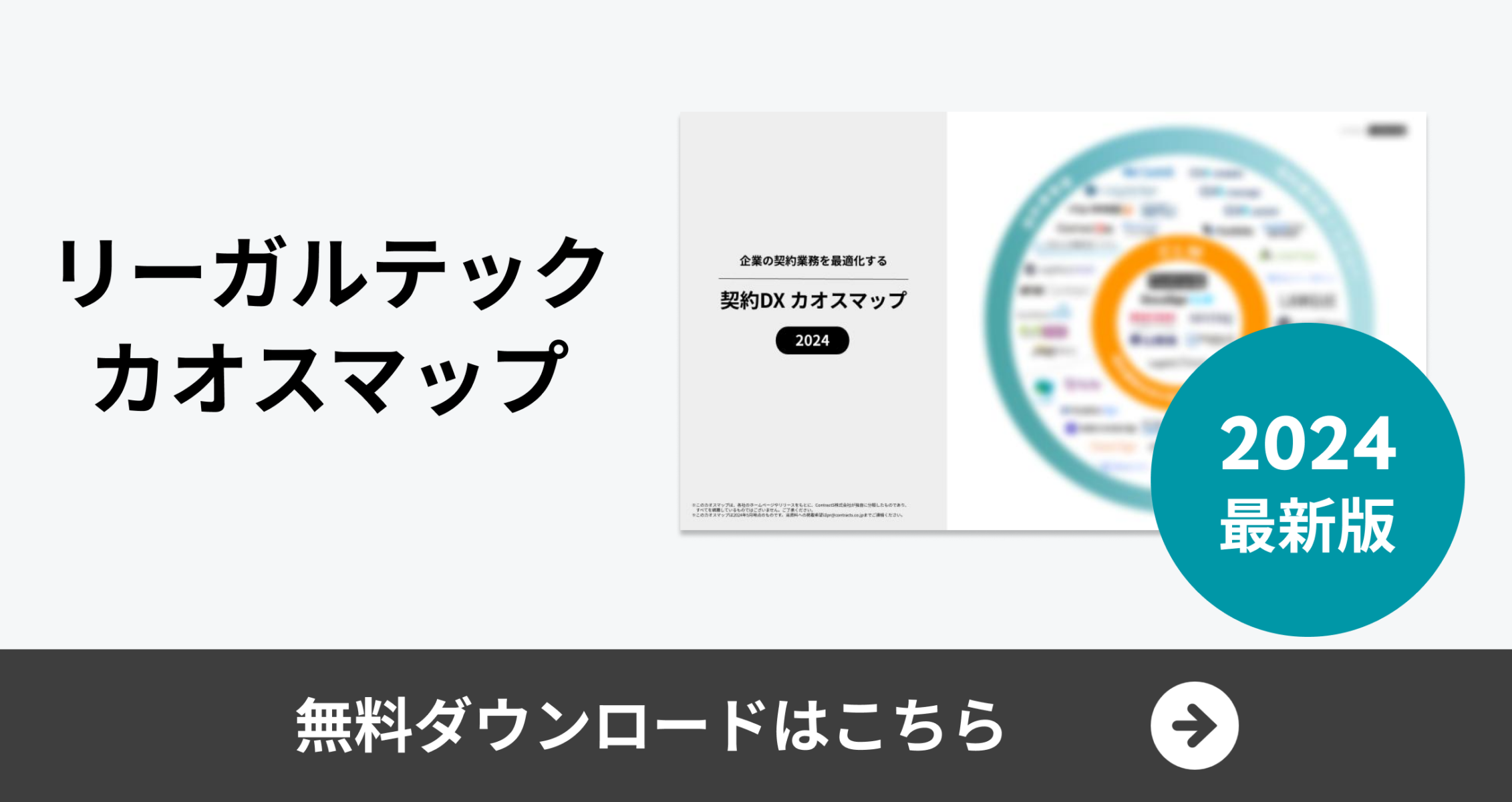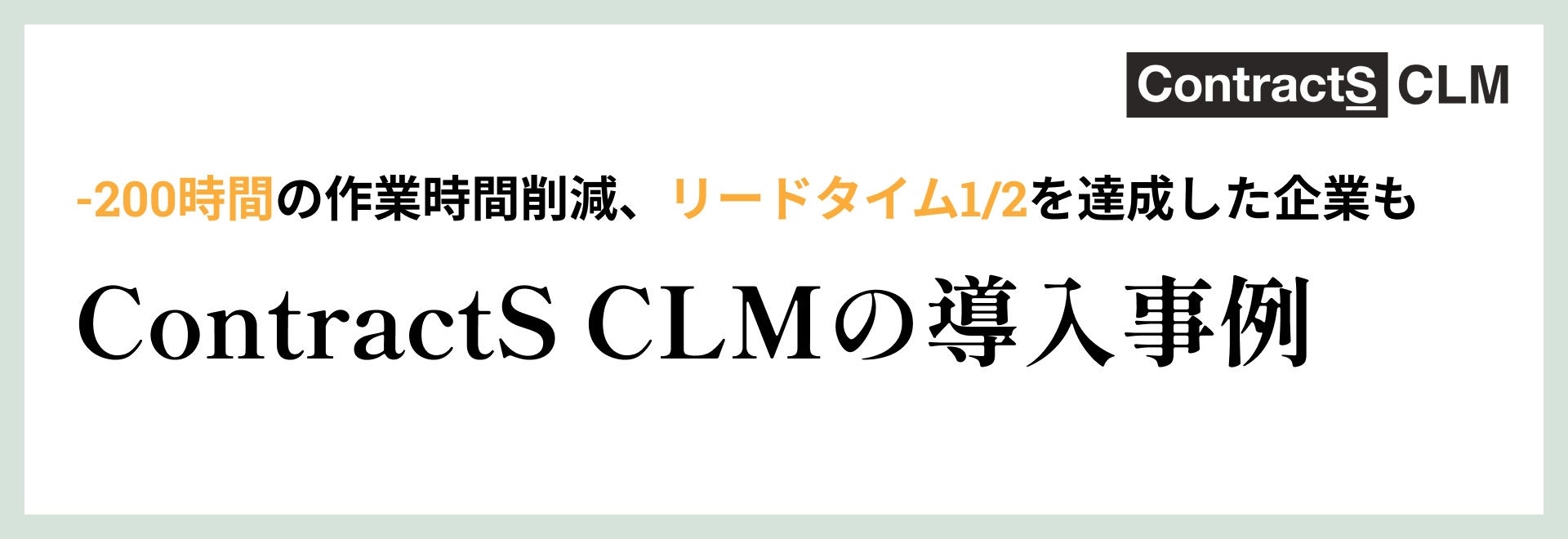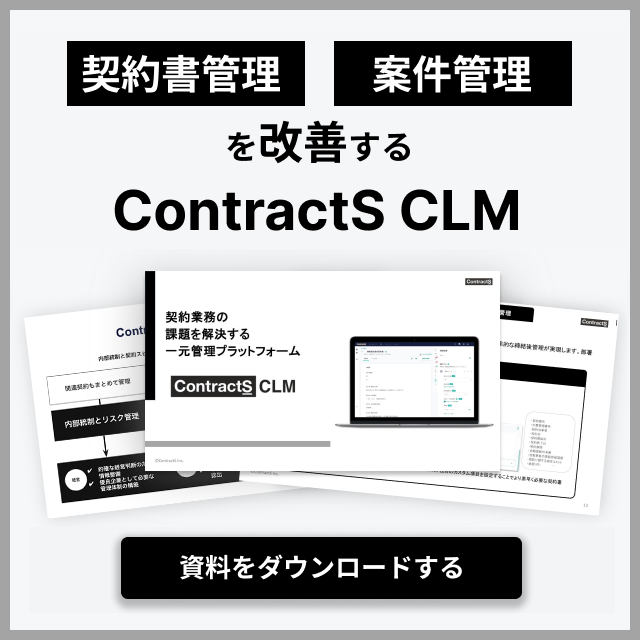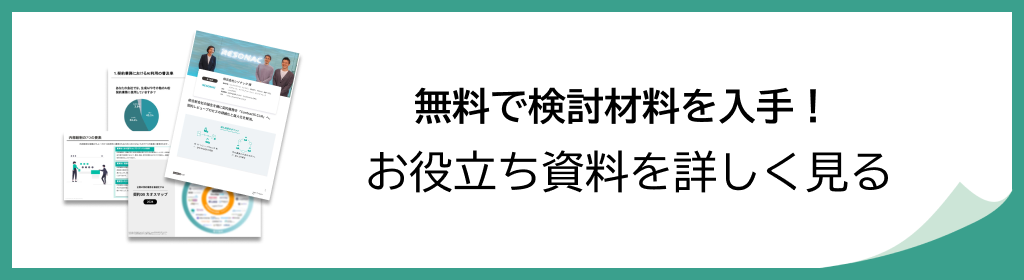ノウハウ 簡単に理解できる!企業がすべきリスク管理の重要性とやり方
更新日:2025年03月7日
投稿日:2024年02月21日
簡単に理解できる!企業がすべきリスク管理の重要性とやり方
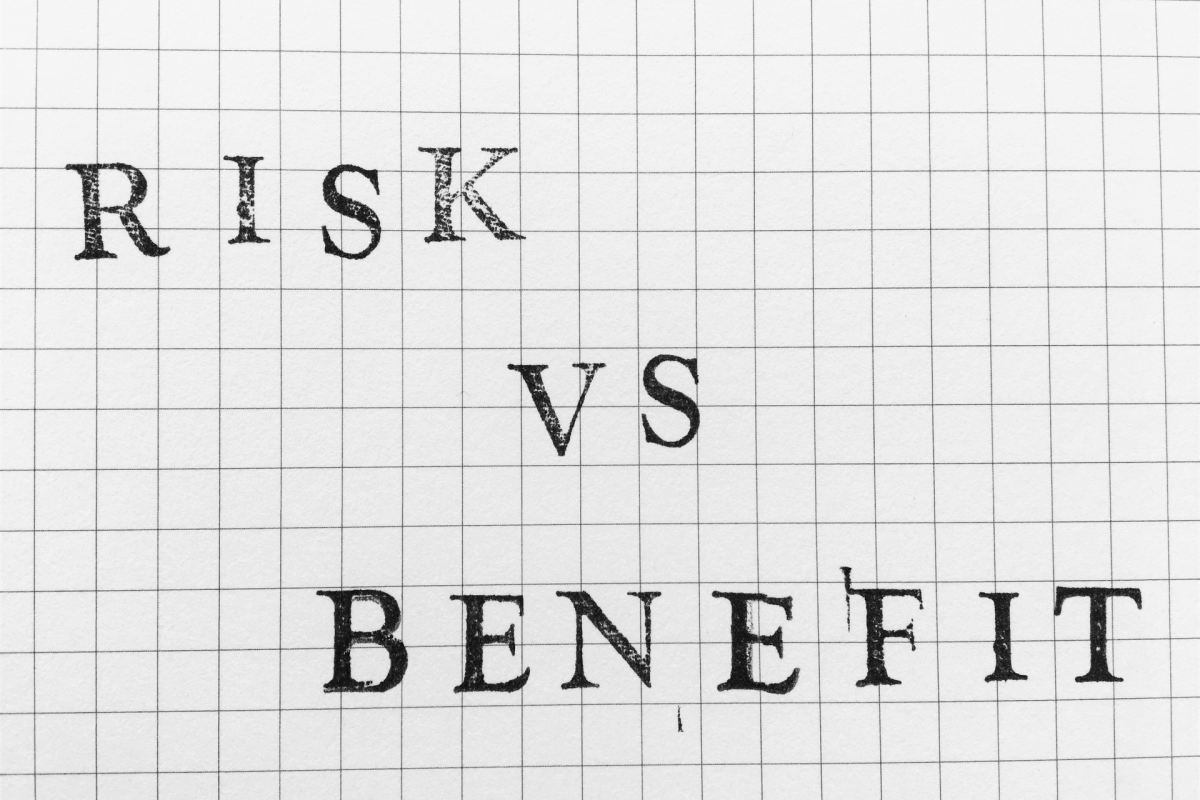
「リスク管理(リスクマネジメント)」は、どんな企業にも重要性が高い取り組みの1つです。
しかし、リスク管理とは具体的に何をするのか?危機管理と何が違うのか?など不明な部分が少なからずあることでしょう。
今回は、リスク管理の意味や危機管理との違いといった基礎知識に加え、リスク管理のやり方や社内のリスク管理意識を高めるためのポイントも詳しく解説します。
リスク管理とは?
リスク管理とは、想定されるリスクを未然に防ぐための対策を検討・実施する取り組みのことです。
企業の取り組みとして行われるリスク管理において、リスクとは企業経営や事業の継続を妨げる事象を指します。
どんなリスクが想定されるかは企業ごとに異なりますが、リスク管理の具体的な内容としてはセキュリティリスクやコンプライアンスリスクの回避などが代表的です。
いずれにしても、リスク管理はすべての企業に必要と言っても過言ではありません。
リスク管理の前に知っておきたい関連用語
リスク管理を正しく行うための事前知識として、リスク管理と関連する用語も知っておきましょう。
主な関連用語としては、危機管理・リスクヘッジ・セキュリティリスクが挙げられます。
それぞれの意味を、以下より解説します。
リスク管理と危機管理の違い
危機管理はリスク管理と混同されがちな取り組みですが、目的が異なります。
リスク管理は「事前に想定したリスクの回避」が目的であるのに対し、危機管理は「危機が起きた際にベストな形で解決すること」が目的です。
危機は未然に防止するのが理想的ですが、自然災害のように自社の努力だけでは防止できない危機も存在します。
そのような危機に直面したとき、被害を最小限に抑えながら迅速に解決できるように備えておくことが危機管理です。
リスクヘッジとは
リスクヘッジはリスクを予測し、そのリスクに対応できるように備えておくことを指します。
元は金融用語として使われていましたが、ビジネスにおいても利益や顧客の損失などを防ぐための回避策を立てるといった取り組みに対し、リスクヘッジという用語が使われるようになりました。
リスク管理と似ていますが、リスクヘッジは「特定のリスクで生じる損失を抑えるための戦略」です。
つまり、リスクヘッジはリスク管理という大枠に含まれる取り組みの1つと言えます。
セキュリティリスクとは
企業に起こり得るリスクは様々な種類があり、セキュリティリスクもその1つです。
セキュリティリスクとは、システムの脆弱性の悪用・データの改ざんや登用・不正アクセス・ウイルス感染などで損害が生じるリスクを指します。
外部の攻撃から情報を守るためにファイアウォールを導入したり、データが消失しても事業を継続させるためにバックアップサービスを活用したりといった取り組みも、セキュリティリスクを見据えた活動になります。
リスク管理が重要とされる理由
近年、企業におけるリスク管理の重要性に注目が集まっています。
その理由としては、IT技術の発達や災害により社会が急激に変動しやすく、今後の予測が難しくなっていることが挙げられます。
変動しやすく不確実な環境下で持続的な企業競争力を確保するには、リスクに柔軟かつ迅速に対応し得る戦略が必要です。
また、事業の拡大に伴い業務の一部をアウトソーシングで遂行する企業も増えています。
そのため、品質問題や委託先の業務停止といったトラブルも増加傾向にあります。
このような傾向もまた、リスク管理が重要と言われる要因の1つです。
企業で発生し得るリスクの例
企業経営において発生し得るリスクの種類は多岐にわたりますが、大きく分けると「純粋リスク」「投機的リスク」の2通りがあります。
それぞれの違いについて、以下より解説します。
純粋リスク
純粋リスクとは、企業に損害や損失だけをもたらすリスクのことです。
具体的には、以下4つのリスクが該当します。
財産リスク | 財産が、地震や台風などの自然災害、盗難や詐欺などの人的災害などの被害を被るリスク |
費用・利益リスク | 取引先の倒産や施設閉鎖などによる、自社の費用増加や利益減のリスク |
人的リスク | 病気や事故により人員を損失するリスク |
賠償責任リスク | 権利侵害や事故などにより他者へ損害賠償請求を受けるリスク |
純粋リスクは損害保険の加入などにより対策できるため、比較的リスクマネジメントがしやすいです。
リスクの概念としても理解しやすいため、従来は専ら純粋リスクがリスクマネジメントの対象とされていました。
投機的リスク
投機的リスクとは、損失や損害だけでなく利益を生む可能性もあるリスクのことです。
具体例としては、以下のようなリスクが投機的リスクになります。
経済的情勢変動リスク | 景気や為替、金利の変動などによるリスク |
政治的情勢変動リスク | 政策変更、政権交代、消費者の動向の変化などによるリスク |
法的規制変更リスク | 税制改正、法令の改正などによるリスク |
技術的情勢変化リスク | 新発明や技術革新、特許などによるリスク |
社会情勢の変化により発生し得る投機的リスクは、グローバル化が進む現代において増加傾向にあります。
リターンを生むこともある投機的リスクは「利益の源泉」と考え、以下に損失の可能性を抑える対策を講じるかが、企業成長に欠かせないポイントです。
企業におけるリスクの具体例
企業の営業活動で必要不可欠な契約には、契約書の作成と管理がつきものです。
契約書作成・管理の体制を適正に整備しないことで、機会損失や信頼失墜などの可能性が生じます。
ここでは、どんな企業にも起こり得る「契約書にまつわるリスク」の具体例をご紹介します。
契約書の紛失
ずさんな契約書管理により、契約書を紛失するリスクです。
他の書類に紛れ込んでいる、社内の誰かが持ち出した、外出先に置き忘れたといったケースで起こる可能性があります。
契約書は、当事者双方が適切に契約を履行するための重要な事項が記載されています。
紛失すれば契約を正しく履行できず、相手側から不信感を与えるだけでなく、法的トラブルに発展するおそれもあります。
審査・承認を経ずに契約が締結される
作成した契約書は、社内で審査と承認のプロセスを挟む必要があります。
契約書の審査は、双方にとって合理的な条件を設けているか・文面は分かりやすいか・誤字脱字はないかなどが確認され、各承認者の承認を得て内容が確定するというのが基本的な流れです。
上記のプロセスを怠ると、「不当な契約」や「認識の齟齬」の他、その契約が法的効力を失うリスクも高まります。
契約の期限を見落とす
契約には期限があるものの、膨大な契約書を管理しているとすべての契約期限を記憶することは現実的ではありません。
そのため、期限前に更新などの対応が漏れないような管理体制を整える必要があります。
契約の期限を見落とすことで、意図しないタイミングで取引が終了し、利益減や取引先から信用を失うといった結果につながります。
リスク管理で意識すべき「発生確率」と「影響度」
リスク管理を実施する前に、まずは想定されるリスクを洗い出したうえで優先順位を付ける必要があります。
これは「リスクの算定・評価」という、リスク管理で重要な段階です。
リスクの算定と評価は、「リスクの発生確率」と「リスクの影響度」という2つの軸に沿って行います。
影響度に関しては、金銭的な損失だけでなく人名や企業イメージに関わる損失も考慮しましょう。
2つの軸を掛け合わせ、発生しやすく顕在化した際の影響度が大きいリスクから優先的に対策していく必要があります。
また、優先度の高いリスク管理に取り組みながら、優先度の低いリスクも常時観察していくことが大切です。
リスク管理の基本的なやり方
リスク管理の基本的なやり方としては、大きく特定・評価・対処・改善という4つのプロセスに分けられます。
各プロセスの詳細について、以下より解説します。
リスクの特定(Identification)
最初に、自社の内外の環境を把握したうえでリスクを特定する必要があります。
大・小問わず、自社に影響を及ぼしかねないリスクは多く挙げていくことが大切です。
リスクを特定する手段としては、「ヒューリスティック手法」「ブレーンストーミング」「文献調査」が挙げられます。
ヒューリスティック手法
ヒューリスティックとは、経験や先入観に基づき正解を導き出す思考法です。
例えば「空が曇っていて辺りが暗いから雨が降るだろう」と考えて外出時に傘を持って行くのも、ヒューリスティックの結果導き出されたリスク管理の1つと言えます。
つまり論理的に1つ1つの筋道を立ててリスクを特定するのではなく、自身の経験や先入観で直感的にリスクといえる要素を判断するということです。
とはいえ、ヒューリスティック手法によるリスク特定は個人の認知バイアスに影響される場合もあるため、他の手法と併せて活用すると良いでしょう。
ブレーンストーミング
複数人でアイデアを出し合いながら新たな発想を生み出す会議手法を、ブレーンストーミングといいます。
細かなルールはなく、「質より量」を意識しながら参加者全員が自由に意見を出し合うことが大切なポイントです。
ただし、誰かのアイデアに対して否定したり一方的に評価したりといったことは避けましょう。
個人の発想からは出し得ないアイデアが生まれるブレーンストーミングは、自社に潜むリスクを見逃さずに抽出しやすい手法とも言えます。
文献調査
自社のメンバーが複数人集まっても、活かせるノウハウ・知識はどうしても限られます。
そこで役立つ手段が、学協会や行政などが公開している文献調査です。
特定の事故・災害に関する専門家の所見や統計なども取り入れることで、自分たちだけでは気付けなかったリスクを発見したりリスクの影響度を正確に評価しやすくなります。
リスクの評価(Assessment)
リスクを特定したら、次にリスクの優先順位をつけるための評価を行います。
会社や組織には数多くのリスクが存在していますが、一度にすべてのリスクに対応することは現実的ではないからです。
リスクを評価する方法は、「定性的リスク評価」と「定量的リスク評価」の2つがあります。
定性的リスク評価
まずは定性的リスク評価から実施するケースが一般的です。
「定性的」とは数値化できない要素のことで、リスク評価においては自社に及ぶ影響度や対応の緊急度といった側面から優先順位をつけていきます。
具体的にはリスクの発生確率を縦軸、リスクの影響度を横軸として以下のような図にします。
発生確率
| 高 | 高×小 | 高×中 | 高×大 |
| 中 | 中×小 | 中×中 | 中×大 |
| 低 | 低×小 | 低×中 | 低×大 |
| 小 | 中 | 大 |
影響度
先述したように、最優先で回避に努めるべきは発生確率・影響度が共に高いリスクです。
次に影響度が大きく発生確率が低いもの、影響度が小さく発生確率が高いもの、発生確率が低く影響度も小さいものといった順番で対応を決めていきましょう。
定量的リスク評価
定性的リスク評価の次に、定量的リスク評価も行います。
「定量的」とは数値化が可能な要素を指す言葉で、定性的とは逆の意味を持ちます。
定量的リスク評価では、特定したリスクに対して優先度に応じたポイントを付けていきます。
過去の事例などを参考に発生確率を算定し、影響度は金銭的な損失なども考慮しながら数値化します。
これを元に、優先度のポイントを付けてみましょう。
リスクはできるだけ定量化すると、より評価の精度を高められます。
リスクの対処(Treatment)
リスク評価で定めた優先順位に沿って、リスクの対応策を決定していきます。
リスクの対応策は、大きく分けて「回避」「軽減」「受容」「移転」の4つがあります。
回避(Avoidance)
回避とは、リスクの発生を未然に防いだりリスクの影響から守るための対策を指します。
発生確率が高いリスクや、事業にもたらす利益が少ない状態で発生した場合の影響度が大きい場合に回避の対策を取るケースが一般的です。
リスク回避の例としては、以下のような対策が挙げられます。
・利益よりもリスク発生時の損失が大きいと見込まれるため、事業展開を中止する
・自社の情報の不正利用を防ぐためにサーバールームのセキュリティを強化する
軽減(Mitigation)
軽減は、リスクの発生確率を下げたり発生した際の影響度を抑えたりする対策です。
具体例としては、以下のような対策が挙げられます。
・災害発生時に備えて自社保有の建物を補強する
・社用のデバイスを紛失した際に備えて遠隔でデータを消去できるシステムを導入する
リスクを軽減させるために費やすコストは、リスクの発生確率とその結果に見合ったものになることが望ましいです。
受容(Acceptance)
リスクの受容(保有)は、リスクを把握しながらも特に対処せず発生を受け入れることです。
発生確率が低く影響度も小さいリスクまで徹底的に対処するのは難しいため、あえて受け入れて無駄なコストの消費を抑えた方が賢明とも言えます。
また、現状としてそのリスクに対して実施できる対策を決めかねたり、リスクはあっても事業継続のために受け入れざるを得なかったりするケースでも受容を選ぶ場合があります。
移転(Transfer)
リスクの移転(転嫁)は、リスクが発生した際にその影響を自社以外へ移すための対策です。
あくまで自社が受ける影響を抑えるための対策であり、リスクそのものを除去するわけではありません。
発生確率は低くても、発生時の影響は大きいと見込まれるリスクへの対策として移転が選ばれることが多いです。
リスク移転の具体例としては、以下のような対策が挙げられます。
・何らかの損害が発生した際に備えて保険に加入する
・セキュリティが強い外部サービスで自社のデータを保管する
モニタリングと制御(Monitoring and Control)
リスクの対策を決定したら、実際にその対策を実行します。
しかし実行をゴールとして状況を振り返らなかった結果、思わぬ事故が発生するケースも珍しくありません。
ただ実行するだけでなく、以下の点に注目しながらモニタリングを行いましょう。
・計画通りに対策が行われているか
・期待した効果は表れているか
・新たな対策を行う余地はあるか
・新たなリスクのきっかけやリスクそのものが現れていないか
継続的な改善(Continuous Improvement)
モニタリングを通して対策の効果を見直し、改善点を洗い出します。
リスク対策の実行後も状況が芳しくない場合は改善点を明確化し、それを考慮しながらリスク管理のやり方を修正するといった「PDCAサイクル」を継続させましょう。
リスク管理体制を強化するポイント
効果的なリスク管理体制を整備するには、以下4つのポイントを押さえることが大切です。
専任のチームを設置する
様々なプロセスで構築されるリスク管理体制を継承するためには、専任チームの設置が必要不可欠です。
専任チームは、主にリスクの未然防止策や従業員へのリスク管理教育を行う他、有事の際は経営者の補佐・危機管理対策本部としてトラブルの早期解決を目指します。
経営企画・戦略の部署がその役割を担うか、別途担当者を選定して専任チームを作り、最適な危機管理体制を維持していきましょう。
過去に起きたインシデントを振り返る
対策すべきリスクを特定するには、関係者や各部門のリーダー、対象分野の専門家に過去のインシデントを振り返ってもらう方法が適しています。
どのような事態が発生し、どのように防ぐべきかなどをヒアリングしましょう。
すべてのプロセスでステークホルダーと情報を共有する
リスク管理体制を構築するすべてのプロセスで、ステークホルダー(利害関係者)との情報共有を行いましょう。
自社が特定したリスク情報の共有は、双方の信頼関係を築くために重要な取り組みです。
また、ステークホルダーからフィードバックを得られることがあり、そのフィードバックを反映した効果的な施策を実施すれば、より信頼関係を深められます
定期的な見直しを継続する
リスク対策を実行したら、定期的な見直しと改善の継続を行いましょう。
最近になって顕在化したリスクや対策されていないリスクの有無も確認し、必要な措置を策定しましょう。
また、従業員に対してリスク対応の教育を実施しても、時間が経てばリスクに対する意識が下がっていく可能性もあります。
リスク対応力を維持・強化するために、トレーニングや研修の機会も定期的に設けましょう。
社内のリスク管理意識を高めるには?
リスク管理においては自社に合った手法を組み込んだプロセスも重要ですが、同様に社内全体のリスク管理意識を高める必要もあります。
リスク管理意識が高ければ、新たなリスクやそのきっかけの発現を検知しやすくなるためです。
しかしすべての方が日頃からあらゆるリスクを考慮しながら業務に従事しているわけではなく、仕事をこなす中で少しずつリスク管理意識が薄れていく可能性も考えられます。
社内のリスク管理意識を維持するには、定期的な社内研修が有効です。
リスク管理の策定・実行を行う従業員だけでなく、すべての従業員に対してリスク管理の必要性を理解してもらうための研修を実施しましょう。
リスクはすべての企業につきもの!高い意識の継続と適切な管理が大切
どんな企業でも、リスクがまったく存在しないとは言えません。
特に不確実な現代社会においては、事前にリスクを想定してその対策を講じることが重要です。
ただし起こり得るリスクのすべてに対応するのではなく、優先順位をつけてそれぞれに適した対策を検討すると良いでしょう。
リスク管理のプロセスはある程度定型化されていますが、効果を高めるためのやり方は企業によって異なるため、PDCAサイクルを継続させる必要があります。
社内全体の意識を高める社内研修も怠らず、現代社会で企業競争力と安定的な経営を維持させるためのリスク管理に取り組みましょう。