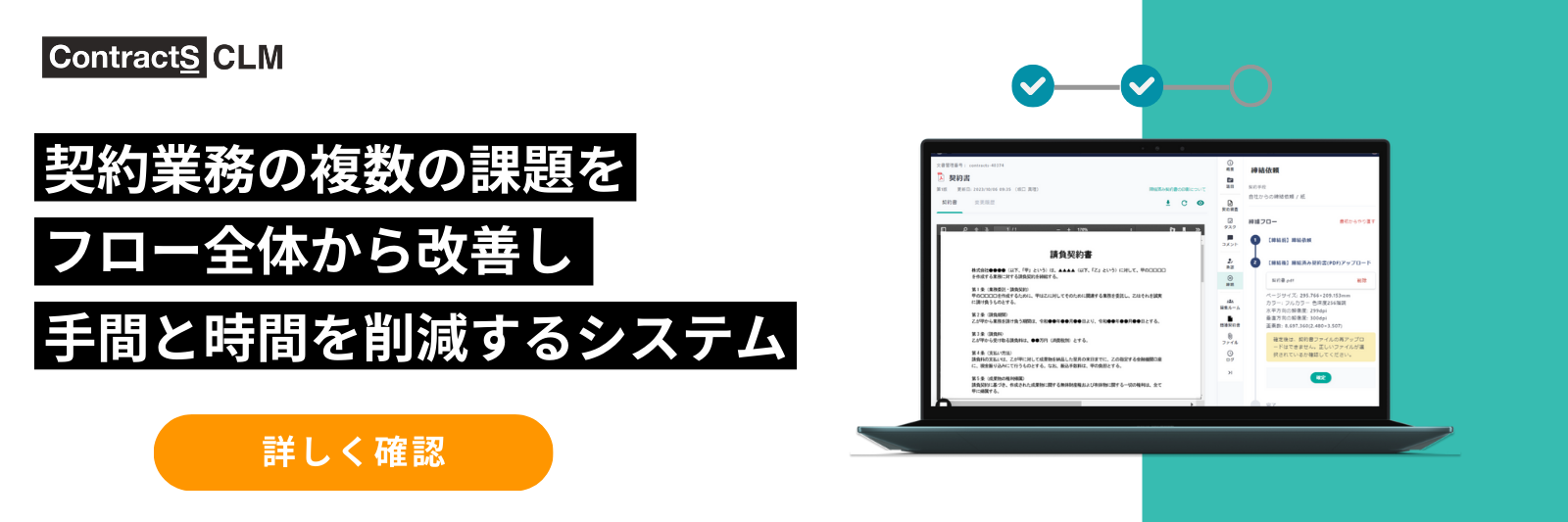ノウハウ 社会人として知っておきたい法律の知識!役立つ法務の勉強会も解説
更新日:2025年03月7日
投稿日:2024年02月15日
社会人として知っておきたい法律の知識!役立つ法務の勉強会も解説

法務は、企業の法的トラブルを予防し、万が一トラブルが発生したら迅速な解決に向けて動くという役割があります。
幅広い法的トラブルに対応するには、多くの法律を学ぶと共に知識をアップデートし続けることが大切です。
今回は、法務に必要な法知識を身につける・アップデートする際に役立つ勉強方法や勉強会を詳しくご紹介します。
法務職に従事するうえでおすすめな検定や資格も解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
企業法務の勉強会とは
企業法務に従事する方の中には、最新情報のキャッチアップやスキルアップを目的とした集まりに参加し、最新の動向や実務の情報を提供し合いながら学んでいる方がいます。
勉強会では、法令の変更と改正が及ぼす影響について学んだり、実例を用いた実践などが行われます。
知的財産権、契約や訴訟、コンプライアンスや法的リスク、企業法務で活用できるシステムなどもテーマになりやすいです。
法務に携わるのであれば、法令の変化に伴う対応ができなければならず、最新の情報を知り、知識をアップデートし続けることが重要です。
勉強会に参加することで情報や知識を深められることはもちろん、専門家や他の企業の法務担当者とのつながりを持てるというメリットを得られます。
企業法務の役割とは
企業において法務とは、法的トラブルの予防・法的トラブルの対応・契約書の作成と管理などを主な役割としている部門です。
また、近年は法知識を活かして事業戦略を支援する「戦略法務」も重要視されています。
法的対応や法律事務専任の部門として法務を設置することで、万が一の事態が起きても迅速な対応が可能になります。
企業のコンプライアンス違反に対して一層の厳しさが増している現代社会において、法律には抵触せずともモラルを問われる行動により、自社のブランドイメージや信頼を失うリスクは付きものです。
法務部は単に法律を遵守した企業活動に向けた支援だけでなく、社会情勢に応じて発生するレピュテーションリスクにも対応するという役割も果たします。
企業法務のキャリアパス
企業法務でどのようなキャリアを実現したいかによって異なるステップも考えられますが、一般的には以下のようにステップアップを目指します。
- 若手法務部員
- 中堅スタッフ
- マネジメント
- 経営層
法務経験5年未満の人材は、契約書の作成などを行います。
企業法務部門に配属されるということは、法学を学んでいたなど法的知識は有していて、企業からも期待されているでしょう。しかし、若手の間は、高度な知識が必要な仕事を1人で任せられることはほとんどありません。
上司のサポートや指示を受けながら、実務を通して仕事で使えるスキル・知識を身につける期間です。
5年以上の法務経験があれば、より専門性の高い知識が求められてきます。社内ルールの構築など、業務は契約書の作成にとどまりません。
若手のうちは、ひな形に基づく契約書作成を任されることが多いですが、中堅になるとひな形の作成からお願いされることもあります。
企業法務のスペシャリストとして働き続けたい人もいる一方、法務部門をまとめたり、法的な面から経営を支える人材になりたい人もいるでしょう。
組織を引っ張っていきたい人は、チームリーダーとなる機会が増える中堅スタッフのタイミングで、コミュニケーション能力を高めたり、進捗管理などには慣れておきたいところです。
法務経験10年以上となれば、管理職に昇進する可能性があります。人材育成や評価なども業務に含まれるようになります。
重大な法的リスクが生じた際、経営層に直接助言する役割も担います。法的知識のない上層部にも分かる説明ができること、解決策を提案できることなどが求められます。
また、法令を守った企業活動に導くことに加え、組織が中長期的な目標を達成でき、成長し続けるための方向性を示すことのできる能力も必要となります。
法務に必要な知識・スキル
企業の法務従事するうえで身につけておきたい知識・スキルとしては、以下の3つが挙げられます。
|
①法律の知識 |
自社の業務に関係する法律の知識、法改正などの最新情報を素早く掴んで柔軟に対応する力 |
|
②文書作成・プレゼンテーション能力 |
契約書・議事録・社内規程・プレゼンテーション資料などの文書を作成し、分かりやすく伝える能力 |
|
③コミュニケーション能力 |
法改正の影響や法律に関わる事項を各部門へ伝えたり、社内での法律相談に対応したりする能力 |
初めて法務に従事する方は、上記の3つを主軸としてスキルアップを目指していくと良いでしょう。
社会人でもできる法務の勉強方法
日々の業務により自由に使える時間が限られているものの、法務では日々の勉強やスキルアップが必要不可欠です。
社会人でも知識の習得やスキルアップを目指すための勉強方法としては、以下の4つがおすすめです。
・書籍を読む
・OJT研修を受ける
・勉強会に参加する
・SNSで情報を収集する
一口に勉強方法といっても様々な手段がありますが、自分のレベルに応じて選ぶべきものは変わります。
参加のしやすさ・信頼性・費用の観点で各勉強方法の比較表をまとめたので、選ぶ際の参考にしてください。
|
勉強方法 |
参加のしやすさ |
信頼性 |
費用 |
|
書籍 |
〇 (初心者向けの書籍も多数あるため活用しやすいが、選択肢が幅広く迷う場合もある) |
〇 (専門家監修・推奨の書籍が多数ある) |
〇 (数千円程度で購入可能) |
|
OJT研修 |
〇 (用意された時間の限り先輩や上司から指導を受けられる) |
◎ (書籍には書いていない、自社での法務において実践的なスキルも身に付く) |
◎ (業務として研修を受けられるため費用がかからない) |
|
勉強会 |
〇 (オンライン開催も多くあり参加しやすいが、開催日時や場所が指定されることもある) |
〇 (省庁や法務関連団体などは信頼性が高いが、民間のコンサルタント主催なら吟味が必要) |
△ (参加には数万円~数十万円程度の費用が必要) |
|
SNS |
◎ (好きなタイミングで閲覧できる) |
△ (正確性に欠けた情報もあるため精査が必要) |
◎ (ネット環境があれば費用をかけず情報を収集できる) |
法務に従事する社会人が知っておくべき法律
法律の種類は多岐にわたり、どんな法律の知識を身につけるべきかは企業ごとに異なります。
ただし、以下のような法律は業種を問わず関わる可能性が高いため、基礎知識は確実に覚えておくと良いでしょう。
民法
民法とは、日常生活において適用される法律です。
契約や相続、物に対する権利など、企業活動の様々なシーンに関わるルールが定められています。
特に、契約書の作成や審査を主な業務とする法務の場合、契約に関する民法上のルールは理解を深めておきたいポイントです。
会社法
会社法は、会社の設立・運営・仕組みなどについて定めている法律です。
具体的には、株式会社の設立・株式発行の手順・運営で必要な書類・社債の発行・組織変更などに関するルールが定められています。
数ある法令の中でもボリュームが多く難解とされていますが、法務に従事する以上は最低限自社の運営に関わるポイントだけでも押さえておくことが大切です。
労働法
労働法は、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」など、雇用・労働に関するルールを定めた法律の総称です。
一般的に雇用関係は人事労務が担当していますが、労使関係のトラブルが発生した場合は法務が対応するケースが多いため、労働法の知識も身につけておく必要があります。
企業のコンプライアンス遵守や働き方改革が強く求められる昨今、法務においては労使関係のトラブル対応だけでなく、トラブルを未然に防ぐために労働法に則った取り組みも重要とされています。
独占禁止法
独占禁止法は、企業の公正かつ自由な競争を促進するためのルールを定めた法律です。
有力な企業が競合相手を排除したり、談合により価格競争を制限したりといった行為は独占禁止法で禁止されています。
独占禁止法に違反すると、悪質とみなされた場合は刑事罰を受けることもあります。
経営者だけでなく、従業員のコンプライアンス教育にも独占禁止法は必要な知識であり、法務担当者なら特に理解を深めておくことが大切です。
その他
上述した法律の他、自社が行う事業によっては以下のような法令の知識も理解する必要があります。
・特定商取引法
・知的財産法
・宅建業法
・建設業法
・食品衛生法
・貸金業法
・労働者派遣法 など
特定の事業に関する規制を設けた法令の遵守も、法務担当者として重要なテーマです。
企業法務に特化した勉強会・勉強の場
企業法務に特化した勉強の場の例として、以下12の勉強会・コミュニティの情報をまとめました。
企業法務研究会(加藤&パートナーズ法律事務所)
|
運営母体(主催者) |
加藤&パートナーズ法律事務所の客員弁護士、伊勢田道仁氏 |
|
対象 |
企業法務に関わる全ての人 ※業種は問いません。 |
|
参加費・入会金など |
不要 |
開催時の社会情勢を取り巻く企業法務の課題について検討します。勉強会は2ヶ月に一度の開催です。
企業法務の担当者同士のつながりが生まれ、情報交換のための空間となることが期待されています。
企業法務研究部会(一般社団法人企業研究会)
|
運営母体(主催者) |
一般社団法人企業研究会 |
|
対象 |
企業法務担当者 |
|
参加費・入会金など |
一般会員27万円+税 正会員24万円+税 ※第55期の参加費です。 |
実践的な講演・発表を通じて企業法務の知識を身につけます。企業法務担当者同士のつながりによって、自社の課題解決のきっかけが見つかります。
法改正に伴う実務の変更が生じた際の対策を考え、実行することにも役立つはずです。
企業法務勉強会(あなたのまちの司法書士グループ)
|
運営母体(主催者) |
あなたのまちの司法書士グループ |
|
対象 |
司法書士 |
|
参加費・入会金など |
不要 |
10人程度が集まり、企業法務の基礎を学ぶ勉強会です。毎月開催されています。
各参加者が、指定書籍の割り当てられた章を15~20分程度で発表します。発表されたテーマについて、ディスカッションや質疑応答を行うというスタイルです。
経営法友会によるセミナーや研修
|
運営母体(主催者) |
経営法友会 |
|
対象 |
国内上場している企業 会員企業の推薦を得ている企業の法務担当者 |
|
参加費・入会金など |
入会金5万円、年会費15万円 ※入会すると研修をお得に受けられます。 |
ガバナンスや取締役会の運営、株主総会の議決権など、幅広いテーマのセミナーが開催されます。ディスカッションが含まれるセミナーもあります。
九州企業法務研究会(公益財団法人九州生産性本部)
|
運営母体(主催者) |
公益財団法人九州生産性本部 |
|
対象 |
企業法務担当者 |
|
参加費・入会金など |
入会金は不要。下記の通り会費がかかります 維持会員(企業・団体)1口24万円/年 法人会員(企業・団体)1口8万円/年 労働組合会員(企業・団体)1口4万円/年 会員になるとセミナー・研究会の参加費が3割引になります。 今回紹介する勉強会の非会員企業の参加費は15.4万円ですが、賛助会員企業になると12.1万円です。 |
企業法務が直面する最新の課題、法改正、コンプライアンスなどのテーマについて、ゲストの専門家による解説が受けられます。ゲストを交えた情報交換も行います。
大江橋法律事務所提供のセミナー
|
運営母体(主催者) |
大江橋法律事務所、または、別団体 |
|
対象 |
セミナーによる |
|
参加費・入会金など |
セミナーによる |
企業活動に関係する法律などがテーマのことはもちろん、訴訟に関するテーマが充実しているのが特徴です。
対象者について、企業法務担当者でなければならないといった条件はなくても、法律事務所に所属している人の参加が認められていないセミナーもあります。
BUSINESS LAW SCHOOL
|
運営母体(主催者) |
株式会社商事法務 |
|
対象 |
セミナーによる |
|
参加費・入会金など |
セミナーによる |
企業法務の基礎知識の学習と、実務への対応を考えるプログラムが提供されています。
例えば2023年1月から12回にわたって開催された契約書の作り方と読み方を学べるセミナーでは、6万円+税の受講料、2023年4月に開催された印紙税について学ぶセミナーでは3万円+税の受講料となっていたようです。
PASONA提供のセミナー
|
運営母体(主催者) |
セミナーによる |
|
対象 |
セミナーによる |
|
参加費・入会金など |
セミナーによる※無料のものもあります。 |
PASONAが運営する企業法務にまつわるサイト「企業法務ナビ」では、企業法務に関わるテーマのセミナーの情報提供をしています。
法令を学んで実践形式の体験ができたり、契約書作成のワークショップ、バーチャル株主総会のシミュレーションなどが行われました。
サイト内で紹介しているセミナー全てではありませんが、概ね法務担当者を対象としています。
企業法務セミナー(BUSINESS LAWYERS)
|
運営母体(主催者) |
BUSINESS LAWYERS |
|
対象 |
セミナーによる |
|
参加費・入会金など |
セミナーによる |
法改正への対応や契約書の作成などに関するセミナーを実施しています。
参加者は「想定参加者」という呼び方で募っています。参加者は「想定参加者」という形で募集しており、必ずしも法務担当者に限定しているわけではありません。例えば、インボイス制度に関するセミナーでは、経営者層や経理担当者も対象としていました。
また、無料ウェビナーも充実しています。
有料セミナーの場合でも、BUSINESS LAWYERS LIBRARYだとお得になり、無料で受けられるものもあります。例えばインボイス制度に関するセミナーは、1万円+税のところ、BUSINESS LAWYERS LIBRARYライトプラン会員は3,000円+税、BUSINESS LAWYERS LIBRARYスタンダードプラン会員は無料で受講可能です。。
ビジネス法務入門講座(東京商工会議所)
|
運営母体(主催者) |
東京商工会議所 |
|
対象 |
ビジネスで必要な法律の基礎を学びたい方(総務・人事担当者・営業担当者など) |
|
参加費・入会金など |
一般3.6万円+税 会員1.8万円+税 |
(F1-1)ビジネス法務入門講座:イベント・セミナー詳細 | 東京商工会議所
企業法務実務基礎講座(大阪商工会議所)
|
運営母体(主催者) |
大阪商工会議所 |
|
対象 |
企業法の実務についての基礎知識を習得したい方 法務部に配属されたばかり・経験年数の短い方 |
|
参加費・入会金など |
一般5.7万円+税 会員4.12円+税 |
法務互助会(Slackコミュニティ)
参加者約270人のSlackのコミュニティです。情報共有や相談、求人の募集や紹介などが行われます。
企業規模や経験年数に関係なく、法務担当者なら誰でも参加可能です。ただし、参加するには社名を公表する必要があります。
企業の法務職に役立つ資格・検定
法務に関する資格取得や検定は、勉強を進めるにあたって良い機会となるだけでなく、法務担当者としての評価や信頼性の向上にもつながります。
法務関連の資格・検定にも様々な種類がありますが、その中でもおすすめな「ビジネス法務検定」「知的財産管理技能検定」「個人情報保護士」の概要を以下の通りまとめました。
| 資格・検定 | 学べること | 試験期間 | 受験料 | 難易度 |
| ビジネス実務法務検定 | ビジネスに関わる法令の基礎知識・実践的な知識 |
・2~3級:年2回 |
・3級:5,500円 |
初学者~法務スペシャリスト向け |
| 知的財産管理技能検定 | 知的財産を正しく管理・運用するスキル | 年3回(3月・7月・11月) |
・3級:学科・実技ともに6,100円 |
初学者~知的財産関連業務の経験者向け |
| 個人情報保護士 | 個人情報保護法に基づき、適正に個人情報を利用するための知識 | 年4回(3月・6月・9月・12月) | 11,000円 | 初学者~個人情報管理に関連する業務経験者向け |
それぞれの資格・検定の詳細について、以下より解説します。
ビジネス実務法務検定
ビジネス実務法務検定は、東京商工会議所が主催している検定試験です。
法務部門だけでなく、営業部門・販売部門・管理部門などの業務に関わる法的知識を、幅広くカバーしています。
3級~1級までの区分があり、2級以上は難易度が高いといはいえ、合格すれば法務従事者としての高評価に期待できます。
知的財産管理技能検定
知的財産管理技能検定は、知的財産を正しく管理・運用するスキルを証明できる国家試験です。
知的財産とは絵画や小説といった著作物・デザイン(意匠)・ブランド(商標)・発明など誰かが生み出した「形がない財産」を指し、知的財産法で保護されています。
企業活動の中では自社の知的財産が無断で使用されたり、他社の権利を侵害したりするリスクも潜みます。
そのようなリスクを回避するために必要な知識を学べる検定が、知的財産管理技能検定です。
3級~1級までの区分があり、1級は特許専門業務・コンテンツ専門業務・ブランド専門業務の3通りに分けられています。
個人情報保護士
個人情報保護士は、個人情報の理解を含め、企業において個人情報を適正に利用できるスキルを証明可能な民間資格です。
情報技術の発展により個人情報がデータとして蓄積されるようになった現代は、情報セキュリティ強化の重要性も高まっています。
法務担当者には、適正な個人情報の管理・利用の実現に向けて、個人情報保護法をはじめとする高度な知識が求められます。
その知識を習得し、証明するには個人情報保護士の資格取得が最適です。
まとめ
企業法務は一生変わらないものではありません。法令や制度が変われば、実務にも影響します。
そのような可変的な企業法務のスキルを養うために、法務の基礎から実践に役立つスキルまで学ぶ手段として勉強会があります。他の組織の企業法務担当者とのディスカッションによって課題の解決策が見つかるといったメリットも得られます。
条件や受講料はセミナーによって異なり、定員が設けられているものもあるので、会社経由でお得に受けられるものはないかなども含め、勉強会に興味を持ったら早めにリサーチを始めることをおすすめします。