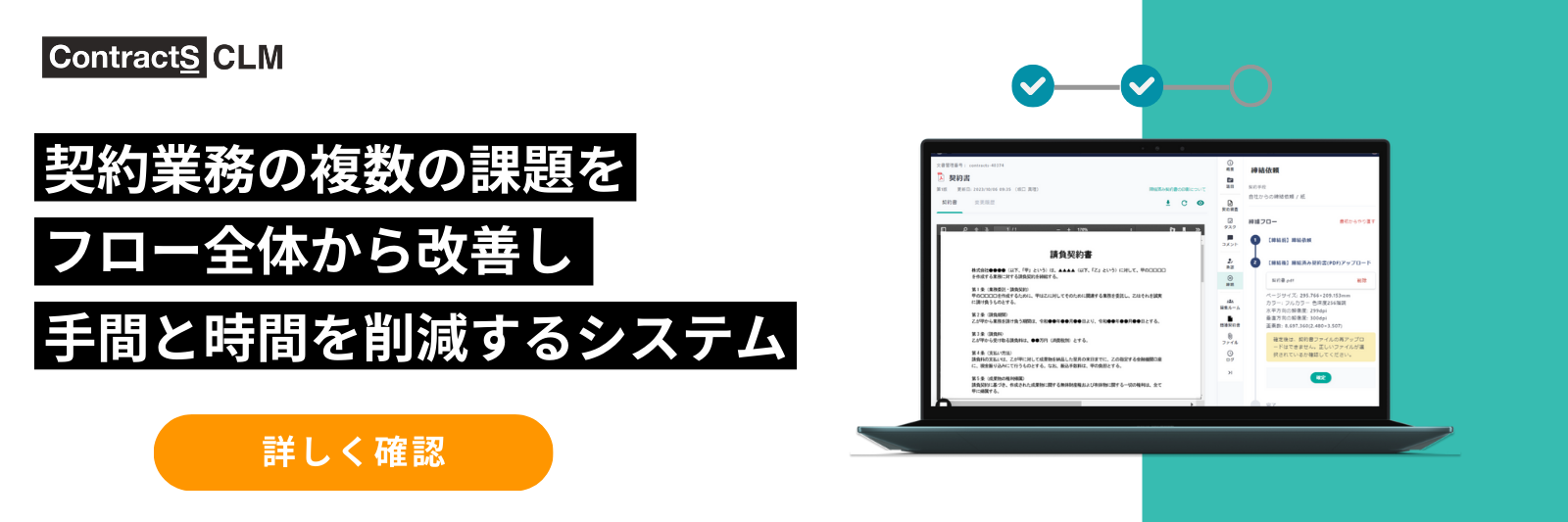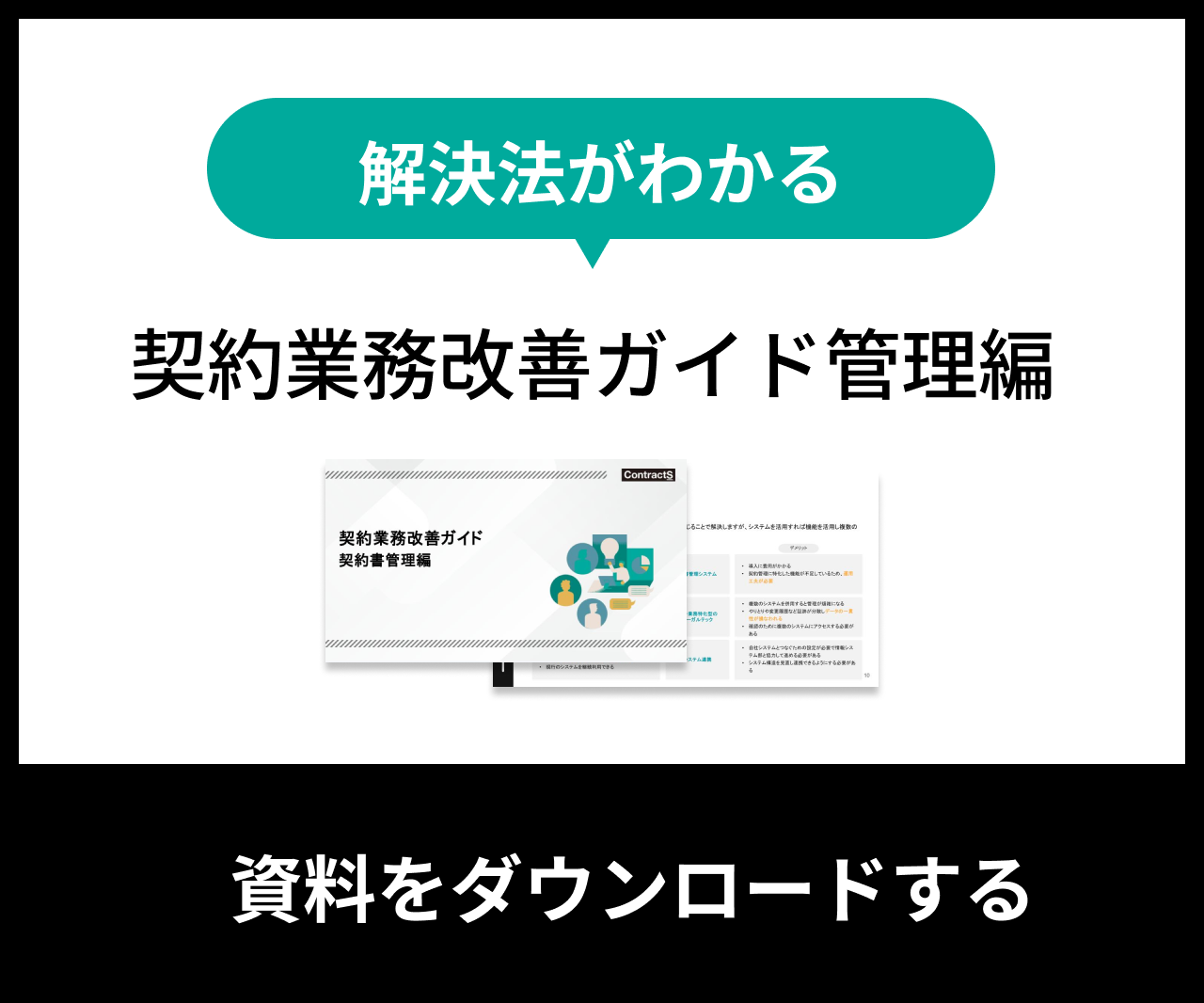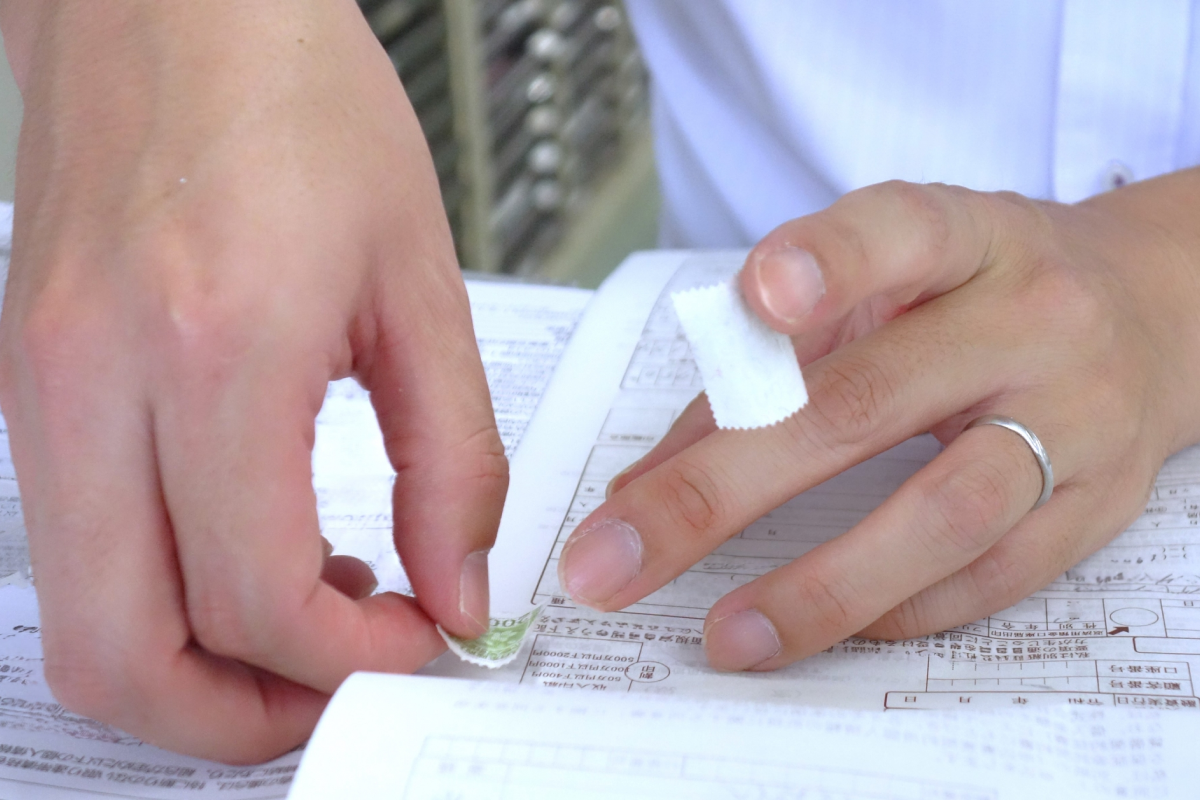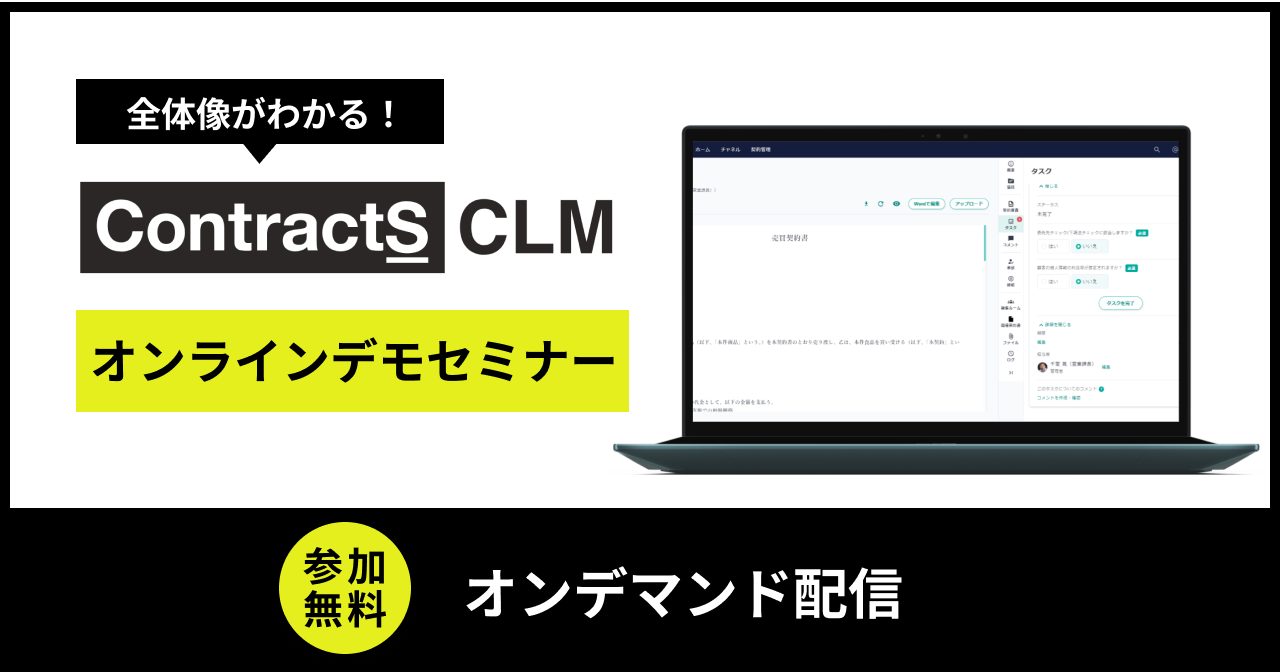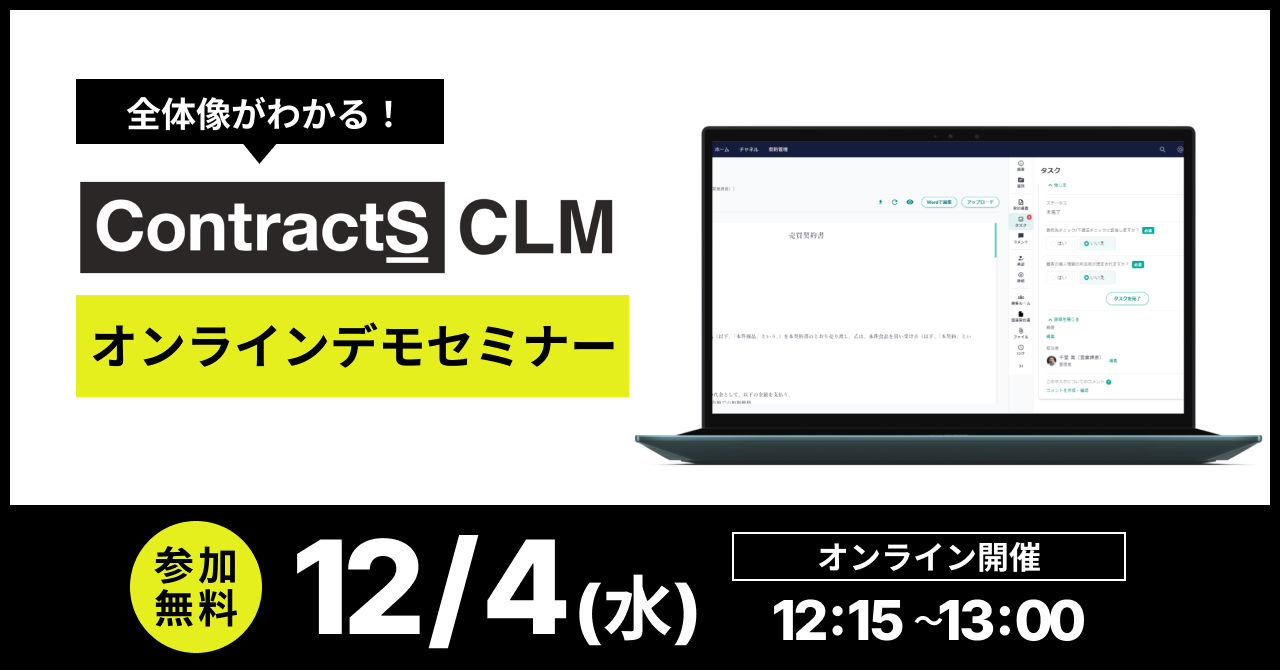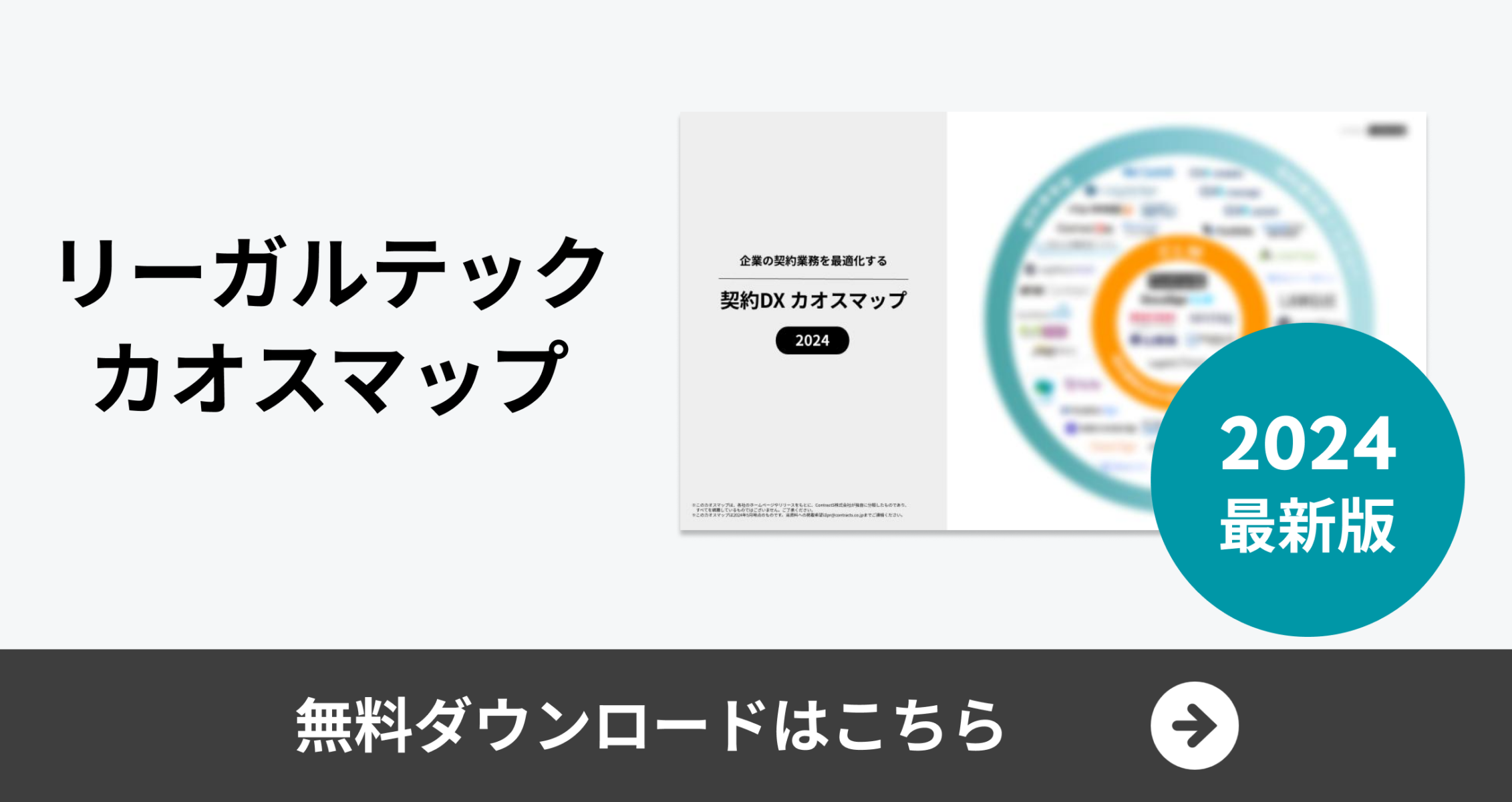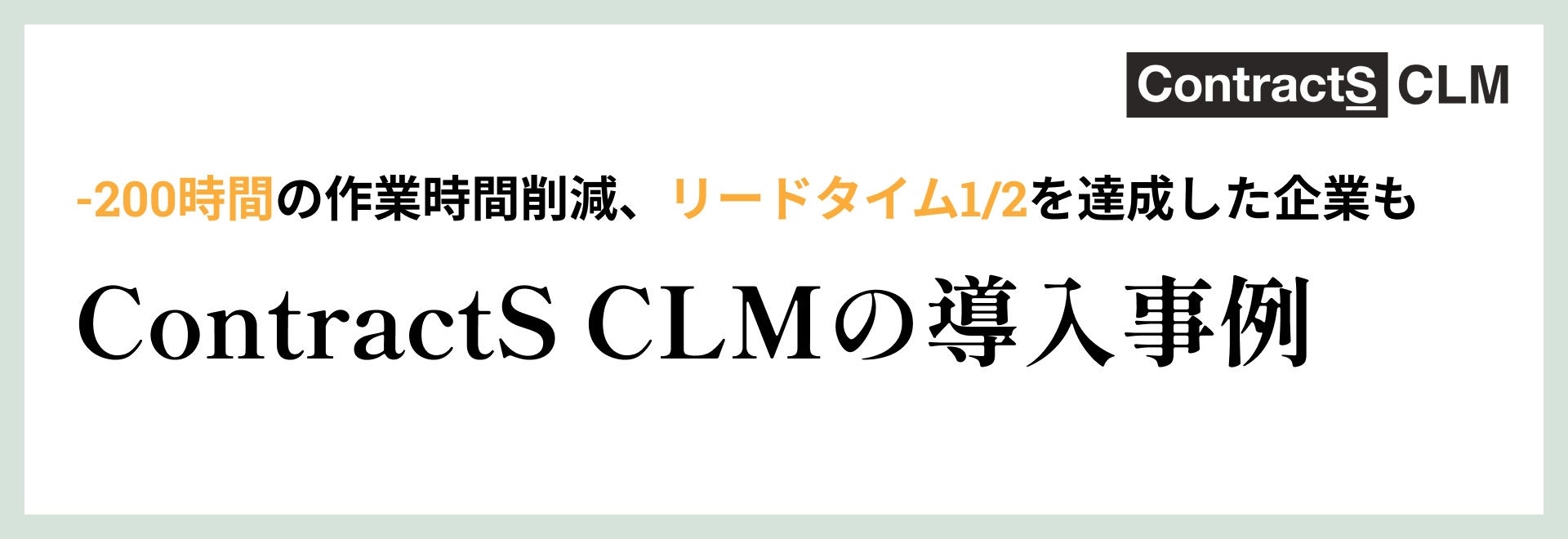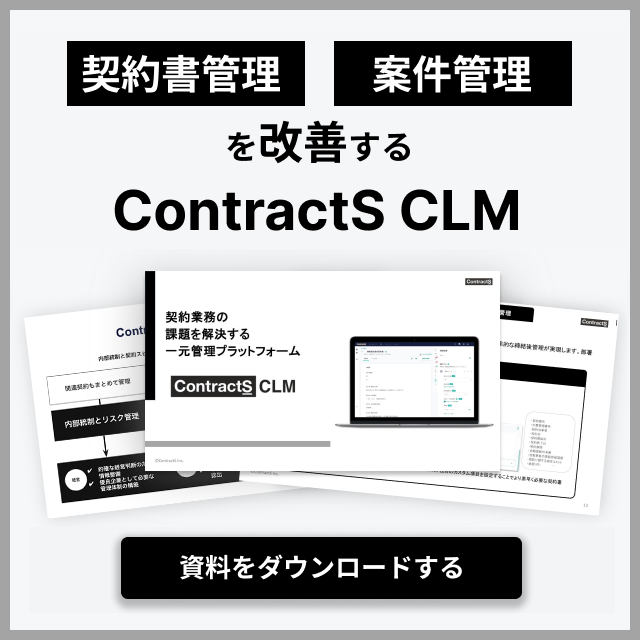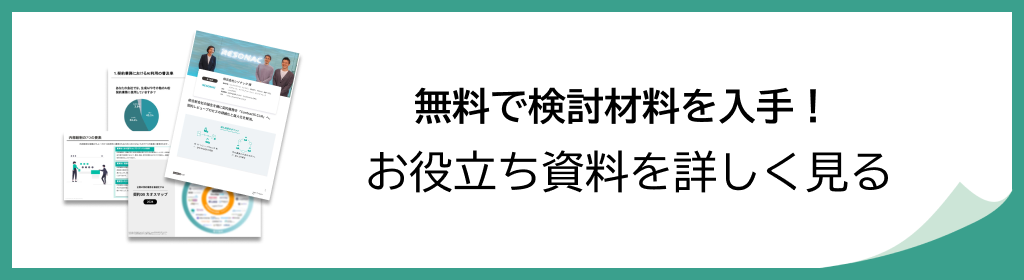ノウハウ 株主総会議事録とは?必須の記載事項など書き方の注意点【例文付き】
更新日:2025年02月7日
投稿日:2023年11月29日
株主総会議事録とは?必須の記載事項など書き方の注意点【例文付き】

株主総会議事録とは株主総会の概要をまとめた文書です。
硬い文体のため、どのような書き方をすれば良いのか悩む方は多いのではないでしょうか。必須でないなら難しそうだから作成したくない方もいるかもしれません。
そもそも株主総会議事録は作成しなければならないものなのか、文書に含める内容や書き方について、作成時の注意点とあわせてまとめました。
Contents
株主総会議事録とは
株主総会を開催した際に作成する文書です。会議の内容、決定事項などを記録します。
会社法第318条第2項第3項により、議事録は本店に10年、支店には写しを5年間保管しなければなりません。
株主や債権者は正当な理由があれば、閲覧請求することで、株主総会議事録の閲覧やコピーを求めることができます。
また、議事録は株式会社変更登記の申請時にも必要となることがあります。変更登記申請が必要となる事項についての話し合いが行われ、決議されたことを証する株主総会の議事録の添付が必要だからです。
手間で属人的な契約書管理にお困りではありませんか? ContractS 契約管理PROなら契約書以外の書類管理も実績あり
⇒ContractS 契約管理PROの資料を見てみる
株主総会議事録の作成は必要?
会社法第318条第1項では、株式会社は株主総会を開催したら株主総会議事録の作成が必要であると定められています。
また、定時株主総会か臨時株主総会か問わず作成が必要です。
会社法施行規則第72条第2項においても、議事録は書面または電磁的記録で作成しなければならないと定められています。
1人会社(1人株主)の場合も、この義務から除外されることはありません。
1人会社では、取締役と株主が同一人物であり、株主総会に出席するのも1人だけです。そのため、みなし決議(書面決議)を活用し、株主総会の開催を省略することは可能です。しかしながら、議事録の作成義務が免除されるわけではありません。法令に則った形式で正しく議事録を作成し、適切に管理する必要があります。
保管期間は株主が複数いる会社と同じく10年間です。
押印は必要?
基本的には不要ですが、後々のトラブルを避けるために少なくとも議長・代表取締役の記名押印があると安心です。
ただし、以下の場合は押印が必須です。
- 定款で定められている
- 株主総会で代表取締役を選定した
定款とは会社のルールをまとめたものです。会社設立時から会社が存続する限り必要な書類です。
定款に実印押印と定められていれば、実印を押します。
取締役会を設置していない会社は、株主総会で代表取締役を選ぶことができます。株主総会で代表取締役を決めた場合、2週間以内に出席した役員全員の実印が押印された議事録を当該役員全員の印鑑証明書と共に提出することが登記手続上、必要となります。
ただし、株主総会開催時点の代表取締役が株主総会に出席して押印した場合、押印に使用した印鑑が登記所に提出のものと同じであれば、商業登記規則第61条により、出席者全員分の捺印は不要です。
誰が作成する?
作成の担当者は、該当の株主総会中に取締役の権限があった人です。
代表取締役も取締役も作成できるのはもちろん、株主総会中に任期満了となった前取締役も作成可能です。株主総会が終わるまでは取締役の権限があるためです。
一方、株主総会の途中で取締役と承認された人は作成できません。
株主総会議事録の記載項目
会社法施行規則第72条第3項に必須項目の記載があります。条文ごとに記載項目をご紹介します。
株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第342の2第1項
ロ 法第342条の2第2項
ハ 法第342条の2第4項
ニ 法第345条第1項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ホ 法第345条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ヘ 法第361条第5項
ト 法第361条第6項
チ 法第377条第1項
リ 法第379条第3項
ヌ 法第384条
ル 法第387条第3項
ヲ 法第389条第3項
ワ 法第398条第1項
カ 法第398条第2項
ヨ 法第399条の5
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
| 法第342条2の第1項 | 監査等委員である取締役の選任・解任・辞任に関する意見 |
| 第2項 | 監査等委員である取締役を辞任した人は辞任後最初の株主総会で辞任理由を述べることができること |
| 第4項 | 監査等委員である取締役以外の選任・解任・辞任に関する意見について |
| 第345条第1項 | 会計参与の選任・解任・辞任に関する意見 |
| 第2項 | 会計参与を辞任した人が辞任後最初の株主総会で辞任理由を述べることができること |
| 第361条第5項 | 監査等委員である取締役の報酬について |
| 第377条第1項 | 一定の書類の作成に関する事項について会計参与と取締役の意見が異なる時、会計参与は意見を述べられること |
| 第379条第3項 | 会計参与の報酬について会計参与が株主総会で述べた意見 |
| 第384条 | 株主総会の議案や書類などに法令・定款違反があれば、監査役は株主総会での報告する義務があること |
| 第387条第3項 | 監査役の報酬について監査役が株主総会で述べた意見 |
| 第389条第3項 | 公開会社でない株式会社では、監査役の監査範囲を会計に関することに限定された監査役が、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案について、法務省令で定めた書類を調査して株主総会で報告しなければならないこと |
| 第398条第2項 | 会計監査人が株主総会に出席して述べた意見を述べられるケースについて |
| 第399条の5 | 監査等委員の株主総会への報告義務について |
株主総会議事録の書き方
株主総会議事録は、書き方が法律で定められているわけではありませんが、記載事項には必ず触れましょう。
先に記載した項目で、株主総会の日時、場所、出席者の書き方は難しくありません。
特に悩むのは、会議の議題や目的、決定事項についてかと思います。この部分は、例えば「定款の定めにより」「取締役と監査役の任期満了に伴う改選に関する件」「承認可決した」といった書き方をします。
株主総会議事録は見やすく、分かりやすくまとめることがポイントです。
そのために、議事録は1枚にまとめることが理想的です。
また、株主総会の経過や発言内容などの書き方に悩むこともあるでしょう。その場合は箇条書きを用いるなど、ひと目で理解できる構成を取り入れましょう。誰の何についての意見か分かる文章になっているか意識するだけでも、1文が読むのに適切な長さとなります。
株主総会議事録の項目ごとの記載文例
書式の定めはないので、一度ひな形を用意すればスムーズに作成できます。そこで、必須項目の文例について紹介します。
株主総会が開催された日時及び場所
第○回定時株主総会議事録
令和○年○月○日○時から当社の本店にて定時株主総会を開催した。
【出席者や議題について】
以上をもって全議案の審議を終了した。議長は○時に閉会を宣言した。
出席者について
開催を宣言した文言に続き以下のように記します。
株主の総数○名
発行済株式の総数○株
(自己株式の数○株)※自己株式を有する場合のみ。自己株式:株式会社が保有する自己の株式のこと
議決権を行使できる株主の数○名
議決権を行使できる株主の議決権の数○個
出席株主数(委任状による者含む)○名
出席株主の議決権の数○個
出席取締役○○
出席監査役△△
以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより本定時総会は適法に成立した。そこで、代表取締役○○は議長席に着き、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。
議事の経過と結果、総会で述べられた意見・発言について
開会宣言の次に記します。
法務局の記載例が参考になります。
株主総会で議事録係のすること
株主総会の始まる前に総会の議案を確認しておくと、議事録にまとめるべきポイントを押さえやすいです。日時や出席者など、事前に記入できる箇所は書いておくと良いでしょう。出席者を把握することで、誰の意見か掴みやすくなります。
自分で判読できる形で良いので、総会の内容が簡潔に分かるメモを残します。
議事録にする際に再確認したいこともあると思います。定款で禁止されていない限りは録音できるので、録音もしておくと安心です。録音する際は断りを入れましょう。
発言内容や意図に気になることがある場合、念のため確認したいことがある旨を伝えた上で質問してください。総会の終了前に質問する際は、確認したい点が後で分かるようメモに工夫しましょう。
メモや録音を参照しながら議事録を作成します。早めに取りかかると、株主総会の記憶が曖昧となって解釈を誤るといった事態を防げます。
ただメモや録音を書き写すのではなく、読みやすくてひと目で理解できるようまとめることを意識します。
総会の最中に疑問をクリアにしたはずでも、まとめながら気になることが出てくるかもしれません。議事録の内容に誤りがないよう、不安があれば出席者に確認をしてください。作成を終えたら、共有する前に出席者にチェックしてもらうこともおすすめです。
株主総会議事録作成の注意点
法令に則った書き方を守りましょう。会社法施行規則第72条第3項には必要事項がまとめられています。抜け漏れにご注意ください。
知識がないと法令を読み誤る可能性があります。法務に携わる人は知識・経験共に豊富ではあると思いますが、心配なことがあれば弁護士など専門家に相談してみてください。
作成期限は定められていませんが、株主総会が終了してから合理的な期間内の作成が推奨されています。株主総会終了後1~2週間以内には作成したいところです。
株主総会と電子化
会社法の改正で、定款に定めることにより2023年3月以降の株主総会から株主総会資料(株主総会参考資料、事業報告、監査報告など)は自社のホームページなどウェブサイトで原則提供できるようになりました。「電子提供制度」というものです。株主にURLなどを通知することで、株主は資料をチェックできるようになります。
株主総会が開催される日の3週間前又は招集通知発送のいずれか早い日までに資料の掲載を始めるよう定められています。
制度が始まる前は招集通知とあわせて2週間前までに送付することになっていたので、株主は早く資料を確認できるようになり、企業は印刷や郵送にかかる費用と手間を省けます。
ただし、インターネット交付が難しい方にはこれまで通り書面交付にも対応することとなっています。
また、議事録は電子作成も認められています。
記名押印を定款で定めている場合、電子署名も可能です。電子署名についてはこちらで詳しく解説しています。
取締役会のない会社が株主総会で代表取締役を選定した場合、議長と出席者全員の実印又は会社実印が必要となるため電子署名は認められない点は要注意です。
まとめ
株主総会議事録は株主総会が開催されたら作成が必要な文書です。
書式は定められていませんが、記載しなければならない項目については、会社法施行規則で定められています。
記載事項の抜け漏れに気をつけながら、総会の概要がひと目で分かる書類を作成できるよう、作成者は以下を心がけましょう。
- 株主総会の日時や出席者など、事前に分かる項目については総会が始まる前に記入する
- 総会の流れが分かるメモを残す
- 定款で禁止されていなければ録音もしておく※出席者の了承を得る
- 気になる点はすぐに質問する(作成段階でも不安があれば確認を)
不備に注意して、株主総会終了後1~2週間以内に完了できるのが理想です。
会社法の改正で株主総会資料の電子交付ができるようになりました。議事録の電子作成も認められています。
電子作成に対応したサービスを活用することで、これまで以上に効率的な作成が可能です。そして、誤りが訂正されているかやリーガルチェックの手間も軽減されます。