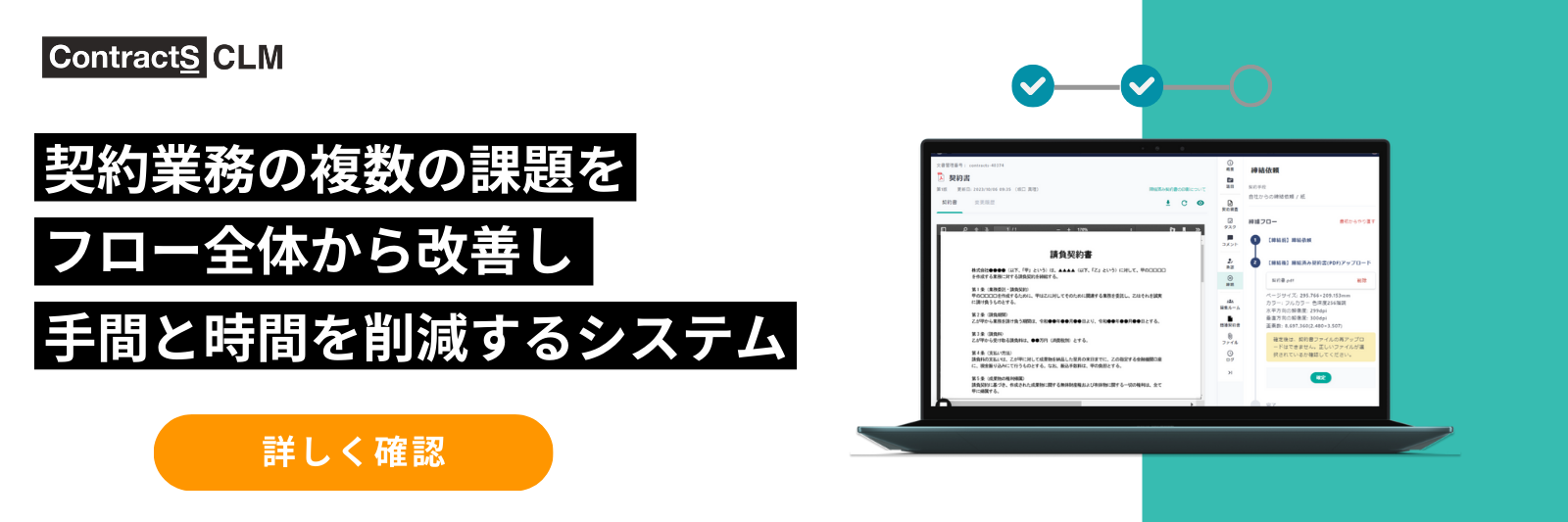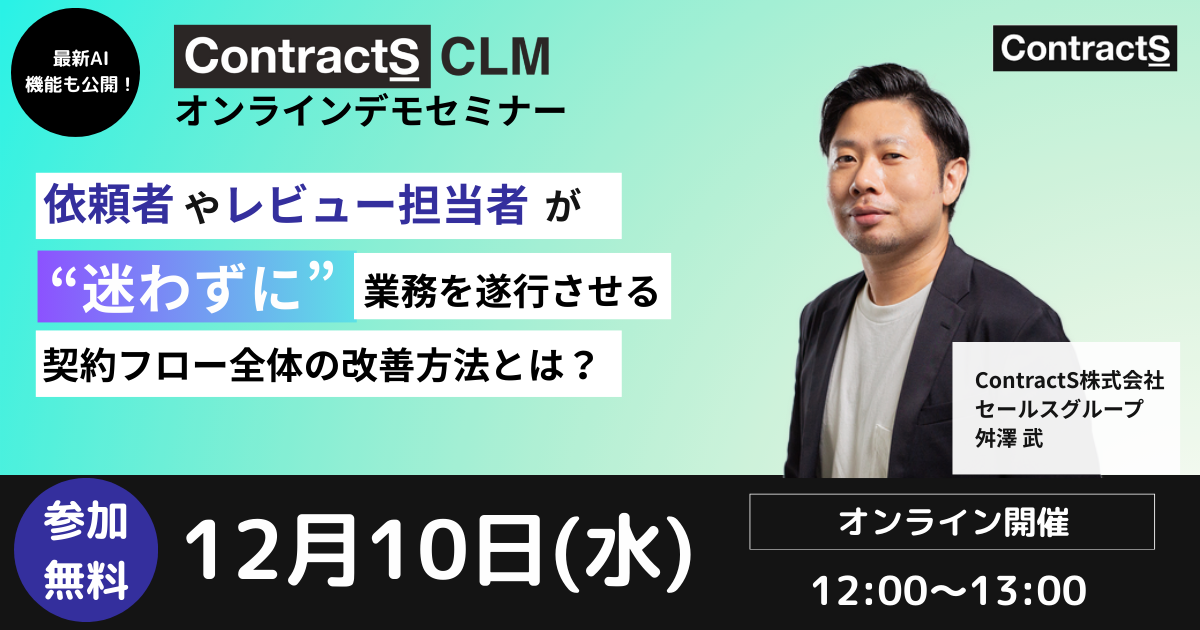ノウハウ 法的リスクとは? 業種別の種類と効果的な対処法を解説
更新日:2025年02月7日
投稿日:2023年11月21日
法的リスクとは? 業種別の種類と効果的な対処法を解説

信頼される組織であり続けるためには、企業が直面する法的リスクに備えることが重要です。
企業にはさまざまなリスクがあり、特に注意すべきポイントは業種によって異なります。
本記事では、業界ごとに想定される法的リスクを紹介し、適切に対処できない場合に生じるリスクや、その対策・対応方法について解説します。
法的リスクの種類
法的リスクとは法令違反に伴うリスクです。
法的な問題が起こると、企業が損害を被ることになります。どのようなリスクが想定されるのか、業種別に紹介します。
ビジネスの根幹である契約業務はコンプライアンスの観点から内部統制と高い関連性があります。資料では、契約管理からどのように内部統制を強化しうるのか解説しています
⇒『コンプライアンス強化実現のための内部統制と契約管理』を見てみる
製造業・メーカー
製造・メーカー業は分業が進んでおり、多様な雇用形態の人が働いています。そのため、契約内容が一律ではなく、労務管理の不備や契約内容の誤りといったリスクが懸念されます。
また、人手不足や離職率の高さは業界全体の課題です。十分な人材を確保できなければ、長時間労働が常態化する恐れがあります。
近年の働き方改革の流れは、製造・メーカー業にも大きな影響を与えています。インターネットの普及により、労働者が法令や労働基準について容易に調べられるようになったことで、自社の時間外労働が法令に違反していないか、未払いの残業代がないかといった点に気づきやすくなりました。その結果、企業に対して法令違反を訴えるケースも増えています。
さらに、どの企業・業種にも共通して言えることですが、コンプライアンス(法令や社内規則、道徳観などの遵守)の重要性はますます高まっています。コンプライアンスを軽視する企業は信頼を失いやすく、取引先や顧客から敬遠され、結果として売上減につながるリスクがあります。
加えて、薬品工場や危険な作業を伴う工場では、製造過程でのミスが重大なケガや健康被害を引き起こす可能性があります。労災保険だけでは対応しきれない労働災害が発生すると、企業は損害賠償責任を負うだけでなく、業務上過失致死傷罪に問われる可能性もあります。場合によっては、労働基準法などの労働関連法令に違反していると認定されることも考えられます。
電気・ガス
2016年の電力自由化をきっかけに、電気事業法は大きく改正されました。現在の事業活動が適法かどうかを正確に判断できなければ、気付かぬうちに法令違反を犯している可能性があります。
また、事業に関連する制度の変更にも迅速な対応が求められます。
電気そのものに違いはありませんが、安定した電力の供給や、お得な料金プランの提供など、事業者ごとに特色があります。こうした違いは顧客層にも影響し、関わる法令も異なる場合があります。自社の顧客や提供するサービスに関連する法令を正しく把握していなければ、法令違反のリスクを抱えることになりかねません。
さらに、2017年にはガスの自由化も始まり、ガス会社に関する法制度の改正も行われています。改正内容によっては、事業者の収益に影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。
個人情報の流出やコンプライアンス違反が発生すれば、顧客からの信頼を損なうだけでなく、対応にかかるコストが経営を圧迫する恐れがあります。また、サイバー攻撃を受けると、顧客の個人情報が流出するだけでなく、都市ガスの製造や供給にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、脱炭素化の流れが進むことで、ガスの需要が減少すれば、現在の料金を維持することが難しくなるかもしれません。顧客の減少により売上が低下すれば、経営悪化のリスクも高まります。
電気もガスも、社会にとって欠かせないインフラです。たとえ小さな違反でも、企業の信頼が揺らぎ、顧客が安心して利用できなくなる可能性があります。
運輸・通信
運送業もまた、人材不足が大きな課題となっている業界です。離職率の高さを解消できなければ、残された労働者の長時間労働が深刻化し、業務の継続に支障をきたす可能性があります。
インターネットショッピングの普及により、自社だけで必要な人材を確保することが難しくなっています。そのため、外部委託などを活用する企業も増えており、直接雇用か否かといった契約の複雑化が進んでいます。また、業務ルールの周知徹底にも手間がかかるため、社内ルールが適切に守られない場合、顧客への不手際が発生し、信用問題につながるリスクがあります。
特に、長距離輸送を少人数で担当するケースでは、長時間労働のリスクが高まります。十分な休息が取れず、健康状態に問題を抱えたまま業務に従事すると、事故の発生リスクが上がります。万が一事故が発生すれば、企業は民事責任や刑事責任を問われる可能性があり、さらに労働関連の法令違反による処分を受けるリスクも考えられます。
一方、情報通信業やIT企業は、多様な分野でオンライン化が進む中で欠かせない存在となっています。通信トラブルなどの際には迅速な対応が求められ、場合によっては時間外労働や不規則な勤務が発生しやすい業界でもあります。
また、顧客との契約内容の解釈に相違があると、トラブル発生時に適切な対応ができず、クレームにつながる恐れがあります。
さらに、IT企業は特許権・商標権・著作権といった知的財産を扱う機会が多く、機密情報の管理が重要です。情報漏えいが発生すれば、企業は損害賠償を負う可能性があり、信用失墜にも直結するため、厳格な管理体制が求められます。
個人事業主
近年、働く時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が増えています。企業と業務委託契約を結ぶことで、個人事業主は契約に基づいた業務を期限内に提供する形で働いています。
副業・専業を問わず個人事業主が増加する中、国も個人事業主を保護するための法制度を整備しています。厚生労働省の資料では、企業が個人事業主と取引を行う際に注意すべきリスクが詳しく紹介されています。
契約書の作成は必須
業務委託契約を締結する際は、必ず契約書を作成しましょう。業務内容や報酬(例:「コンテンツ制作 ○円」など)を明確に記載しないと、後にトラブルの原因となる可能性があります。
また、業務には付随する作業が発生することが多いですが、個人事業主の報酬は基本的に成果に対して支払われます。付随業務を報酬に含めるかどうかを明記しておくことで、報酬をめぐるトラブルを防ぐことができます。
さらに、契約期間や更新の有無も明記しておくことが重要です。
報酬の支払い期限を守る
個人事業主への報酬は、業務提供後60日以内に支払わなければなりません。契約時に締め日・支払日を明確にし、契約書に記載しておかないと、支払い遅延のトラブルや未払いの疑念を招く恐れがあります。
適切な関係性の維持
個人事業主は労働基準法の適用を受けませんが、ハラスメントと受け取られる言動や、育児・介護といった個々の事情への配慮が欠けると、不信感を抱かれる原因になります。
行政指導のリスク
契約書の作成など、企業が個人事業主と契約する際に守るべきルールを遵守しないと、行政指導の対象となる可能性があります。適切な契約と誠実な対応を心がけることが、信頼関係を築くうえでも重要です。
卸売・小売・飲食業
製造業や運送業と同様に、飲食業も人手不足が深刻な課題となっています。
十分な人材を確保できない場合、少ない人数で店舗を運営せざるを得なくなり、その結果、長時間労働や十分な休日の確保が難しくなることが懸念されます。これが労働基準法違反に該当する可能性もあり、適切な労務管理が求められます。
また、飲食業界は「ブラック企業」と見なされやすい側面もあり、特に有名店では企業イメージの悪化が取引先や消費者の離反を招き、売上減少につながるリスクがあります。
飲食業は消費者と直接関わる機会が多いため、理不尽なクレームを受けるリスクも高い業界です。適切なクレーム対応策を講じないと、従業員が精神的な負担を抱え、心身の不調による休職や退職を余儀なくされるケースも考えられます。
従業員の働く環境を守れなければ、人材の確保はますます困難になります。労働関連の法令違反を防ぐためにも、適切な労働環境の整備が不可欠です。企業の信頼を維持し、持続的な成長を実現するためにも、法令を遵守した運営が求められます。
金融・保険業
違約金や損害賠償金、和解に伴う罰金などが発生する可能性があります。
また、マネーロンダリングなどの内部不正や、不正アクセス・サイバー攻撃といった外部からの不正は、企業の信用問題に直結します。場合によっては損害賠償責任を負うことになり、企業の収支に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
サービス業
サービス業は消費者と接する機会が多いため、不当なクレームがいつ寄せられるかわかりません。従業員を守る体制が整っていないと、精神的な負担が増し、離職につながる可能性があります。結果として人手不足が深刻化し、残った従業員の長時間労働を招く恐れがあります。
また、店舗に問題が発生した際は迅速な対応が求められます。しかし、理不尽なクレームに対応するマニュアルがないと、現場の従業員が過度な負担を抱えることになり、業務環境の悪化につながる可能性があります。
企業において法的リスクが高い場合の影響
訴訟を起こされると、企業の信用が失われるだけでなく、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、取引や契約が法令に違反している場合、契約自体が無効となることがあります。さらに、業務停止命令などの行政処分が科されるリスクもあり、事業の継続に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
リスクコントロールの方法
企業にはあらゆる法的リスクが想定されます。リスクを未然に防ぎ、問題が発生したとしても不利益を最小限にするために取り組んでおきたいことが3つあります。
社外弁護士をつける
問題やトラブルが発生した際に、弁護士に相談できる体制が整っていると安心です。
訴訟を起こされた場合に限らず、契約書のチェックなど、法的トラブルを未然に防ぐためにも弁護士を頼ることができます。契約書に不備がなければ、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。
問題が大きくなるほど解決にかかる労力も増えます。弁護士の中には、早めの相談を推奨している人も多いため、何かあったらすぐに相談できるよう、相談のタイミングをあらかじめ決めておくことが重要です。
まだ提携する弁護士が決まっていない場合は、早めに探すことをおすすめします。費用面などの条件が合わない場合、別の弁護士を探す必要があり、依頼できるまでに時間がかかる可能性があります。スムーズに対応できるよう、事前に準備を進めておくとよいでしょう。
システムを活用する
これまで紹介したように、企業活動にはさまざまなリスクが伴います。特に、ビジネスに直接関わる契約書は重要な要素の一つです。契約書の適切な作成、レビューや適切な保管管理ができるよう、しっかりとした体制を整えることが求められます。
また、契約業務はリスク管理と関わりが深い反面、手作業での作成によるミスの発生や管理の未整備による書類紛失トラブルなどが多くの企業で起きやすい状態となっています。業務プロセスを見直し、契約業務に非効率がありそれがリスクにつながると判断できる場合はシステムの活用で改善を図りましょう。
リスクモニタリングができる社内体制を作る
リスクにいち早く気づき、迅速に対処できる環境を整えることは非常に重要です。しかし、実施した施策がリスクの緩和にどの程度効果を発揮したのかが分からなければ、同じ問題が再発し、適切に対応できない可能性があります。
リスクを共有し、その原因を分析したうえで対策を考え、実行後に効果を検証し、必要に応じて改善を行う——この一連のプロセスを責任を持って進められる体制を構築することが不可欠です。
とはいえ、企業が自力で調査から対策の評価までを行うのは容易ではありません。例えば、SNS上の投稿が企業の信頼を損なうリスクや、店舗でのトラブルの発生を予測したい場合には、モニタリングシステムの導入を検討する価値があります。これにより、リスクを即座に察知し、適切な対処法を提示してもらうことが可能になります。
さらに、リスクが拡大し、社内対応だけでは事態が沈静化しない場合には、外部の専門家によるサポートを受けられるサービスの活用も選択肢の一つとして考えられます。
まとめ
業種によってあらゆる法的リスクが想定されます。特に、人材確保に苦戦していると、人手不足による問題、例えば長時間労働などが起こりやすいです。
消費者と接する機会が多いと、不適切なクレームが寄せられた時の対応を考えておくことも求められます。
雇用や取引など何かしらの契約を締結する際には、内容を確認した上で契約書を交わさないと、後に不都合が生じます。最悪の場合、訴訟や損害賠償に応じなければなりません。
法的リスクをコントロールするには、リスクにいち早く気づいて対処できる社内体制を整えることも一つの対処法です。
【関連記事】法務リスクとは?リスクマネジメントと管理方法を具体例で解説