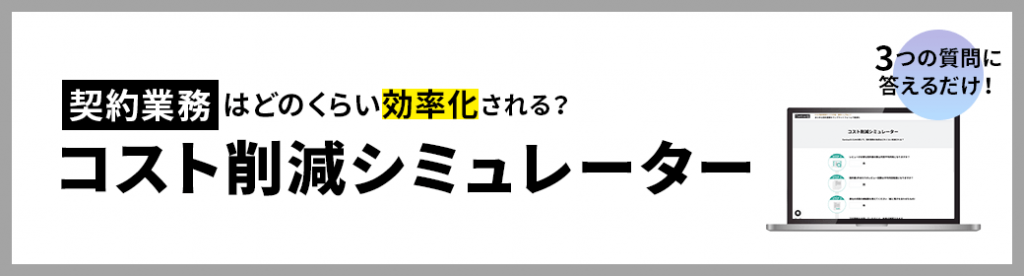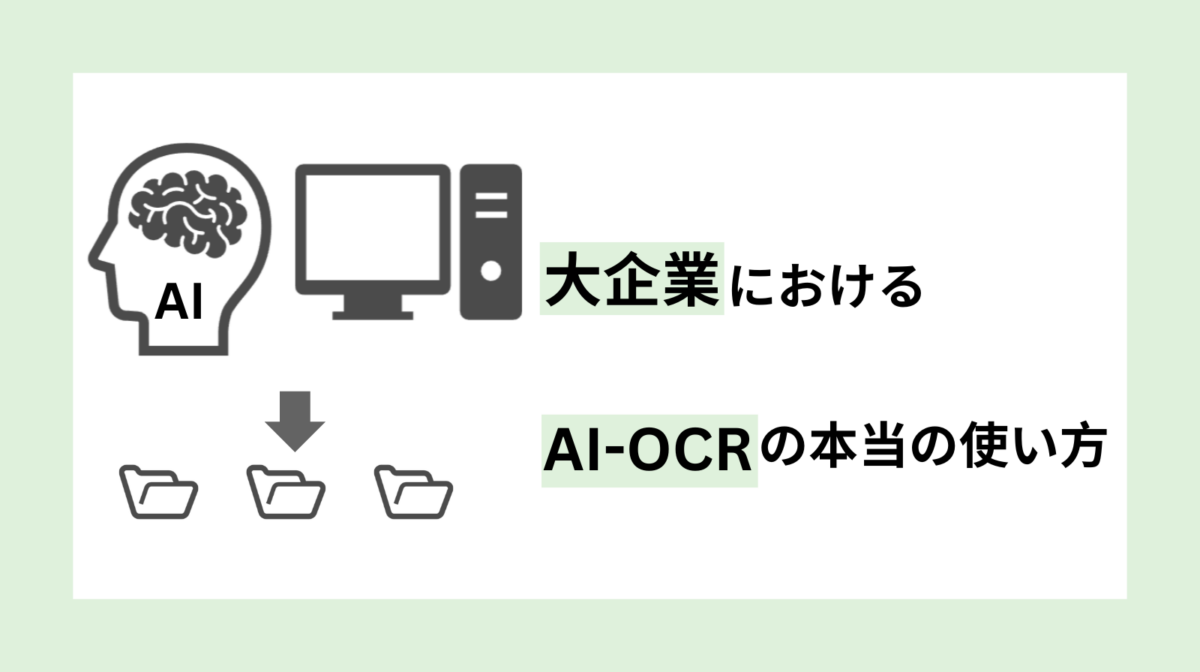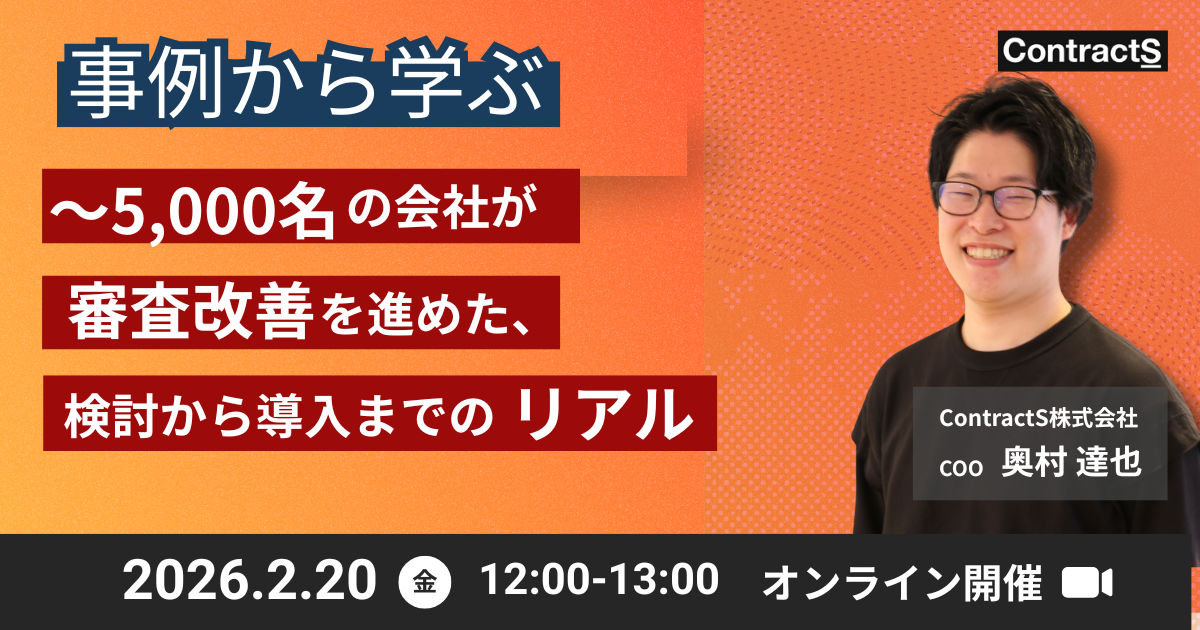ノウハウ 【一覧】契約書の保管期間とは?会社法や法人税法などの法律に沿って解説
更新日:2025年03月27日
投稿日:2023年09月27日
【一覧】契約書の保管期間とは?会社法や法人税法などの法律に沿って解説
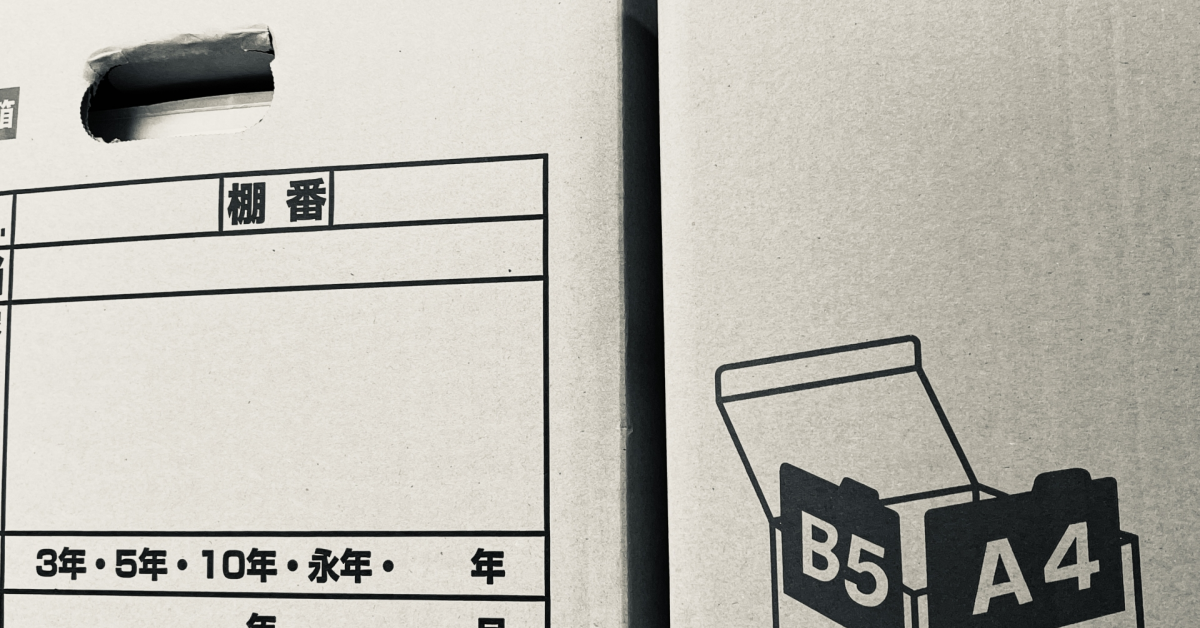
契約書の保管期間に関しては、会社法など複数の法令に定めが置かれており、これらの期間を遵守する必要があります。
そこで今回は、各法令が規定している契約書の保管期間や保管方法についてまとめました。また、契約書を保管する際に注意すべきポイントや、効率的な契約書の管理方法についても解説します。
【一覧】契約書の保管期間は?会社法、法人税法と法律をもとに解説
契約書は取引に関する重要な内容が記載されているため、契約を締結したからといって破棄して良いものではありません。
また、契約書は法律によって一定期間の保管が義務付けられている点にも注意が必要です。
契約書の種類によって、保管が必要な期間の根拠法令も異なります。
契約書全般に適用される保管期間と根拠法令、契約書の種類別に適用される保管期間と根拠法令をまとめると、以下の通りです。
|
対象書類 |
保管期間 |
根拠法令 |
|
会計帳簿及び事業に関する重要な資料(契約書を含む) |
10年 |
会社法第432条 |
|
帳簿や取引に関する書類(契約書を含む) |
7年(最長10年) |
法人税法第126条、法人税法施行規則第59条 |
|
雇用契約書 |
5年 |
労働基準法第109条 |
|
労働契約書 |
||
|
労働者派遣個別契約書 |
3年 |
労働者派遣法第37条・42条 |
|
秘密保持契約書 |
目安として1年~5年程度 |
– |
|
売買契約書 |
10年 |
会社法第432条、法人税法第126条、法人税法施行規則第59条 |
|
リース契約書 |
契約書の法律別の保管期間
①会社法上の保存期間は10年
会社法では、「事業に関する重要な資料」を10年間保管しなければならないとされています。
(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
【引用元:会社法432条 – e-gov法令検索】
契約書は、現代のビジネス環境において必要不可欠な重要文書であるため「事業に関する重要な資料」に該当します。
②法人税法上の保存期間は7年
法人税法では、税務関係の「帳簿」や「書類」(契約書も含む)を7年間保管しなければならないとしています。
なお、欠損金がある場合の保管期間は10年とされています。この点からも、基本的に契約書は10年間の保管をしておくことが望ましいといえます。
(青色申告法人の帳簿書類)
第百二十六条 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
(以下省略)
【引用:法人税法126条 – e-gov法令検索】
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
(以下省略)
【引用:法人税法施行規則59条 – e-gov法令検索】
電子帳簿保存法上の保存期間は法人税法と同じ
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿・決算関係書類・取引関係書類などを電子データとして保存する場合の要件を定めた法律です。
契約書を始め、青色申告に用いる各種書類や請求書・領収書・見積書などを電子化する場合は、電子帳簿保存法の要件に従う必要があります。
電子帳簿保存法の対象書類の保存期間は、法人税法と同じく7年(最長10年)です。
労働基準法上の保存期間は5年
詳細は後述しますが、労働基準法が適用される契約書としては雇用契約書や労働契約書があります。
現行の労働基準法では、契約書を含む「雇入れ・解雇・災害補償などに関する書類」は5年間の保存を義務付けています。
対象書類を電子化しても、労働基準法上の保存期間は変わらない点に注意が必要です。
契約書の種類別の保管期間
契約書にはさまざまな種類があり、それぞれ保管すべき期間が異なります。この記事では、主な契約書の種類ごとに具体的な保管期間を解説します。
雇用契約書の保管期間
従業員を雇う際に用いる雇用契約書は、賃金・就業場所・就業時間・業務内容など労働に関する重要事項を確認のうえ同意を得るための書類です。
雇用契約書は、労働基準法第109条にて5年間の保存が義務付けられています。
また、雇用契約書だけでなく、以下のような労働関係に関連する書類もすべて5年間保存する必要があります。
・履歴書
・雇入決定関係書類
・労働条件通知書
・身元引受書 など
労働契約書の保管期間
企業が従業員を雇う際に用いられる契約書としては、労働契約書もあります。
労働契約書も、労働基準法に従い5年間の保管が義務付けられています。
労働契約書は雇用契約書と似ていますが、労働基準法第15条で交付が義務付けられている点が主な違いです。
労働者派遣個別契約書の保管期限
派遣社員を雇う場合に用いられる契約書の1つである労働者派遣個別契約書は、法律で保管期間が義務付けられていません。
なお、派遣雇用契約に関する書類には派遣元・派遣先で派遣社員の就業実態を把握するための「派遣元管理台帳」と「派遣先管理台帳」という書類があります。
これらは労働者派遣法第37条・42条で各法定記載事項が確定するたびに記載が必要とされている他、3年間の保管が義務付けられています。
万が一トラブルが生じたとき、台帳と併せて労働者派遣個別契約書も同期間保管しておくと雇用条件や勤務内容について確認が容易となり、スムーズに対応しやすくなります。
秘密保持契約書の保管期間
秘密保持契約を締結する際に用いる秘密保持契約書も、一定期間の保管が義務付けられているわけではありません。
また、秘密保持契約の有効期間も提供する秘密情報の内容によって適した期間が変わります。
例えばIT技術の情報など短期間で陳腐化しやすい場合は1年程度、顧客情報など重要な情報は5年程度が目安です。
情報の内容を考慮のうえ慎重に有効期間を定めておきましょう。
売買契約書の保管期間
商品やサービスの売買取引で用いられる売買契約書は、取引・事業に関する契約書です。
そのため、法人税法・会社法に従い10年間の保管が必要です。
リース契約書の保管期間
車両・事務用品・IT機器などの商品を一定期間リースする場合は、リース契約書を作成のうえ契約を締結します。
リース契約書の保管期間を定めた法律はありませんが、事業に関わる契約書であるため会社法に基づき10年間は保管しておきましょう。
その他の契約書の保管期間一覧
一部の契約書や、そのほかの重要書類については、別の法律に特別な定めが置かれている場合があります。
また、産業廃棄物処理や建築業など、特定の法令に基づいて営業活動を行っている場合、さらに別途規定が置かれている場合があるため特に注意が必要です。
|
対象書類 |
保管期間 |
|
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関する書類 |
2年 |
|
労災保険に関する書類 |
3年 |
|
労災保険の徴収・納付等に関する書類 |
3年 |
|
派遣元管理台帳 |
3年 |
|
雇用保険の被保険者に関する書類 |
4年 |
|
有価証券届出書 |
5年 |
|
株式会社の事業報告(本店備え置き分) |
5年 |
|
株主総会議事録(本店備え置き分) |
10年 |
|
効力が存続している契約書 |
法令上の根拠はないが、性質上永久保存が望ましい |
契約書は当事者のどっちが保管する?
紙の契約書で原本が1通だけの場合、どちらが保管するかは契約内容や当事者間の合意によって変わりますが、主要な当事者が保管するケースが多いです。
当事者のどちらかが原本を保管するなら、その旨は契約書に明記しておくことをおすすめします。
将来的に契約に関してトラブルが生じたとき、保管者側に対する誤解が生じないようにするためです。
また、原本の保管者側は紛失・破損・汚損が生じない適切な方法で保管し、必要に応じて速やかに提出できる環境を整えておく必要があります。
契約書を保管する際に注意すべき3つのポイント
ここまで紹介したように、基本的に契約書は10年保管することが望ましいものの、契約書は次々に溜まっていくため、適切に管理することが重要です。
以下からは、契約書を保管する際に注意すべきポイントを3つ紹介します。
ポイント1.契約書管理台帳を作成する
契約書を適切に管理するために、契約書管理台帳を作成しましょう。
契約書管理台帳には、契約当事者や契約内容、効力発生日・終了日、更新日などの情報を記載し、契約状況を一目で確認できるようにしておきます。
また、契約書の保管場所やアクセス方法も記録しておけば、必要なときに迅速に契約書を取り出すことができます。
契約書管理台帳があれば、大量の契約書がある場合や、異なる部署や担当者間で情報を共有する場合に大きな助けとなりますが、台帳自体を定期的に更新し、最新の情報を保持する必要があります。
ポイント2.紛失・機密流出対策をする
契約書は企業の重要な文書であるため、適切な管理を行い、紛失や機密流出を防ぐ必要があります。
例えば外部への持ち出しに関しては決裁者の許可を必要とし、社内でも特定の場所での閲覧のみを許可するといった形の規定を設けるようにしましょう。
もっとも、紙ベースでの保存には限界があります。
紙の契約書は、火災や水害、物理的な損害のリスクに常にさらされており、人為的なミスや不注意による紛失も考えられます。
このようなリスクを考慮し、原本の保存場所とは別にスキャンなどで電子データ化し、別の場所に保管するという方法も有効です。
そうすることで、ひとつの場所での問題が発生した際にも、他の場所に保管されているコピーで情報の損失を回避できます。
ポイント3.不要な契約書は定期的に破棄する
情報の整理や保存スペースの効率的な利用、セキュリティリスクの軽減のため、不必要な契約書は定期的に破棄するようにしましょう。
一般的債権の消滅時効は10年であるため、契約期間終了後10年を経過した契約が法的紛争に発展するケースはほとんどありません。
また先ほど紹介した法律の保管要件から考えても、契約書は10年保管すれば足りるため、基本的に10年を経過した契約書は破棄しても問題ないといえます。
社内での情報共有のため、過去の契約書も保管しておきたい場合には、スキャンして電子的に保管するなどの対策が必要です。
契約書保管の手順
契約書を適切に・効率的に保管するなら、以下のステップで保管環境を整えることをおすすめします。
1 契約書の管理担当者・部署の決定
2 契約書管理台帳の作成
3 不要な契約書の破棄
4 契約書の分類
5 契約書のファイリング
紙の契約書は、保管担当の決定から契約書のカテゴリー設定までのプロセスを経てファイリングすることで管理しやすくなります。
とはいえ、契約書の数が多いとそれに伴う業務負担も大きくなり業務全体の効率が低下する可能性もあるため、状況に応じて紙ではなくデジタル化するなどより効率的な他の方法も検討すると良いでしょう。
契約書を保管する3つの方法
契約書は次々に増えていくため、適切な管理をしなければ必要な時に情報を取り出すことができなくなってしまいます。ここでは、契約書を保存する具体的な方法を3つ紹介します。
方法1.紙のまま保存する
現在でも、多くの企業が契約書を紙のまま保存しています。
しかし現代の情報管理やビジネス ニーズを考えると、紙のままの保存にはいくつかのデメリットもあります。
紙の契約書を適切に整理・管理することは難しく、時間の浪費や作業の非効率を招きがちです。
また、保管スペースを圧迫するという問題もあり、紛失のリスクも伴います。
そのため、紙ベースでの保存だけに頼るのではなく、以下に紹介するスキャン保存や電子契約の導入なども検討するようにしましょう。
方法2.スキャンして保存する
次に紙ベースの契約書をスキャンして電子データとして保存するという方法です。
電子データで保存すれば物理的なスペースは不要であり、大量の情報も瞬時に検索することができます。
ただし、契約書などをスキャンして保存する際には、電子帳簿保存法などが定める法律の要件を満たす必要があります。
もし要件を満たさないまま紙の原本を破棄してしまうと、法律の保存義務に反したことになるため注意が必要です。
▶関連記事:電子帳簿保存法とは?対象と要件をわかりやすく解説!
スキャン・保管作業の外注も要検討
スキャン対象の契約書が膨大だと、工数に対して社内のリソースが足りない可能性があります。
その場合は、書類のスキャニング作業を代行している外部への委託も検討しましょう。
費用はかかりますが、スキャニング作業に社内のリソースを割く必要がないため、自社の人材はコア業務に集中することができます。
また、サービスによってはデータを保管するフォルダの構築やファイルのリネームといった作業も代行できるため、スキャン後の自社での設定作業を減らすことができます。
方法3.電子契約で保存する
最後に、紙の契約書を使用せず、最初から電子契約で作成・保管するという方法です。
現在では 電子帳簿保存法や電子署名法の施行により、日本でも電子契約が急速に普及しています。
電子帳簿保存法によると電子契約として作成された契約書は、紙に印刷せずそのままデータとして保管しなければならないため、ファイリング、台帳登録といった多くの作業を自動反映、もしくはなくすことができます。
紙の契約書の保管に関して陥りがちな問題
紙の契約書を保管する場合に問題として、以下のようなものがよく聞かれます。
どの契約書を破棄して良いのか分からない
契約書は種類によって異なる保管期間が定められており、破棄して良いタイミングも契約書ごとに変わります。
契約書の保管期間が分からなければ、破棄せずそのまま保管を続ければ良いと考えてしまいがちです。
しかし定期的に破棄しないとオフィス内に膨大な契約書が溜まり、かえって管理の煩雑化につながります。
更新が必要な契約書を管理できない
契約内容によっては定期的な更新が必要ですが、紙の契約書が自主的にそれを通知してくれることはありません。
そのため更新が必要な契約書の更新日を、保管担当者自身が常に把握している必要があります。
しかし人が管理をしている場合、ヒューマンエラーにより、更新の抜け漏れが生じて今後の取り引きに支障が出るリスクを伴います。
紛失のリスクがある
紙の契約書ならではの欠点として、紛失のリスクが避けられないことにも注意が必要です。
紛失リスクを防止するには、保管場所の徹底や持ち出しの制限といった対策があります。
しかし他の書類に紛れて意図せず外部へ出てしまいそのまま紛失するなど、予期せぬ紛失トラブルが生じるケースも珍しくありません。
「人的ミスによる紛失をいかに回避するか」も考慮したルールの策定が重要となります。
必要な契約書をすぐに探し出せない
契約書の数が多いほど、必要な契約書をすぐに探し出すための工夫も重要です。
特に、複数の部署で異なる契約書を保管していたり、保管場所の整頓が徹底されていない場合は契約書を探すために余計なタイムロスが発生します。
1つの担当部署でカテゴリー別に契約書を保管していても、当該のカテゴリーのスペースを探してファイルを取り出し、1枚ずつページをめくって必要な契約書を探すという一連の作業は避けられません。
紙の契約書を減らして安全に保存するなら電子契約
法律で定められた期間中、紙の契約書を確実に保存することは難しく、年月の経過とともに保存が必要な契約書の量も増えていきます。
保存する紙の契約書が増えると、上述した破棄・更新管理・紛失リスク・検索性などに関する課題が立ちふさがり、管理体制の不備が目立つようになります。
契約書の管理を煩雑化させず、安全に保存するなら契約書の電子化がおすすめです。
契約書を電子化するには、紙の契約書をスキャンして電子データに変換する他、電子契約システムを導入するという方法もあります。
電子保存する3つのメリット
ここまで解説したように、契約書は基本的に10年間保存すべきですが、大量の契約書を10年にわたって保存することは簡単ではありません。
そこで、今後発生する契約書に関しては積極的に電子化をすすめ、将来見込まれる保管の手間を少なくしておくことが一つの方法としてかんがえられます。以下からは、契約書を電子保存するメリットを3点紹介します。
メリット1.契約書を探す手間を省ける
契約書を電子保存することで、検索性が高まり、契約書を探す手間が省けるというメリットがあります。
電子保存された契約書はデータベースやクラウドストレージに保管されキーワードや日付、関連性などを様々な条件で即座に検索することができます。
契約関連業務では、契約内容の確認や照会、更新などのタスクが頻繁に発生するため、こうした検索機能の利点は計り知れません。
さらにデータを一元管理することにより、複数の関係者が同じ情報にアクセスできるため、必要に応じて編集や共有を行うことが容易となります。
メリット2.契約書の紛失・流出を防げる
契約書を電子保存することで、物理的な書類保管と比べ、紛失や流出のリスクを大幅に軽減することが可能です。
従来の紙ベースの契約書は、火災や水害、盗難などのリスクに常にさらされていました。また、管理が煩雑となり紛失のリスクが増大することもあります。
これに対し、最新のクラウドサービスでは高度な暗号化技術が用いられており、外部からの不正アクセスを防止するとともに、バックアップ機能も備えているためデータの消失に備えることもできます。
また電子契約には改ざん防止措置が含まれていることも多く、契約書の内容が後から改ざんされることを防ぐことが可能です。
メリット3.コストカットできる
紙の契約書を使用せず、最初から電子契約で作成・保管するという方法は、コストカットが期待できます。
電子契約の導入には、初期費用やシステム維持のコストが発生しますが、長期的に見れば印紙代の削減をはじめとする契約業務の大幅なコストカットに繋がります。
紙ベースの契約書には印刷や郵送といったコストがかかり、専用のスペースやファイリングキャビネットの購入費用が発生するとともに、オフィスのスペースを圧迫してしまいます。
電子契約であればこれらのコストは発生せず、業務効率化ができることで、より生産的な業務に専念することも可能です。
さらに、電子契約の導入により森林資源の保護や廃棄物の削減にも貢献でき、企業の社会的責任を果たす一助にもなります。
電子契約書でも注意したい保存時の課題
電子化した契約書も、適切な管理体制のもとで保存しないと様々な課題に直面する可能性があります。ここでは、電子契約導入後に起こりがちな課題について解説します。
契約の期限を見落とすことがある
電子化しても、契約期限を見落として更新を見逃すリスクは伴います。
電子契約システムの場合は契約の自動更新機能が備わっていることもあるため、利用すれば更新忘れのリスクは回避できます。
その一方で、解約予定だった契約まで自動更新されてしまい、余分な費用の支払いが生じる可能性もあるため注意が必要です。これを防ぐには、通知後の適切な対応を指示できるインストラクションを通知文面に含められるシステムを選ぶことや、通知後の対応について周知徹底することが重要です。
検索性の確保にも工夫が必要
電子契約書の保管において問題となりがちなポイントが、データの整理です。
電子データでも、保存先のフォルダが整理されていなければ、後から探すことが困難になります。
契約書に設定できるキーワードが少ないと、必要な契約書を適切に抽出できず、契約期限の見落としやトラブル対応の遅れといったリスクにつながります。
セキュリティリスクの対策が重要
電子契約書ならではの課題として、不正アクセスやハッキングによる情報漏洩が挙げられます。
第三者による契約書データの閲覧・持ち出しを防ぐには、IPアドレス制限やSAML認証といった仕組みと合わせデータのアクセス権限の制御が重要です。
また、データの修正や削除が行われた場合は、誰が操作を行ったかを追跡できる環境も整える必要があります。
一元管理を可能とする環境の構築に手間がかかる
契約書を含む、契約関連の資料や情報の保存場所は分散しがちです。
契約に関するデータとしては、電子契約書・契約に関するメールのやり取り・契約書審査での審査コメントなどがあります。
これらをいかにして一元管理するかを考え、必要に応じて新しい環境を構築するにも手間がかかります。
電子契約書管理の課題を楽に解決する方法
セキュリティリスクや一元管理などの課題を解決しながら電子契約書を管理する方法としては、以下の3通りがあります。
契約書管理台帳を作成する
契約書の基本情報・契約の期限・保管場所・担当者などの情報を記した、契約書管理台帳を作成するという方法です。
あらかじめ台帳を作成しておけば、契約書ごとの契約状況や更新期限を簡単に把握できます。
作成方法としてはExcelの使用が手軽ですが、カスタマイズ性が高いがゆえに、作成者によってはデザイン性・視認性・検索性に欠ける台帳となる可能性があります。
また、手入力で作成する必要があるため、情報の抜け漏れにも注意すべきです。多くの電子契約システムには台帳機能が備わっていますが、自動反映されるか、検索しやすいものか導入前に確認しておきましょう。不足がある場合、管理機能の強いものを選択するか双方を利用することが望ましいです。
中央管理をする
部署ごとに異なる文書管理体制やワークフローを採用すると、他部署の担当者が必要な情報をスムーズに取得できず、管理状況の確認が難しくなります。また、管理状態を第三者がチェックできないことから紛失のリスクも高まります。
これを防ぐには、自社で取り扱うすべての契約書を一ヵ所に集約して管理するという方法が有効です。
具体的には、文書管理システムや契約管理システムを導入し、そのシステム上で文書のデータを管理します。
なお、文書管理システムは文書全般の管理に対応可能ですが、管理する書類の量によっては管理項目が増え、混乱が生じます。
契約書だけでもボリュームが多い場合は、契約管理に特化したシステムの導入を検討しましょう。
CLMや契約管理のシステムを導入する
CLMとは、契約に関わるプロセス全体をシステムを利用して体系的に管理することで、それができるシステムをCLMシステムといいます。
CLMシステムを使うと、契約書の作成・承認・送付・締結・保存・更新など、あらゆるプロセスを同一のシステムで行えるため、業務を進める中で情報が集約され入力の手間、情報整理の手間が省かれ、契約業務の効率が大幅に向上します。
また、契約書の管理に特化した契約管理システムも、契約書の作成や更新機能、アクセス制限機能などが備わっており、安全な契約管理に有効です。
システムごとに備わっている機能や操作性は異なるため、利用の際は目的や自社が抱える課題を明確にしたうえで選定しましょう。
契約書を電子化、管理するなら「ContractS CLM」
ContractS CLMは、契約書作成、押印承認、審査のやり取り、管理まで行うことができるシステムです。電子締結「ContractS SIGN」やそのほかの電子締結との連携も可能なため、契約書の管理を改善しながら集約管理によるプロセスの課題を解消することができます。
また、紙締結、電子締結と締結形式を問わず双方の契約書を格納でき、紙と電子の二重管理により業務の流れが複雑化してしまう課題も解消実績があります。
契約書管理では、自動反映の契約書管理台帳や全文検索、組織ごと、フォルダごと、契約書ごとといった細かな単位でアクセス制限も可能です。契約書の電子化と契約管理の両方を改善したい方はぜひ詳細をご覧ください。
まとめ
今回は契約書の保管期間について解説しました。
契約書などの重要書類については法律で保存期間が定められており、それぞれ期間が異なりますが、基本的には10年間保存しておくと理解しておけばいいでしょう。
契約書等を紙で保存する場合、常に紛失や流出といったリスクに備える必要があります。より契約業務を効率化し、リスクを軽減するためには、電子契約の導入がおすすめです。
『ContractS CLM』は、契約書の作成から管理、更新までの潮流、契約ライフサイクル管理(CLM)を実現し、契約関連業務全般を最適化する電子契約サービスです。契約書の電子化から契約管理まで、全プロセスを網羅的に解決し、契約DXを推進します。
ContractS CLM導入による費用対効果をシミュレータで算出できます。ぜひお試しください。