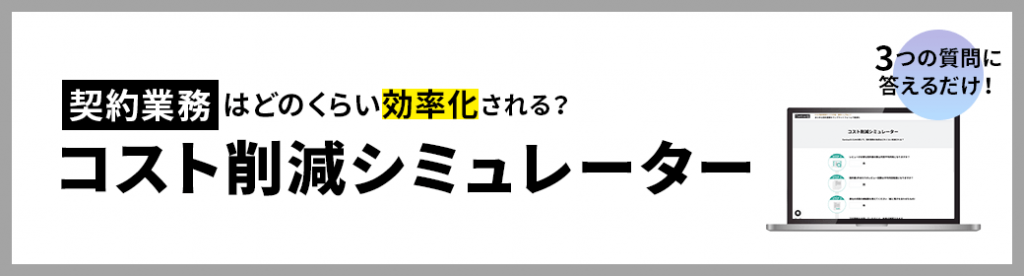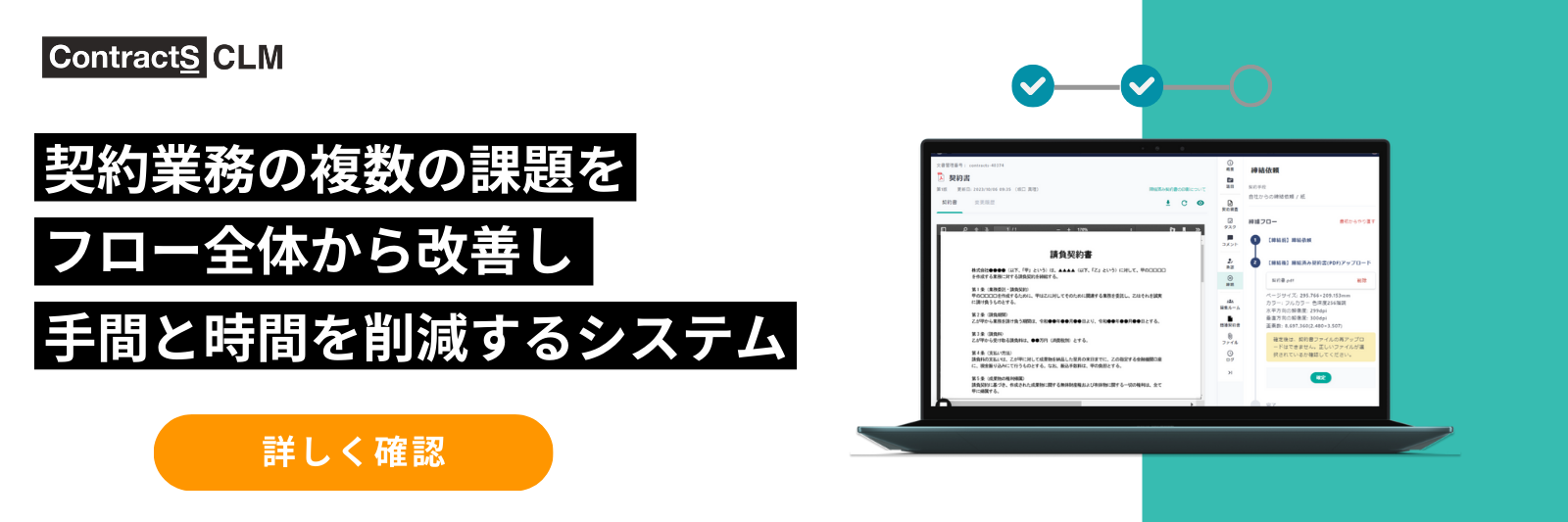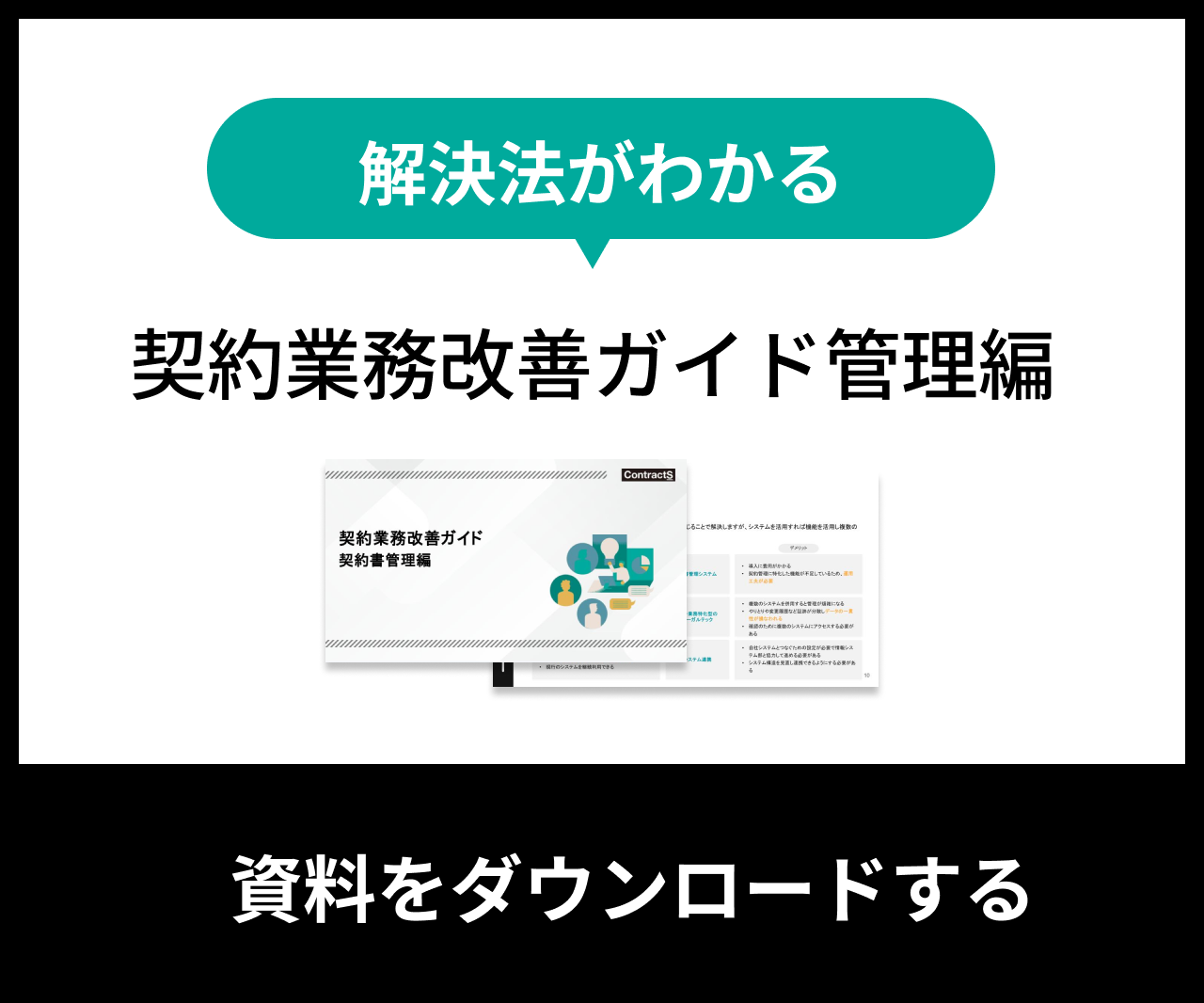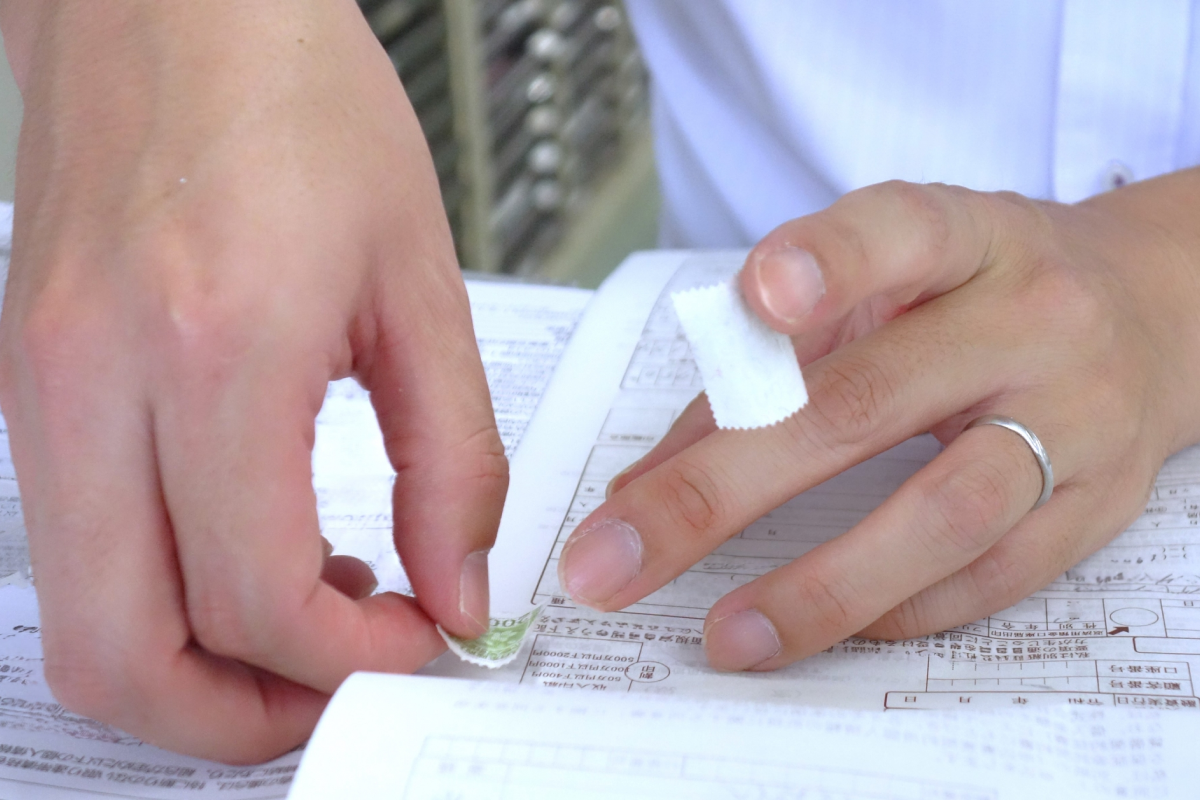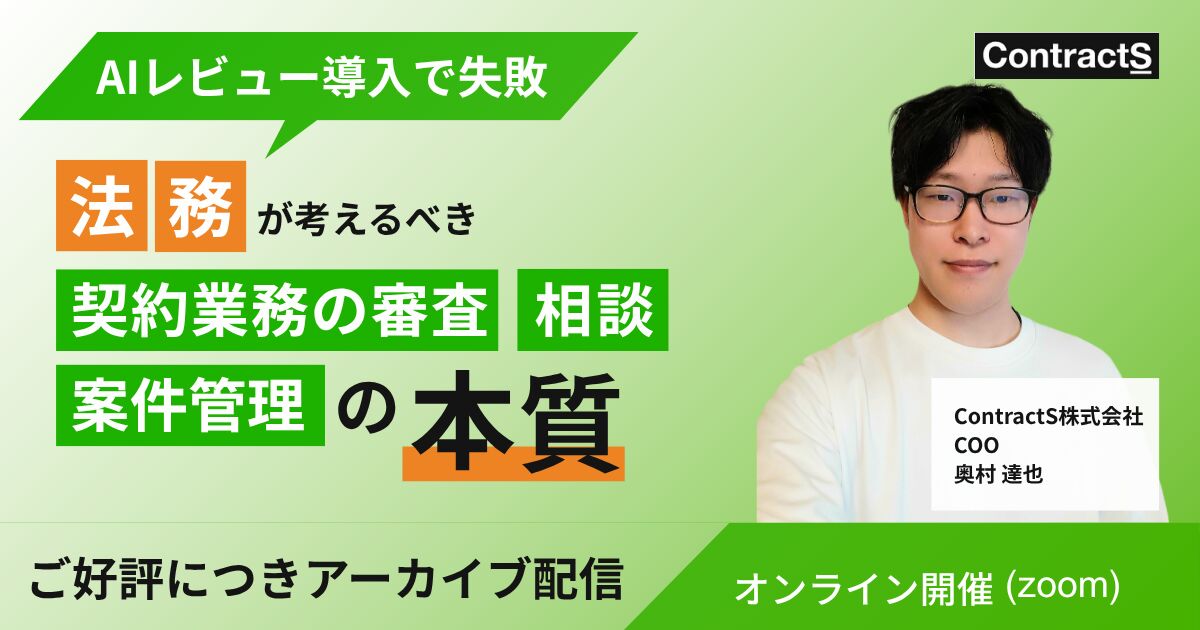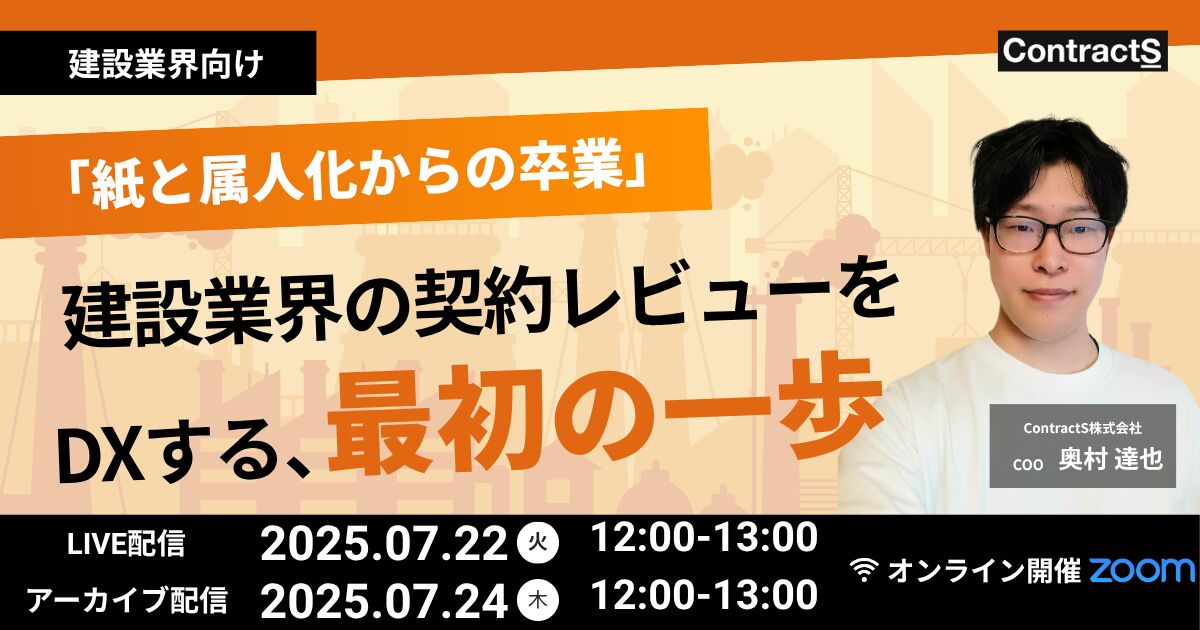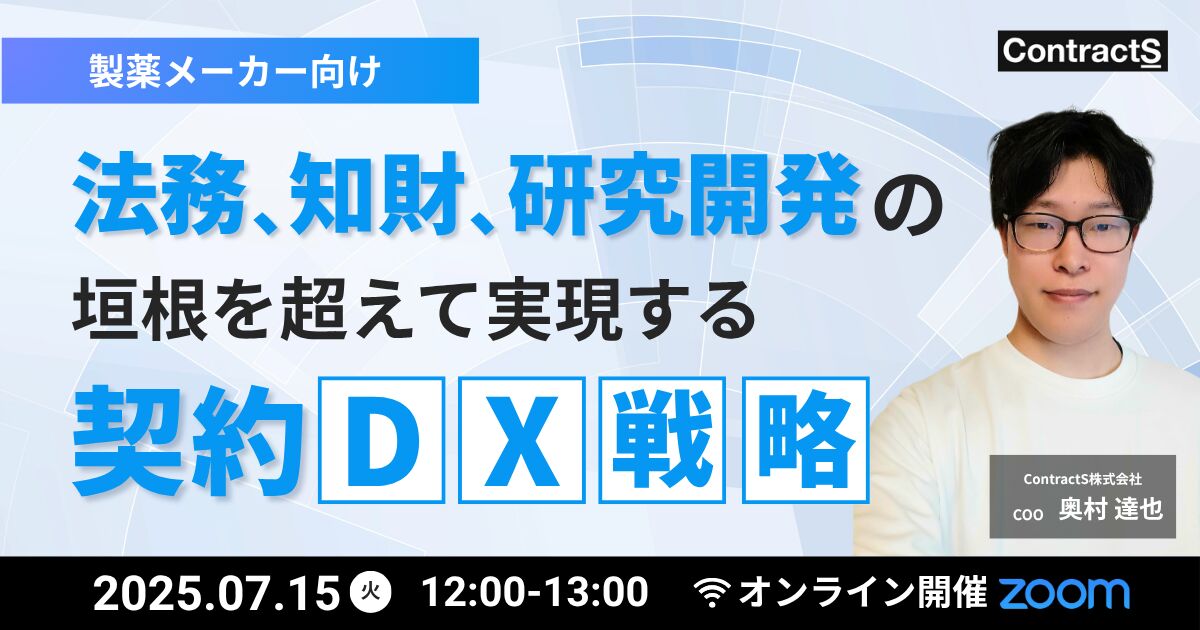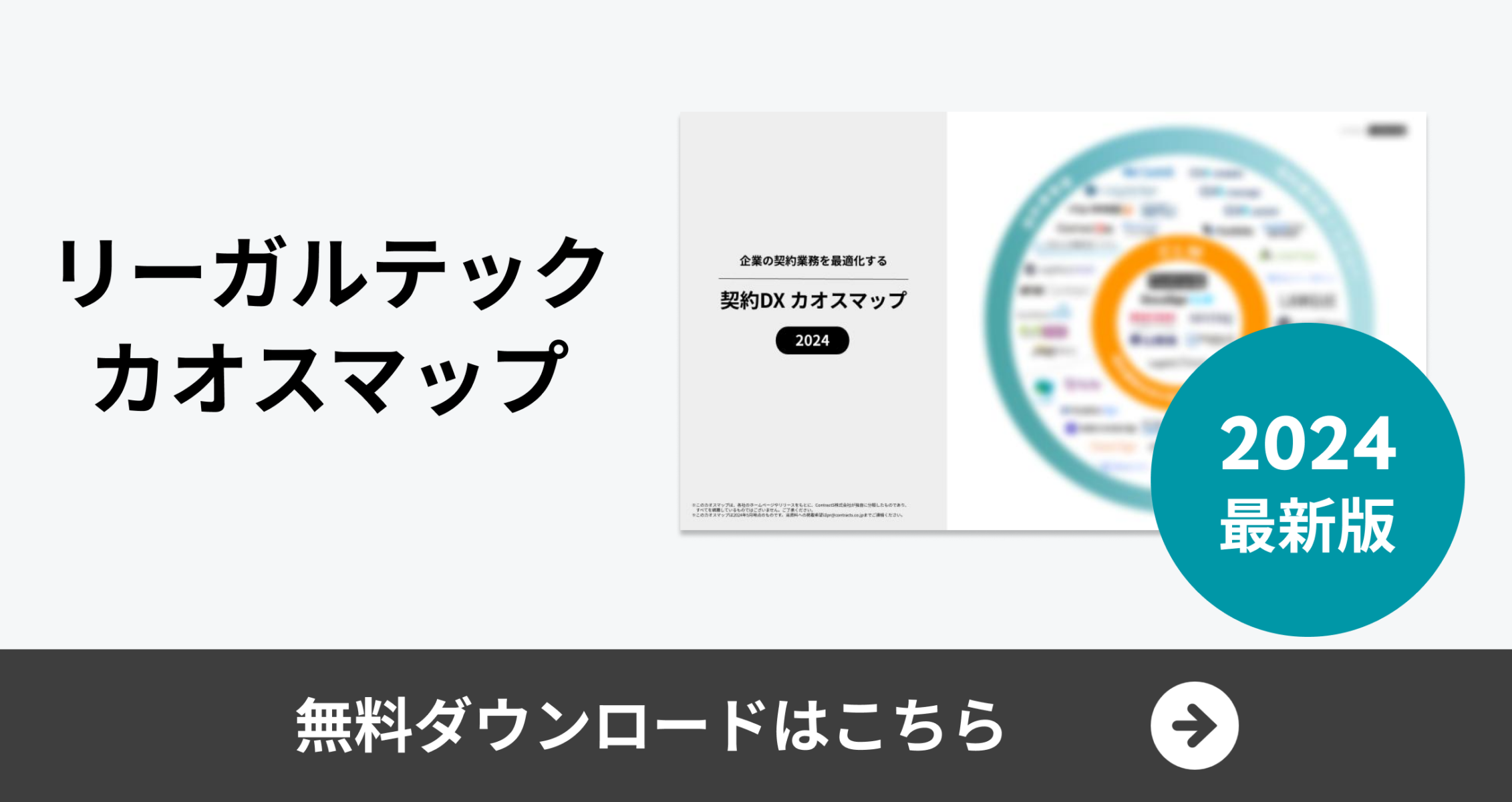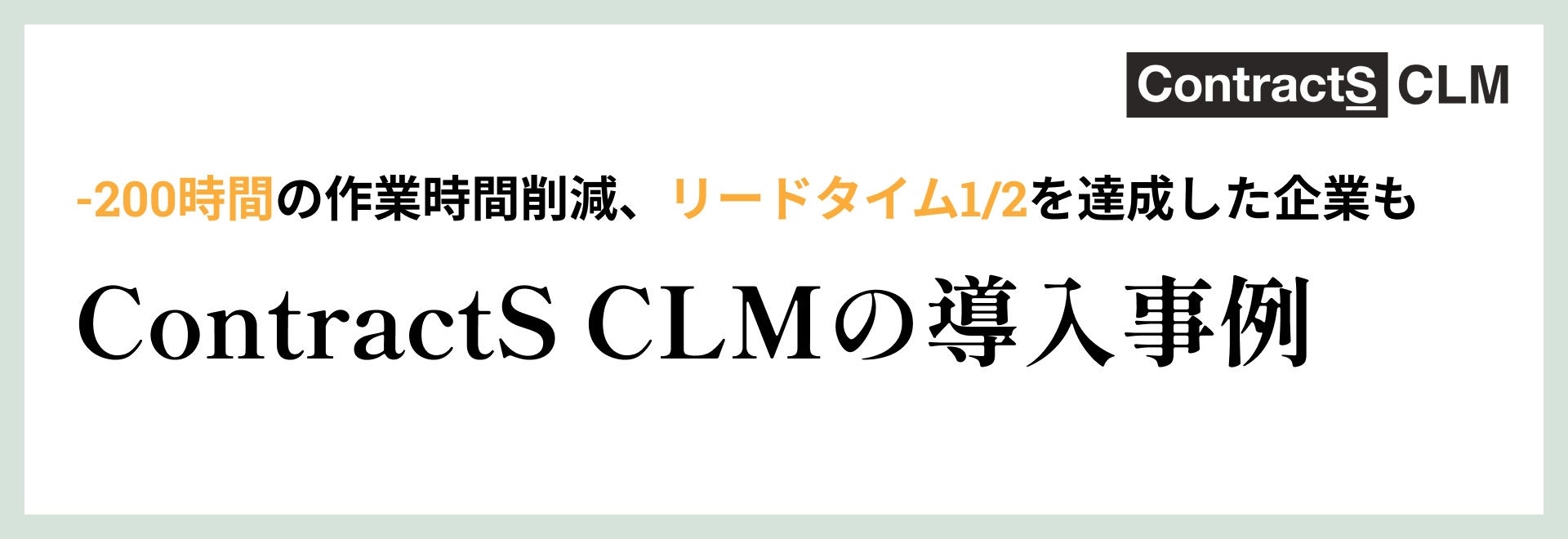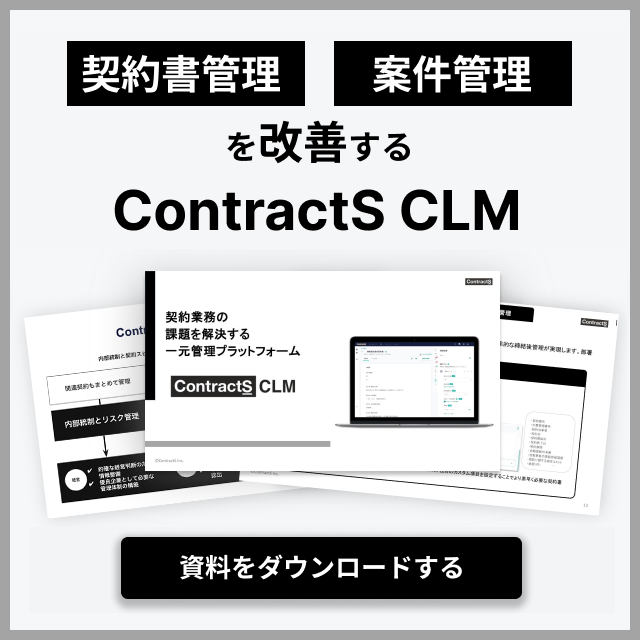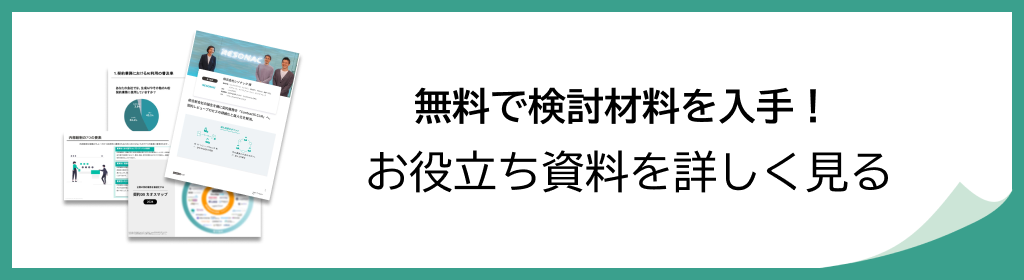ノウハウ 電子契約で印紙が不要な理由を分かりやすく。収入印紙の削減のほかにメリットはある?
更新日:2025年05月7日
投稿日:2023年08月29日
電子契約で印紙が不要な理由を分かりやすく。収入印紙の削減のほかにメリットはある?

ビジネスで取り扱う文書の中には、収入印紙を貼り付けなければならないものがあり、貼付忘れが発覚した場合、ペナルティが課されます。一方、デジタル形態の電子署名を使うことで、収入印紙の貼付は不要となります。
本記事では、収入印紙の節約を検討中の方へ向け、どのようなケースで収入印紙が不要となるのか、理由とあわせて紹介します。さらに、印紙税を減らせること以外の電子契約を活用するメリット、導入する前に知っておくべきことや注意点についても解説します。
印紙税、収入印紙とは
印紙税とは、契約書や領収書など、金銭のやりとりを伴うことを証明する文書を作成した場合に課される税金です。また、収入印紙は印紙税を納めるために文書に貼り付ける証票です。
印紙税法では、「課税文書」を作成したら、定められた税額の収入印紙の貼り付けが必要です。
例えば売買取引契約書や業務委託契約書など、継続的取引の基本となる契約書は7号文書に該当し、1通あたり4,000円の収入印紙を貼らなければなりません。
また、不動産売買契約書や工事請負契約書なども、それぞれ税額が定められています。課税文書の詳しい税額や非課税文書の条件については印紙税額で確認できます。
電子契約で収入印紙が不要な3つの理由
実は電子契約で収入印紙が不要なわけについては、法令上では積極的に根拠が記されておらず、法文の消極的な解釈や、国税庁の通達や総理国会答弁などにより、解釈上不要とみなされています。
非常に曖昧な運用ではありますが、実際に多くの企業がこの解釈に基づいて対応しています。
理由1.印紙税法と関係法令
そもそも印紙税とは、契約書や領収書に課される税金であって、一般的には収入印紙を購入・貼付することで税金を納付します。
ここで、印紙税の対象となる文書のことを課税文書といい、どんな文書が課税文書であるのかについては、印紙税法2条および別表第一に記されています(参照:e-gov法令検索)。
別表をみると「電子契約も課税文書」と書かれているわけではありませんが、「電子契約は課税文書ではない」と積極的に規定されているわけでもありません。
そこで、もう少し根拠を深堀りするために、印紙税法2条および3条に関する国税庁の通達をみてみましょう(参照:国税庁)。
ここでは、印紙税の納付義務者である「作成者」に関する規定が置かれており、間接的に、国税庁が課税文書をどのように想定しているかを知ることができます。
(作成等の意義)
第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)
(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時
(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時
(3) 一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時
(4) 認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時
(5) 第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時
この通達では、課税文書は「用紙等」に記載され、相手方に「交付」されることが前提となっています。
しかし、電子契約で作成された電子データは「用紙等」とは言い難く、またデータの送信行為を「交付」ということも解釈上限界があります。
このように、印紙税法および国税庁通達の記載からみて、「そもそも電子契約は課税文書として想定されていない」と解釈できます。
理由2.国税庁の通達
次に、国税庁がどのように考えているのか、国税庁による通達からみていきましょう。
本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものである。しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。
引用:事前照会者の求める見解となることの理由 -国税庁
国税庁によるこの回答では、「電子データにより注文請書を送信しても、やはり現物の”交付”がない以上、その電子データ自体は課税文書にあたらない」としています。
また、別の質疑応答では、この点につきより明確に回答しています。
問:借入人から貸付人に文書を交付する代わりに、ファクシミリ通信や電子メールを利用して送信する場合、印紙税の取扱いはどうなりますか。また、ファクシミリや電子メールで送信した後に、持参するなどの方法により改めて正本を交付する場合はどうなりますか。
答:請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
ただし、ファクシミリや電子メールで文例3から文例6までのような文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を貸付人に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。
引用:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い – 国税庁
二つの回答から、国税庁の見解として以下の二点をまとめることができます。
- 用紙等で作成され、交付された場合には課税文書となる文書であっても、電子的に送信された場合には「用紙等で作成され、交付された」とは言えないため、課税対象とはならない。
- ただし、電子的に送信されたのとは別に、用紙等の原本や正本を持参した場合「用紙等で作成され、交付された」といえるため、課税対象となる
理由3.国会での総理答弁
最後に、行政の長である内閣総理大臣が、参議院で質問に答えた際の回答を抜粋します。
事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
引用:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書 – 参議院
総理大臣は、電子データが非課税である理由として、電子データは文書と比較して改ざんが容易であり法的安定性を欠くからとしています。
しかし、電子帳簿保存法やe-文書法などによって、すでに他の法令上は電子データが紙の文書と同等に(あるいはそれ以上に)改ざんが難しく法的安定性をもつとされている以上、今後は印紙税法の改正もありえるかもしれません。
続いて、総理大臣は「課税の適正化及び公平化を図る観点等から何らかの対応が必要かどうか、文書課税たる印紙税の性格を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい」とも発言していますが、現在までに法改正等はありません。
電子契約を印刷した場合の取り扱い
電子契約を印刷した場合、その印刷した文書の利用方法によって取り扱いが変わるため、注意が必要です。
電子契約締結後に印刷した場合
この場合、すでに原本として電子契約が成立しており、その後印刷したものはあくまでコピーという扱いになります。
したがって、印刷した文書は非課税となります。
印刷したもので契約した場合
電子契約データを相手方に送信した場合であっても、正式な契約の締結が、紙に印刷した契約書で行われた場合は、その紙の書面が「原本」となります。
この場合、印刷された紙の契約書が原本ということになるため、課税文書となります。
電子の領収書の場合
メールなどで受け取った領収書を社内で確認や保管のために印刷するといった場合、印刷した領収書への収入印紙は不要です。金銭のやりとりを証明するためにコピーしたものではないためです。
注文請書の場合
電子化しメールなどで送信する注文請書への収入印紙は不要です。ただし、印刷したものを相手に送付するケースでは、印刷した注文請書に収入印紙を貼り付けなければなりません。
電子契約検討時に知っておきたいこと
電子契約を検討するにあたり、なりすましや電子データの改ざんを懸念する方は多いです。
こうしたリスクを軽減するために、「電子署名」「電子証明書」「タイムスタンプ」に対応したシステムが選ばれています。
電子署名とは
電子署名とは、電子化された文書にシステム上で入力し、署名者本人が文書に同意したことや、データが改ざんされていないことを証明する仕組みです。手書きの署名や押印と同様の働きをします。
電子証明書とは
電子証明書とは、電子署名したのが確かに本人であることを証明するものです。認証局が本人であることを担保し、付与します。紙の文書における印鑑証明書のような役割を担います。
タイムスタンプとは
タイムスタンプとは、付与された時点で電子データが存在していて、付与して以降、改ざんされていないことを証明する技術です。オリジナルのデータとタイムスタンプの付与されたデータの比較によって、データの改ざんが確かにないことを簡単に確認することができます。
電子契約できない文書
電子契約は多くのビジネスシーンで活用されていますが、全ての契約や書類が電子化できるわけではありません。法律や制度上の制約により、依然として紙でのやり取りが必要なケースもあります。ここでは、電子契約に対応できない主なケースを解説します。
法律により公正証書が必要な契約
一部の契約については、法令により「公正証書」の形式での締結が義務づけられています。公正証書とは、公証人が関与して作成する公的な文書であり、その信頼性や強制力の高さから、電子契約では代替できません。
代表的な例として、以下のような契約があります
- 事業用定期借地契約
- 企業担保権の設定・変更に関する契約
- 任意後見契約
これらの契約では、法的効力を持たせるために書面による公正証書の作成が必要であり、電子化は認められていません。
スキャナ保存が認められない書類
電子帳簿保存法では、帳簿などの電子保存が認められていますが、保存方法には「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3区分があり、それぞれに条件があります。
例えば、以下のようなケースではスキャナ保存は認められていません。
- 一度紙に出力した帳簿や書類に手書きで修正や加筆を加えたもの
- 紙で作成した書類を、保存要件を満たさない方法でスキャンしたもの
これらの書類は、たとえ電子化して保存したとしても、法的には正式な保存と見なされず、原本(紙)のまま保存しなければならないとされています。
また、スキャナ保存には、一定の解像度や階調など、細かい運用ルールが求められます。これらの基準を満たせない場合には、紙での保存を継続する必要があります。
ただし、令和6年1月1日以降にスキャナ保存する書類については、スキャナで読み取った解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になりました。
電子契約を導入する3つのメリット
電子契約を導入すれば印紙税を節税できるというメリットがありますが、実は電子契約には他にも多くの利点があります。
メリット1.業務を効率化できる
紙ベースの契約書は、作成や送付、ファイル管理などの手間がかかり、管理の負担も大きくなりがちです。一方、電子契約の場合にはこれらのプロセスをデジタルで完結できるため、作業時間の短縮につながります。
また、大量の書類を扱う業務では人的リソースも多く必要になりますが、電子契約を使えば人為的なミスや誤送信のリスクも減らせます。
メリット2.リモートワークに対応できる
電子契約の導入は、リモートワークのニーズに対応します。物理的な場所や時間に縛られることなく、どこからでも締結できるため、働き方が多様化している現代のビジネス環境に適合します。
関係者の間で簡単に署名・承認できるため、書類の送受信にかかる時間やコストを削減できることから、労働生産性の向上と同時にワークライフバランスの改善にも寄与します。
メリット3.改ざんや紛失リスクを軽減できる
最後に、電子契約は改ざんや紛失のリスクの軽減にもつながります。先ほど紹介した国会答弁のころ(2005年)とは異なり、現在は紙の契約書よりも、むしろ電子契約のほうがセキュリティが強固であるとさえ言えます。
電子契約はクラウド上で安全に管理され、アクセス制限を設けることもできるため、物理的なダメージや紛失、不正な改ざんのリスクを最小限に抑えることができます。
また、バージョン管理により変更履歴を追跡できるため、契約に関する紛争が生じた場合も、事実関係を迅速かつ容易に確認できるのも大きな利点です。
▶関連記事:電子契約を行うメリット、デメリットは?導入検討のポイントを分かりやすく解説
電子契約を導入する際の4つの注意点
電子契約の導入は業務効率化やコスト削減に大いに寄与しますが、システムを選定・運用する際には、法令遵守や保存方法の適正な管理が不可欠です。以下では、導入時に特に注意すべき4つの観点について解説します。
注意点1.自社のニーズに合ったサービスを選ぶ
電子契約サービスの導入にあたっては、自社のビジネス要件や目的に最適なソリューションを選択することが重要です。
例えば大量の契約を処理する必要がある場合には、一括で契約を管理でき、リマインダー機能が備わったサービスが適しています。契約書の内容を柔軟にカスタマイズしたい場合や、テンプレートを多様に使い分けたい場合は、カスタマイズ性の高いサービスを選ぶのが良いでしょう。。
また、使いやすいインターフェースをもつものや、適切なカスタマーサポートを提供するものを選ぶことも重要です。
注意点2.電子帳簿保存法など法令に則したものを選ぶ
電子帳簿保存法やその他の関連法令に対応したサービスを選ぶこともポイントです。
この法律は、税務上の重要書類を電子データで保存する場合のルールを定めたもので、保存方法ごとに対象書類や満たすべき要件が異なります。
電子帳簿保存法における保存方法は大きく以下の3つに分類されます。
|
保存方法 |
内容 |
|
電子帳簿保存 |
帳簿や決算関係書類を電子的に作成し、そのまま電子データで保存する方法 |
|
スキャナ保存 |
紙で受け取った契約書や領収書などをスキャンして電子保存する方法 |
|
電子取引データ保存 |
電子メールやWebサービスなどで受け取った契約書・請求書などを電子データのまま保存する方法 |
電子帳簿保存法では以下のような書類の電子保存が認められています。
|
書類のタイプ |
具体例 |
|
決算に関係する書類 |
貸借対照表、損益計算書、附属明細書、監査報告書など |
|
財務・税金に関する書類 |
会計帳簿、資産負債状況書類、財産目録、事業報告書、領収書、見積書、注文書、請求書など |
|
会社経営に関する書類 |
定款、株主総会議事録、取締役会議事録、組合員名簿など |
|
取引に関する書類 |
売買契約書、就業条件明示書、請負契約書など |
これらの書類は、作成方法や受領方法に応じて、適切な保存方法を選び、次のような保存要件を満たす必要があります。
|
保存要件 |
内容 |
|
解像度・階調 |
スキャナ保存の場合は、200dpi以上の解像度や一定の階調を備えた画像で保存し、データの正確性を確保する |
|
タイムスタンプ |
電子データにタイムスタンプを付与し、改ざんされていないことを証明する必要がある |
|
検索性・再現性 |
「取引日」「金額」「取引先」などで検索でき、原本に近い内容を再現できる状態で保存する |
|
閲覧性 |
税務調査時などにすぐ確認できる状態で保存されていることが求められる |
|
操作ログの記録 |
データの操作履歴を記録し、いつ誰がどのような操作をしたかが把握できるようにする |
これらの条件を満たさない場合、電子保存が認められず、従来通り紙での保存が義務づけられる可能性があります。
そのため、電子契約サービスや会計ソフトを選ぶ際には、電子帳簿保存法に対応しているかどうかを事前に確認することが重要です。さらに、法改正などに迅速に対応できる更新機能のあるシステムを選ぶことで、運用後も安心して活用し続けることができます。
注意点3.セキュリティの強固なものを選ぶ
セキュリティの強固なサービスを選ぶことも重要です。
契約文書は企業の重要な情報を含んでおり、これらの情報が第三者に漏洩した場合、企業の信頼やビジネスに大きな打撃を与えます。
信頼性の高いセキュリティ対策を施した電子契約サービスを選ぶことで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。データ暗号化、二要素認証、アクセス制限などの機能をもつサービスを選びましょう。
▶電子締結機能を持つ契約ライフサイクル管理システム
「ContractS CLM」のセキュリティについてはこちら
注意点4.電子締結した契約書を印刷しても原本にできない
電子契約で締結された契約書は、「電子データ」が法的な原本とされます。
たとえ内容が同一であっても、それを紙に印刷したものはあくまで「写し(コピー)」であり、正式な原本としては扱われません。
特に電子帳簿保存法では、電子取引に該当する契約書や請求書等の書類について、紙での保存は原則認められていません。法令上は、電子データのまま適切に保存することが義務付けられています。
実務上、社内の確認用に印刷するケースはあるかもしれませんが、それはあくまで補助的なもので、保存義務を果たすものではないことに注意が必要です。
つまり、「電子契約書を印刷すれば紙の原本が手元に残るから安心」と考えてしまうと、法令違反につながる恐れがあります。電子契約を使うなら、紙との違いを理解して、それに合った保存ルールを守ることが大事です。
電子契約システムの導入手順
以下の手順で電子契約システムを導入することで、契約業務の効率化やコスト削減などを実現することができます。
- 現状の契約業務フローを整理
- システムを導入する目的と必要な要件を明確にする
- 電子契約サービスの選定
- 社内や取引先に事前に周知する
- 電子契約サービスの導入
- マニュアル作成や研修の実施
- 本格運用と定期的な見直し
これらの手順をひとつひとつ詳しく解説します。
現状の業務フローを整理する
まず、現在の契約業務の流れを把握し、課題を明確にします。現在の契約手続きがどのように進行しているのかを確認し、誰が関与しているのかを整理します。また、締結後の契約書がどのように保管・管理されているのかを把握することも必要です。
さらに、契約業務における課題を明確にしておくと、適切な電子契約システムの選定につながります。例えば、契約の承認に時間がかかる、契約書の郵送や持参の負担が大きい、契約書を紛失することがある、あるいは契約の更新を忘れることが多いといった問題点が考えられます。
これらの課題をリストアップし、導入後にどのような改善をしたいかを明確にしておきましょう。
導入目的と必要な要件を明確にする
電子契約システムを導入する目的を明確にし、それに応じた必要な機能を整理します。導入の目的としては、ペーパーレス化によるコスト削減、契約締結の迅速化、契約管理の効率化、コンプライアンスの強化などが考えられます。
また、導入するシステムに求める機能についても検討が必要です。例えば、電子署名に対応しているか、契約ワークフローを自動化できるか、契約書を検索や更新通知の機能で効率的に管理できるかなどが選定ポイントの一つとなります。
理想を言えば、必要な機能をすべて備えたシステムが望ましいですが、機能が多くなるほどコストも上がる傾向にあります。そのため、予算とのバランスを見ながらシステム選びをしやすいように、「必須機能」と「あると望ましい機能」をあらかじめ整理しておくことがポイントです。
電子契約システムを選定する
適切な電子契約システムを選定するには、まずサービス事業者のホームページなどで情報を収集し、複数のシステムをリストアップすることから始めましょう。
提供されている機能、費用、導入事例などを比較することで、自社に合った候補を絞り込むことができます。
次に、必要に応じて資料請求や問い合わせを行い、より詳細な情報を入手します。
また、多くのサービスでは無料トライアルが提供されているため、実際に使ってみて、操作性を確認するのも効果的です。
選定にあたっては、次のようなポイントを慎重に検討しましょう。
- システムの機能が自社の業務に適しているか
- 操作がわかりやすく、社内に浸透しやすいか
- セキュリティ対策が十分に講じられているか
- 法的要件(電子帳簿保存法など)に対応しているか
- 費用が予算内に収まるか
こうした点を総合的に確認することで、導入後のトラブルを防ぎ、長期的に活用できるシステムを選ぶことができます。
社内や取引先に事前周知する
電子契約システムを導入する際には、社内や取引先に事前に周知を行うことが不可欠です。周知が不十分なまま導入を進めると、社内の混乱を招いたり、取引先に不信感を持たれる可能性があります。
まず社内向けには、電子契約の導入目的やメリットを丁寧に説明し、どの契約を電子化するのか、従来の紙の契約書はどのように扱うのかを明確にします。また、システムの利用方法や申請フローについても事前に説明し、スムーズに進められるようにしましょう。
取引先に対しては、電子契約を導入することを事前に案内し、操作に不安を持つ企業に対してはサポート体制を整える必要があります。また、従来の紙の契約書を希望する取引先がある場合の対応方針も決めておきましょう。
電子契約サービスを導入する
社内や取引先への周知が完了したら、いよいよ電子契約サービスの導入を進めます。
導入にあたっては、事前に移行スケジュールを立て、段階的に進めることがポイントです。まずは一部の契約に限定して電子契約を試験的に導入し、運用上の課題や不明点を洗い出す試験運用から始めると、全社導入もスムーズに進みやすくなります。
導入後は、社内や取引先の反応を確認しながら、出てきた疑問や懸念に丁寧に対応して運用を安定させていくことが重要です。
また、システム提供ベンダーによるサポートも積極的に活用し、設定方法や使い方を確認しながら、着実に導入を進めましょう。
マニュアル作成や社内研修を実施する
電子契約システムを導入しても、従来の契約方法に慣れている方は操作に戸惑う可能性があります。そのため、利用方法をまとめたマニュアルを作成し、社内研修を実施することが重要です。
マニュアルには、システムの基本的な操作方法、電子契約の申請フロー、トラブル時の対応策などを含めます。社内研修では、その場で一緒に操作を行い、研修の時間内で安心感が少しでも得られるようにサポートしましょう。
本格運用と定期的な見直し
システムを本格運用した後も、定期的に運用状況を見直し、改善を続けることが大切です。導入による効果を測定し、業務スピードの向上やコスト削減の効果などを確認します。また、システムを利用する従業員や取引先からのフィードバックを収集し、使い勝手の向上や追加機能の検討を行いましょう。
さらに、電子契約に関連する法規制は変更される可能性があるため、最新の法改正に対応できているか定期的にチェックすることも重要です。
電子契約でコストを削減した事例
多くの企業が最近、電子契約の導入を進め、業務効率化やコスト削減を実現しています。以下では、実際に電子契約を導入した2つの企業の事例を紹介します。これらの事例から、電子契約がどのようにコスト削減に寄与し、業務プロセスの改善に役立ったか見てみましょう。
契約業務の一元化でコスト削減に成功した事例

株式会社ツインバードは、各部署が個別に契約書を管理する体制の中、全社的な契約状況の把握が困難であること、契約書の作成や承認、締結に関する依頼方法が統一されておらず、対応に時間がかかることなどの改善のため契約業務を一元管理し、契約フローを効率化することを目的に、CLMシステム「ContractS CLM」で業務改善を行っています。
システム導入後は、紙・電子を問わずすべての契約を一元的に管理できるようになり、当初の課題が改善されています。契約の進捗状況はリアルタイムで把握できるようになり、業務の属人化が解消。ルールの統一や情報の自動蓄積により、誰でも必要な契約情報にアクセスできる体制が整いました。
契約書の検索性が高まり、法務部門への問い合わせが減少。電子契約の推進により、月間約50万円のコスト削減を達成しています。
続きを読む>>各部署で行っていた契約書管理を一元化。管理体制の強化とコスト削減を実現!
クラウド移行で業務効率とコストを両立した事例

株式会社キユーソー流通システムは、捺印・押印の申請や承認フローの複雑さ改善で、さらに進んだ業務効率化を目指し業務改善を行っています。
導入後は、契約の進捗状況が可視化され、業務の効率化を実感。また、電子契約の活用により、印紙代や郵送代といった紙の契約書にかかるコストも削減されました。さらに、契約プロセスの全社的な見直しとルールの再周知が進んだことで、リスクマネジメントの強化にもつながっています。
詳しく見る>>全国拠点の契約を「ContractS CLM」へ集約。 物流ビジネスのリスクを防ぐ法務のインフラに