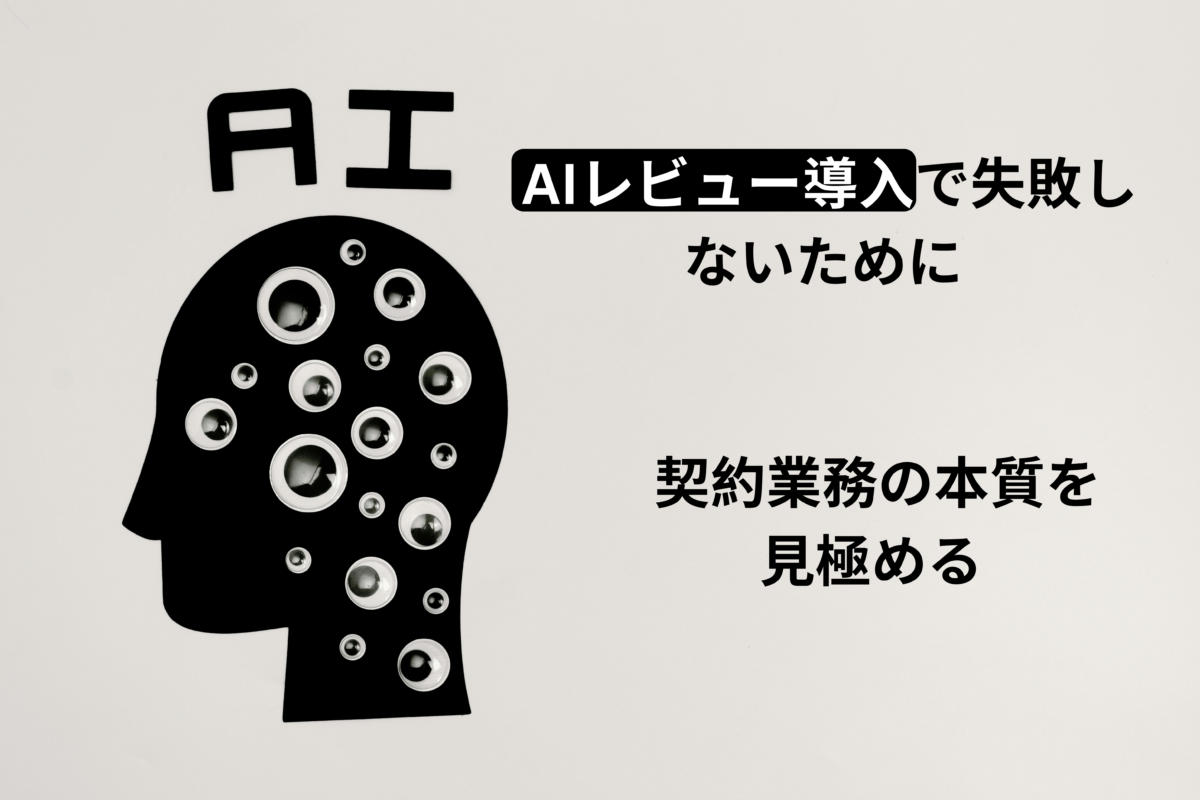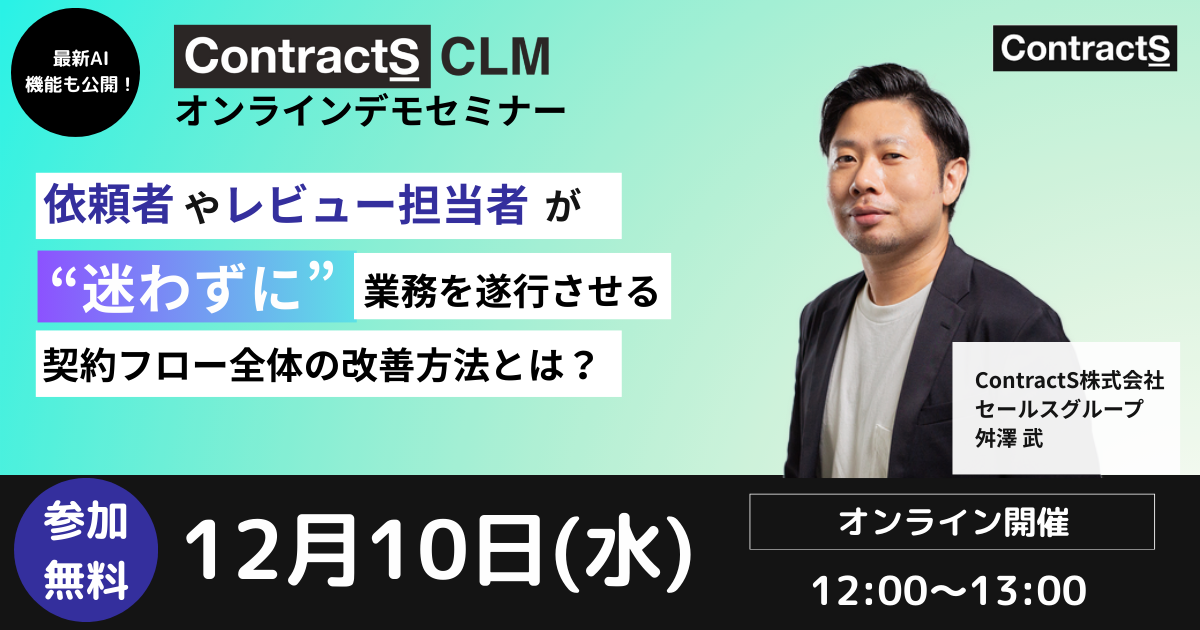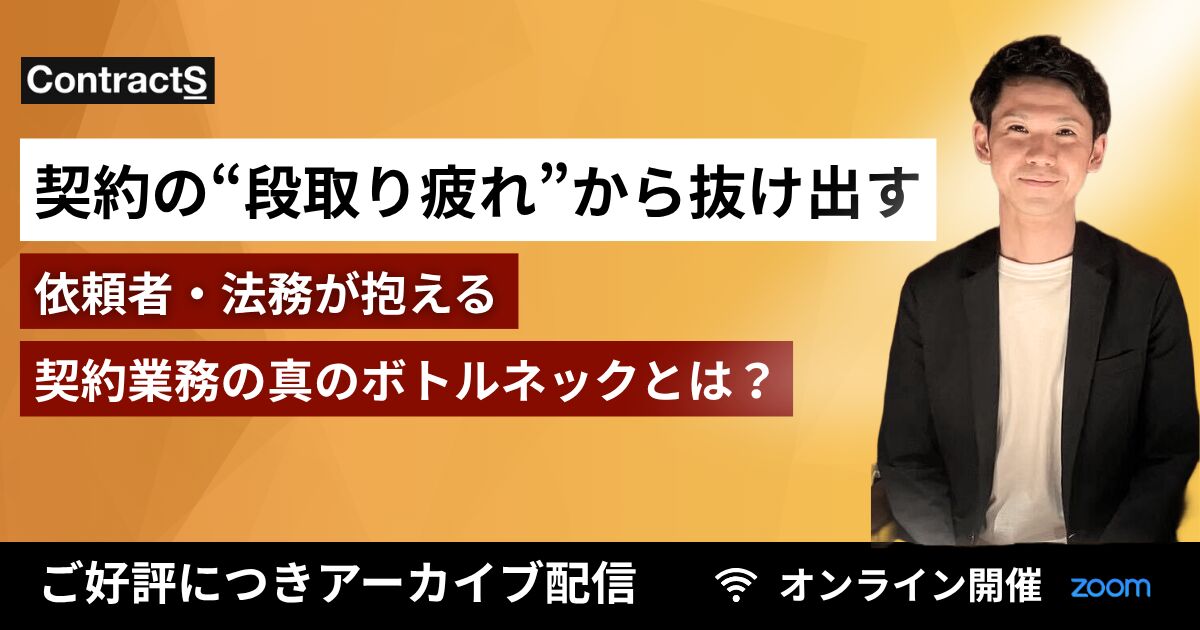ノウハウ 注文書や発注書を電子化する方法とメリットを解説(電子帳簿保存法対応)
更新日:2025年03月6日
投稿日:2023年08月15日
注文書や発注書を電子化する方法とメリットを解説(電子帳簿保存法対応)

「注文書や発注書を電子化したいけど、ノウハウがない」
「電子帳簿保存法の要件はどうなっている?」
注文書および発注書の電子化を検討している方で、このようにお悩みの方はいませんか?
これらの書類を電子化することで、法令への適合および業務効率化・コスト削減を実現できます。そこで今回は、注文書・発注書を電子化するメリットとデメリット、具体的なステップについて解説します。
発注書は電子化できる?
発注書とは商品やサービスの発注時に作成する書類のことで、「注文書」とも呼ばれています。
物品の製造委託や情報成果物作成の委託など、下請法の適用対象となる取引では、発注者側の発注書の作成が義務付けられています。
下請法の適用外の取引なら発注書を作成する義務はありませんが、基本的には作成しておくことをおすすめします。
発注書には、発注者・受注者の認識を合わせてトラブルを未然に防ぐという役割があるからです。
従来の発注書は紙媒体での作成・保存が主流でしたが、電子帳簿保存法の改正により、電子化のうえ保存することも可能になりました。
なお、電子データで発注書を受け取った受注者は、電子データのまま保存することが義務付けられています。
▼【最新版】電子帳簿保存法改正をまとめておさらいできる!
資料ダウンロードはこちら
電子保存しなくてもいい場合もある
ここまで紹介したように、電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引により送受信される納品書は、電子データとして保存する必要があります。
一方で、改正後も紙ベースで取り引きされた納品書は、引き続き紙の形で保存可能です。しかしこの場合、電子データによる保存と紙による保存とが併存することになり、管理方法が複雑化するため、税務調査などで必要な情報を見つけるのが難しくなる可能性があります。
現代のビジネス環境では電子取引を完全に排除することは難しいため、自社では電子的に納品書を作成し、他社から紙ベースで納品書を受け取った場合にはスキャンして電子的に保存することをおすすめします。
このように全ての納品書を電子化し一元的に管理することで、管理の効率化と情報の検索性を高めることが可能になります。
発注書を電子化する3つの方法
発注書を電子化する方法は複数あり、それぞれ適したシーンや利便性が異なります。
以下より、発注書を電子化する主な方法を3通りご紹介します。
紙の発注書をスキャンする
発注書をスキャナでPDFなどの電子データに変換し、保存する方法です。
発注者から受け取った紙の発注書や、自社が作成した紙の発注書の控えを電子データで保存したいときに適しています。
その都度スキャンする手間はかかりますが、紙での発注書作成・発行が主流の環境でも、省スペース化やオフィスの外からのアクセスが可能といったメリットを得られます。
逆に、電子データで受け取った発注書を印刷し、紙で保存することは認められていないため注意しましょう。
スキャナ保存の要件
紙の発注書をスキャナ保存するにあたって、電子帳簿保存法で定められた以下の要件を満たす必要があります。
発注書をスキャナ保存する際は、要件を満たす保存方法が可能な環境の整備も伴うことを念頭に置き、導入を検討しましょう。
電子データの発注書を作成する
自社が発注者側の場合、WordやExcelなどの書類作成ソフトを利用して電子データの発注書を作成するという方法があります。
日頃の業務で使用しているソフトを使った方法なら取り入れやすい他、カスタマイズ性が高いため取引先や商品ごとに最適な内容へ編集できる点もメリットです。
ただし、発注書の数が多いと管理が煩雑化しやすいことに加え、データの改ざんが比較的簡単なため対策に工夫が必要というデメリットもあります。
発注書の作成機能があるサービスを利用する
電子契約サービスや文書管理サービスなど、各種書類のテンプレート機能を備えたサービスで電子データの発注書を作成する方法です。
上記のサービスはタイプスタンプ付与・電子署名機能、閲覧制限機能などが備わっていることが多く、改ざんを防止しながら保存要件を満たした形式での電子化が可能になります。
さらに電子契約システムを搭載しているサービスなら、作成から相手側への送付まで簡単に行えるため、業務効率化にもつながります。
発注書の電子化が進んでいる理由
近年は、発注書を含む各種書類の電子化を導入する企業が増加しています。
国内で書類の電子化が進んでいる背景には、以下のような事情があります。
電子帳簿保存法の改正
以前の電子帳簿保存法では、対象書類を電子保存する場合は税務署への事前申請が必要な他、より厳しい制約を伴う保存要件が設けられていました。
しかし、2022年1月の改正による「事前申請制度の廃止」と「保存要件の緩和」で、電子化の導入ハードルが下がりました。
さらに、電子データの文書を紙で保存する措置が廃止されたことも、電子化導入へ踏み出すきっかけになり得るポイントです。
新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルスの影響によりテレワークを導入する企業が増えたことも、書類の電子化が進んだ要因のひとつです。
労働政策研究・研修機構は、「新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響に関する調査」を実施し、その結果を公表しています。
資料によると、新型コロナウイルスの流行前は多くの企業で取り組まれていなかったテレワークが、流行後の2020年4月~5月にかけて実施率がおよそ3倍にまで拡大していることが分かっています。
さらに、調査に回答した企業全体のうち、約67%は「デジタル化に関する取り組み」を実施していると回答しています。
その中の3割近くは、デジタル化の取り組み内容について「ペーパーレス化」と答えました。
また、同調査の「ポストコロナにおいて推進されると考える事項」に関しては、全体の6割を超える企業が「ペーパーレス化」を回答しています。
実施の有無にかかわらず、書類のペーパーレス化(電子化)は新型コロナウイルスの流行を機に、その重要性に注目が集まったと分かる結果となりました。
注文書・発注書を電子化する8つのメリット
注文書を電子化すると、いろいろなメリットが得られます。以下ではその中でも特に大きなメリットを5つ紹介します。
メリット1.電子帳簿保存法への対応
まず一つ目のメリットは、電子帳簿保存法への対応です。
先ほど紹介したように、電子帳簿保存法の改正により、全ての事業者は電子データとしてやりとりした注文書や発注書を電子データのまま保存する必要があります。
改正法の完全施行までの宥恕期間(猶予期間)は2023年末までとなっているため、2024年1月1日以降はすべての事業者がデータ保存に対応しなければなりません。
改正以降も紙でやりとりした注文書等は紙のまま保管することも可能ですが、そうすると過去の注文書等の保管方法が紙・電子データの2パターン生じることとなり、管理が煩雑になってしまいます。そのため、あらゆる取引関係書類をすべて電子化し、一元的な管理へ移行する企業が増えているのです。
電子帳簿保存法に従わない場合には、推計課税・追徴課税、青色申告の取消し、100万円以下の罰金を課される可能性があるため、早急な対応が必要です。
メリット2.印紙税が不要なためコスト削減になる
二つ目のメリットはコスト削減です。
注文書・発注書を電子化することで、紙やインク、印刷、保管スペースなどのコストを大幅に削減することが可能です。注文プロセスも高速化し、作業時間も大幅に短縮されます。
電子化によりコストを削減できるのは、電子データであれば物理的な資源を必要としないからです。
例えば、紙やインクを購入したり、印刷したりする必要がなくなります。また、保管スペースも必要としないので、オフィスのスペースを有効に活用することができます。
その結果、コストを大幅に削減し、それを他の重要な業務に投資することができます。
▶なぜ電子契約では印紙が不要なのか?理由と根拠を分かりやすく解説
メリット3.データの正確性と追跡性の向上
三つ目のメリットは、データの正確性と追跡可能性の向上です。
注文書・発注書を電子化することで、データの整合性と一貫性が保たれ、エラーが大幅に減少するため、注文の追跡と監査が容易になります。
例えば、手書きの注文書では読み取りミスや書き間違いなどが起こり得ますが、電子化することでこれらのミスを避けることができます。また進捗状況が自動で表示されるため、注文の追跡も簡単になり、いつどのような注文があったのかを一目で把握することが可能になります。
メリット4.環境負荷の軽減
四つ目のメリットは、環境負荷の軽減です。
紙を作るためには大量の木材が必要であり、廃棄により空気中の二酸化炭素増加をもたらしますが、紙の使用量が減れば、その生産と廃棄に伴う環境への負荷を同時に軽減できます。
日本国民全員がA4用紙1枚を節約すると、二酸化炭素の削減量は840トン(杉の木約6万本が1年間に吸収できる量)にも及ぶとの試算もあります(参照:その資料は本当に必要?ペーパーレス化のもう一つの環境メリット!- Operation Green)。SDGs(持続可能な開発目標)で掲げられた17の目標のうち、ペーパーレス化は8番(働きがいも経済成長も)と12番(つくる責任つかう責任)に該当するものです。
メリット5.リアルタイムな注文管理
納品書を電子データとして保存し管理することで、注文の詳細やステータスをすぐに把握できるようになります。
具体的には、製品の出荷状況、在庫状況、配送スケジュールなどの情報にいつでもアクセスすることが可能です。
これにより、企業はより迅速かつ効率的に業務を進めることが可能となり、顧客に対するレスポンスも速やかになります。また、問題が発生した際にも、リアルタイムの情報に基づいて即座に対応できるため、業務運営のスムーズさを保つことができます。
メリット6.業務効率化
発注書の作成・保管業務を紙ベースで行うと、データ入力・印刷・ファイリングなどの作業が発生します。
管理する発注書の枚数が多いほど、その作業に充てざるを得ない時間は増えていきます。
さらに、過去の発注書を確認する場合は、ファイルをひとつひとつ開いて探す手間も生じます。
発注書の電子化を進めれば、必要事項の入力だけで作成でき、書類探しの際は検索機能を使って簡単にデータを引き出すことが可能です。
これにより、作業時間が大幅に短縮され、業務効率化につながります。
メリット7.リモートワークへ対応できる
近年は新型コロナウイルスの影響だけでなく、「働き方改革」という観点でもリモートワーク対応の重要性が高まっています。
紙の発注書を用いる場合、テレワーク中でも作成や送付のたびに出社が必要です。
一方で、クラウド型サービスによる電子化を導入すれば、自宅にいても適切な発注書の作成と送付ができるようになります。
データはクラウド上に保存されるため、オフィスにいなくても円滑な書類管理を実現できます。
メリット8.紛失・機密漏洩等リスク管理に有効
紙の発注書を保管する場合のデメリットとして、紛失・盗難のリスクもあります。
発注書を電子化すれば物理的な紛失のリスクが低く、アクセス制限により不正な閲覧・持ち出しも防止することが可能です。
書類にまつわるセキュリティリスク管理を強化したい場合にも、電子化の推進は有効な取り組みといえます。
発注書の保存期間
紙・電子データのどちらでも、法律で定められた期間は発注書を保存しておく必要があります。
発注書は取引の事実を証明する証憑書類であり、会社法や税法にて以下の通り保存期間が定められています。
|
対象者 |
保存期間 |
法律 |
|
法人 |
7年 |
税法 |
|
10年 ※青色申告の事業年度に欠損金が出た場合、青色申告書を提出しなかった事業年度に最大損失欠損金が生じた場合 |
会社法 |
|
|
個人事業主 |
7年 |
所得税法 |
発注書などを法律上の期間中に保存していないと、追徴課税を求められるリスクが高まります。
求められたらすぐに取り出せるように、検索性を確保のうえ保存しておくことが大切です。
注文書・発注書を電子化する際に知っておきたい6つの注意点
ここまでは、注文書や発注書を電子化するメリットを紹介しました。しかし、注文書を電子化することにはデメリットもあります。
注意点1.初期費用とランニングコストが発生する
納品書を電子化するには、必要なハードウェアやソフトウェア・クラウドサービスの導入、それらを運用するためのITインフラの構築など、初期費用が発生します。
さらに、システムを維持・運用するためのランニングコストも必要です。これには、システムのメンテナンス、アップデート、トラブル対応などが含まれます。
これらの費用は、電子化を進める企業の負担となります。
しかし、これらの費用は初期投資と捉えることで、長期的に見れば納品書の電子化による経済的なメリットがこれらのコストを上回るでしょう。
注意点2.社内の業務フローの更新が必要
発注書の電子化は簡単に導入できるように思えて、無計画に実施すると現場の混乱を招くおそれがあります。
特に、IT技術に触れる機会が少ない現場では、電子保存やデータ作成がスムーズにできない可能性が考えられます。
そのため、自社の環境に応じて電子化導入後の業務フローを整えておく必要があります。
注意点3.抵抗感の克服とレクチャーが必要
次の注意点は、従業員の電子化への抵抗感を克服し、新しいシステムの操作を教える必要があるという点です。
特に、ITスキルが必要な作業に抵抗感を持つ従業員にとって、新しいシステムへの移行は大きなストレスとなりえます。
これに対する対策として、電子化のメリットを理解してもらい、抵抗感を解消するための啓もう活動が必要です。さらに、操作方法や業務の流れを理解してもらうための研修も重要となります。
注意点4.セキュリティリスクを伴う
納品書の電子化は、情報漏えいやハッキングといったセキュリティリスクを伴います。
納品書には、取引の詳細や顧客の個人情報など重要な情報が含まれているため、これらの情報が不適切にアクセスされたり、漏洩したりすることは、企業にとって大きなリスクとなります。そのため電子化する際には、高度なセキュリティ対策が必要です。適切な暗号化技術の利用やアクセス制御、セキュリティ更新の定期的な実施など、堅固なセキュリティ体制を整備することが求められます。
もっとも、紙の注文書には紛失や破損のリスクがあります。また、物理的なスペースを必要とするため、災害などによる被害を完全に防ぐことは困難です。
一方、電子化された注文書はクラウド上に保存されるため、そのようなリスクを大幅に減らすことが可能です。
クラウドサービスには専門的なセキュリティ対策が施されているものが多く、適切な選択をすればセキュリティ面でもメリットを享受できるでしょう。
注意点5.最新の法規制を確認する
電子帳簿保存法など、発注書の電子化に関わる法令は改正されることがあります。
現行の規制に沿わない方法で発注書データを保存すると、公的に取引関連の書類だと認められません。
電子化を導入した場合でも、関連法令の確認がその都度必要になります。
注意点6.取引先との調整が必要
電子の導入状況は企業によって異なり、自社で電子化を進めても取引先が対応できない可能性があります。
電子化を進める場合は、必ず取引先に電子化対応の可否を確認しましょう。
対応が難しい取引先は別途紙での発行を継続するなど、柔軟な対応も必要になります。
発注書の書き方・作り方
下請法では、適用対象の取引における発注書の記載内容について、以下の項目を定めています。
① 発注者・受注者の名称
② 委託をした日
③ 受注者が請け負った委託内容(商品やサービスなど)
④ 商品やサービスなどを受け取る期日
⑤ 商品やサービスなどを受け取る場所
⑥ 受け取ったものの検査を完了する期日(必要な場合)
⑦ 発注者が支払う代金の金額
⑧ 代金の支払期日
⑨ 手形の期日・満期(手形を交付する場合)
⑩ 金融機関名・貸付又は支払い可能額・支払期日(一括で決済する場合)
⑪ 電子記録債権の金額・満期日(電子記録債権で支払う場合)
⑫ 原材料の品名・数量・対価・引渡し期日・決済期日と方法(原材料を有償で支給する場合)
下請法が適用されない取引でも、基本的には上記の項目に沿って発注書を作成するとトラブルが起こりにくくなります。
発注書・送付メールの記載例
下請法に基づき発注書を作成する場合・メールで送付する場合の記載例を、以下よりご紹介します。
【発注書】
|
発注書 発注日 2025年2月1日
株式会社○○○○ 御中 ○○株式会社 下記の通り発注申し上げます。 合計金額 ¥ ○○○,○○○
小計 ¥ ○○○,○○○ 納品期限 2025年2月28日 備考 |
【送付メール本文】
|
株式会社○○○○ ○○担当 ○○ ○○様 いつもお世話になっております。 ○○株式会社の○○です。 先日は御見積書をご送付いただき、誠にありがとうございました。 ぜひ発注をお願いしたく、PDF形式にて発注書を添付させていただきます。 ご査収のほどよろしくお願いいたします。 【添付内容】 ○○発注書 1通 ご不明点や添付ファイルについてお困りごとがございましたらお知らせください。 何卒よろしくお願いいたします。 |
注文書・発注書を電子化する具体的なステップ
ここからは、電子化を進めるための具体的なステップを紹介します。
ステップ1.自社のニーズを明確にする
納品書の電子化を行うためには、まず自社が何を求めているのかを明確に理解することが重要です。
具体的には、どのような情報を保存する必要があり、その情報がどのように使われるのか、どの程度のセキュリティレベルが必要なのかなど、自社の要件を詳細に洗い出すことから始めましょう。
ステップ2.適切なサービスやソフトウェアを選択する
発注書を電子化できるシステム
発注書を電子化できるシステムとしては、以下のようなものがあります。
|
システム |
特徴 |
|
契約管理システム |
電子契約書の作成から送付まで行えるシステム。 改ざん防止機能やセキュリティ対策が充実している傾向にある。 契約件数に応じてコストがかかる。 |
|
文書管理システム |
業務で使用する文書全般を電子保存・作成できるシステム。 汎用的で導入しやすいが、管理する文書が多いと煩雑化する可能性がある。 |
|
WEB受発注システム |
商品の受発注や商品をWEB上で一括管理できるシステム。 発注業務の効率と精度の向上に有効だが、管理や設定が複雑な場合がある。 |
それぞれのメリット・デメリットを理解のうえ、現場の状況を考慮して最適なシステムを選びましょう。
ステップ3.ワークフローを設計する
選んだサービス・ソフトウェアの仕様を加味して、新しいワークフローの設計やルールの見直しを行います。
一度サービス・ソフトウェアをテスト運用し、その中で必要と思われたものや削減しても良い工程などを、新しいワークフローに反映させましょう。
ステップ4.導入と教育を行う
適切なサービスとソフトウェアを選んだら、次に導入と教育を行います。
システムの導入は、専門的な知識が必要な場合もありますので、必要に応じてIT部門に相談しながら進めることも考えましょう。
また、新しいシステムをスムーズに利用するためには、従業員への教育も重要です。操作方法だけでなく、なぜ電子化が必要なのか、どのようなメリットがあるのかを理解してもらうことで、抵抗感を軽減し、積極的に取り組んでもらうことができます。
ステップ5.スキャンしてデータ化する
紙で保管していた発注書をスキャンして、電子データに変換します。
発注書をスキャンする主な方法としては、以下の3つが挙げられます。
・オフィスの複合機を使う
・専用のスキャナーを使う
・スマートフォンで撮影する
大量の書類をスキャンするなら複合機、複合機のスキャン機能では対応できない原稿がある場合はスキャナーの使用がおすすめです。
手軽さを重視するならスマートフォンでスキャン専用アプリを使うという方法もありますが、電子帳簿保存法の要件に沿う形式で保存できるかどうかを確認しておきましょう。
まとめ
注文書の電子化は、時間とコストの削減、データの正確性と追跡可能性の向上、環境負荷の軽減など、多くのメリットをもたらします。
しかし、初期費用やランニングコスト、従業員教育、セキュリティリスクなど、デメリットも存在します。そのため、自社のニーズに合わせて適切なサービスを選び、その導入と運用を計画的に行うことが重要です。