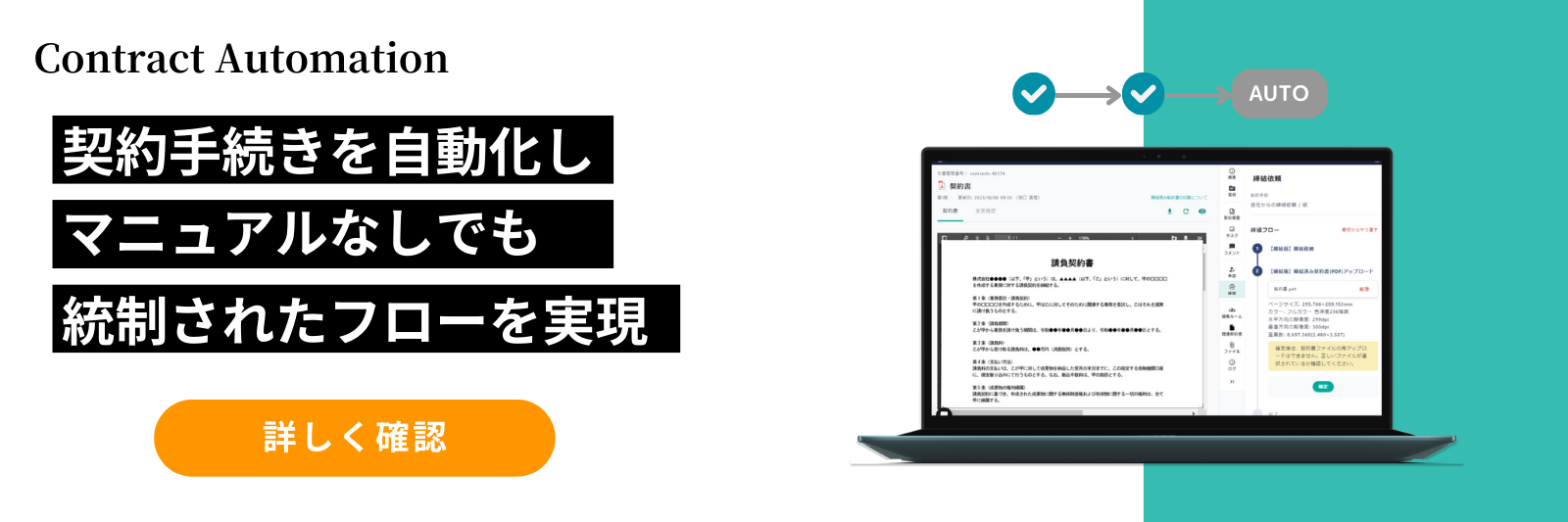ノウハウ ガバナンス強化とは?強固にするメリット・方法と事例
更新日:2025年03月27日
投稿日:2023年06月26日
ガバナンス強化とは?強固にするメリット・方法と事例

ガバナンス強化は、企業の透明性のある経営と持続的な成長に欠かせません。
企業価値を高めるだけではなく、労働環境の改善など従業員にもメリットをもたらします。
本記事では、どのようにガバナンスを強化するための方法とポイントを解説します。ガバナンス強化の具体例も紹介しています。
ガバナンスとは
英語でgovernanceと綴り、「統治、管理、支配」といった意味を持ちます。
ビジネスでは「企業の管理体制」というニュアンスで用います。
ガバナンス強化とは
ガバナンス強化とは、透明性のある企業経営によって企業価値を高め、成長を続ける組織であるための取り組みです。
情報漏えいや粉飾決算などの企業の不祥事が相次いだことを受け、健全な経営のための体制を築く必要性から、ガバナンス強化の重要性が主張されるようになりました。
経営の透明性を高めることはもちろん、株主の権利と平等性を守ること、また、従業員の雇用を守ることも、ガバナンス強化の目的と言えます。
ガバナンス強化のメリットは、以下のように企業価値の向上の他にもあります。
- 労働環境の改善
- 中長期的な売上増
- 顧客が信用して自社の製品・サービスを選択してくれる
ガバナンス強化によって、業務や責任の範囲も明らかになるため、不正の起こりにくさも相まって、働きやすい環境が整備されます。
不祥事の後、企業の売上が下がる事例は少なくありません。消費者は、良いイメージの企業の製品・サービスを選びたいものです。
ガバナンス強化で透明性のある経営を続け、信頼できる企業のイメージを持たれることは、自社が選ばれる最低条件と言えるでしょう。
コーポレートガバナンスとは?
ここからは、コーポレートガバナンスに関する基本的な知識を解説します。
コーポレートガバナンスの定義
コーポレートガバナンス(corporate governance)とは、企業の経営を透明性や公平性を確保するための仕組みであり、主に企業の役員や取締役に対し、株主や利害関係者、社会全体に対する責任や義務が生じることを指します。
企業の目的や経営方針に沿って適切にコーポレートガバナンスを実践することで、企業価値の最大化、リスク管理、投資家との信頼関係の強化などの目的が達成できます。
コーポレートガバナンスの目的
コーポレートガバナンスの主な目的は、企業価値の最大化、リスク管理、投資家との信頼関係の強化などです。企業が透明性を確保し、投資家や株主、利害関係者に対して正確な情報を提供することで、経営方針や財務状況についての信頼を築くことができます。
これにより、企業の評価が向上し、投資家からの資金調達や株式の取引、ビジネスの遂行が円滑に行われるようになります。
似た言葉との比較
企業の透明性・信頼性について考える文脈では、コーポレートガバナンス以外にも出てくる用語があります。
コーポレートガバナンスの理解が深まるよう、似ている3つの言葉の意味を解説しながら比較していきます。
内部統制との違い
内部統制とコーポレートガバナンスには関連性がありますが、それぞれ異なる概念であるため注意が必要です。
内部統制は、企業が自己の業務を適正かつ効率的に遂行するための仕組みです。具体的には、企業内部のルールや手続きを整備し、業務の信頼性や効率性を確保することを目指します。すなわち、内部統制は主に組織内のプロセスやリスク管理に焦点を当てている点に特徴があります。
一方コーポレートガバナンスは、企業の透明性や公平性を確保し、投資家との信頼関係を構築するための仕組みです。つまり、コーポレートガバナンスは企業の組織全体に関わるものであり、経営方針や意思決定プロセス、情報開示などに焦点を当てているものです。
このように、内部統制が企業内の具体的な業務遂行における仕組みであるのに対し、コーポレートガバナンスはより広範な視点で企業の経営を考えるものである点で異なります。
内部統制についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
CSRとの違い
CSRとは、Corporate Social Responsibilityの頭文字をとったもので、「企業の社会的責任」という意味です。
従業員や顧客、消費者や投資家はもちろん、環境や地域社会といった企業活動が影響を及ぼす全ての範囲に対して責任を負います。例えば地域住民のためのイベントを開催するなどがCSR活動の一環です。
コーポレートガバナンスはCSR実現のための仕組みのひとつと言えます。
コンプライアンスとの違い
コンプライアンスは「法令遵守」と訳されますが、法令にとどまらず、社内規則や社会規範、企業倫理などを守ることを示します。コンプラとも略されます。
コンプライアンス徹底の結果、コーポレートガバナンスの目的である企業の透明性・信頼性につながる、という関係です。
コーポレートガバナンスが注目を浴びている背景
コーポレートガバナンスが注目を浴びるようになったのには、企業の不正・不祥事の増加と、グローバル化が関係しています。
企業の不正・不祥事を見聞きすることが増えたのは、1990年代のバブル崩壊後。
経営不振を打開するため、不正会計や過度な長時間労働などをせざるを得ない状況に陥りました。
その結果生じた不正が問題視され、企業の不正や不祥事を防ぐ体制が必要と考えられるようになりました。
また、グローバル企業であれば各国の基準に合った経営体制が求められます。結果、コーポレートガバナンスはより無視できないものとなってきています。
非上場企業におけるコーポレートガバナンスの扱い
コーポレートガバナンスは上場企業には義務づけられている一方、非上場企業では義務とされていません。
一方、非上場企業にコーポレートガバナンスの意識が不要であるということではありません。顧客や取引先と良好な関係を築き続ける上では適切なガバナンス体制が欠かせません。
コーポレートガバナンス・コードとは
コーポレートガバナンスコードとは、金融庁と東京証券取引所が作成した、コーポレートガバナンスを実行するための仕組みで、5つの原則で構成されています。
- 株主の権利・平等性の確保
- 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
- 適切な情報開示と透明性の確保
- 取締役会等の責務
- 株主との対話
適切に取り組むことで、企業は成長を怠ることなく、常に企業価値の向上に積極的に取り組むことが期待されます。その結果、投資家への還元にとどまらず、社会の発展にも貢献します。
コーポレートガバナンスの役割
コーポレートガバナンスコードには、基本的に上場企業が遵守すべき重要なガイドラインが含まれていますが、企業の業界競争力を高め、成長を促進するためのポイントが含まれているため、中小企業にとっても見逃せない基本的なルールです。
企業がこれらの原則に目を通し、実践することで、市場での存在感を強化し、顧客の信頼を獲得するチャンスを得ることができます。
役割1.株主の権利・平等性の確保
コーポレートガバナンスの第一原則は、株主の権利と平等性の確保です。企業は、株主の権利と平等性の確保に努めるべきとされています。株主の権利を実質的に確保し、適切な環境を整備することで、株主が権利を適切に行使できるようにする必要があります。
特に、少数株主や外国人株主に対しては、権利の実質的な確保や行使に関する課題や懸念があるため、十分な配慮が求められます。
株主の平等性も重要であり、平等な待遇を確保するための措置を講じる必要があります。
役割2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
コーポレートガバナンスの第二原則は、株主以外のステークホルダーとの適切な協働です。企業は、持続的な成長と企業価値の創出において、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などのステークホルダーとの協力関係を重視すべきとされています。ステークホルダーが提供するリソースが成果につながることを認識し、適切な協働を追求する必要があります。
具体的には、労働条件の改善、環境への配慮、地域社会への貢献などの活動があります。
役割3.適切な情報開示と透明性の確保
コーポレートガバナンスの第三原則は、適切な情報開示と透明性の確保です。
企業は、財務情報や経営戦略、経営課題、リスク、ガバナンスに関連する非財務情報などについて、法的要件に基づく適切な開示を行うだけでなく、法的要件によらない情報提供にも積極的に取り組むべきとされています。
取締役会は、開示や提供される情報が株主との建設的な対話の基盤となることを考慮しながら、特に非財務情報が正確で理解しやすく、利用者にとって有用な情報となるように努める必要があります。
役割4.取締役会等の責務
コーポレートガバナンスの第四原則は、企業の最高意思決定機関である取締役会等の責務です。
経営者は株主に対する責任を持ち、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、働きかけるべきとされています。具体的には、企業戦略の方向性を示すこと、経営陣のリスクテイクを支援する環境整備を行うこと、独立した客観的な立場から経営陣と取締役の監督を効果的に行うことなどが挙げられます。
役割5.株主との対話
最後の原則は、株主との対話です。企業は、株主総会以外でも株主との建設的な対話を行い、対話を通じて株主の声に耳を傾け、関心や懸念に真摯に向き合い、自社の経営方針を分かりやすく説明し、株主の理解を得る努力をしなければならないとされています。
また、株主を含むステークホルダーの立場を理解し、適切な対応を行うことも重要です。これにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することができます。
株主の声を聴き、彼らの関心や懸念に真摯に向き合うことで、企業の経営に対する信頼関係を築くことができると言われています。
コーポレートガバナンスの主要な構成要素
コーポレートガバナンスの実現には、いくつかの重要な構成要素が存在します。以下では、その主要な要素について解説します。
構成要素1.取締役会
取締役会は企業の経営を担当する役員が所属する組織です。役員らは企業の長期的な方針や目標を策定し、経営の決定を行います。取締役会のメンバーは、幅広い専門知識や経験を持つことが求められ、株主やステークホルダーの利益を最大化するために適切な経営判断を下す役割果たします。
構成要素2.監査役・監査委員会
監査役・監査委員会は、取締役会の監視役を担い、企業の経営が法令や定款に従って行われ、適切に運営されているかどうかを監督・監査する役割があります。また、監査役等は、企業の経営状況を監視し、問題があれば是正する役割を担っており、不正行為の予防にも取り組む必要があります。
そのため監査役等は、独立性と専門性を備え、企業の経営を適切に監視できる体制を構築することが重要です。
構成要素3.社内統制システム
社内統制システムは、企業内部のコントロールシステムを指し、業務プロセスの適正性やリスク管理の確保、内部統制の整備などが含まれます。
社内統制システムは、企業が適切なガバナンスを実現し、内部の不正やミスを防止するために重要な役割を果たします。効果的な社内統制システムの確立により、企業の透明性や信頼性が向上します。
構成要素4.株主総会
株主総会は、株主が出席して企業の方針や重要な決定を行う場であり、株主は企業の所有者として、経営に対する権利や意見を行使することができます。
株主総会では、企業の財務状況や経営の透明性に関する情報が提供され、株主の関与や意見交換が行われます。株主総会は、企業と株主のコミュニケーションの場であり、企業経営の重要な要素となっています。
構成要素5.情報開示
情報開示は、企業の情報を適切に開示することで透明性を確保する取り組みです。企業は財務情報や業績データ、重要な事象などを公表することにより、株主やステークホルダーに対して適切な情報提供を行います。
情報開示は、投資家の意思決定や企業評価に影響を与える重要な要素であり、公正な市場環境の構築にも貢献します。
コーポレートガバナンスの効果
コーポレートガバナンスは企業経営において重要な役割を果たし、その効果は多岐にわたりますが、特に以下の4つの側面で顕著に現れます。
効果1.企業価値の向上
適切なコーポレートガバナンスの実践は、企業価値の向上に直結します。
これは、透明性と公正性が高まることで、意思決定プロセスが明確化され、業績が向上しやすくなるためです。
ガバナンスの透明性向上にもとづく企業価値の向上により、企業の株価が安定的に上昇する可能性、および新規資金調達の促進も期待できます。
効果2.投資家との信頼関係の強化
コーポレートガバナンスは、投資家との信頼関係を強化します。企業の運営状態が明るみになることで、投資家は企業の動向を正確に把握しやすくなり、より信頼性の高い投資判断が可能になります。
これにより、企業と投資家との間には強い絆が生まれ、長期的な投資が促進されます。
効果3.企業風土の改善
コーポレートガバナンスの適切な運用は、企業風土の改善にもつながります。経営陣が公正に行動すると、それが組織全体に浸透し、倫理的な行動を促します。さらに、公正な評価と報酬制度が整えられることで、従業員の士気は向上し、生産性が高まります。
このように企業風土の改善は、優秀な人材の獲得や定着にも寄与し、企業の競争力を強化します。
効果4.リスク管理の最適化
コーポレートガバナンスはリスク管理の最適化に寄与します。
適切なガバナンス体制は、組織のリスク識別と管理を改善し、潜在的な問題に対する早期対応を可能にします。これにより、変化するビジネス環境に対応し、持続的な成長を達成することができるでしょう。
コーポレートガバナンスの課題
コーポレートガバナンスには、手間や時間、コストがかかります。
また、株主に取り組みのメリットを理解してもらうことも重要です。
社内体制構築に手間、時間とコストがかかる
仕組みを考えたり監査するためには、適切な人材が必要です。外部に監査を委託するなら、弁護士費用などもかかります。
コーポレートガバナンスは、取り組みの効果が見えるまでにある程度の時間を要します。どこまで費用をかけるか、そして、どのように効果を測定したり仕組みを改善していくかのバランスが難しいものです。
株主の過度な重視
投資目的の一番の理由は利益の還元です。
しかし、短期的な利益を優先し、株主への還元ばかりに注力してしまうと、コーポレートガバナンスで実現が見込まれる中長期的な目標の達成が難しくなる可能性があります。
経営陣と株主の利益相反
経営陣と株主の求める利益が一致するとは限りません。前述のように、経営陣が中長期的な成長に向けて戦略を立てても、株主が短期的な利益を求めていれば、コーポレートガバナンスは機能しにくいです。
株主の考えを尊重して短期間で利益を出すことに集中し過ぎると、将来的な企業価値の向上を考慮した取り組みが疎かになり、長い目で見た時に株主の恩恵が少なくなることが懸念されます。
企業の規模と複雑性
監査で不正や不祥事につながりかねないといった指摘を受けないよう、ミスを防ぐためにチェック工程を増やすなど、完了までの時間的コストが増える可能性があります。
また、社外監査を実施すれば、内部で完結するよりも時間がかかります。
大企業は意思決定までのプロセスが複雑で、決定や情報伝達に時間がかかる傾向があります。
コーポレートガバナンスという新たな仕組みを導入することで、さらに情報伝達が滞ることが懸念されます。結果、企業の透明性が損なわれたり、組織の信頼を揺るがすような問題の早期発見が妨げられる恐れがあります。
コーポレートガバナンスを強化する方法
コーポレートガバナンス強化の方法として挙げられるのは以下の4点です。
- 社内規定の作成と整備
- 社外取締役や監査役の設置
- 執行役員制度やワークフローシステムの導入
- 内部統制を強化する
社内規定の作成と整備
コーポレートガバナンスの目的や役割などを開示することは、透明性の確保につながります。
ステークホルダーはもちろん、従業員にも遵守すべきことを周知しましょう。ルールが分からなければ正しいやり方で業務を進められません。社内規定を作成し、周知することでルールを守りやすい状態を作りましょう。
社外取締役や社外監査役の設置
第三者の目があると、不正や不祥事は起こしにくく抑止力が働きます。
社外取締役や社外監査役の客観的な視点により、社内では気づけない問題になりそうな要因にも気づくことができます。
執行役員制度の導入
執行役員は、取締役に代わって業務執行の権限を持つ役員です。
一方、取締役は意思決定を行う役割を担います。このように意思決定と執務の権限が分かれることで、役員それぞれの負担が軽くなり、取締役は意思決定や監視に注力できるので、コーポレートガバナンス体制を適切に、そして効率よく活用できます。
内部統制を強化する
内部統制には守るべきルールが必要ですが、ルールを作る際には、業務の内容や流れを見える化し課題を発見してから取り組みましょう。自社の業務実態に合ったルール作りにより、適切なガバナンス体制が築けます。
また、見える化により属人化している業務の存在に気づくこともあります。属人化している業務は、ルールに則っているか判断しにくいです。業務の属人化をなくし正しい運用がされていることが確認できることも、内部統制の強化に必要です。
ワークフローシステムを導入する
ワークフローシステムとは社内の業務手続きを電子化するシステムです。
ワークフローシステムを使うと、業務プロセスの可視化が図られ、透明性が確保されます。
また、ワークフローシステムは申請などを一括管理、抽出できるため、監査時の提出書類として活用できたり、文書の不正な改ざんや持ち出し対策が可能です。
ガバナンス強化のポイント、注意点
ガバナンス強化にはどのような点を抑えればよいのでしょうか。それぞれご紹介します。
組織の課題を把握する
ハラスメント、機密情報の管理体制など、組織の課題を知り、問題の起こらない体制を築くことがポイントの一つです。
指摘したら自分の成績に影響を及ぼすことを懸念して、正直に答えられない方がいるのは自然なことです。
外部窓口を活用し、課題を見つけやすい状態を作ることも大切です。
従業員の協力を得る
ルールは守られないと意味がありません。ルールを守ろうと思える企業体質や経営者の姿勢が重要です。経営陣や管理職がルールに則ってガバナンス強化に取り組む姿勢を見せることで、従業員もルールを守ろうと思えるものです。
ガバナンス強化の事例
ここでは、企業のガバナンスはどのように強化されるのか、強化するとどのような効果を得られるのか。日本と海外の具体例を紹介します。
日本の事例
全日空商事株式会社は、申請や報告といったどの部門にも共通の業務に対してワークフローシステムを導入しました。
勤怠や経理などとも連携することで、業務の不正やミスが起こりにくく、内部統制が機能している状態をつくれます。結果、社内全体のガバナンスの強化に活かされています。
海外の事例
アメリカでは、上場規則でコーポレートガバナンスガイドラインの開示を義務づけています。
例えばAppleでは以下をまとめたガイドラインを開示しています。
- 取締役の役割
- 取締役の独立性
- 他の会社との兼任
- 取締役会議長とCEOとの関係
- ステークホルダーとの関係
- 取締役と経営幹部・従業員との関係 など
ガバナンスに関するガイドラインを開示していることで、情報開示という形で企業の透明性が確保されています。
取締役の独立性やステークホルダーとの関係の明記は、コーポレートガバナンス・コードと共通しています。ガイドラインに従って役割を果たしたり関係性を保つことで、ガバナンスが守られ、強化されると言えるでしょう。
契約業務の改善でガバナンス強化を実現した事例
全ての契約業務の一元管理と、部署ごとに管理していた契約書の一元管理によってガバナンス強化を実現した事例を簡単に紹介します。
全ての契約業務の一元管理でガバナンス強化を実現した事例
- 課題
契約に関してあらゆるツールが使われていたために、進捗の把握が課題に。 - ゴール
契約受注から更新管理まで、全ての契約のプロセスの見える化によって、契約業務の効率化とガバナンス強化を図ること。 - 効果
契約業務の進捗の把握が容易になり効率化も実現。過去の契約書の検索もスピーディーにできるなど、契約に関する管理体制が効果的に機能するように。
紙・電子ともに全ての契約業務を一元化。「ContractS CLM」でガバナンス強化と契約業務の効率化を実現
部署ごと管理していた契約書の一元管理でガバナンス強化を実現した事例
- 課題
紙の契約書がメインで、契約は部署ごとに管理。依頼形式もまちまちで、過去の契約書の検索をはじめ、管理や業務効率の点で課題があった。 - ゴール
社内の契約書の一元管理、契約業務の属人化解消と効率アップを達成すること。 - 効果
全ての契約の一元管理を実現。情報が自動でストックされるため、属人化も解消。契約業務の管理体制が上手く行き、ガバナンスが強化された状態に。
各部署で行っていた契約書管理を一元管理化。 「ContractS CLM」で管理体制の強化とコスト削減を実現!
まとめ
企業の健全な成長と持続的な発展を実現するために、ガバナンス強化は不可欠です。
コーポレートガバナンスは、企業経営において透明性や公平性を確保するための重要な仕組みです。
その基本原則として、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話が挙げられます。
また、コーポレートガバナンスの効果として、企業価値の向上、投資家との信頼関係の強化、企業風土の改善、リスク管理の最適化があります。これらの効果により、企業は持続的な成長と社会的な責任を果たすことができます。
このように、コーポレートガバナンスは企業にとって不可欠な要素であり、適切な実践によって企業の信頼性や競争力を向上させることができます。企業経営の視点から、株主やステークホルダーとの関係性や情報開示の重要性、取締役会の責務などを理解し、コーポレートガバナンスを適切に導入することが求められます。
ガバナンスの強化は、企業価値の向上、信頼獲得に貢献します。経営の透明性と公正性を重視し、強固なガバナンス体制を築くことで、競争力を高め、発展し続ける企業を目指しましょう。