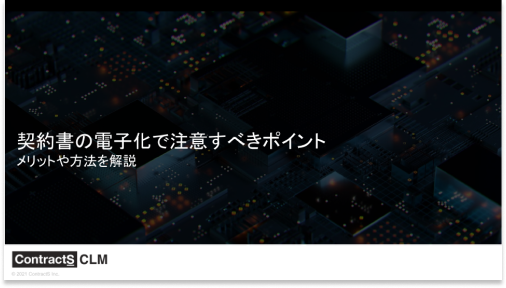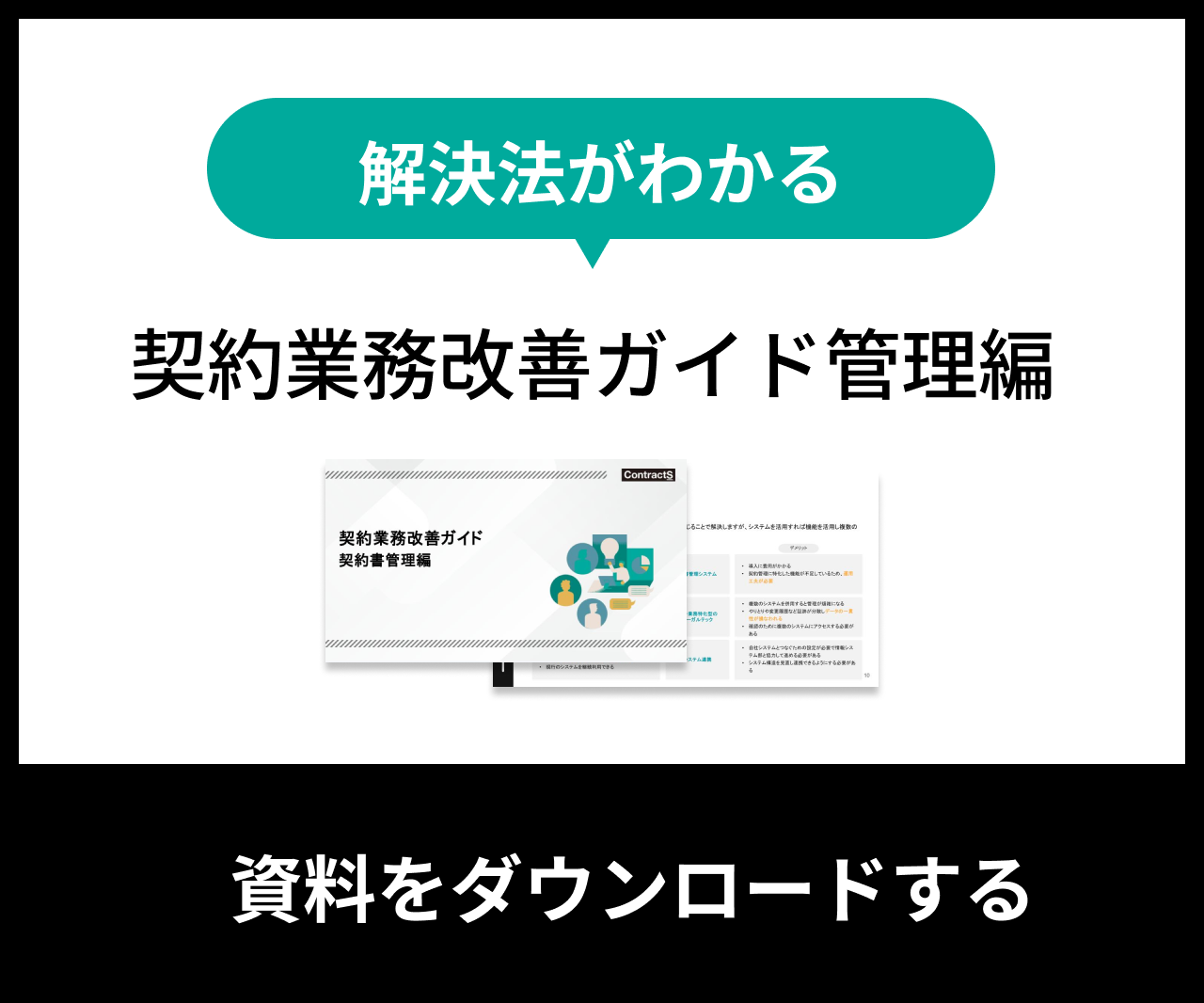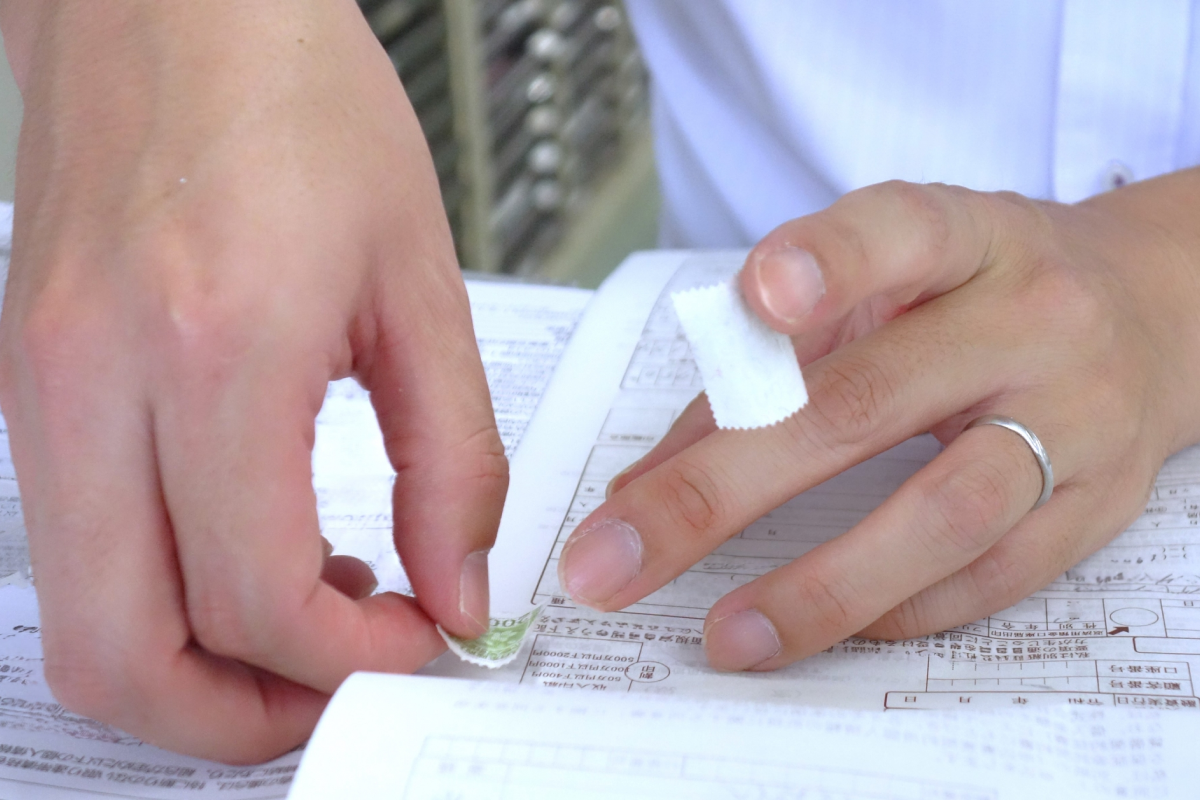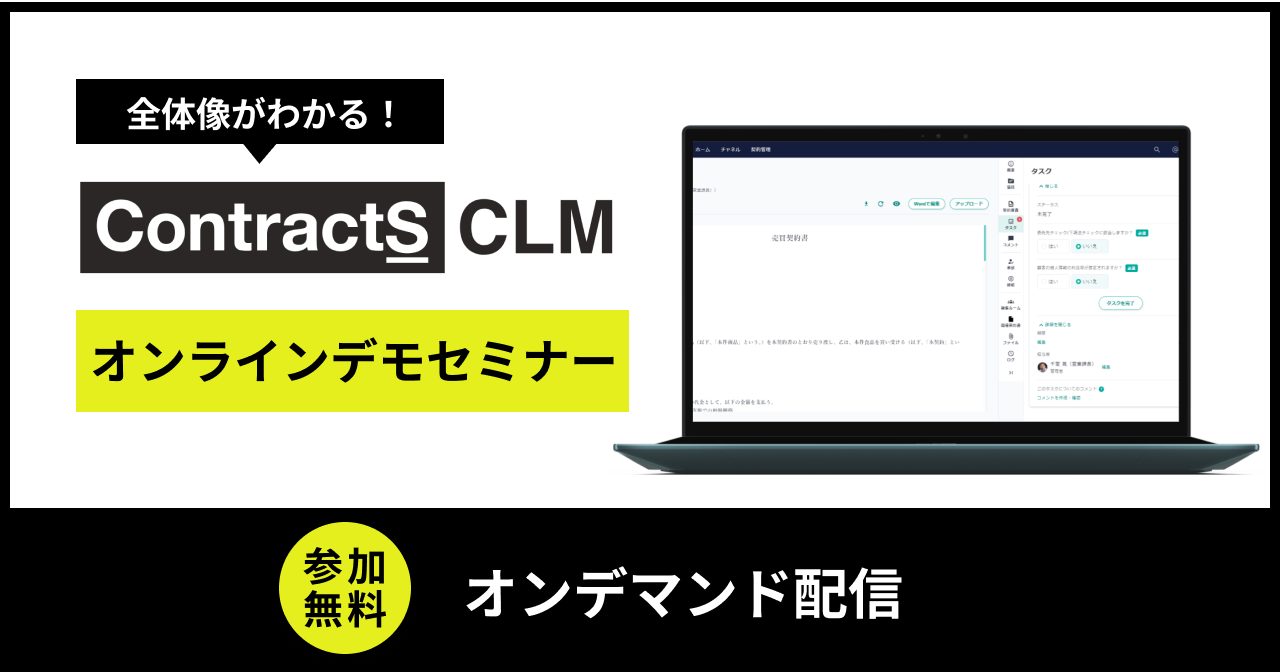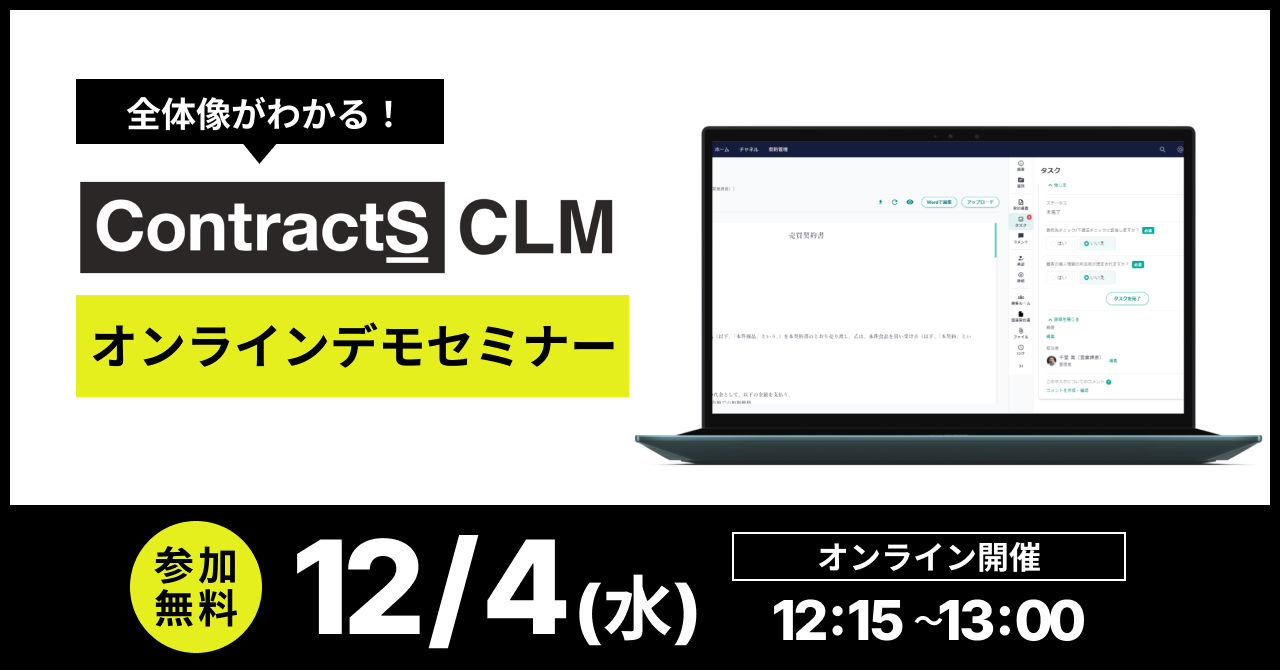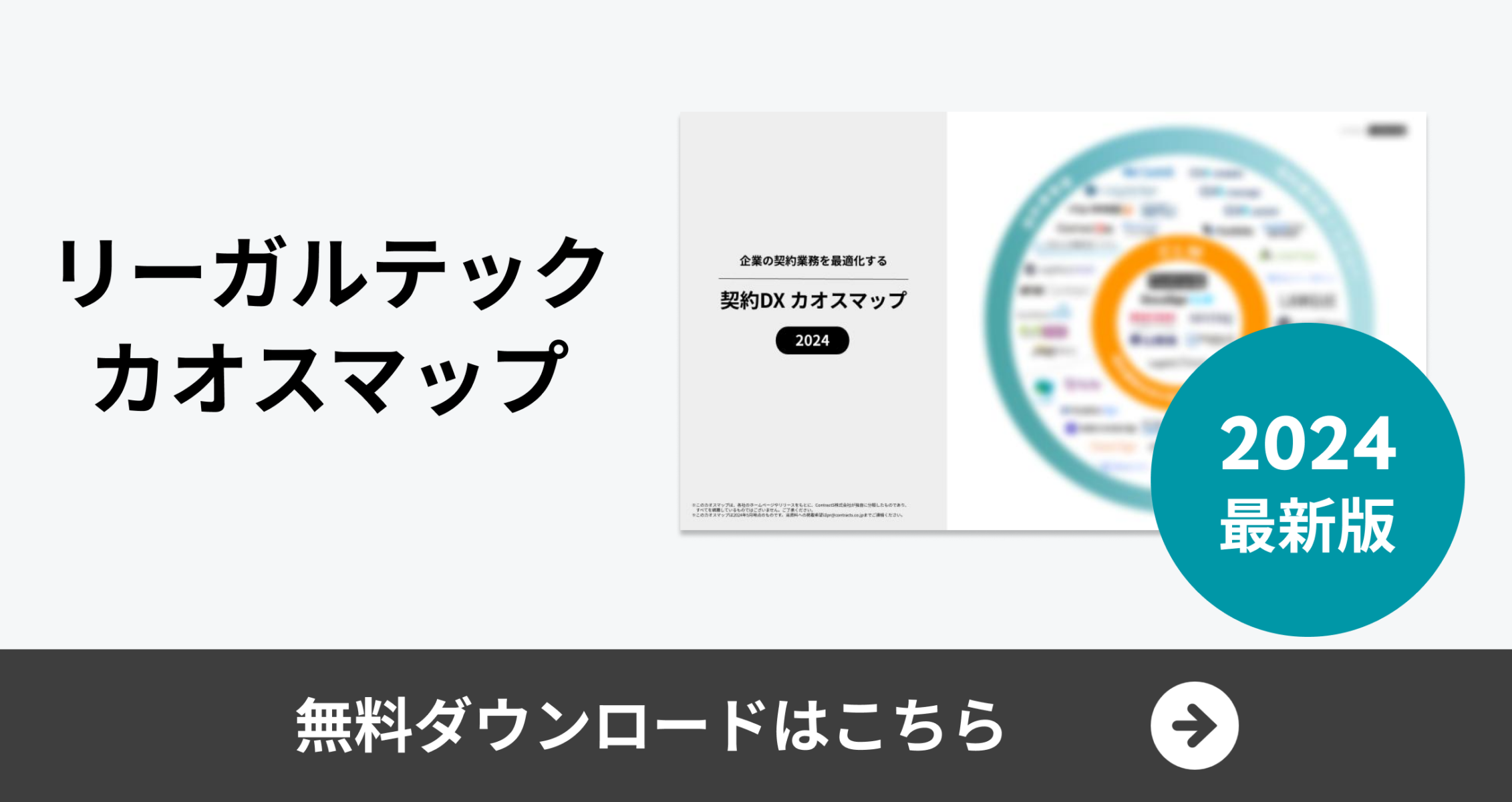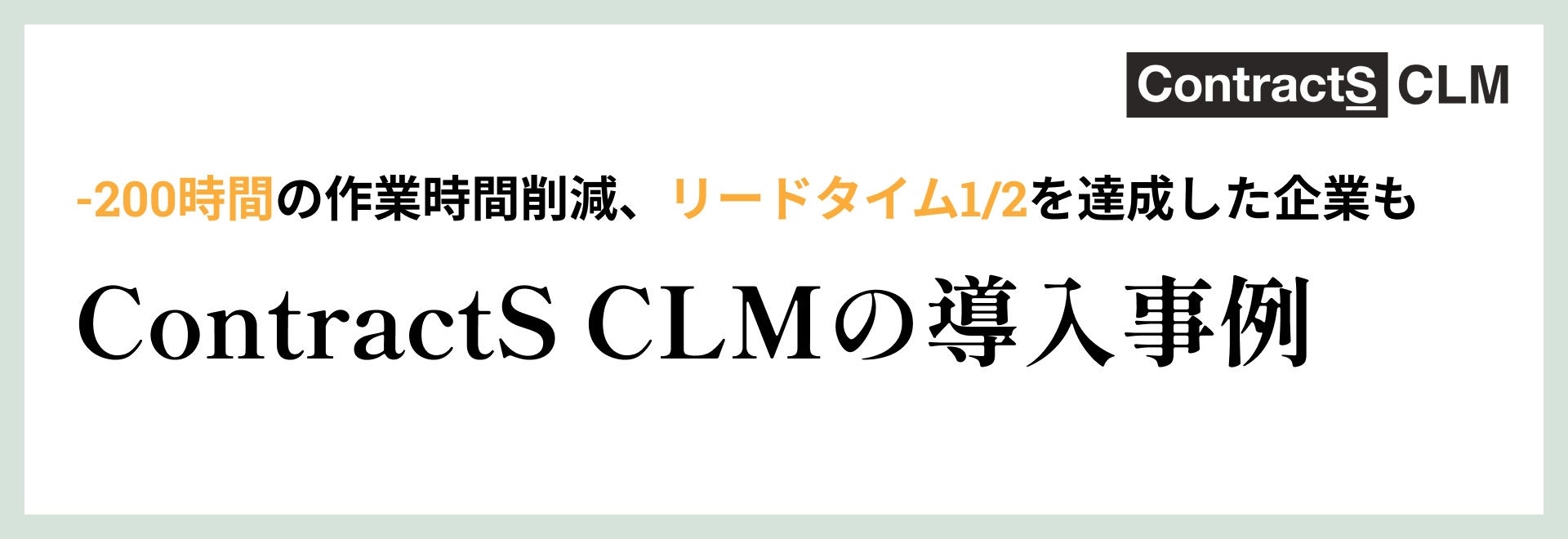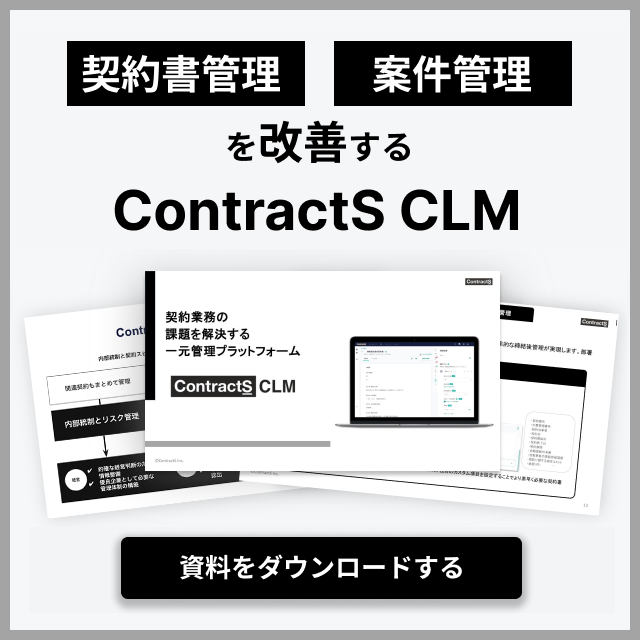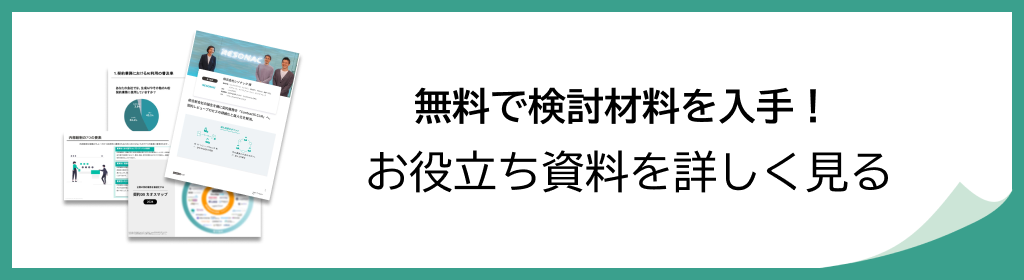ノウハウ 電子署名法とは?電子署名法2条、3条について解説
更新日:2025年03月27日
投稿日:2021年12月21日
電子署名法とは?電子署名法2条、3条について解説

リモートワークの推進から導入検討をする企業が増えた電子契約。利用拡大の一つの要因に、電子署名法2条、3条があります。
電子署名可能な電子契約システムを導入する前に一度確認しておきたい「電子署名法」について、条文をもとに本記事で詳しく解説します。電子契約サービスは合法なのか、法に則ったサービスの見分け方についても言及しています。
▶︎▶︎【無料ダウンロード】電子契約システム比較ガイド
電子署名法とは
電子署名法は、正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)」といい、平成13年4月1日に施行されました。
インターネットの急速な普及に伴い、電子取引の利用が国民に浸透してきた背景から、「電子署名の円滑な利用を確保し、電子商取引をはじめとするネットワークを利用した社会経済活動の推進を図る」目的で制定された法律です。
出典:総務省 電子署名及び認証業務に関する法律の施行(電子署名法)
▶︎【電子契約システム導入を検討している方におすすめ】電子契約とは?システム選定ポイントから導入の流れまでを解説
電子署名法のポイント
電子署名法は、以下のような章・条立てで構成されています。
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定(第三条) 第三章 特定認証業務の認定等 第一節 特定認証業務の認定(第四条―第十四条) 第二節 外国における特定認証業務の認定(第十五条・第十六条) 第四章 指定調査機関等 第一節 指定調査機関(第十七条―第三十条) 第二節 承認調査機関(第三十一条・第三十二条) 第五章 雑則(第三十三条―第四十条) 第六章 罰則(第四十一条―第四十七条) |
本記事では一般的な契約について定めている電子署名法2条、3条について詳しく見ていきます。
電子署名法2条の「電子署名」
まずは電子署名法2条について、実際の条文を見ていきましょう。
電子署名法
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律
この条文から
- 当該情報(電子データ)について行われる措置であること
- 電子データが当該措置(電子署名)を行なった者が作成したものであることを表示する目的のもの
- 電子データに改変がないことを確認できるもの
が、「電子署名」であるとこの条文で定義されていることがわかります。
電子契約サービスはすべて2条に準拠している?
世の中にある電子契約サービスは「電子署名可能」とうたっているサービスが多いですが、そういったサービスはすべて法律に準拠した電子署名が可能なのでしょうか。
実は、世の中にある電子契約サービスは全て電子署名法2条1項の定める「電子署名」に該当するわけではありません。
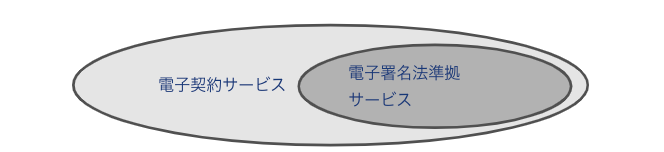
電子署名法2条1項の電子署名に該当することについて、お墨付きを得ているサービスであれば締結相手方への説明も円滑に進みます。
例えば、契約マネジメントシステムContractS CLMはグレーゾーン解消制度を利用し、ContractS CLMの電子契約機能ContractS SIGNが電子署名法2条1項の電子署名に該当することについて確認しました。その結果、デジタル庁・法務省・財務省より、電子署名に「該当する」との回答を得ています。
このように、電子署名法準拠の電子署名であることが確認できています。
【関連記事】グレーゾーン解消制度とContractS SIGNの照会結果について
2条の「電子署名」と認められた場合の効果
では、2条1項の定める「電子署名」と認められた場合どのような効果あるのでしょうか。
契約は基本的には、形式は問わず口頭でも締結できるものですが、一方で「法令が定める一部の契約」について、書面の作成が必要となったり方式が定められています。
2条1項の定める「電子署名」と認められると例えば以下のようなことが可能となります。
事業者署名型サービスは電子署名法2条に該当するのか
世の中に電子署名法2条についての注目度が高まった背景として、令和2年7月に「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により 暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」(いわゆる電子署名法2条Q&A)が公表されました。
このQ&Aで、契約者当事者自身が申請・発行を受けた電子証明書を利用した当事者型電子署名だけではなく、事業者が、電子認証局への申請・本人確認を経て発行を受けた電子証明書を利用して署名する事業者署名型も2条1項の定める電子署名に該当しうると公表されました。
実際の文章を掲載します。
“サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。”
“そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるものになっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことにより、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示すためのものであること」という要件(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすことになるものと考えられる。”
出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)
実際の例では、ContractS CLMの電子契約機能ContractS SIGNは、このQ&Aが指すところの「事業者署名型」に該当すると共に、グレーゾーン解消制度を利用し、ContractS SIGNが電子署名法2条1項の電子署名に該当すると関係省庁より回答を得ています。
電子署名法3条の電子署名
次に、電子署名法3条について説明します。具体的な条文を見てみましょう。
電子署名法
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律
ここでは、電磁的記録に当該規定の要件を満たす電子署名が行われた場合、当該電磁的記録が真正に成立したものと推定するという規定されています。
そして、成立の真正が推定されるための要件は下記の2点です。
① 電子文書に電子署名法第3条に規定する電子署名が付されていること。
⑴同法第2条に規定する電子署名に該当するものであること
⑵「その電子署名を行うために必要な情報を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるもの」に該当すること
② 「本人による」=電子署名が本人(電子文書の作成名義人)の意思に基づき行われたものであること。
「必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなる」とは?
電子署名法2条だけではなく電子署名法3条の規定が適用されるためには、3条の要件①⑵及び②も満たす必要があります。
つまり、暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成することができないと認められる電子署名である必要があり、当該電子署名について相応の技術的水準が要求されています。
では、具体的にどのようなサービス要件を満たせば、電子署名法3条が定めるところの電子署名に該当するのでしょうか。
令和2年9月4日、総務省・法務省・経済産業省より、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A (電子署名法第3条関係)」(いわゆる電子署名法第3条Q&A)が公表され、その中では以下のように説明されています。
「これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理すること」の具体的内容については、個別のサービス内容により異なり得るが、例えば、サービス提供事業者の署名鍵及び利用者のパスワード(符号)並びにサーバー及び利用者の手元にある2要素認証用のスマートフォン又はトークン(物件) 等を適正に管理することが該当し得ると考えられる。
あくまで、電子署名法3条は該当することで、真正に成立することが「推定」されるのみなので、2要素認証を使ったサービスを使えば確実に真正に成立したとみなされるわけではありません。
まとめ
紙の締結以外の選択肢として利用が拡大している電子契約サービス。これに伴い電子署名の法的な根拠性についてはこれまで以上に議論がされています。
まずは、法的な解釈の基礎となる「電子署名法」について内容を把握し、万が一会社間で契約がトラブルになった時にも冷静に対処できるように準備を進めていきましょう。