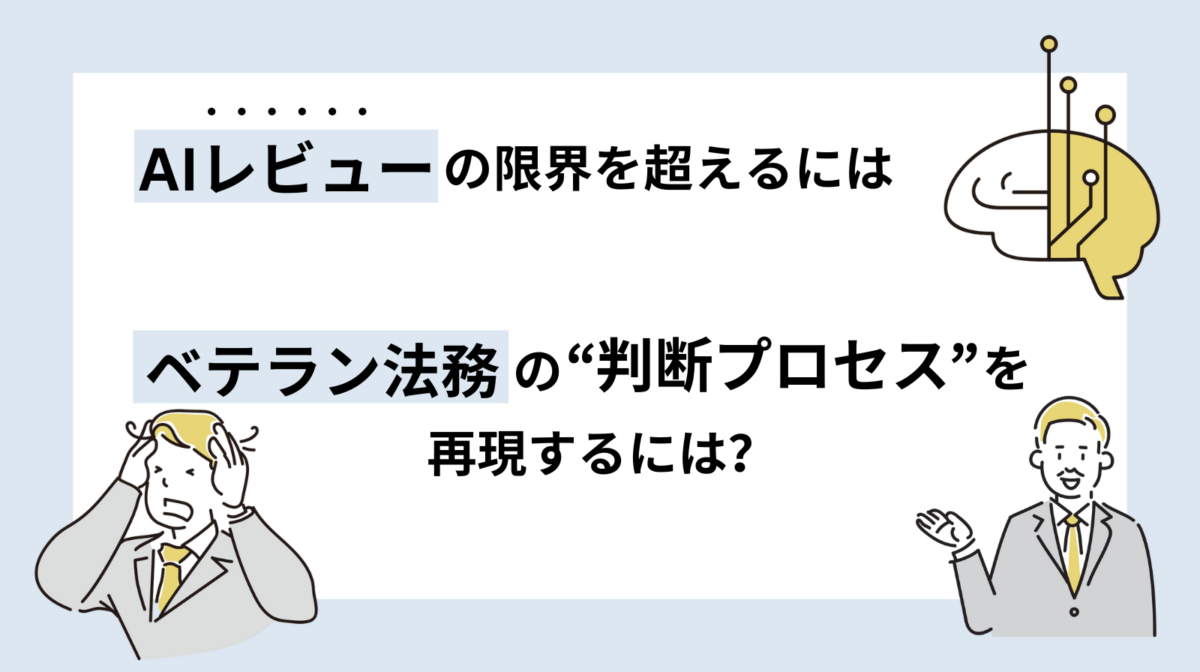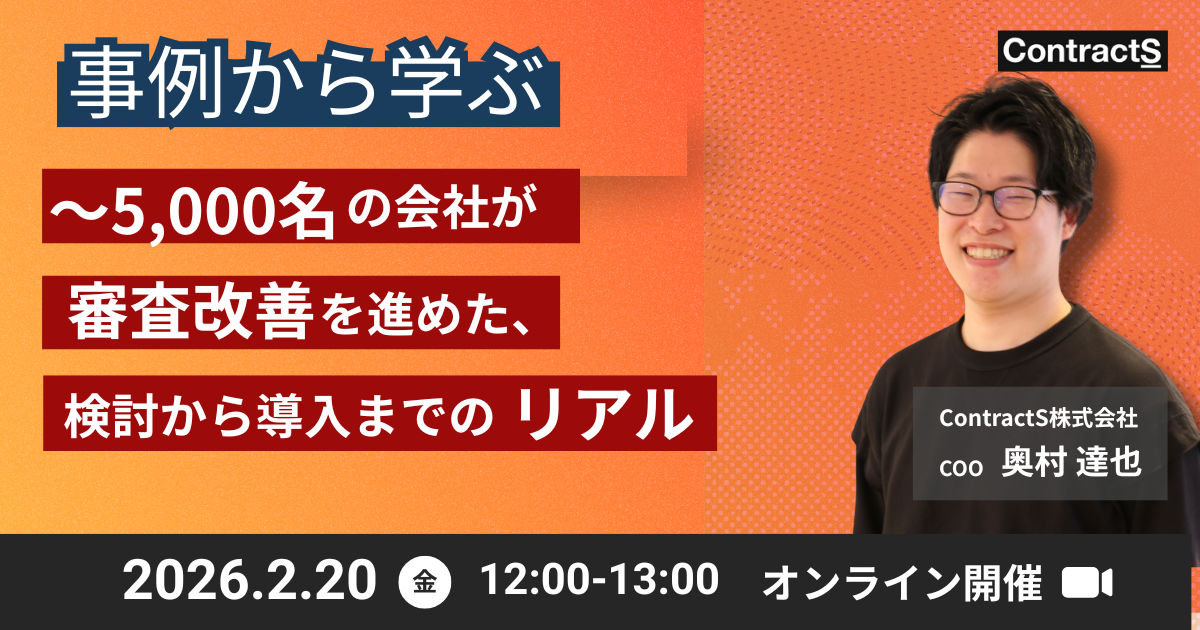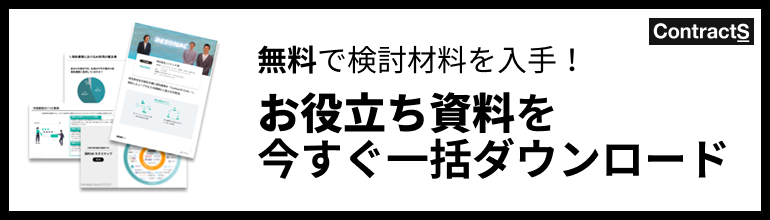ノウハウ 契約の成立とは?基礎から実務までまとめて解説
更新日:2025年03月27日
投稿日:2021年12月2日
契約の成立とは?基礎から実務までまとめて解説

契約の基本である「契約の成立」。2020年4月に民法が改正され、「契約の成立」の観点で改正がありました。
この記事では契約の成立要件や有効要件、契約書などの実務について解説します。契約がなぜ必要とされるのか、ふと不思議に思った経験のある方、契約業務の合間にぜひご覧ください。
契約の成立とは
この章では、民法改正に触れながら、契約の成立要件、有効要件について解説していきます。
そもそも「契約」とはなんでしょうか。
そもそも契約とは
簡単に言うと、契約とは当事者双方の意思が合致した約束です。ただ、単なる約束とは違って、契約には法的拘束力が生じます。
売買契約を結ぶと、売り手に物を渡す義務と代金を受け取る権利が生じます。そして買い手には物を受け取る権利と代金を支払う義務が生じます。ここで買い手が代金を期日までに支払わなかったとします。すると本来の商品の価格を請求されるだけではなく、さらに金銭を請求されることもあります(損害賠償請求)。
このように契約の締結により、当事者に法律上権利や義務が生じます。そして契約が守られない場合は、強制的に契約内容が実現されたり、損害賠償が課される可能性があるのです。
契約の成立
「契約成立」につい民法ではどのように規定されているのでしょうか。
まずは、改正民法にて新設された第522条「契約の成立と方式」についての条文を見てみましょう。
第522条(契約の成立と方式)
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。出典:民法
このように民法では契約は締結を申込み、それを相手方が承諾をした際に成立をすると定めています。
契約の成立は法令に定めがない限り形式を問わない
一般的に契約は「契約書」のような書面にサインや印鑑を押し、初めて成立するように思われていることが多いですが、口約束など正式な形あるものがなくても、契約は成立します。
これを「契約方式自由の原則」といいます。
一方で、企業間の契約や企業と個人の契約では「契約書」という書面で契約をやり取りすることが基本となっています。
これは、契約内容を書面に残すことで、例えばトラブルになった時等に合意内容の証拠になるためです。
契約方式自由の例外
契約方式自由の例外として、契約書で締結することが定められている契約もあります。
近年、書面電子化の動きがあるため、書面でないと有効ではない契約か否か、法律の改正は細かく確認しましょう。
▶︎▶︎こちらの記事もおすすめ:電子帳簿保存法徹底解説!令和4年1月改正まで完全フォロー
「契約の成立」に関する民法改正のポイント
2020年4月に実施された民法改正ですが、このなかで「契約の成立」に関わるものについて説明していきます。ポイントは大きく分けて二つです。
民法522条1項
まず一つ目が先ほど紹介した民法522条1項についてです。契約の成立について条文として明文化されました。
契約の成立には「申込み」と「承諾」が必要ということでしたが、「申込み」と「承諾」についてもう少し詳しく見ていきましょう。
「申込み」は承諾があれば契約を成立させるという法的な効果を期待する「意思表示」であり、「承諾」は申込みに応じて契約を成立させるという「意思表示」です。
「意思表示」とは法律効果を発生させようという効果意思を外部に示す行為です。
例えば、売買契約で考えると、売り手が「このパソコンを10万円で買いませんか」と相手に言うのが「申込み」で、買い手が「買います」と言うのが「承諾」です。
つまり新民法は「申込み」「承諾」という「意思表示」の有無を重視しているといえます。
民法522条2項
次に民法522条2項についてです。この条文も民法改正により、新たにつくられました。
一般的に契約は「契約書」のような書面にサインや印鑑を押し、初めて成立するように思われています。しかし口約束など正式な形あるものがなくても、契約は成立します。これを「契約方式自由の原則」といいます。契約書が必要な契約は別途条文に規定が置かれています。
つまり新民法は契約の成立において形式よりも「意思表示」の有無を求めているといえます。
一方で契約内容を書面もしくは電子機器上で残すことは、トラブルになった時などに合意内容の証拠となります。よって、依然として契約書が大事であることに変わりはありません。
契約の拘束力
契約が成立すると特定の人に特定の行為を請求できる権利(債権)と特定の人に特定の行為をしなくてはならない義務(債務)が発生します。
このように契約は一度成立すると契約から一方的に逃れることができず、契約の内容を実現させるために契約に「拘束」されます。これを契約の拘束力といいます。
契約の有効要件
このように「申込み」と「承諾」の「意思表示」があれば、基本的に形式は問わず、契約が成立することがわかりました。
しかし契約の内容や当事者の状態によっては、成立した契約が無効や取り消しになることもあります。
契約が有効に成立するための要件について見ていきましょう。
契約内容の有効性
契約の内容が①確定性、②適法性、③社会的妥当性の3つの要件を満たすことが必要です。
確定性
先ほど、契約の成立によって当事者双方に法律上の権利と義務が発生するというお話をしました。ここで契約の内容が不明瞭だと自分の権利や義務の内容が不明確になってしまいます。
例えば、商品を買った際にその商品の値段が明確に定まっていないと困りますよね。
そこで契約の内容は、当事者双方にとって明確なものである必要があります。これが確定性です。
適法性
契約は成立することで当事者双方を法的に拘束します。つまり、契約内容実現のために法が助力してくれるのです。
そしてそのための前提として、契約内容が適法である必要があります。
例えば、詐欺をするという内容の契約があったとしましょう。この契約を有効としてしまうと、同時に法的拘束力も生じてしまいます。そのため、契約内容は法律に反していないことが求められます。
強行規定と任意規定
公の秩序に関する法律のうち、強制的に守ることを定めた規定を「強行規定」といいます。
これに対し、同じように公の秩序に関する法律ではあるものの、原則を定め、契約当事者間の意思によって適用しないことができる規定を「任意規定」と言います。
取締規定
行政上の取締りの観点から、行為を禁止し、その違反に対して刑罰等を課す規定を「取締規定」といいます。
この取締規定に違反すれば全て契約が無効になるわけではない点は注意が必要です。
社会的妥当性
契約内容が社会の一般的秩序や一般的道徳観念に適合していることは法律の一般原則です。
例えば、改正民法90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めており、「公序良俗」に反する法律行為は無効と明文化しています。
契約当事者の有効性
契約当事者について以下の三つの要件を満たすことが必要です。
①意思能力があること、②行為能力があること、③意思表示に瑕疵がないこと
それでは一つずつ内容を見ていきましょう。
意思能力があること
契約の「意思能力がある」とは、契約当事者が契約内容に対して意思表示をする能力がある状態を指します。
この「意思能力がない」対象者については、明文化されていませんが、一般的には、子供や泥酔者などは意思能力がないと考えられています。
このように契約の内容を理解した上で契約を結ぶか判断できる能力が意思能力です。
これに関しては「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」(民法3条の2)と定められています。
行為能力があること
契約の「行為能力」があるとは、契約当事者が単独で契約行為を行う能力がある状態を指します。
先ほどの「意思能力」の有無は基準が明文化されていません。そのため、意思能力があると思って契約したのに、実は意思能力がなかったということがあり得ます。
すると契約の相手方にしてみれば、突然契約が無効になってしまい、とても不便です。
そこで、「行為能力」が制限されている「制限行為能力者」を民法で類型的に定めることにしました。
制限行為能力者は未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が該当します。
制限行為能力者が行った契約は無効になる場合があります。
意思表示に瑕疵がないこと
契約は当事者双方の意思が合致し、申込みと承諾が行われることで成立します。
先ほどの例では、売り手が「このパソコンを10万円で買いませんか」と「申込み」、買い手が「買います」と「承諾」すると、売買契約が成立します。
この時売り手には「このパソコンを10万円で売りたい」という内心の意思があり、買い手にも「10万円でこのパソコンを買いたい」という内心の意思があります。
しかし、内心の意思と実際に意思表示した内容がずれる場合があります。パターンとしては次の二つです。
パターン①
売り手にパソコンを10万円で売るつもりはなかったのに、「パソコンを10万円で売りたい」という意思表示をしてしまった場合
パターン②
買い手にパソコンを10万円で買うつもりはなかったのに、「買います」という意思表示をしてしまった場合
そしてこれらの意思の不一致がさらに五つに分けられます。
心裡留保
一つ目が心裡留保です。これは本人が内心の意思と意思表示にずれがあることを認識している場合をいいます。この時、意思表示は無効とされます。
通謀虚偽表示
当事者双方が直接的にあるいは間接的に共謀して、虚偽の意思表示をすることを通謀虚偽表示といいます。
先ほどのパソコンの例でいうと、売り手にパソコンを売る意思がないことを売り手も買い手も認識していながら、あえて売買契約が成立したかのように振る舞うことです。
民法94条では「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」とされています。また、94条2項では「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」とされています。
つまり、双方に売り手にパソコンを売るいしがないことを知っていながら、結んだ契約は無効です。しかし、何も知らない第三者が売り手から買い手にパソコンが売り渡されたと思い、さらに買い手からパソコンを買う場合があります。この場合は通謀虚偽表示があったとしても契約は無効になりません。
錯誤
内心の意思と意思表示にずれがあることに気づいていない場合を錯誤といいます。
例えばmacだと思って買ったパソコンが実はwindowsだった場合です。
この場合「macのパソコンを買いたい」という内心の意思に対し、「(windowsの)パソコンを買います」という意思表示をしているので、錯誤があります。
民法95条によると「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」は、取り消しができるとされています。
つまり、今回の例では買い手が「macのパソコンが欲しいと思っていた」などと売り手に言いながら、「(windowsの)このパソコンを買う」と意思表示した場合です。
この場合は「動機が相手に表示され」、「錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかった」に該当します。
ただし、実質的には内心と意思表示が異なっていることを立証するのは非常に難しいと考えられます。
詐欺・強迫
騙されたり、脅迫されることで、内心の意思とは異なる意思表示をする場合をいいます。
例えば、売り手に(本当はそんな価値はないのに)、このパソコンはとても性能がいいと騙されて、買ってしまった場合は詐欺に当たります。
そして売り手にこのパソコンを買いなさいと脅されて、(本当は買いたくないのに)買った場合は強迫になります。
この場合、民法96条で「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定められています。
しかし、詐欺の場合は騙された側にも責任があります。そのため、詐欺があったことを知らない第三者に対しては、意思表示を取り消すことができません。
商法における契約の成立
これまで民法における契約の成立と有効要件について見てきました。しかし、契約の当事者によっては民法ではなく、商法を使います。
商法を使うのはどのような時か、また、民法とは何が違うのでしょうか?
商法が適用されるのは誰に対してか
まず商法1条により、「商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。」と規定されます。
つまり、「商人」が契約の当事者である時は、商法を使うということです。
さらに商法4条により、「この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。」と定義されています。
例えば、営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり(会社法第5条)、すべて営業(資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。)になります。
つまり、株式会社などが業務の一環として契約を結ぶ場合は、商法を使います。
ただし、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
つまり、サラリーマンや内職は「商人」に当たらないということです。
契約の成立に関する民法と商法の違い
それでは、契約の成立に関して民法と商法にどのような違いがあるのか見ていきましょう。
ポイントは「商人」、例えば株式会社は日々さまざまな取引を行っています。そのため、契約の成立を迅速に行う必要があるということです。
さらに、「商人」には繰り返し継続的に取引をしている相手がいると考えられます。
これらの事実を踏まえて商法509条では、
「商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。」
という規定を置いています。
つまり、いつも取引をしている商人が相手の場合、申込みと承諾の意思表示が合致しなくても、商人による諾否の返事がなかった場合には申込みに対して承諾と見なされるのです。
とはいえ、申込みのたびに諾否の返事をすることが必要なことは第1項でも定められていますから、たとえいつもと同じでもレスポンスは返すべきでしょう。
契約の成立に関する民法改正が実務に与える影響
それでは民法改正によって実務にどのような影響があるのか見ていきましょう。
民法改正による実務の変化
先ほど民法の改正により、契約の成立には「申込み」と「承諾」の意思の合致が必要であると明示されました。
また、契約内容には確定性が必要であることを有効要件で見てきました。
したがって、契約内容をきちんと特定したうえで申込みをすることが必須となります。もし契約の内容を具体的に特定していなかったら、それは契約の「申込み」とはみなされず、単なる「申込みを誘う行為」(申込誘引)という、その前段階の行為にすぎなくなってしまうのです。
そして「申込み」に対する「承諾」を電子メールや郵便物でする際には、「承諾」の意思表示が相手に届いたかを確認することが大切です。
商法を踏まえた実務
次に民法ではなく、商法を使う場合、実務はどのようになるのでしょうか。
先ほど商法においては、いつも取引をしている「商人」に申込みをした場合、「承諾」がなくても契約が成立しました。
これを踏まえると、継続している契約の管理と「承諾」の意思表示を明確にすることが、より重要になります。
「承諾」した覚えのない契約によるトラブルを事前に防ぐための取り組みが必要になります。
まとめ
これまで民法改正に触れながら、契約の成立を中心に見てきました。
契約の成立には「申込み」と「承諾」が必要で、形式は自由であるとされましたが、契約書の管理が重要であることに変わりはありません。
むしろ民法改正により、契約書において何を重視すべきかが明確になったといえるでしょう。
▶2023年から契約書の処理方法が変わります
【徹底解説】電子帳簿保存法改正とは?要件、対象の事業者などをわかりやすく解説